

エンジニア採用に悩む企業は少なくありません。求人を出しても応募が集まらない、面接してもスキルの見極めが難しい──こうした問題の背景には、市場の人材不足やエンジニア特有の働き方の変化があります。
本記事では、エンジニア採用を成功させるために必要なペルソナ設計からチャネル戦略、面接・内定後の対応まで、押さえておきたいコツを体系的に解説していきます。
エンジニア採用はなぜ難しいのか
エンジニアを採用したくても、なかなかうまくいかない──。このような悩みを抱える企業は少なくありません。母集団形成が難しい、スキルの見極めが難しい、内定辞退が多いなど、採用プロセスのあらゆるフェーズにおいて課題が発生しやすいのがエンジニア採用の特徴です。
その背景には、エンジニア特有の市場構造や働き方の変化があります。ここではまず、企業がエンジニア採用で苦戦する理由を、市場的な観点から整理します。
エンジニア市場の実態
経済産業省の調査によれば、2030年には最大で79万人のIT人材が不足すると予測されています。このように、市場全体で供給不足が続いており、企業間の競争は激化の一途をたどっています。
加えて、エンジニアの働き方も多様化しており、正社員だけでなく副業やフリーランス、リモート勤務などのニーズが増加しています。こうした変化に企業が柔軟に対応できなければ、候補者に選ばれるのは難しくなります。
【参考文献】「IT人材需給に関する調査」
企業が採用に苦戦する主な理由
多くの企業がエンジニア採用に苦戦する背景には、以下のような課題があります。
- 求める人物像が曖昧でミスマッチが生じやすい
- 求人票が魅力的に映らず、応募数が伸びない
- 選考スピードが遅く、他社に先を越される
これらの課題はどれも「企業側の準備不足」に起因することが多く、戦略的な採用活動を行っている企業との差が明確に表れます。次章からは、採用成功のためのステップとコツを順に解説していきます。
【ステップ1】求める人物像の具体化とペルソナ設計
エンジニア採用の第一歩は、「どんな人物を採りたいのか」を明確にすることです。ここを曖昧にしたまま進めると、求人票や選考基準、面接内容に一貫性がなくなり、採用活動が迷走する原因になります。
以下では、ペルソナ設計を行う際に企業が意識すべきポイントを解説します。
- 現場の声を取り入れたリアルなペルソナを描く
- エンジニア特有の志向性・価値観を理解する
- スキル・志向・動機の3軸で整理する
それぞれについて詳しく説明します。
現場エンジニアと協力して人物像を描く
人事部門だけでペルソナを設計してしまうと、現場とのズレが生まれがちです。業務の実態やチームの雰囲気を最も把握しているのは現場のエンジニアです。彼らと共に、必要なスキルや人物像を具体的に定義することが、採用のミスマッチを防ぐ最大のコツです。
志向やキャリアパスを踏まえた設計にする
エンジニアは給与や役職だけでなく、「どんな技術に触れられるか」「どのような成長機会があるか」を重視する傾向があります。したがって、単に要件を並べるのではなく、「どんな志向の人なら活躍できるのか」「入社後にどのようなキャリアパスがあるか」を明確にし、それに合ったペルソナを設定しましょう。
スキル・志向・動機の3軸で要件を整理する
ペルソナ設計では、以下の3軸で要素を洗い出すと整理がしやすくなります。
- スキル(使用経験のある技術、業務経験)
- 志向(働き方、チーム開発へのスタンス)
- 動機(なぜ転職を考えるのか、重視する価値観)
この3軸を意識することで、より現実的で再現性の高い人物像を描くことができます。
【ステップ2】魅力的な求人票・採用情報の作成
どれだけ良い人材像を定めても、それを正しく伝えられなければ意味がありません。エンジニアに「この会社で働きたい」と思ってもらうためには、求人票や採用ページが彼らの価値観に刺さるよう設計されている必要があります。
ここでは、エンジニアに響く求人票を作成するための4つのポイントを紹介します。
- 業務内容や開発環境を明確に記載する
- 社風や制度の魅力を簡潔に言語化する
- タイトル・構成に訴求力を持たせる
- エンジニア目線を意識した表現にする
それぞれについて詳しく説明します。
業務内容を具体的に記載する
エンジニアは、抽象的な表現よりも、具体的な内容を求めます。「自社サービス開発」や「業務改善システムの設計」など、仕事内容をはっきりと書くことが重要です。また、「担当フェーズ」や「チーム体制」まで記載すると、実際に働く姿がイメージしやすくなり応募率が向上します。
技術スタックや開発環境を明確に示す
「言語:Python/Java」「インフラ:AWS/Docker」「開発手法:アジャイル」など、使用する技術やツールを明確に記載しましょう。技術者は、これらの情報をもとに自分のスキルが活かせるかどうかを判断します。
社風や評価制度を簡潔に言語化する
「働きやすい環境」といった抽象的な表現ではなく、「リモート率90%」「フレックスタイム制あり」「半年ごとの目標面談」など、具体的な制度や風土を紹介することで、信頼感が増します。エンジニアは組織文化や評価方法にも敏感です。
訴求力のあるタイトルと構成を意識する
求人票のタイトルは、検索やスカウト時に最も目に入る情報です。「成長企業でPythonを極める!自社開発エンジニア募集」など、技術・魅力・雰囲気が一目で伝わるタイトルを設計しましょう。また、文章構成も「仕事内容→開発環境→求める人物像→待遇・制度」のように流れを整えると読みやすくなります。
【ステップ3】最適な採用チャネルの選定
エンジニア採用で成功している企業の多くは、候補者との「接点づくり」に力を入れています。求人を出すだけで応募が集まる時代ではなく、候補者に“見つけてもらう・興味を持ってもらう”ためのチャネル戦略が重要です。
ここでは、最適なチャネル選定のための4つのコツをご紹介します。
- ポジションやフェーズごとにチャネルを使い分ける
- 直接アプローチ可能なダイレクトリクルーティングを活用する
- SNS・オウンドメディアなどで接点を増やす
- フリーランスや副業人材も検討する
それぞれについて詳しく説明します。
ポジションやタイミングに応じて手法を選ぶ
エンジニアの職種やレベルによって効果的なチャネルは異なります。たとえば、若手層には転職サイトやイベント、即戦力層には人材紹介やリファラルが有効です。また、採用スピードを優先したい場合は、エージェントとの連携強化が功を奏することもあります。
ダイレクトリクルーティングを活用する
スカウト型採用は、エンジニアにとって煩わしい反面、内容次第で高い効果を生みます。ポイントは、「テンプレートではない、個別最適化されたメッセージ」を送ること。候補者のGitHubやQiita、ブログなどから関心領域を把握し、響くメッセージを届けることで返信率は大きく変わります。
SNSや採用広報で認知を広げる
Twitter(現X)、LinkedIn、noteなどでエンジニア向けの発信を行い、自社の文化やプロジェクトの魅力を可視化しましょう。社員インタビューやプロジェクト紹介記事、開発イベントのレポートなどが効果的です。採用広報は、候補者の“指名検索”を増やす力になります。
副業・フリーランスも選択肢に含める
採用が難航している場合や即戦力を短期で確保したい場合は、副業人材やフリーランスの活用も有効です。業務委託契約で一時的に協業し、成果を見てから正社員化する「お試し採用」の導入も、企業・候補者双方にメリットがあります。
【ステップ4】選考フローの最適化と面接体制の強化
採用活動の中で、候補者に最も強く企業の印象が残るのが「選考プロセス」です。特にエンジニアは複数社を同時に検討する傾向があるため、スピード感・妥当性・透明性のある選考が求められます。
ここでは、選考フェーズを改善するための4つのコツを紹介します。
- 現場エンジニアを面接に参加させる
- スキルチェックを事前に設計する
- 選考のスピード感を意識する
- 面接中の情報提供で納得感を高める
それぞれについて詳しく説明します。
現場エンジニアを選考に参加させる
技術面やチーム適性の見極めは、人事だけでは限界があります。現場エンジニアを一次面接や最終面接に参加させることで、技術的な深掘りやチームとの相性判断が可能になります。また、候補者側にとっても「一緒に働く相手が見える」ことは大きな安心材料となります。
スキルチェック方法を事前に設計する
スキル評価の方法が曖昧だと、選考の公平性が損なわれます。コーディングテスト、ポートフォリオレビュー、課題選考など、事前に方法を決めておくことが重要です。また、GitHubなどのアウトプットも活用し、実務に即した観点での評価を心がけましょう。
選考期間を短縮しスピード感を持たせる
エンジニア採用では、「良い人材ほどすぐ他社で決まる」現実があります。選考日程の調整に時間がかかったり、社内の合議が長引いたりすることで、候補者が離脱するケースも多く見られます。事前に稟議フローや評価基準を整え、迅速に意思決定できる体制を整備しましょう。
面接時の情報提供で候補者満足度を高める
面接は、企業が候補者を評価する場であると同時に、候補者が企業を見極める場でもあります。評価ばかりに偏らず、「自社で働くメリット」や「キャリアアップの支援体制」など、相手の不安を解消する情報提供も丁寧に行いましょう。これが内定承諾率にも大きく影響します。
【5ステップ】内定後フォローと入社後定着支援
エンジニア採用において、内定を出しただけで終わりではありません。むしろ、内定から入社、そして定着に至るまでのサポートこそが、最終的な採用成功を左右します。採用後の辞退や早期離職を防ぐためには、心理的なフォローと物理的な環境整備が重要です。
ここでは、内定後〜入社後にかけて企業が取り組むべき3つのポイントを解説します。
- 内定承諾前後も密にコミュニケーションを取る
- オンボーディングプランを丁寧に設計する
- 働きやすく評価される職場環境を整える
それぞれについて詳しく説明します。
内定後も継続的にコミュニケーションを取る
内定から入社までの期間に「他社からの逆オファー」「不安による辞退」が起こるケースは少なくありません。そのため、定期的な連絡やオフィス見学・社員との懇親会の実施など、候補者との関係性を維持する工夫が求められます。信頼関係を築けていれば、内定辞退のリスクは大きく下がります。
入社前オンボーディングを丁寧に設計する
オンボーディングとは、入社後の早期戦力化を目指す受け入れ施策のことです。エンジニアの場合は、入社初日から環境構築や業務に関われるよう、PCやアカウント類の事前準備、マニュアル整備、教育担当のアサインを徹底しましょう。準備が整っている職場は、それだけで安心感を与えます。
技術的・心理的に働きやすい環境を整備する
柔軟な働き方(リモート・裁量労働)や、適切な評価制度、スキルアップ支援など、エンジニアが長く働きたいと感じる環境づくりが重要です。特に成長意欲の高い人材は、「学び続けられるか」「成果が正当に評価されるか」を重視するため、制度面の見直しも定着率向上に直結します。
エンジニア採用に成功している企業の特徴
エンジニア採用を成功させている企業には、いくつかの共通点があります。単に報酬や知名度が高いだけでなく、「求職者視点で設計された採用活動」を地道に行っている点が特徴です。
ここでは、特に成果を上げている企業に共通する3つの特徴を紹介します。
- 採用ブランディングに注力している企業
- 採用ターゲットを明確にしている企業
- 選考スピードが早い企業
それぞれについて詳しく説明します。
採用ブランディングが強い企業
採用ブランディングとは、自社が「どんな価値観で、どんな人を求めているか」を明確に打ち出し、候補者に選ばれる企業イメージを形成する活動です。成功している企業は、noteやYouTube、SNSを通じて現場のリアルな声や社内文化を継続的に発信し、候補者の心をつかんでいます。
採用ターゲットを明確にしている企業
誰でもいいという採用ではなく、「このような志向・スキル・価値観を持つ人が自社にフィットする」というターゲットを明確に定義している企業は、ミスマッチが少なく、選考プロセスもスムーズです。さらに、求人票やスカウト文もその人物像に合わせて最適化されており、候補者からの共感を得やすくなります。
選考スピードが早い企業
市場において優秀なエンジニアは、常に複数社から声がかかっている状態です。成功している企業は、書類選考から内定までを平均1〜2週間以内に完結させており、レスポンスも非常に速い傾向にあります。こうしたスピード感ある対応が候補者の信頼を勝ち取り、他社との競合を制する鍵となっています。
【成功事例】課題別に見るエンジニア採用の成功パターン3選
エンジニア採用で成果を上げている企業は、自社の課題を正しく見極め、それに応じた打ち手を講じています。本章では、「返信率改善」「ブランディング不足の克服」「工数不足の解消」という3つの課題に対し、効果的に対応した事例を紹介します。
「返信率を改善」して成果を出したスカウト運用の工夫
ある中小企業では、ダイレクトスカウトを使ってエンジニアにアプローチしていたものの、返信率はわずか1%未満。そこでスカウト文面の見直しに着手しました。具体的には以下の対応を実施。
- 候補者のプロフィールに言及するパーソナライズ文を導入
- 「なぜあなたなのか」「どのような貢献を期待しているか」を明記
- 送信タイミングを平日昼・夜間に絞って最適化
その結果、返信率は1%から6%に改善。月間20〜30件の面談設定ができるようになり、3ヶ月で2名のエンジニアを採用することに成功しました。テンプレート任せのスカウトから脱却することがカギです。
「ブランディング不足」を乗り越えて採用に繋げた発信施策
あるBtoB SaaS企業では、企業知名度が低く、スカウトを送っても「知らない会社なので辞退します」と返されることが続出していました。
そこでnoteでの社内カルチャー発信や、テックブログ、イベント登壇などの施策を実施。現場エンジニアが交代でブログを書いたり、社内で起こったトラブルとその乗り越え方をドキュメント化することで、「この企業で働くイメージ」がわく状態を作りました。
結果として、スカウト返信時に「ブログ見ました」「考え方に共感しました」と書かれる機会が増加。認知度が低くても、共感をベースにした採用が可能になる好事例となりました。
「工数不足」を乗り越えた仕組み化による成果創出事例
エンジニア採用を担う人事担当が1名しかいないあるスタートアップでは、母集団形成に時間が割けず、機会損失が多発していました。
そこで、スカウト運用の一部を業務委託化し、さらに社内の開発メンバー2名にスカウト文面レビューを任せる体制に変更。Slack連携を使って候補者情報を共有し、スカウトから面談設定までのプロセスを自動化しました。
この結果、担当者の稼働時間を月30時間削減しながら、月平均3名のエンジニアと面談設定が可能になりました。仕組み化と巻き込み体制が採用活動を支える鍵となった好事例です。
エンジニア採用のコツについてよくある質問(FAQ)
エンジニア採用のコツについてよくある質問をまとめました。
なぜエンジニアの採用は難しいの?
エンジニア市場は常に人材不足で、優秀な人ほど引く手あまたです。さらに、働き方や価値観が多様化しており、企業側にも柔軟な対応が求められます。
どの採用チャネルを使えばいい?
求人媒体、エージェント、スカウトなど複数を使い分けるのが基本です。ポジションや人材タイプによって最適なチャネルは異なります。
エンジニアに響くスカウトメッセージのコツは?
相手のGitHubやSNSを確認し、興味関心に沿った内容で書くと効果的です。テンプレートは避け、1通1通丁寧にパーソナライズしましょう。
面接に現場エンジニアは必要?
現場エンジニアの視点は、技術的なスキルだけでなくチームフィットも見極められます。採用のミスマッチを防ぐためにも必ず同席すべきです。
フリーランスの活用ってどうなの?
即戦力の確保やスピード重視のプロジェクトには非常に有効です。正社員採用前のお試し導入としても活用できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、エンジニア採用が難しい理由から、採用を成功に導くための具体的なステップまでを紹介しました。
ペルソナ設計、求人票の改善、チャネル戦略、選考体制の強化、そして内定後のフォローまで、それぞれに重要なポイントがあります。
自社の採用課題を振り返りながら、どこにボトルネックがあるのかを確認してみてください。
本記事を参考に、より戦略的で実効性のあるエンジニア採用を進めていきましょう。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
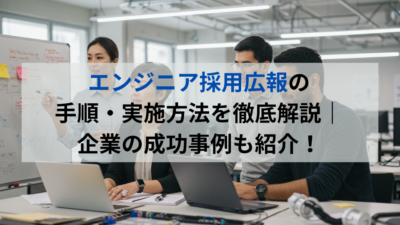
エンジニア採用広報の手順・実施方法を徹底解説|企業の成功事例も紹介!
- エンジニア採用
コーポレート用アイキャッチのコピ-5-400x225.jpg)
エンジニア採用の基準を明確にする方法 注意点と運用のコツ
- エンジニア採用
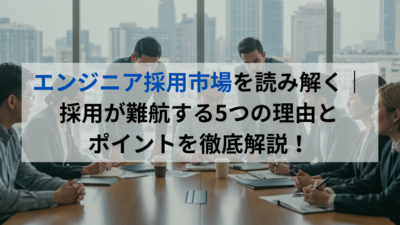
エンジニア採用市場を読み解く|採用が難航する5つの理由とポイントを徹底解説!
- エンジニア採用
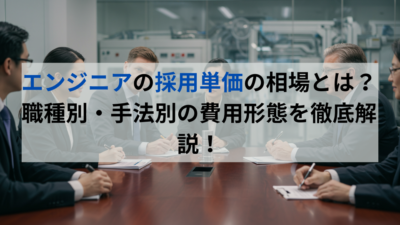
エンジニアの採用単価の相場とは?職種別・手法別の費用形態を徹底解説!
- エンジニア採用
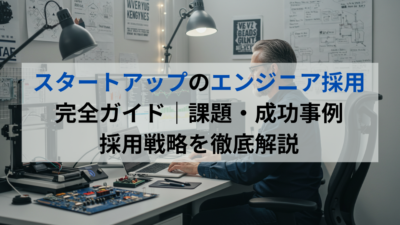
スタートアップのエンジニア採用完全ガイド|課題・成功事例・採用戦略を徹底解説
- エンジニア採用
- 採用代行
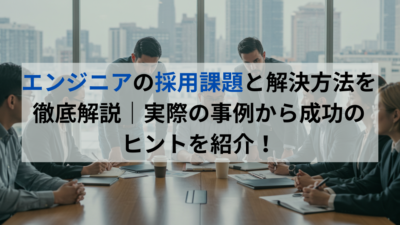
エンジニアの採用課題と解決方法を徹底解説|実際の事例から成功の ヒントを紹介!
- エンジニア採用
- 採用代行







