
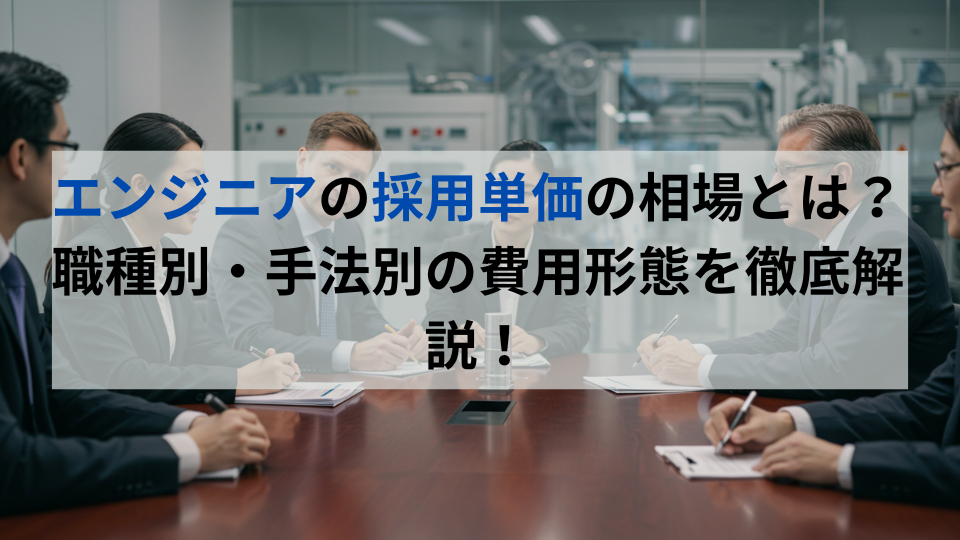
エンジニア人材の採用単価は、職種の専門性や人材不足、採用チャネルの多様化といった要因により、年々高騰しています。
実際に「1人あたり100万円以上のコストがかかっている」という事例も珍しくなく、採用活動の効率性や費用対効果を見直す必要性が高まっています。
本記事では、エンジニア採用単価の計算方法や相場、コストが上昇する理由を体系的に整理し、具体的な削減方法やチャネル別の単価比較まで解説しています。
採用の最適化を図りたい人事・採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
採用単価とは?
「採用単価」とは、1人の人材を採用するのにかかった平均コストを示すもので、企業の人事戦略において非常に重要な数値です。
導入として、本章では以下のポイントについて詳しく解説していきます。
- 採用単価における内部コストとは?
- 採用単価における外部コストとは?
- 採用コストと採用単価の違い
- 採用単価の計算方法
それぞれについて詳しく説明します。
採用単価における内部コストとは?
内部コストとは、企業が自社内で直接負担する採用活動にかかる費用を指します。具体的には、人事担当者の人件費や採用広報のための時間、面接や説明会にかかる工数などが含まれます。これらは普段の業務に隠れやすいですが、採用単価を算出する際には正しく加算する必要があります。
特に注意すべきなのは、人事担当者の稼働時間もコストに換算することです。例えば、月の一定割合を採用業務に費やしている場合、その人件費を反映させることでより実態に近い単価が算出されます。
採用単価における外部コストとは?
外部コストとは、求人広告や人材紹介サービス、スカウト媒体など、社外に支払う費用のことを指します。一般的に可視化しやすいため、採用コストの大部分を占めるケースが多いのが特徴です。
例えば、求人媒体への掲載料や、エージェントを通じた採用時の紹介手数料がこれに該当します。外部コストは投資対効果の検証がしやすいため、定期的に分析し、最適なチャネル選定に活かすことが求められます。
採用コストと採用単価の違い
採用コストと採用単価は混同されがちですが、意味合いが異なります。採用コストは「採用活動にかかった総額」を指し、採用単価はその総額を採用人数で割った「1人あたりの平均コスト」を表します。
つまり、同じコストを使っても採用人数が多ければ単価は下がり、少なければ単価は高くなります。採用単価は採用活動の効率性を測る指標として用いられるため、単なる費用集計ではなく人数との関係性を考慮することが重要です。
採用単価の計算方法
採用単価は以下の式で求められます。
(内部コスト + 外部コスト) ÷ 採用人数
シンプルな計算式ですが、内部コストの算出方法や外部コストの範囲をどこまで含めるかによって数値が変わるため、定義を明確にすることが欠かせません。
また、計算結果を社内で比較・分析することで、自社の採用効率を客観的に把握できます。採用単価を定期的に算出・モニタリングすることが、長期的な採用戦略の改善につながります。
エンジニアの採用単価の相場
エンジニアの採用単価は一律ではなく、職種やスキルレベル、企業の知名度、勤務地など複数の要因によって変動します。
ここでは、手法別の比較に入る前に、相場を左右する代表的な視点を整理しておきましょう。
- エンジニア職種ごとの採用単価の違い
- 経験・スキルレベルによる相場の変化
- 企業規模やブランド力が相場に与える影響
- 地域・勤務地による相場の傾向
各要因について詳しく説明します。
エンジニア職種ごとの採用単価の違い
エンジニアと一口に言っても、Web系、AI・機械学習、インフラなどで相場は大きく異なります。特に先端領域や専門性が高い分野では、採用難易度が高いため採用単価も上昇する傾向にあります。
たとえば、AIエンジニアやクラウドスペシャリストは需要が供給を大きく上回っており、一般的なWebエンジニアに比べて採用単価が数十万円単位で高くなるケースも珍しくありません。
| 年齢層 | 経験年数 | Webエンジニア | AI・機械学習エンジニア | インフラエンジニア |
|---|---|---|---|---|
| 25歳前後 | 1〜3年 | 約50〜70万円 | 約80〜100万円 | 約60〜80万円 |
| 30歳前後 | 4〜6年 | 約80〜120万円 | 約150〜200万円 | 約100〜140万円 |
| 35歳前後 | 7〜10年 | 約120〜150万円 | 約200〜250万円 | 約130〜170万円 |
上記はあくまで目安ですが、需要の高いAI・機械学習分野では同じ経験年数でも採用単価が倍近くになる傾向が見られます。
一方でWebやインフラ分野は比較的市場供給が多いため、相場は落ち着いています。
経験・スキルレベルによる相場の変化
採用単価は、候補者の経験年数やスキルセットによって大きく変動します。新卒やジュニア層は比較的採用しやすいため単価が抑えられる一方で、即戦力を求める中堅・シニア層の単価は跳ね上がります。
特に5年以上の経験を持つシニアクラスでは、採用単価が100万円を超えることもあるため、企業は投資対効果を慎重に検討する必要があります。
| カテゴリ | 目安年齢 | 経験年数 | 採用単価の相場 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 22〜24歳 | 0年 | 約30〜50万円 |
| ジュニア層 | 25〜28歳 | 1〜3年 | 約50〜80万円 |
| ミドル層 | 29〜34歳 | 3〜5年 | 約80〜120万円 |
| シニア層 | 35歳以上 | 5年以上 | 約120〜200万円 |
このように、同じエンジニア職でも経験やスキルレベルによって採用単価は大きく変動します。特に即戦力層はコストが高くなりやすいため、企業は採用計画の段階で明確にターゲットを定めることが重要です。
企業規模やブランド力が相場に与える影響
大手企業や知名度の高い企業は、応募が集まりやすいため採用単価を比較的低く抑えられる傾向にあります。反対に、スタートアップや認知度の低い企業は候補者獲得のために広告や紹介手数料などにコストをかける必要があります。
そのため、ブランド力のある企業ほど採用単価を下げやすいという相場の差が存在します。採用単価を下げるには、広報やブランディング戦略の強化が効果的です。
地域・勤務地による相場の傾向
勤務地も採用単価に大きな影響を与える要素です。首都圏は競争が激しく採用単価が高騰しやすい一方で、地方では採用単価が相対的に低めに推移するケースが見られます。
ただし、地方では母集団形成が難しいため、採用単価は低くても採用成功率が下がるリスクがあります。リモートワーク制度の有無も、相場を変動させる要因となっています。
採用手法ごとの採用単価の相場
エンジニアの採用単価は、どの採用手法を用いるかによって大きく異なります。ここでは、代表的な採用チャネルごとの相場を整理しました。まずは全体感を表で把握し、その後に各手法の特徴と費用感を詳しく解説します。
| 採用手法 | 採用単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 求人媒体(ナビサイト・求人広告) | 約30〜70万円 | 母集団形成に強み。掲載課金型でコスト管理しやすい。 |
| ダイレクトリクルーティング(スカウト) | 約40〜100万円 | 積極的アプローチで即戦力獲得に有効。返信率に左右される。 |
| 人材紹介サービス | 約100〜200万円 | 成功報酬型。年収の30〜35%が一般的。 |
| リファラル採用 | 約10〜30万円 | 社員紹介制度。謝礼やインセンティブ中心で低コスト。 |
| 採用代行(RPO) | 約50〜150万円 | 月額や成功報酬の組み合わせ。採用工数削減に強み。 |
求人媒体(ナビサイト・求人広告)の採用単価
求人媒体を利用する場合、採用単価はおおよそ30〜70万円程度が目安です。大手ナビサイトは掲載費が高めですが、母集団形成力に優れており、多くの候補者にリーチできます。
特に新卒採用や若手層の採用に強く、コストをコントロールしやすい手法といえます。ただし、応募が集まりやすい一方でマッチング精度は媒体ごとに差が出やすい点には注意が必要です。
ダイレクトリクルーティング(スカウト)の採用単価
ダイレクトリクルーティングでは、採用単価は40〜100万円が相場です。企業が能動的に候補者へスカウトを送るため、効率的に即戦力人材へアプローチできます。
ただし、スカウト返信率や面談化率によって成果が左右されるため、文面の工夫や対象者の精査が単価抑制のカギとなります。エンジニア採用では近年もっとも活用が広がっている手法です。
人材紹介サービスの採用単価
人材紹介サービスは、採用単価が100〜200万円と高額になるケースが一般的です。紹介手数料は候補者の年収の30〜35%が目安となるため、年収が高いエンジニアほどコストも跳ね上がります。
一方で、候補者の質や採用成功率の高さが強みです。即戦力人材を早期に獲得したい企業には効果的ですが、予算との兼ね合いを考慮する必要があります。
リファラル採用の採用単価
リファラル採用では、社員紹介の謝礼やインセンティブを中心とするため、採用単価は10〜30万円程度に収まります。もっとも低コストで効果的な採用手法のひとつとされています。
ただし、社員の紹介ネットワークに依存するため、母集団形成の規模には限界があります。他手法と組み合わせて活用すると効果が高まります。
採用代行(RPO)の採用単価
採用代行(RPO)は、月額契約や成功報酬を組み合わせた料金形態が多く、採用単価は50〜150万円程度が目安です。応募対応や面接調整など、工数削減効果が期待できます。
また、採用活動の仕組み化やノウハウの蓄積にもつながるため、中長期的な観点でコストを抑えることが可能です。工数不足や専門性の不足に悩む企業に向いています。
【2025年】採用代行(RPO)とは?メリットや費用、業務内容を徹底解説!
エンジニアの採用単価が高い理由
エンジニア職は、他職種と比べても採用単価が非常に高い傾向にあります。実際に、ITエンジニアの平均採用単価は60万円〜100万円以上に及ぶケースも珍しくありません。
本章では、その背景として考えられる主な要因を以下の観点から整理して解説します。
- エンジニア不足と求人倍率の上昇
- スキル要件の高度化・複雑化
- チャネル多様化に伴う費用の分散
- IT需要の拡大と市場競争の激化
それぞれについて詳しく説明します。
エンジニア不足と新規求人倍率の上昇
近年、エンジニア職の人材不足は深刻化しています。2025年には最大79万人のIT人材が不足するとも言われており、新規求人倍率は5倍以上に達する分野もあります。その結果、少ない人材を複数社で取り合う構図となり、採用単価は自然と高騰します。
(出典:経済産業省「IT人材白書」)
【2025年最新版】ITエンジニア不足の現状と企業が取るべき対策を徹底解説!
スキル要件の高度化・複雑化
近年はAI、クラウド、セキュリティなどの先端領域における採用ニーズが急増しています。こうした分野は高度な知識や経験を必要とするため、条件を満たす候補者が極めて少ないのが現状です。
その結果、希少スキルを持つ人材には高額の紹介手数料や広告投資が発生しやすく、必然的に採用単価が上昇してしまいます。
チャネル多様化に伴う費用の分散
採用活動においては、求人媒体・スカウト・人材紹介・リファラルなど、複数のチャネルを同時に活用するケースが一般化しています。多様化は候補者接点を増やすメリットがある一方で、コスト管理を難しくします。
複数のチャネルへ投資することで、1名の採用にかかる費用が累積しやすい状況となり、結果的に採用単価が押し上げられていきます。
IT需要の拡大と市場競争の激化
デジタル化やDX推進により、あらゆる業界でエンジニア需要が高まり続けています。そのため、優秀な人材を巡る競争は年々激しくなっているのが実情です。
競合より先に採用するために、高い報酬や採用コストを負担してでも確保しようとする動きが加速し、採用単価を押し上げる要因となっています。
エンジニアの採用単価を抑える方法
高騰しがちなエンジニアの採用単価を抑えるには、感覚的な施策ではなく、構造的な見直しとコスト意識が不可欠です。
本章では、具体的に効果的な5つのアプローチを紹介します。
- 採用コストの内訳を可視化・分析する
- 採用要件・基準の見直しを行う
- 費用対効果の高い採用手法を選定する
- 定着率向上によって採用回数を減らす
- 雇用形態の柔軟化
各アプローチを理解することで、無駄なコストをかけずに採用活動を進めることができます。
採用コストの内訳を可視化・分析する
採用単価を抑えるためには、まず「どこにお金を使っているのか」を明確にする必要があります。求人広告や人材紹介費用、スカウト配信、面接対応にかかる人件費など、細かく分類することで全体像が見えてきます。
その上で、数値をもとに費用対効果を分析することで、効果の薄い施策を削減できます。限られた予算を効率的に配分できるようになり、結果的に採用単価を下げることにつながります。
採用要件・基準の見直しを行う
採用要件が過度に厳しいと、対象となる候補者が少なくなり、採用コストは自然と高くなります。実務に必須のスキルと、入社後に研修やOJTで育成可能なスキルを分けて考えることが重要です。
このとき、「Must要件」と「Want要件」を適切に整理することで対象者の幅が広がります。候補者が増えれば競争率が下がり、結果として採用単価の抑制にもつながります。
費用対効果の高い採用手法を選定する
採用単価は利用するチャネルごとに大きく異なるため、自社の状況に合わせて手法を選ぶことが重要です。求人媒体、スカウト、人材紹介、リファラルなどを比較し、最適な手法を組み合わせましょう。
特に、過去のデータからCPA(応募単価)やCPS(採用単価)を検証することで有効なチャネルが明確になります。成果が出やすい手法に集中投資することで、コスト削減と効率化を同時に実現できます。
定着率向上によって採用回数を減らす
採用単価は採用回数が増えるほど積み上がるため、社員が長く働ける環境を整えることが欠かせません。オンボーディングの充実やキャリア形成支援により、早期離職を防ぐことができます。
「定着を前提とした採用設計」を行うことで採用回数そのものを減らせるため、1人あたりの採用コストを大幅に抑えることが可能になります。
雇用形態の柔軟化
正社員採用に固執せず、副業人材やフリーランス、業務委託といった多様な雇用形態を活用する方法も有効です。必要なスキルを必要な期間だけ確保できるため、費用を最適化できます。
特にエンジニア領域では、副業やフリーランスを活用して即戦力を低コストで確保するケースが増えています。柔軟な採用戦略は、採用単価を抑える上で大きな武器となります。
エンジニア 採用単価についてよくある質問(FAQ)
エンジニア 採用単価についてよくある質問をまとめました。
採用単価の適正ラインってどう判断する?
自社の採用目的やポジションの重要度、過去データとの比較から費用対効果を見て判断するのが一般的です。定着率や採用後のパフォーマンスも考慮に入れると、より現実的な判断ができます。
リファラル採用は本当にコスパがいい?
リファラル採用は広告費や紹介料が不要なため、一般的には低コストで高パフォーマンスを期待できます。ただし、社員の紹介ネットワークに依存するため母集団形成には限界があります。
中途採用と新卒採用で単価管理の考え方は違う?
はい、違います。中途採用は即戦力重視で単価が高くなりやすく、新卒採用は将来性重視でボリューム採用が前提のため、単価管理の視点が異なります。
採用単価の社内共有はどの部署まで行うべき?
採用に関わる人事部門だけでなく、経営層や配属予定部署の責任者まで共有するのが理想です。採用コストを組織全体で理解・改善していく意識が重要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、エンジニア採用における「採用単価」の定義や内訳、相場感、そしてコスト高騰の背景と対策について解説しました。
エンジニア採用は職種やスキル、地域、採用手法などによって単価が大きく変動します。また、採用活動の効率性を測るうえで、採用単価は非常に重要な指標となります。
本記事を通じて、自社の採用単価の見直しや改善のヒントが得られたのではないでしょうか?
採用単価をただの「コスト」ではなく「戦略的指標」として活用し、費用対効果の高いエンジニア採用を実現していきましょう。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

エンジニア採用のコツは?5つのステップや成功事例を解説!
- エンジニア採用
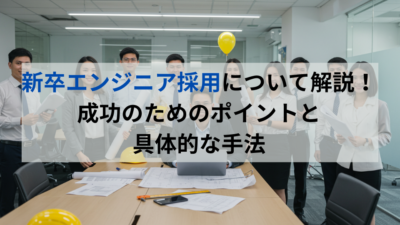
新卒エンジニア採用について解説!|成功のためのポイントと具体的な手法
- エンジニア採用
コーポレート用アイキャッチのコピ-5-400x225.jpg)
エンジニア採用の基準を明確にする方法 注意点と運用のコツ
- エンジニア採用
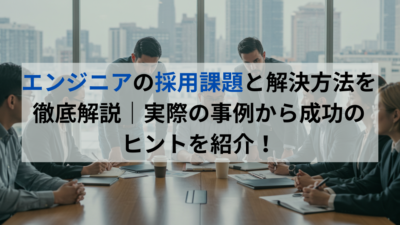
エンジニアの採用課題と解決方法を徹底解説|実際の事例から成功の ヒントを紹介!
- エンジニア採用
- 採用代行
コーポレート用アイキャッチ-7-400x225.jpg)
エンジニア採用代行サービス5選|おすすめの理由から費用まで紹介します!
- エンジニア採用
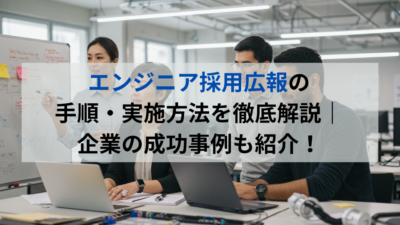
エンジニア採用広報の手順・実施方法を徹底解説|企業の成功事例も紹介!
- エンジニア採用







