

「面接代行の料金っていくらぐらい?」「固定型と従量課金型、どちらが得なの?」
採用業務の効率化を考える企業にとって、こうした疑問は多いのではないでしょうか。
面接代行は便利な一方で、契約形態や依頼範囲によって費用が大きく変わります。
そこで本記事では、料金体系の種類と特徴、採用区分別の費用相場、コスト削減のコツまでをわかりやすく解説します。
面接代行とは?
面接代行とは、企業が自社で行っている採用面接業務の一部または全部を、外部の専門業者に委託するサービスです。特に採用活動が集中する繁忙期や大量採用を行う際に効果を発揮します。
- 面接代行の基本的な定義
- 依頼できる業務範囲
- 導入される主なシーン
- RPO(採用代行)との違い
面接代行とは何か
面接代行は、候補者との日程調整から面接の実施、評価レポートの作成まで、面接フェーズの業務を外部が代行する仕組みです。一次面接を外部に任せ、最終面接は自社で行うなど、柔軟な形で利用できます。
依頼できる業務範囲
業務範囲は企業のニーズによって異なりますが、一般的には以下が含まれます。 – 書類選考通過者への連絡・日程調整 – オンラインまたは対面による一次・二次面接の実施 – 面接評価表やフィードバックの作成 – 応募者対応や辞退防止のフォロー これらを組み合わせることで、人事担当者は戦略的業務に集中できます。
導入される主なシーン
例えば、採用繁忙期で面接官のスケジュールが埋まってしまう場合、大量採用や全国拠点での採用を短期間で進めたい場合、面接官ごとの評価基準のバラつきをなくしたい場合などが挙げられます。特に短期間で多くの候補者をさばく必要がある業種では有効です。
株式会社マイナビの調査によると、採用活動の課題として「応募が集まらない」に次いで「面接官の工数不足」を挙げる企業が多く、特に中小企業では面接代行のニーズが高まっています。この背景には、人事担当者が採用業務に追われ、戦略的な業務に手が回らない現状があります。
【参考文献】「マイナビ『中途採用状況調査2024年版』」
RPO(採用代行)との違い
RPO(Recruitment Process Outsourcing)は採用業務全体を包括的に支援するサービスです。一方、面接代行は業務範囲を面接フェーズに特化しており、必要な部分だけを切り出して依頼できる柔軟性があります。そのため、コストや契約期間も比較的抑えやすいという特徴があります。
面接代行とは?依頼できる業務・費用・おすすめサービス4選を解説!
面接代行の料金に関する基本情報
面接代行の料金は、契約形態や依頼内容、採用区分によって幅があります。ここでは、代表的な料金体系と費用内訳、採用区分ごとの特徴を解説します。
- 面接代行の料金体系3種類
- 費用構成のポイント
- 新卒・中途・アルバイトの費用
面接代行の料金体系3種類
料金体系は主に「月額固定型」「従量課金型」「成功報酬型」の3つに分けられます。それぞれの特徴と向き不向きを押さえておきましょう。
月額固定型
毎月一定額を支払う方式で、一定期間内の面接業務を一括で任せられます。面接数が多い企業や、年間を通じて採用活動が継続している企業に向いています。コスト予測がしやすい反面、採用が少ない月でも固定費が発生します。
従量課金型
面接1件あたりの単価で計算される方式です。繁忙期や特定ポジション採用など、必要な時期だけ利用したい場合に適しています。初期費用を抑えやすいですが、面接数が増えると総額が高くなる点には注意が必要です。
成功報酬型
採用が決定した人数や成果に応じて支払う方式です。採用に至らなければ費用が発生しないため、予算を抑えやすいのが特徴です。ただし、1名あたりの報酬単価が高めに設定される場合が多く、長期利用には向かないケースもあります。
費用構成のポイント
面接代行の料金には、以下のような費用が含まれるのが一般的です。
- 面接官の稼働費用(人件費)
- 面接会場利用料やオンライン面接システム利用料
- 候補者への日程調整・案内などの事務コスト
- 面接評価表やフィードバックレポート作成の管理費
これらは業者によって含まれる範囲や計上方法が異なるため、契約前に必ず見積書で確認することが重要です。
新卒・中途・アルバイトの費用
採用区分によっても費用相場は変動します。一般的に面接1件あたり5,000円〜15,000円程度が相場となっています。
新卒採用:応募者数が多く、日程調整や説明対応の工数が増えるため、単価は比較的低いものの総額は高くなりやすい
中途採用:専門スキルや経験値を確認する必要があるため、面接時間が長く、1件あたりの単価が高くなる傾向
アルバイト採用:短時間の面接が中心で単価は低いが、大量採用が必要な場合は総額がかさむ
自社の採用パターンに合わせて、どの料金体系と採用区分の組み合わせが最も効率的かを見極めることが、費用対効果を最大化する鍵です。
費用を抑えるために押さえておくべきポイント
面接代行は便利なサービスですが、契約内容次第では想定以上に費用がかかってしまう場合があります。ここでは、無駄な出費を防ぎ、費用対効果を高めるための5つのポイントを解説します。
- 業務範囲の明確化と自社作業の切り分け
- 契約形態の見直し(短期→長期など)
- 不要なオプションの排除
- 複数サービスの比較
- 認識の共有を行う
業務範囲の明確化と自社作業の切り分け
まず重要なのは、委託する業務範囲を明確にすることです。日程調整や一次面接の実施など外部に任せる部分と、最終面接や内定通知など自社で行う部分を切り分けることで、費用を大きく削減できます。 必要のない業務まで外注してしまうと、コストが膨らむ原因になります。
契約形態の見直し(短期→長期など)
面接代行には月額固定型や従量課金型などさまざまな契約形態があります。採用活動が長期にわたる場合は、短期契約よりも長期契約に切り替えることで単価を下げられるケースがあります。 反対に、採用が不定期の場合は従量課金型を選び、必要なときだけ利用する方がコスト効率が良くなります。
不要なオプションの排除
多くの面接代行サービスでは、録画面接や候補者評価の詳細レポート作成など、追加オプションが用意されています。便利ではありますが、全ての機能が必ずしも必要とは限りません。利用頻度の低いオプションは外して、必要最低限の機能だけに絞ることで費用を抑えられます。
複数サービスの比較
同じ条件でも、業者によって料金体系やサービス内容は大きく異なります。必ず複数社から見積もりを取り、料金だけでなく、業務範囲やサポート体制も比較検討しましょう。また、キャンペーンや初期費用無料などの割引条件がある場合もあるため、契約前に確認することが重要です。
認識の共有を行う
サービス提供側と自社の間で、依頼内容や成果物に関する認識がずれていると、後から追加作業が発生し費用が増えるリスクがあります。契約前に、業務フローや納品形式、連絡方法などを詳細にすり合わせることで、余計なコストを防げます。特に業務開始前の打ち合わせは省略しないことが重要です。
面接代行を導入するデメリット3選
面接代行は多くのメリットがありますが、導入にあたっては注意点も存在します。ここでは、代表的な3つのデメリットを紹介します。
- 企業文化や魅力が伝わりきらない
- 採用ノウハウが社内に蓄積しにくい
- コストが継続的に発生する
企業文化や魅力が伝わりきらない
面接代行では、外部の面接官が候補者と直接接するため、社内の雰囲気や価値観、企業の魅力を十分に伝えられない場合があります。 特に、カルチャーフィットが重要なポジションや企業独自の理念を重視する採用では、このギャップが採用後のミスマッチにつながることもあります。
採用ノウハウが社内に蓄積しにくい
面接の設計や評価方法などを外部に委託すると、採用ノウハウが社内に残りにくくなります。その結果、将来的に自社で採用活動を内製化しようとした際に、面接官のスキル不足や評価基準の不統一が発生する可能性があります。
コストが継続的に発生する
面接代行はスポット利用も可能ですが、多くの場合は一定期間の契約が必要です。利用が長期化すると、継続的なコスト負担となります。特に月額固定型の場合、採用活動が少ない時期でも費用が発生するため、費用対効果を常に意識する必要があります。
面接代行が向いている企業
全ての企業に面接代行が適しているわけではありません。しかし、以下のような条件に当てはまる企業にとっては、大きな効果を発揮する可能性があります。
- 人事のリソースが不足している企業
- 応募者数が多い企業
- 採用スピードを重視する企業
- 面接の質や評価基準を均一化したい企業
- オンライン面接や地方採用を多用する企業
人事のリソースが不足している企業
採用担当者の人数が少ない、または他業務と兼務している企業では、面接代行によって業務負荷を大幅に軽減できます。これにより、限られた人事リソースを戦略立案や採用マーケティングに集中できます。
応募者数が多い企業
大量応募が予想される新卒採用や短期間での大量採用では、面接調整や実施に膨大な時間がかかります。面接代行は複数の面接官を同時に稼働させられるため、短期間で多くの候補者をさばくことが可能です。
採用スピードを重視する企業
優秀な人材ほど複数企業から内定を得てしまうため、スピード感が求められます。面接代行を活用することで、日程調整の遅れや面接待ちによる辞退を防ぎ、採用競争で優位に立つことができます。
面接の質や評価基準を均一化したい企業
複数の面接官が関わると、質問内容や評価基準にばらつきが出やすくなります。面接代行では、統一された基準で面接を行えるため、評価の一貫性が保たれ、採用の公平性が向上します。
オンライン面接や地方採用を多用する企業
全国から応募者を集める場合や、遠隔地での採用を行う場合、オンライン面接に対応できる体制が不可欠です。面接代行業者はオンラインツールや遠隔面接のノウハウを持っており、地方採用や海外人材の面接にも柔軟に対応できます。
面接評価シートとは?意味・使い方・導入メリットをわかりやすく解説
【5ステップ】面接代行の導入フロー
面接代行をスムーズに導入するためには、いきなり契約するのではなく、事前準備から運用改善までの流れを押さえることが重要です。
- 自社の課題・ニーズを明確にする
- サービス会社の選定
- 契約締結
- 社内体制の整備
- 効果確認と改善の繰り返し
ここでは、導入時に踏むべき5つのステップを解説します。
自社の課題・ニーズを明確にする
まずは、自社の採用課題を具体的に整理します。 「面接官の時間不足」「応募者対応の遅れ」「評価基準のバラつき」など、現状のボトルネックを可視化し、面接代行に求める役割を明確化しましょう。この段階でニーズを言語化しておくことで、後のサービス比較や契約条件交渉がスムーズになります。
サービス会社の選定
面接代行業者は多数存在し、得意分野や提供範囲もさまざまです。 – 新卒・中途・アルバイトなど採用ターゲットの違い – 対応できる面接形式(対面、オンライン、グループ面接など) – 面接官の質や評価手法 – オプションの有無(候補者管理、レポート作成など) 複数社から見積もりと提案を受け、費用だけでなく対応品質や柔軟性も比較することが重要です。
契約締結
契約時には、料金体系(固定型、従量課金型、成功報酬型)と業務範囲を明確にします。 特に注意すべきは、追加費用が発生する条件やキャンセルポリシーです。契約書には「対応可能な面接件数」「レポート提出頻度」「緊急対応可否」なども記載しておくと、後のトラブル防止につながります。
社内体制の整備
導入後に最大限の効果を発揮するためには、社内連携が不可欠です。「候補者情報の共有方法 →面接結果のフィードバックフロー→最終選考や採用決定」このような運用ルールを事前に社内と業者双方で共有し、情報の齟齬を防ぎます。
効果確認と改善の繰り返し
面接代行は導入して終わりではありません。 採用スピード、候補者満足度、採用決定率などの指標を定期的に測定し、改善点を業者と共有しましょう。改善サイクルを回すことで、契約期間中にサービスの質を高めることが可能です。
導入前に確認すべき注意点
面接代行の導入は業務効率化に直結しますが、準備不足のまま契約すると期待した成果を得られないことがあります。
- サービス選定と比較の手順
- 契約内容と運用ルールの明確化
- 導入後の評価・改善体制の構築
- コミュニケーション体制の整備
- ブラックボックス化の回避策
ここでは、導入前に押さえておくべき5つの注意点を解説します。
サービス選定と比較の手順
選定時には、価格だけでなく実績・得意分野・担当者の対応品質を確認しましょう。特に面接官の経験や候補者対応の丁寧さは、採用ブランドにも影響します。最低でも3社以上から比較検討を行い、相見積もりを取ることをおすすめします。
契約内容と運用ルールの明確化
契約書には「業務範囲」「対応時間」「緊急対応の可否」「追加費用条件」などを詳細に記載します。また、社内での承認フローや候補者データの取り扱いルールも事前に固めておくことで、運用開始後の混乱を防げます。
導入後の評価・改善体制の構築
定期的にKPI(採用決定率、候補者満足度、面接通過率など)を確認し、改善案を業者と共有する仕組みを作ります。この評価サイクルを怠ると、導入初期の状態が長期化し、パフォーマンス低下を招きます。
コミュニケーション体制の整備
業者任せにすると、情報共有のタイミングや精度が下がることがあります。連絡窓口を一本化し、週次や月次で定例ミーティングを設けることで、課題や改善点を早期に共有できます。
ブラックボックス化の回避策
業務委託すると、面接の詳細や候補者の反応が見えにくくなることがあります。これを防ぐために、面接記録や評価シートの共有を必須項目とし、社内でもモニタリング可能な体制を作りましょう。
面接評価シートとは?意味・使い方・導入メリットをわかりやすく解説
【厳選】おすすめの面接代行サービス3選
面接代行を導入したいと考える企業担当者向けに、数あるサービスの中から特に評価の高い3社を厳選して紹介します。それぞれの特徴や費用感を整理しましたので、自社の採用課題に合ったサービスを選ぶ参考にしてください。
株式会社uloqo(旧プロジェクトHRソリューションズ)
株式会社uloqoは、全国対応可能な面接代行と採用業務改善コンサルティングを強みとする企業です。経験豊富な面接官による一貫した評価基準のもと、候補者の一次面接から最終選考前の絞り込みまで柔軟に対応します。 企業の採用課題に合わせた面接設計や改善提案も可能で、中小から大手まで幅広く利用されています。
特徴
- 全国対応可能な面接代行サービスを提供
- 一次面接から最終面接前の候補者絞り込みまで対応
- 経験豊富な面接官による評価の一貫性
- 採用業務全体のプロセス改善コンサルティングも可能
- 企業ごとの採用基準に沿った柔軟な面接設計
費用
- 初期費用:要問い合わせ
- 面接1件あたり:5,000〜8,000円(目安)
- 月額固定型プランも選択可能
- 長期契約での割引制度あり
- ヒアリング後に詳細な見積もり提示
パーソルワークスデザイン株式会社
パーソルワークスデザイン株式会社は、パーソルグループの強固なネットワークを活かし、大規模採用や短期間での採用活動に強みを持つ会社です。面接代行だけでなく、応募者スクリーニングや日程調整など採用業務全般を一括で委託可能。多様な業種・職種への対応力と、柔軟な契約形態により、企業の採用効率を飛躍的に高めます。
特徴
- 大手人材サービス企業パーソルグループの一員
- 大量採用・短期集中採用に強み
- 面接代行に加え、スクリーニングや日程調整も一括対応
- 多様な業種・職種に対応可能
- 採用業務の一部アウトソースから全面委託まで柔軟に対応
費用
- 初期費用:無料〜
- 面接1件あたり:5,000円前後(規模による)
- 月間稼働量に応じたボリュームディスカウントあり
- パッケージ料金プランあり
- 詳細見積は案件規模・期間により変動
株式会社アールナイン
株式会社アールナインは、採用支援・面接代行分野で豊富な実績を持つ企業です。面接官の派遣だけでなく、採用基準策定や面接官トレーニング、オンライン・対面の両方への対応など、多角的なサービスを提供。採用活動の質と効率を高めるソリューションを一貫して提供し、企業の長期的な採用力強化を支援します。
特徴
- 採用支援のプロフェッショナルとして業界実績多数
- 面接官トレーニングとセットでの提供も可能
- 対面・オンラインの両方に対応
- 採用基準策定から合否判断まで一貫対応
- 採用活動全体の効率化と質の向上を実現
費用
- 初期費用:要相談
- 面接1件あたり:6,000〜9,000円程度
- 月額制プランも選択可能
- 業種や採用職種により変動
- 詳細は打ち合わせにて決定
面接代行 料金についてよくある質問(FAQ)
面接代行 料金についてよくある質問をまとめました。
面接代行の料金相場はどれくらい?
依頼内容や契約形態によりますが、1件あたり5,000〜9,000円程度が一般的です。月額制や長期契約割引を設けている業者もあります。
料金体系にはどんな種類がある?
主に「月額固定型」「従量課金型」「成功報酬型」の3つがあります。採用の頻度や規模によって最適な方式を選びましょう。
新卒・中途・アルバイトで料金は変わる?
はい、変わります。新卒は単価が低めでも総額が高くなりやすく、中途は1件あたりの単価が高く、アルバイトは短時間面接で低単価ですが大量採用だと総額が増えます。
面接代行の料金に含まれる項目は?
面接官の人件費、会場やオンラインツールの利用料、日程調整や案内などの事務コスト、評価レポート作成費用などが含まれるのが一般的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?本記事では、面接代行の料金について、体系ごとの特徴や費用の内訳、新卒・中途・アルバイト別の相場、費用を抑えるためのポイントまで解説しました。
面接代行のコストは、契約形態や採用規模によって大きく変動します。固定型・従量課金型・成功報酬型のいずれが自社に合うかを見極め、不要なオプションや業務範囲の調整で費用対効果を高めましょう。 本記事を参考に、自社の採用パターンに最適な面接代行サービスを選び、採用活動の効率化とコスト削減を同時に実現してください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
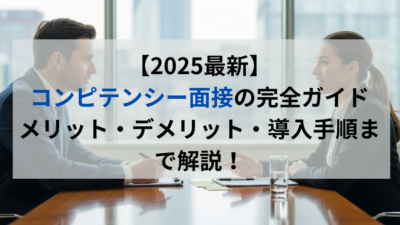
【2025最新】コンピテンシー面接の完全ガイド|メリット・デメリット・導入手順まで解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-4-400x225.png)
カジュアル面談の正しい進め方とは?質問内容まで徹底解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-2-400x225.jpg)
面接官の質問リスト集|質問設計方法、NG例から学ぶ注意点まで徹底解説!
- 面接代行
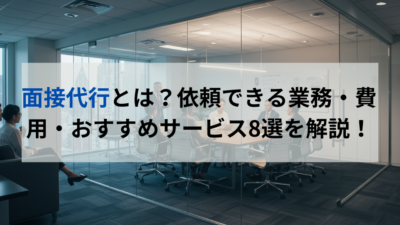
面接代行とは?依頼できる業務・費用・おすすめサービス8選を解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-1-400x225.jpg)
【保存版】面接官が知っておくべき心得5選|準備から注意点まで徹底解説!
- 面接代行
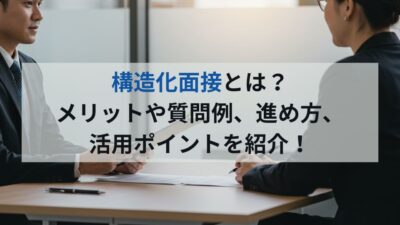
構造化面接とは?メリットや質問例、進め方、活用ポイントを紹介!
- 構造化面接
- 面接代行







