
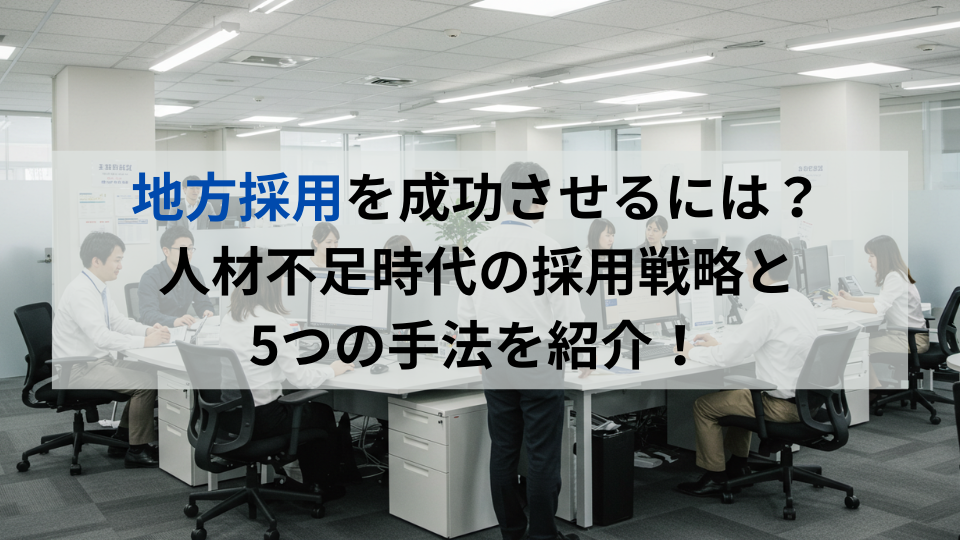
「地方で人材がなかなか採れない」「応募があってもミスマッチばかり」
そんな悩みを抱える地方の企業は多いのではないでしょうか。
特に地方では、地元人材の減少や若者の都市部流出が深刻です。
そこで本記事では、地方採用を成功させるためのポイントや有効な手法を、わかりやすく紹介します。
地方採用とは
地方採用とは、都市部以外の地域に拠点を置く企業が、地方在住の人材や地方大学の学生を対象に行う採用活動のことを指します。
従来は「地元出身の新卒学生の囲い込み」が中心でしたが、昨今では中途採用やUIターン希望者を対象とした広範な戦略へと変化しています。
地方採用とは単なる「採用地域」の話ではなく、企業が人材とのマッチングの新たな軸を取り入れる動きでもあります。
採用の難易度が高まる今、地方採用は企業の成長を支える戦略的な選択肢といえるでしょう。
地方採用の現状とは
地方採用をめぐる現状は、少子高齢化や人口移動、労働市場の構造変化など、複数の要因が複雑に絡んでいます。
ここでは主な4つの観点から現状を整理します。
- 少子高齢化に伴う労働力人口の減少
- 都市部への人口集中と地方離れ
- 地方の有効求人倍率の上昇傾向
- コロナ禍以降の地方求職者の価値観変化
少子高齢化に伴う労働力人口の減少
日本の労働力人口は、長期的に減少傾向が続いており、地方ではより深刻な影響が出ています。
内閣府の予測では、2014年の労働力人口が約6,587万人から、2030年には約5,683万人、2060年には約3,795万人まで急速に減少するとされています。
これに伴い、地方では採用市場そのものが成立しない可能性も指摘されています。
都市部への人口集中と地方離れ
若者を中心に都市部への人口流出が続いており、教育や就職のタイミングで地方を離れるケースが多く見られます。
特に東京圏への転入超過は慢性化しており、地方では若年人材の確保が年々困難になっています。
その結果、地域内の人材循環が停滞し、採用活動が地元人材だけに頼る限界に達しているのが実情です。
地方の有効求人倍率の上昇傾向
厚生労働省が発表した令和7年3月の「一般職業紹介状況」によると、全国の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍で、前月よりも0.02ポイント上昇しました。
これは求人数が求職者数を上回っている状態を意味し、引き続き企業にとっては厳しい採用環境が続いていることを示しています。
コロナ禍以降の地方求職者の価値観変化
新型コロナウイルスの影響により、求職者の働き方やキャリア観に大きな変化が生まれました。
都市部に固執せず、地元での勤務やテレワークを前提とした柔軟な働き方を希望する声も増加しています。
今後は、「働きやすさ」「暮らしやすさ」に焦点を当てた採用広報が、地方企業にとってより重要な戦略となっていくでしょう。
【要注意】地方採用で起こりがちな課題とは
地方採用には、都市部とは異なる特有の課題が存在します。
特に以下の4点は、多くの企業が共通して直面している問題です。
- 地元人材への依存による人材不足
- 採用ターゲットの設計が曖昧
- 地方で働く魅力が伝わっていない
- 転職潜在層・若手人材へのアプローチ不足
地元人材への依存による人材不足
地方企業の多くは、採用対象を「地元で暮らす人材」に限定している傾向があります。
しかし少子高齢化の影響で若年層の数は減少しており、地元人材だけに頼る戦略では採用が頭打ちになりやすいのが現実です。
採用ターゲットの設計が曖昧
「誰を採用したいのか」が明確でないと、求人内容が漠然とし、応募者が集まりにくくなります。
特に地方では応募者数が限られているため、求める人物像が曖昧だと、せっかく応募があってもミスマッチが生じやすくなります。
ペルソナ設計の不足は地方採用の大きな落とし穴といえるでしょう。
地方で働く魅力が伝わっていない
都市部と比べ、地方企業は給与水準や福利厚生面で不利な印象を持たれやすいのが事実です。そのため「なぜ地方で働くのか」という問いに答えられるだけの情報発信が求められます。生活コストの低さや地域密着の働きがいなど、都市にはない魅力を伝えられないと、応募につながりません。
転職潜在層・若手人材へのアプローチ不足
地方では「積極的に転職活動をしていない層」にどうアプローチするかが重要になります。
しかし多くの企業は求人広告に頼りすぎており、潜在層や若手層との接点を作れていません。
【必見】地方採用を成功に導く5つの戦略
地方採用は課題が多い一方で、工夫次第で成果を大きく高めることができます。
ここでは特に重要な5つの戦略を紹介します。
- U・Iターン人材へのアプローチ
- 検索されやすい求人タイトル・ワードの工夫
- 地方ならではの魅力の可視化
- 採用手法の多様化と組み合わせ活用
- 面接・選考プロセスのオンライン化
U・Iターン人材へのアプローチ
地方採用で成功するためには、地元人材だけでなく「Uターン(地元に戻る人材)」や「Iターン(新たに地方に移住する人材)」を対象にすることが欠かせません。
これらの層は「生活環境の改善」や「地域貢献」といった動機を持っているため、求人情報に生活や暮らしの魅力を盛り込むことが有効です。
検索されやすい求人タイトル・ワードの工夫
求人情報は、検索にヒットしなければ存在していないのと同じです。
「地元名」「Uターン歓迎」「在宅可」などのキーワードを組み込むことで、求職者が検索した際に表示されやすくなります。
SEOを意識した求人票が地方採用では特に重要です。
地方ならではの魅力の可視化
都市部と比べると、給与や福利厚生で不利に見えるケースが多いのが地方企業です。
そのため、地域で暮らすメリットや企業が提供できる独自の価値を明確に示す必要があります。
例えば「通勤ラッシュがない」「住宅費が安い」「地域コミュニティに貢献できる」などの情報は、都市部では得られない価値として訴求力があります。
採用手法の多様化と組み合わせ活用
求人広告だけに依存していては、採用の幅は広がりません。
ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、地域イベントでの出会いなど、複数の手法を組み合わせることが必要です。
とくに地方では母集団が限られるため、手法の多様化こそが安定採用のカギとなります。
面接・選考プロセスのオンライン化
近年、オンライン面接やWeb選考を取り入れる企業が増えています。
これにより都市部在住の候補者にもスムーズに接点を持てるようになり、地方採用の可能性が広がります。
移動コストや時間の削減は求職者にもメリットが大きく、選考体験の向上にもつながります。
オンライン面接のメリットとは?導入方法や運用のポイントなどを徹底解説
【5選】地方採用に効果的な採用手法
ここでは、特に地方採用に有効とされている5つの採用手法をご紹介します。
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- 地域特化型求人メディア
- 地方大学・地域機関との連携
- 求人広告とスカウトメールの併用
ダイレクトリクルーティング
候補者に企業側から直接アプローチする「攻めの採用手法」として、ダイレクトリクルーティングは注目されています。
地方では求人の露出が限られるため、企業側から動くことが採用成功の鍵となります。
ダイレクトリクルーティングのメリット5選|注意点やポイント、成功事例を紹介!
特に転職潜在層にリーチできる点が大きなメリットです。
リファラル採用
既存社員から知人や友人を紹介してもらうリファラル採用は、地方における信頼のネットワークを活かす手法です。
紹介された人材は企業との文化的相性が良いケースが多く、定着率や満足度が高まりやすいという利点があります。
地域特化型求人メディア
全国区の求人サイトでは埋もれてしまう求人も、地域に特化した求人メディアを活用することで、よりターゲット層に届きやすくなります。
「地方の地元就職を支援する学生向けサイト」や「自治体と連携したUIターン促進サイト」など、地域密着型の求人発信が効果的です。
地方大学・地域機関との連携
地元の大学・高専・職業訓練校などとの関係構築も、長期的な採用戦略として重要です。
インターンシップの受け入れや合同説明会の開催を通じて、学生との信頼関係を築くことができます。
また、地域機関との連携は官民連携型の採用支援にもつながります。
求人広告とスカウトメールの併用
求人広告は情報発信に優れており、スカウトメールはターゲットへの個別アプローチに適しています。
双方をバランス良く活用することで、母集団の量と質を同時に向上させることが可能です。
スカウト配信時には、地方ならではの魅力を盛り込むと効果が高まります。
採用を成功に導くスカウトメールとは?メリットから無視される原因、作成手順を徹底解説!
地方出身人材の心理的ハードルと企業の対応策
地方出身者が新たな地域での就職を検討する際には、心理的な障壁を感じることが多くあります。
このセクションでは、よく見られる4つの不安と、それに対する企業側の対応策について整理します。
- 経済的な不安
- 文化や生活環境の違いへの不安
- 家族・親の反対や地元志向
- 人間関係への懸念
経済的な不安
地方出身者が都市部や他地域での就職をためらう大きな理由のひとつが、経済的な負担です。
初期費用として引っ越し代や敷金礼金、生活用品の購入などが発生し、就職活動自体にも交通費・宿泊費がかかります。
特に若年層や就業経験の少ない層にとっては、移住・上京に伴う出費が大きな心理的壁となります。
住宅補助や交通費支援などの生活サポート
企業側は、住宅手当や引越補助制度、交通費支援などを明示し、負担を軽減できる体制を整えましょう。
福利厚生の欄に生活支援をしっかり記載することで、応募者にとって安心材料となります。
文化や生活環境の違いへの不安
地方から都市部、あるいはその逆の転居では、生活リズム・人間関係・通勤事情などの「地域特性」が変わることによる不安も大きいです。
「暮らしについていけるか」「孤立しないか」など、地域に馴染めるかどうかの不安が応募の足かせになりやすいのです。
地域紹介の機会提供
地域の暮らしを事前に知ってもらえるような取り組みが効果的です。
移住社員の座談会、生活紹介動画などを通じて、生活イメージを共有し、心理的なハードルを下げましょう。
家族・親の反対や地元志向
就職や転職の決断において、家族とくに親の意見が大きな影響を与えるケースは少なくありません。
特に新卒や若年層では、地元を離れることに対する親の反対や「地元で働くべき」という意識が根強く、意思決定を阻む要因になり得ます。
家族向け説明会や安心材料の提供
企業側は、保護者向けの情報提供・説明会を通じて、家族にも安心感を与える情報発信を行いましょう。
住宅支援や職場環境など、家族の視点でも安心できる要素を可視化することがポイントです。
人間関係への懸念
新しい環境に飛び込む際、「うまく馴染めるか」「誰に相談すればいいか」といった職場での人間関係への不安を感じる人も多くいます。
特に地方から都市部へ出てくる人は、孤立感や疎外感に対する不安を抱きやすい傾向があります。
職場内コミュニケーション支援やメンター制度
メンター制度や定期面談、オンボーディング支援の導入により、新入社員の不安を軽減できます。こうしたフォロー体制があることを求人情報で示すことで、応募者の安心感につながります。
地方採用についてよくある質問(FAQ)
地方採用についてよくある質問をまとめました。
地方採用って首都圏の人も対象になるの?
なります。
UターンやIターンを希望する人材も対象に含めることで、採用の幅を広げられます。
地元人材だけに頼るのは危険?
危険です。
人口減少や若年層の都市流出が進んでおり、地元人材だけでは人材確保が難しくなる可能性があります。
オンライン面接だけで地方採用は可能?
可能です。移動コストの削減にもなり、応募者にとってもハードルが下がります。
地方ならではの魅力って何をアピールすべき?
通勤の楽さ、生活コストの低さ、地域密着の働きがいなど、都市部にはない価値を伝えることがおすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、地方採用の現状や課題、成功のための戦略についてご紹介しました。
地方ならではの魅力を発信し、ペルソナ設計や多様な採用手法を取り入れることで、より効果的な採用活動が実現できます。
ぜひ本記事を参考に、自社に合った地方採用戦略を検討してみてください。







