

採用活動について自社で考え方は持っているが、「応募者数が想定より少ない」や「面接のタイミングで自社の強みと合致していない」など求めている人材と応募する人材のギャップに悩まされていませんか?
そこで、重要になるキーワードが「採用ブランディング」です。
本記事では、
- 採用ブランディングとは?
- 採用ブランディングのメリット
- 運用する5つのステップ
- 採用ブランディングの事例
などを解説していきます。
他社と差別化した求人や、ブランディングを行いたい企業の人事担当者様は必見の内容です。是非参考にしてください。
採用ブランディングとは?
採用ブランディングの目的は、求職者に「自社で働く価値」を感じてもらい、自社のファンを増やすことで、自社が求める人材を採用することです。広義のブランディングが商品やサービスに関する顧客向けの活動であるのに対し、採用ブランディングでは働く場としての自社を求職者に魅力的に感じてもらうことが重要になります。
具体的には、企業理念や理想の社員像、職場の雰囲気、実際に働く社員の人柄などを情報発信し、他企業と差別化を図り、独自の価値を形成することで長期的に活躍する人材の獲得を目指します。
採用ブランディングが必要な背景
少子高齢化による労働力減少や情報過多によるミスマッチ、それに伴う早期離職の増加を背景に、採用ブランディングは企業にとって必須の戦略です。多くの求人情報の中で注目を集めようと、企業が自社に都合の良い情報ばかりを発信すると、入社後のギャップが生じ離職につながりやすくなります。採用ブランディングを強化し、適切な情報提供で他社と差別化を図ることは、求職者の関心を引きつけて応募者を増やし、入社後のミスマッチを防いで離職を抑制するために不可欠です。
採用ブランディングを行う5つのメリット
採用ブランディングを行うことで見込まれるメリットについて5つ解説します。
企業の認知度が向上する
採用ブランディングを実施することで、これまで接点のなかった人材にも、自社の情報や魅力を伝える機会が増やせるため、企業の存在や価値に対する認知度の向上を見込めます。
企業の採用サイトやSNSなどでも採用ブランディングは行えるため、企業規模にかかわらず、求める人材に適した方法で情報発信が可能です。企業の認知度が高くない中小企業やスタートアップにおいても企業の存在や魅力を伝えやすくなります。
採用ブランディングとして企業情報を積極的に発信すれば、転職潜在層を含む多くの人材にリーチできます。企業の認知度が高まれば、将来の転職先候補として検討してもらえる可能性が高まります。
競合他社との差別化が図れる
求職者は業界・業種を絞って、転職活動することがほとんどです。そのため、同業他社との差別化を行い、求人票に反映できていない場合には、求人が埋もれてしまい、自社の求人が目につかないことになります。
しかし、採用ブランディングを行い、自社の魅力的な要素(例:働き方、給与、商品)を発信することで、他社とは差別化された求人を作成することが可能です。
あらゆる点を他社と異なるように設定するのではなく、同じ給与や同じ働き方の中でも、自社が他社より優れている部分や企業理念などを押し出しアピールすることで競合他社と差別化することが可能です。
求人への応募者の増加が見込める
採用ブランディングは、これまで接点がなかった層にも自社の魅力を伝え、企業の認知度向上につながります。採用サイトやSNSなどを活用すれば、中小企業やスタートアップといった企業規模に関わらず、目指す人材へ効果的に情報を発信することが可能です。これにより、転職を考えている潜在層にも広くアプローチでき、将来の転職先候補としての存在感を高められます。
ミスマッチを防ぎ、定着率の向上が見込める
採用ブランディングは、入社前後のギャップを埋めてミスマッチを防ぎ、人材の定着と活躍を促進します。また、エンゲージメントの高い人材の採用は、将来のリファラル採用にもつながり、採用コストの削減に貢献します。さらに、この取り組みは社員が自社の魅力を再認識する機会ともなり、帰属意識やモチベーションの向上も期待できます。
採用コストの削減が期待できる
採用ブランディングを行い、訴求したい求職者に向けて情報発信を適切に行うことで、自社の求める人材で母集団が形成されることが期待できます。適切な母集団形成が内定辞退や早期離職を防止することに繋がり、長期的な視点で、求人掲載費用や採用にかかるリソースなどのコストを削減可能です。
加えて、採用ブランディングを行うことで、リファラルやダイレクトリクルーティング、自社のWebサイトなどでも募集に成功する可能性が向上するでしょう。
採用ブランディングを行う5ステップ
採用ブランディングを行う5ステップを解説します。
採用目的の整理・自社分析
ず、欠員補充や事業拡大といった採用目的を明確にします。次に、自社の市場での立ち位置を把握するため、KJ法などのフレームワークを活用して自社の特徴を分析しましょう。その上で、「企業情報」「業務内容」「職場環境」の3つの観点から競合他社と比較し、自社の訴求ポイントを精査することが重要です。また、他社と比較した上で入社した中途社員に魅力や決め手を聞くことも、客観的な強みを知る上で有効です。
事業戦略に基づいた、人物像の明確化
事業戦略に基づいて求める人物像を具体的に設定し、社内で認識を統一することも欠かせません。その際は、まずスキルや能力面の基準を固めてから、価値観といった人間性を設定するのが効果的です。詳細な「ペルソナ」を設定することで、ターゲット像がより明確になります。
応募総数をただ増やすだけでなく、条件に合わない応募を減らし、選考の精度を高めることも有効な戦略です。そのためには、自社の立ち位置や求職者が企業選びで重視する点を深く理解することが求められます。
採用ペルソナの作り方とは?項目や作成のコツ、フレームワークを解説
採用コンセプトを策定する
採用ターゲットが明確になった後には、採用のコンセプトを策定するようにしましょう。採用コンセプトとは、採用活動に一貫性をもたらすためのメッセージや基本方針のことを指します。
「応募者に自社の強みをどのような言葉で伝えるか」を中心に、企業イメージの統一感を生まれさせるメッセージを考案しましょう。
メッセージ考案の際には、以下のポイントで企業の独自性をアピールしましょう。
- 企業理念
- 業務内容
- 働く人
- 社風
- 社内制度
採用コンセプトの変更が多くなると、採用活動への一貫性が低下し、採用ブランディングの効果が薄れるため、中長期的な視点で変更が少ないようなメッセージにすることが必要です。
発信する情報を精査し、チャネルを選択する
採用コンセプトに合わせて、情報を発信するチャネルを選択しましょう。企業が情報発信を行えるチャネルや形式には多様な種類があります。
具体的には、
- 採用サイト
- 採用パンフレット
- 採用イベント
- 会社説明会
- オウンドメディア
- SNS
などが挙げられます。
採用チャネルにより、求職者の特性に偏りが大きく生じます。そのため、自社がターゲットとする人材が多く存在するチャネルや媒体を狙って、情報を発信することが費用対効果を高めるためにも非常に重要です。
その中でも、企業が運営する求職者向けWebページやSNSは、企業の魅力を継続的に発信することができ、デザイン性などからも自社の特色が出せることから採用ブランディングの軸となるメディアとなるでしょう。
効果測定・運用を行う
採用ブランディングは、メッセージを公開した後にKPIなどを用いて効果を評価することが不可欠です。採用活動は長期的な視点が必要なため、アンケートや入社者へのヒアリング、エージェントからのフィードバックを基に効果測定を行いましょう。
また、採用市場や求職者のニーズは常に変化します。そのため、PDCAサイクルを回し、改善を続けることが重要です。その際、ブランドの根本的なコンセプトは変えずに、細かな修正(マイナーチェンジ)を繰り返していく運用が求められます。
採用ブランディングの発信に適した手段
採用ブランディングを発信する際に、企業が活用すべき発信手段について解説します。
自社採用サイト・ブログ
自社の採用サイトは、デザインやコンテンツを自由に構築できるため、採用ブランディングのメッセージや独自の魅力を伝えるのに最適です。
社員インタビューや顧客レビューといった、求人媒体では難しい内容を掲載することで、働く人のイメージや求める人物像を具体的に伝えられます。
成功の鍵は、サイトを継続的に更新し続けることです。カジュアルな話題から業績まで、多角的な情報発信でサイトを充実させ、企業の魅力を訴求し続けましょう。
採用SNS
採用活動においてSNSは、低コストで認知度を上げるのに有効で、動画を使えば企業理解を深める効果も期待できます。ただし、高頻度の更新や炎上対策、ターゲットに合わせた媒体選びが不可欠です。
転職情報サイトも重要な採用チャネルです。サイト内の会社紹介ページを充実させ、求職者を自社サイトへ誘導しましょう。その際、求人情報と自社紹介の両方に採用ブランディングの内容を反映させると、方針に一貫性が生まれ、求職者に安心感を与えることができます。
企業説明会・セミナー
企業説明会やセミナーは雰囲気作りを自社に合わせてブースづくりなどを行うことで、採用ブランディングを行うことが可能です。
選考を前提とした企業説明会だけでなく、交流会やセミナー、勉強会の開催を行うことで、転職潜在層へのアプローチが行えます。
カジュアルな場でも採用ブランディングを行うことが可能なため、自社のファン化を促し、採用につなげていくことが重要です。
採用ブランディングの事例
ここでは実際に採用ブランディングの事例を解説していきます。
第一カッター興業株式会社
コンクリート切断工事を専門とする第一カッター興業は、業務内容や高い技術力といった魅力が求職者に伝わりにくく、応募者が少ないという課題を抱えていました。
そこで「サムライ採用」というコンセプトを掲げ、採用動画を制作。スイカをウォータージェットで切断するなど、ユーモアを交えながら自社の技術力をシンプルかつ視覚的にアピールしました。
この動画により、社員の雰囲気や仕事内容への理解が深まり、肉体労働というイメージが強い事業でありながらも、会社自体に興味を持ってもらうきっかけ作りに成功しました。
三幸製菓株式会社
三幸製菓は、応募は多いものの、「新潟勤務の菓子メーカー」という点でのミスマッチが多発していました。
そこで「応募人数=採用人数」という理想を掲げ、採用ナビサイトの利用を停止。代わりに「おせんべいが好きか?」「新潟で働けるか?」という本質的な質問を投げかけ、応募者をタイプ別に分けて個別の選考フローを導入しました。
結果、応募者数は減りましたが、企業との相性が良い候補者に絞り込まれました。これにより、不採用通知の作成や面接にかかる時間が大幅に減り、採用活動全体の効率化に成功。今後はイベントなどを通じ、さらにマッチングの精度を重視していく方針です。
株式会社三井住友銀行
三井住友銀行は、高い知名度がありながらも、外資系企業などに比べて採用開始が遅いために、応募者が少ないという課題を抱えていました。
そこで、採用活動の「早期化」と「Web活用」を重視し、他社との差別化を図りました。具体的には、大学3年生向けの就職イベントの開始時期を2ヶ月前倒しし、開催回数も3割増やしました。
この「時期」に焦点を当てた戦略の結果、サマーインターンシップの応募者数は前年比4倍に増加。採用手法に行き詰まった場合、ターゲット層に合わせて活動のタイミングを見直すことも非常に有効な手段である、という事例です。
採用ブランディングについてよくある質問(FAQ)
採用ブランディングについてよくある質問をまとめました。
なぜ採用ブランディングが重要視されているのですか?
労働人口の減少や情報過多の時代において、求職者とのミスマッチを防ぎ、自社に合った人材を確保するために重要とされています。
採用ブランディングを行うことのメリットは何ですか?
企業の認知度向上、競合他社との差別化、応募者数の増加、入社後のミスマッチ防止、そして採用コストの削減といったメリットがあります。
採用ブランディングの主な発信手段には何がありますか?
自社の採用サイトやブログ、採用に特化したSNSアカウント、そして企業説明会やセミナーなどが主な発信手段として挙げられます。
まとめ
本記事では採用ブランディングについて解説しました。
採用ブランディングは採用活動についてコンセプトを決めるだけでなく、認知の方法や選考フローまで、一気通貫して行うことで、成立します。そのため、採用活動において、自社の考え方と乖離しているフローがある場合には変更する事が重要です。
加えて、採用ブランディングを行う場合には、求職者にアピールするコンテンツが必要になるために、訴求ができる適切なコンテンツの作成についても社員と協力し行うことが重要です。
関連記事

自社に最適な採用チャネルとは?種類と特徴、サービス選定のポイントを徹底解説!
- 採用代行

採用の歩留まりとは?項目例や5つの改善策を解説
- 採用代行
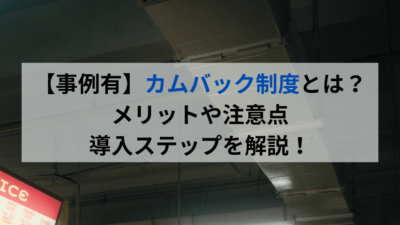
【事例有】カムバック制度とは?メリットや注意点、導入ステップを解説!
- 採用代行
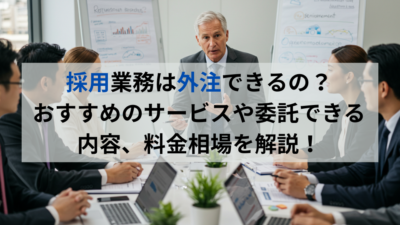
採用業務は外注できるの?おすすめのサービスや委託できる内容、料金相場を解説!
- 採用代行
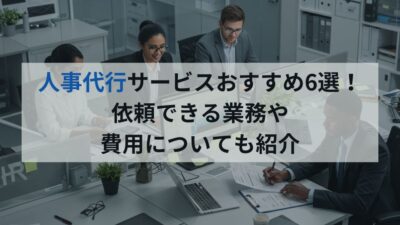
人事代行サービスおすすめ6選!依頼できる業務や費用についても紹介
- 採用代行

【2025年最新版】求人媒体のおすすめランキング10選|種類解説と主要サービスを徹底比較!
- 採用代行






