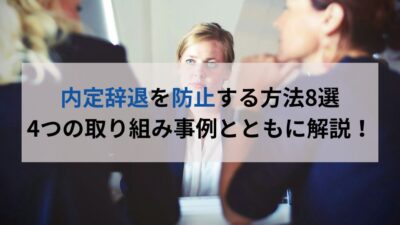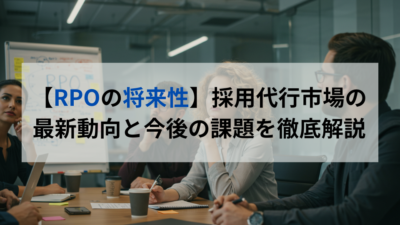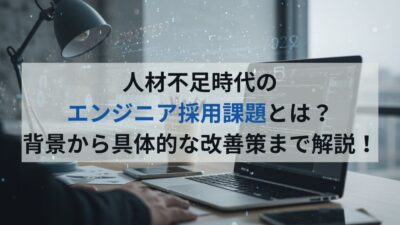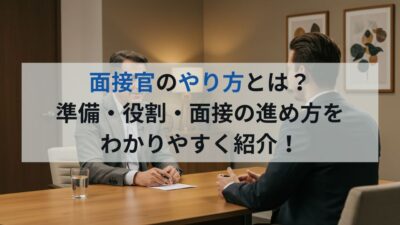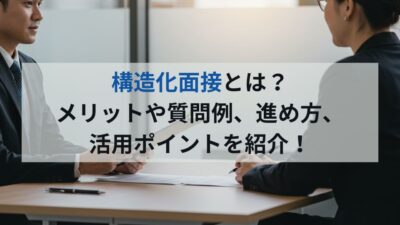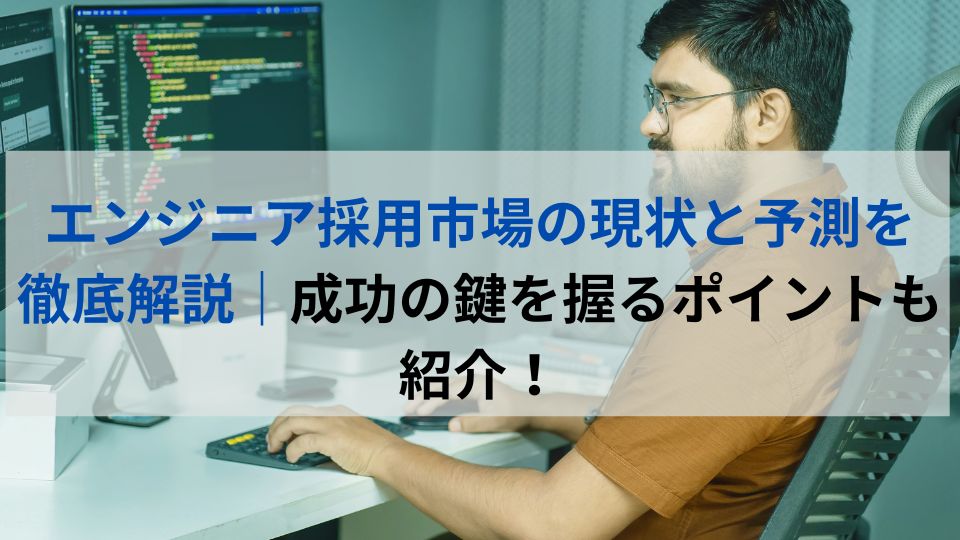
企業のDX推進が加速する現代において、エンジニアの採用は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。しかし、「なかなか採用が進まない」「応募が来ない」といった悩みを抱えている採用担当者の方も少なくありません。
本記事では、最新の市場データやトレンド、採用成功のポイントを徹底解説。これからのエンジニア採用を成功に導くためのヒントがきっと見つかるはずです。
最新データで見るエンジニア採用の未来予測
近年、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速し、エンジニアの採用は多くの企業にとっての課題となっています。
しかし、その一方で「なかなか採用が進まない」「応募が来ない」といった悩みを抱えている採用担当者の方も少なくありません。
ここでは以下の視点からエンジニア採用の将来を予測します。
- 有効求人倍率の推移から見る採用市場の現状
- 2030年にIT人材が約79万人不足する予測
- コロナ禍を経て加速するエンジニアの働き方の多様化
それぞれについて解説していきます。
有効求人倍率の推移から見る採用市場の現状
エンジニア採用の厳しさを物語る最もわかりやすい指標の一つが「有効求人倍率」です。
有効求人倍率とは、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標で、この数字が大きいほど企業にとって採用が難しい状況にあることを意味します。
IT・Webエンジニアの有効求人倍率は、全職種の平均を大きく上回る水準で推移しており、依然として高い値を示しています。
特に、Web系やSaaS(Software as a Service)開発に関わるエンジニア、データサイエンティスト、AIエンジニアなどの専門性の高い職種では、さらに倍率が高くなる傾向にあります。
このデータは、単に求人が多いというだけでなく、企業間で優秀なエンジニアを巡る競争が激化していることを示しています。求職者側は豊富な選択肢の中から企業を選ぶことができるため、企業は「ただ求人を出すだけ」では、もはや優秀な人材を獲得することが難しくなっているのです。
【参考文献】「有効求人倍率の受理地別値(公表値)と就業地別値(試算値)
」愛媛労働局
2030年にIT人材が約79万人不足する予測
経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」によると、このまま何も対策を講じなければ、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足すると試算されています。
出典:)「<https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf>IT人材需給に関する調査(概要) 」経済産業省
この試算の背景には、テクノロジーの進化とDXの加速に伴うIT需要の拡大が、人材供給のペースを上回っていることがあります。特に、AIやIoTといった最新技術に対応できる人材は、現在でも圧倒的に不足している状況です。
多くの企業がDXを経営戦略の中心に据える中、エンジニア人材の獲得は企業の成長を左右する重要な経営課題となりつつあります。この需給ギャップを理解することは、自社の採用戦略を練る上で不可欠です。
コロナ禍を経て加速するエンジニアの働き方の多様化
コロナ禍を経て、エンジニアの働き方は大きく変化しました。
リモートワークやフルフレックス制の導入が進み、働く場所や時間に縛られない働き方が一般的になりました。その結果、エンジニアは地理的な制約を受けることなく、全国、さらには海外の企業にも目を向けることができるようになりました。
また、副業やフリーランスとして複数のプロジェクトに携わるエンジニアも増加傾向にあります。
企業に所属しながらも、自分のスキルを複数の場所で活かしたいと考えるエンジニアが増えたことは、従来の正社員採用だけではターゲット層が狭まることを意味します。
企業は、こうした多様な働き方に対応できる柔軟な採用体制を構築することが求められています。求職者が何を重視しているのかを理解し、それに合わせた魅力的な労働環境や条件を提示することが、今後の採用成功の鍵となるでしょう。
エンジニア採用が難航する5つの根本理由
先ほどエンジニア採用市場の現状と予測について解説しましたが、多くの企業が採用に苦戦しているのには、以下の4つの理由が存在します。
- 企業の求めるスキルと求職者のスキルマッチングの難しさ
- 労働市場の縮小と少子高齢化
- フリーランスや副業人材の増加による採用ターゲットの減少
- 採用手法の多様化と複雑化
ここでは、採用担当者が直面する代表的な課題を5つの観点から深掘りしていきます。
企業の求めるスキルと求職者のスキルマッチングの難しさ
エンジニア採用が難しい理由の一つに、企業が求めるスキルレベルと、応募者のスキルレベルとの間にギャップがあることが挙げられます。
特に、DXを推進したい企業が求めるのは、単にコーディングができるだけでなく、ビジネス課題を理解し、自律的にプロジェクトを推進できる「即戦力」となる人材です。
しかし、そのような高いスキルを持つ人材は市場に少なく、複数の企業から引く手あまたの状態です。
一方で、未経験者や経験が浅いエンジニアは数多く存在しますが、育成体制が整っていない企業では採用に踏み切れないケースも少なくありません。結果として、企業は求める人材に出会えず、求職者側は自分のスキルが活かせる企業を見つけられない、というミスマッチが頻発しています。
この課題を解決するため、採用面接であらかじめミスマッチを防ぐ必要があります。そちらの方も紹介していますので併せて読んでみてください。
エンジニア採用で質問すべき事16選!優秀な人材を獲得する方法
労働市場の縮小と少子高齢化
日本の労働人口は年々減少しており、少子高齢化の進行はエンジニアの採用市場にも大きな影響を与えています。
経済産業省の予測にもあるように、IT人材の需要は拡大し続ける一方で、それを供給する労働力そのものが減少しているため、構造的な人材不足が常態化しています。
この状況下では、単に求人広告を出すだけでは、他の多くの企業に埋もれてしまい、候補者の目に留まることすら困難です。
この課題を解決するため、企業は、従来の採用手法に固執せず、労働人口が減少する中でも優秀な人材を獲得するための新たな戦略を立てる必要があります。
フリーランスや副業人材の増加による採用ターゲットの減少
近年、個人の働き方が多様化し、企業に属さずにプロジェクト単位で働くフリーランスや、本業の傍らで副業を行うエンジニアが増えています。このトレンドは、企業が正社員として採用できる人材の母数を相対的に減らしているという側面を持っています。
高いスキルを持つエンジニアほど、働き方の自由度を求めてフリーランスになる傾向が強く、企業は彼らを正社員として囲い込むことが難しくなっています。
この課題を解決するため、採用担当者は、正社員採用だけでなく、フリーランスや副業人材をプロジェクト単位で活用する選択肢も視野に入れる必要があります。
採用手法の多様化と複雑化
かつては「人材紹介会社に依頼する」といった採用手法が主流でした。
しかし、現在では「ダイレクトリクルーティング」「リファラル採用」「SNS採用」「採用広報」など、様々な手法が登場しています。
この結果、企業はより多くの候補者にアプローチできるようになった一方で、どの手法が自社の採用課題に最適なのかを見極めるのが難しくなりました。複数の手法を使いこなすには、専門知識やノウハウが必要となり、採用担当者の業務は複雑化しています。
この課題を解決するため、各手法の特徴を深く理解しておくことが不可欠です。
エンジニア求人倍率の推移と採用活動への影響
ここでは、エンジニア採用の難易度を測る上で重要な指標である「有効求人倍率」に焦点を当て、その推移が採用活動にどのような影響を与えているかを具体的に解説します。
有効求人倍率の高止まりは、単に採用が難しいというだけでなく、企業の採用活動そのものを根本から見直す必要性を突きつけています。
- エンジニアの求人倍率推移と高止まりの現状
- 求人倍率の高止まりがもたらす課題
現状と課題を抑え、エンジニア採用をよりいいものにしていきましょう
エンジニアの求人倍率推移と高止まりの現状
日本の有効求人倍率は、全職種平均が1倍台で推移しているのに対し、IT・Webエンジニアの分野では常にその数値を大きく上回っています。
特に、Web系エンジニアやSaaS開発者といった専門性の高い職種では、有効求人倍率が10倍を超えることも珍しくありません。
この傾向は、コロナ禍で一時的に採用活動が鈍化した時期もありましたが、その後は企業のDX投資が加速したことで再び上昇傾向にあります。求職者1人に対して10件以上の求人が存在する状況は、エンジニアが売り手市場であることを明確に示しています。
求人倍率の高止まりがもたらす課題
有効求人倍率の高止まりは、採用担当者にとって以下のような具体的な課題をもたらします。
- 応募者数の減少:候補者は引く手数多のため、特定の企業に応募するモチベーションが低くなりがちです。
- 選考辞退の増加:複数の企業から内定をもらうことが多いため、選考中に他社に決まってしまうケースが増加します。
- 採用コストの増大:一人あたりの採用にかかる費用(求人媒体費、エージェント手数料など)が高騰する傾向にあります。
- 入社後のミスマッチ:急いで採用を進めた結果、入社後のスキルや文化のミスマッチが発生し、早期離職につながるリスクが高まります。
これらの課題は、採用活動の効率を低下させるだけでなく、企業経営そのものに悪影響を及ぼす可能性があります。
エンジニア採用成功のために押さえるべきポイント
エンジニア採用の厳しい現状を乗り越え、優秀な人材を獲得するためには、従来の「待ち」の採用から脱却し、戦略的なアプローチが不可欠です。
多くの採用成功事例に共通する重要なポイントは以下の4つです。
- ペルソナ設計と採用ターゲットの明確化
- 選考プロセスにおけるスピードと候補者体験の向上
- 採用広報の強化と自社の魅力の言語化
- 自社エンジニアを巻き込んだ採用体制の構築
これらのポイントを押さえることで、自社の採用活動を根本から改善できるはずです。
ペルソナ設計と採用ターゲットの明確化
採用活動を始める前に、まず「どのようなエンジニアを採用したいのか」を徹底的に言語化することが重要です。
このプロセスを「ペルソナ設計」と呼びます。
以下のような要素も具体的に設定します。
- スキル・経験: 開発言語、フレームワーク、プロジェクト経験、マネジメント経験など
- 人物像: どのような性格か、どのような働き方を好むか、どのような価値観を持っているか
- 転職理由: なぜ転職を考えているのか、転職で何を叶えたいのか
- 情報収集源: どのような媒体やコミュニティで情報を探しているのか
ペルソナを明確にすることで、求人票のメッセージがより具体的になり、ターゲットに響きやすくなります。また、どのような採用手法が効果的か、という戦略も立てやすくなります。
選考プロセスにおけるスピードと候補者体験の向上
引く手あまたのエンジニアは、複数の企業から同時に選考を受けていることがほとんどです。
そのため、選考に時間がかかると、優秀な人材は他社に流れてしまう可能性が高まります。
選考プロセスのスピードは、採用成功率に直結します。
書類選考や面接のレスポンスを素早く行い、候補者を待たせないようにすることが重要です。
また、「候補者体験(CX)」も重要です。面接官の対応、質問内容、連絡の丁寧さなど、候補者が企業に対して抱く印象は、内定承諾率に大きく影響します。
特にエンジニアはロジカルな思考を好む傾向があるため、面接では具体的な質問を投げかけ、質問の意図を明確に伝えることが重要です。
採用広報の強化と自社の魅力の言語化
エンジニアは、入社後の働き方や技術的な環境を重視する傾向が強いです。そのため、「どのような開発環境か」「どのような技術スタックを使っているか」「どのような文化があるか」といった情報を積極的に発信することが、採用成功の鍵となります。
採用広報には、以下のような手法があります。
- テックブログ: 技術的な知見や開発の裏側を記事にして発信する
- SNS: TwitterなどのSNSで日々の業務や社内の雰囲気を発信する
- 登壇・イベント: 技術カンファレンスや勉強会に登壇し、企業の技術力をアピールする
- 採用サイト: 企業の技術や文化、働くメンバーのインタビューを掲載する
これらの活動を通じて、自社の魅力を言語化し、潜在的な候補者にアプローチすることが重要です。
自社エンジニアを巻き込んだ採用体制の構築
採用活動は、採用担当者だけが行うものではありません。特にエンジニア採用では、現場のエンジニアの協力が不可欠です。
現場のエンジニアは、候補者のスキルや技術的な適性を最も正確に見極めることができます。また、候補者も、将来の同僚となるエンジニアと直接話すことで、入社後のミスマッチを避けることができます。
面接官として参加してもらうだけでなく、採用広報の記事作成やイベント登壇に協力してもらうなど、積極的に採用活動に巻き込むことで、より質の高い採用を実現できます。
現場視点から見るエンジニア採用のコツ
エンジニア採用を成功させるためには、彼らが何を考え、何を求めているかを理解することが不可欠です。
単なる採用担当者としての視点だけでなく、現場のエンジニアの視点に立って採用活動を組み立てることで、応募者の心を掴むことができます。
ここでは、より実践的な「現場視点」での採用のコツを解説します。
- エンジニアが求める条件や心理の理解
- 候補者に刺さる求人票作成のポイント
- 書類選考や面接でスキルを正確に見抜く方法
それぞれについて解説していきます。
エンジニアが求める条件や心理の理解
多くのエンジニアが転職を考える際、年収や福利厚生といった待遇面はもちろんのこと、それ以上に「技術的な成長ができる環境か」「裁量権があるか」といった点に注目します。
彼らは、自分のキャリアプランを描き、その目標を達成できる企業を探しています。そのため、単に「給料が良い」というだけでなく、「この会社で働くことで、どのようなスキルが身につき、どのように成長できるか」を明確に提示することが重要です。
また、エンジニアは論理的な思考を好むため、曖昧な表現や抽象的な言葉は嫌います。「一緒に会社を大きくしよう!」といった精神論だけでなく、「どのような技術課題を、どのように解決していくのか」といった具体的なビジョンを伝えることが大切です。
候補者に刺さる求人票作成のポイント
求人票は、候補者が最初に企業と接する重要なツールです。エンジニアに響く求人票を作成するためには、以下のようなポイントを押さえる必要があります。
- 技術スタックを具体的に記載する: 利用しているプログラミング言語、フレームワーク、インフラ環境、開発ツールなどを具体的に記載することで、候補者は自分のスキルが活かせるかどうかを判断できます。
- 具体的な業務内容を記載する: 「〇〇サービスの開発」といった抽象的な表現ではなく、「ユーザー管理機能の新規開発」「パフォーマンスチューニング」など、具体的な業務内容を記載します。
- 裁量権や技術的なチャレンジを明確にする: 「要件定義から関われる」「最新技術の導入に積極的に取り組んでいる」など、エンジニアがやりがいを感じるポイントを強調します。
- チーム体制や文化を記載する: どのようなチームで働くのか、どのようなコミュニケーション文化があるのかを伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎます。
書類選考や面接でスキルを正確に見抜く方法
エンジニアのスキルを正しく見極めるには、現場のエンジニアによる技術的な評価が不可欠です。
書類選考の段階では、GitHubやポートフォリオのURLを提出してもらい、実際のコードや開発実績を評価することが有効です。
面接では、以下のような質問をすることで、候補者のスキルや思考プロセスを深く探ることができます。
「これまでで最も苦労した開発プロジェクトは何ですか?どのように解決しましたか?」: 課題解決能力や困難に直面した際の対応力を探ります。
「最近、個人的に興味を持っている技術は何ですか?なぜですか?」: 最新技術への関心や自律的な学習意欲を探ります。
「あなたのコードを誰かにレビューしてもらうとしたら、どの点を特に見てほしいですか?」: 自身のスキルに対する客観的な評価能力を探ります。
効果的なエンジニア採用手法
| ダイレクトリクルーティング | 人材紹介 | リファラル採用 | 採用代行 | |
|---|---|---|---|---|
| メリット | ・潜在層へのアプローチ ・コスト削減 ・採用ブランディング |
・工数削減 ・コスト削減 |
・ミスマッチ防止 ・コスト削減 |
・工数削減 ・採用力強化 |
| デメリット | ・工数の多様 ・ノウハウが必要 |
・高額な費用 | ・母集団の確保 | ・コストの増加 |
エンジニアの採用が難航する中、企業は従来の採用手法だけでなく、様々なアプローチを組み合わせることが求められます。
主な採用手法は以下の4つです。
- ダイレクトリクルーティング:企業から能動的にアプローチする手法
- 人材紹介(エージェント):専門家にスキル見極めを委ねる手法
- リファラル採用:社員紹介で優秀な人材を獲得する手法
- 採用代行(RPO):採用業務をアウトソースする手法
ここでは、それぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。
ダイレクトリクルーティング:企業から能動的にアプローチする手法
ダイレクトリクルーティングとは、企業が自らデータベースやSNSなどを活用して候補者を探し、直接スカウトメッセージを送る手法です。
メリットは、潜在層へのアプローチ: 転職意欲が低いものの、良い条件があれば話を聞いてみたいと考えている「転職潜在層」にアプローチできます。
コスト削減の面では、成功報酬型の人材紹介に比べ、一人あたりの採用コストを抑えられる可能性があります。
採用ブランディングの面では、 企業の採用担当者が直接コンタクトを取ることで、自社の魅力を丁寧に伝えることができ、採用ブランドの向上につながります。
デメリットは、工数: 候補者の検索、スカウト文の作成、返信対応など、多くの工数がかかります。また、スカウト文の作成や返信率を高めるためのノウハウが必要です。
人材紹介(エージェント):専門家にスキル見極めを委ねる手法
人材紹介会社は、企業が求める人材をヒアリングし、自社の登録者の中から条件に合う候補者を紹介してくれるサービスです。
メリットは、コストの面や工数の面で最小限に抑えることができる点です。
採用が成立するまで費用が発生しない「成功報酬型」が一般的で、無駄なコストを抑えられます。
事前にエージェントが候補者のスキルや志向性を確認してくれるため、面接に至るまでの工数を削減できます。
デメリットは、採用が成立した場合の成功報酬は高額になる傾向があります。
また、エージェントに依存しすぎると、自社の採用ノウハウが蓄積されにくいです。
リファラル採用:社員紹介で優秀な人材を獲得する手法
リファラル採用は、自社の社員に友人や知人を紹介してもらう採用手法です。
メリットは、 企業の文化や働き方をよく理解している社員からの紹介であるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、社員が定着する傾向が高いです。
また、外部サービスを利用しないため、採用コストを大幅に削減できます。
デメリットは、採用人数は社員のネットワークに依存するため、大規模な採用には不向きな点です。
採用代行(RPO):採用業務をアウトソースする手法
採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、採用活動の一部、またはすべてを外部の専門業者に委託するサービスです。
メリットは、工数が削減できる点です。 採用担当者がコア業務に集中できるため、業務効率が向上し、より質の高い採用活動が実現できる点です。
また、自社に採用ノウハウがなくても、代行サービスを通じて専門的な知見を得られます。
デメリットは、コストが大幅にかかるという点です。 業務範囲に応じて費用が発生するため、コストがかかります。
【2025年最新】エンジニア採用を成功に導くスカウトサービス7選 特徴・選び方・注意点も解説!
ITエンジニア採用の最新トレンド
エンジニア採用市場は常に変化しており、最新のトレンドを把握しておくことが、効果的な採用戦略を立てる上で不可欠です。
- ミドル・シニア層の採用
- 未経験者のポテンシャル採用
- 外国人エンジニア採用
ここでは、特に注目すべきITエンジニア採用の最新トレンドを紹介します。
ミドル・シニア層の採用
従来のエンジニア採用は若手中心でしたが、近年は40代、50代のミドル・シニア層のエンジニアを採用する企業が増えています。
彼らは豊富な開発経験やプロジェクトマネジメントの経験を持つため、即戦力として期待できるだけでなく、若手育成やチームリーダーとしての役割も担うことができます。
ミドル・シニア層の採用では、単なる技術スキルだけでなく、これまでの経験から得た課題解決能力やマネジメント能力を評価することが重要です。
未経験者のポテンシャル採用
深刻な人材不足を背景に、未経験者向けの研修プログラムや選考を設けて、ポテンシャル採用に注力する企業も増えています。
ITスクールや職業訓練校などで基礎スキルを習得した未経験者は、成長意欲が高く、自社の文化に馴染みやすいというメリットがあります。
未経験者のポテンシャル採用では、技術スキルだけでなく、論理的思考力やコミュニケーション能力、学習意欲といったポテンシャルを正しく見抜くための選考プロセスが重要です。
外国人エンジニア採用
グローバルな人材獲得競争が激化する中で、海外の優秀なエンジニアを積極的に採用する企業も増えています。
外国人エンジニアは、国内では希少な最新技術のスキルを持つことが多く、企業の技術力向上に貢献してくれます。
ただし、外国人エンジニアの採用では、ビザの申請手続きや、言語・文化の壁を乗り越えるためのサポート体制を整える必要があります。
「エンジニア採用」についてよくある質問(FAQ)
「エンジニア採用」についてよくある質問をまとめました。
エンジニアに響く求人票の書き方は?
求人票には、利用しているプログラミング言語や開発ツールを具体的に記載することが重要です。
また、裁量権の大きさや技術的なチャレンジなど、エンジニアがやりがいを感じるポイントを明確に伝えましょう。
採用活動でエンジニアに協力してもらうには?
現場のエンジニアは、技術的なスキルや適性を正確に見極めることができます。面接官として協力してもらったり、テックブログや社内イベントでの情報発信に参加してもらったりすることで、採用活動の質を高めることができます。
採用広報とは何をすればいい?
テックブログ、SNS、技術カンファレンスへの登壇などを通じて、企業の技術力や文化を発信する活動です。潜在的な候補者に自社の魅力を伝え、興味を持ってもらうことが目的です。
ペルソナ設計とは何?
「どんなスキルや経験を持ち、どんな価値観を持つエンジニアを採用したいか」を具体的に言語化するプロセスです。ペルソナを明確にすることで、求人メッセージがターゲットに響きやすくなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?本記事では、エンジニア採用市場の現状と課題から、具体的な採用成功のポイント、さらには最新トレンドまでを網羅的に解説しました。
エンジニア採用は、「ただ求人を出すだけ」では難しい時代になっています。市場の動向を正確に理解し、自社の魅力や強みを明確に打ち出し、多様な採用手法を戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。
本記事で紹介した内容を参考に、貴社のエンジニア採用が成功に繋がることを願っています。