
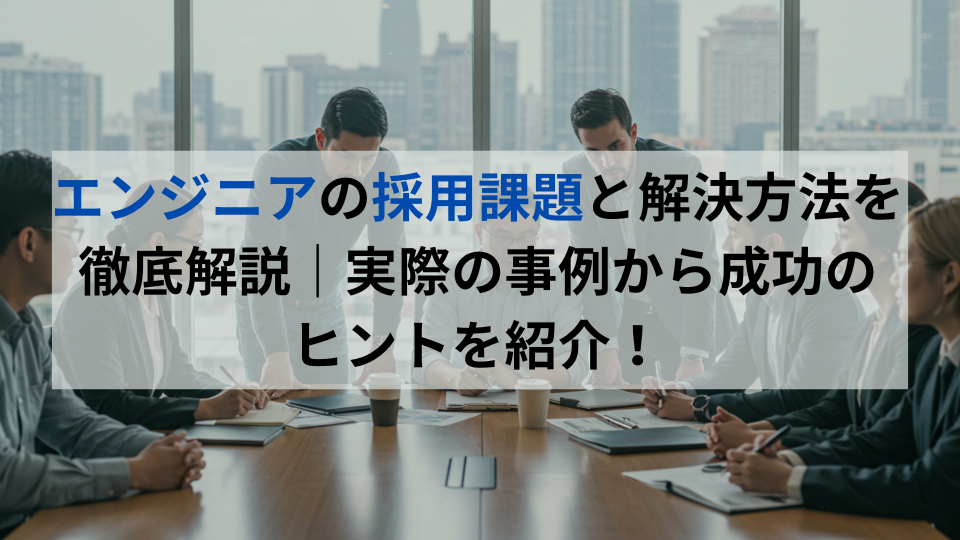
エンジニア人材の需要は高まり続ける一方で、採用市場は慢性的な人材不足と激しい競争にさらされています。
そのため、「なぜ採用がうまくいかないのか」「どうすれば定着までつなげられるのか」と悩む企業も少なくありません。
本記事では、エンジニア採用における課題の背景から、改善に向けた具体的な施策まで紹介します。

関連動画:なぜエンジニア採用は失敗するのか?母集団形成から内定までの落とし穴
エンジニア採用が難しい5つの背景
エンジニア採用が難航するのは、個別施策の巧拙だけが原因ではありません。市場全体の構造変化が積み重なり、企業努力だけでは埋めにくいギャップが生まれています。
ここでは、採用戦略を考える前提となる5つの背景要因を整理します。
- 国内エンジニア人口の不足
- 技術革新スピードの加速
- 企業間の採用競争激化
- 多様化する働き方・副業化
- 採用コストと単価の高騰
これらのポイントについて順に解説します。
国内エンジニア人口の不足
日本ではエンジニアの供給が需要に追いつかず、採用市場が逼迫しています。経済産業省の調査では、2030年までにIT人材が最大約79万人不足すると予測されています。 この不足は、企業にとってエンジニア採用がますます難しくなる大きな要因です。
背景として、少子高齢化による労働人口減少に加え、情報技術分野を志望する若年層の割合が低下しています。結果として、限られた人材の取り合いが激化し、採用競争のハードルは年々高まっています。
出典:)「IT人材需給に関する調査」経済産業省
技術革新スピードの加速
近年のIT分野では、AI、クラウド、IoTなどの技術革新が急速に進行しています。新しいフレームワークやツールが次々と登場し、短期間で業界標準になるケースも少なくありません。企業は常に最新の知識やスキルを持つ人材を確保する必要があります。
しかし、現場のニーズに即応できる人材は限られています。結果として、即戦力となるエンジニアの採用は難易度が高く、採用課題の大きな要因となっています。
企業間の採用競争激化
エンジニア需要は業種を問わず高まっており、IT専業企業だけでなくメーカーや小売業など非IT業界でも高度なIT人材を求める動きが拡大しています。
そのため、採用市場では異業種間での人材獲得競争が激化しています。
優秀な人材は複数の企業から同時にアプローチを受ける状況が常態化しています。結果として、オファー競争が激しくなり、採用コストや内定辞退率の上昇といった課題が発生しています。
多様化する働き方・副業化
リモートワークや副業解禁といった制度が広がり、エンジニアは働く場所や時間を自由に選べる環境を手に入れました。案件単位で働くフリーランスや副業として複数の企業に関わる人も増えています。
結果として、フルタイム正社員として働くことを希望しない人材が増加し、企業が求める就業条件と一致しないケースが多発しています。このミスマッチは、求人票を出しても応募が集まらない原因の一つとなっています。
採用コストと単価の高騰
希少な人材を確保するため、求人広告費やエージェント利用料、リファラルボーナスなどの採用関連コストが上昇しています。加えて、競合企業との取り合いによりオファー金額が高騰するケースも珍しくありません。
この結果、採用1名あたりのコストは年々増加しており、採用活動全体の予算圧迫につながっています。給与水準そのものも上昇傾向にあり、採用後の人件費負担も無視できない課題となっています。
エンジニア採用のコツは?5つのステップや成功事例を解説!
エンジニア採用で直面する6つの課題
エンジニア採用の現場では、多くの企業が共通して直面する課題があります。
これらの課題を理解し、的確に対策を講じることが採用成功への第一歩です。
- ターゲット人材像の不明確さ
- スキル・ポテンシャル見極めの難しさ
- 条件・待遇のミスマッチ
- 採用チャネルの活用不足
- 入社後の定着率の低さ
- エンジニア採用ノウハウの不足
これらの課題について、詳しく解説します。
ターゲット人材像の不明確さ
どんなスキルセットや経験年数の人材を採用するかが明確でないと、求人票やスカウト文面が抽象的になります。結果として、応募が集まりにくく、母集団形成に時間がかかってしまいます。
採用活動全体の方向性が定まらず、現場や経営層との認識ずれが発生しやすいのも課題です。
この状況では、現場が本当に必要とする人材を取りこぼすリスクが高まります。採用基準が曖昧なまま面接が進むと、評価が属人的になり、採用の質も安定しません。
スキル・ポテンシャルの見極め難易度
エンジニア採用では、技術力だけでなく学習意欲やチーム開発への適性など多面的な評価が求められます。ですが、評価指標や選考フローが整っていない企業も多く、候補者の力を正確に測れません。
結果として、優秀層を見逃したり逆にミスマッチ人材を採用してしまうリスクが高まります。
また、技術試験が複雑すぎると候補者が選考途中で離脱するケースも発生します。評価の仕組みが整っていないことは、採用スピードや歩留まりにも影響します。
条件・待遇のミスマッチ
エンジニアは年収だけでなく、技術スタックやリモート可否、働き方なども重視します。これらの条件が企業の提示内容とずれていると、面接段階で辞退されやすくなります。
最終的に内定承諾率が低下し、採用コストや工数がさらに増加するという悪循環に陥りがちです。
条件が合わないままオファーを出しても、入社後の不満や早期離職の原因になります。採用段階での情報共有や期待値調整が不足していることが課題といえます。
採用チャネルの活用不足
求人媒体、スカウト、エージェント、リファラルなど多様なチャネルがある中で、どこにどれだけ投資すべきか判断できない企業が少なくありません。担当者の経験や勘に依存しているケースも多く、効果的な運用ができていないのが現状です。
チャネル戦略がないと、限られた採用予算が分散し、母集団形成がうまくいかないという課題につながります。
さらに、運用体制が不十分だとスカウト送信や応募者対応が後手に回り、採用スピードが落ちます。結果として、優秀な候補者を他社に先に押さえられてしまうリスクが高まります。
入社後の定着率の低さ
採用段階で仕事内容や開発環境を十分に伝えられないと、入社後にギャップが発生します。その結果、早期離職やモチベーション低下につながるケースが目立ちます。
採用活動が短期的な充足だけで終わり、長期的な人材活躍につながらないのが大きな問題です。
特にエンジニアは技術的な成長機会やキャリアパスを重視します。これらが満たされないと定着率が下がり、再び採用コストが発生する悪循環に陥ります。
エンジニア採用ノウハウの不足
一般職の採用ノウハウはあっても、エンジニア採用特有のスキル要件や選考フロー設計に慣れていない企業は少なくありません。
技術面接の設計やスカウト文面の作り方が分からず、優秀な候補者に響くアプローチができていないことが課題です。
結果として、選考が長引いたり候補者体験(CX)が低下し、内定辞退や途中離脱につながることがあります。エンジニア採用に精通した人材や外部パートナーの活用が求められる局面です。
採用課題とは?調査分析方法、採用ターゲットに応じたポイントを解説
エンジニア採用課題を解決するための具体的アプローチ
エンジニア採用は多くの企業で難航しやすく、母集団形成や内定承諾率など様々な課題が存在します。
ここでは、先ほど整理した課題に対して効果的な解決策を具体的に紹介します。
採用ペルソナ設計から選考フロー改善、定着支援まで一連の打ち手を押さえることで、採用成功率を高めることができます。
- 採用ペルソナの明確化
- 技術選考フローの改善
- 条件提示と魅力訴求の最適化
- チャネル戦略と体制の整備
- オンボーディングと定着支援
- エンジニア採用ノウハウの獲得と共有
それぞれについて詳しく説明します。
採用ペルソナの明確化
求めるスキルセットや経験年数、人物像を具体的に言語化することで、求人票やスカウトの方向性が統一されます。これにより、応募の質と量が安定し、選考の歩留まりも改善します。
採用ペルソナが明確になると、現場と人事の認識ずれがなくなり、意思決定がスムーズになります。
さらに、ペルソナ設計は面接評価基準の策定にも役立ちます。評価が属人的にならず、採用の再現性と納得感が高まることが大きなメリットです。
技術選考フローの改善
コーディングテストや技術面接の設計を見直し、短期間で候補者を評価できる仕組みを作ることが重要です。面接官トレーニングを行い、評価基準を標準化することで選考のブレを防ぎます。
無駄なステップを削減し、候補者が離脱しないスピード感ある選考プロセスを実現しましょう。
また、オンライン面接や事前課題を組み合わせることで、面接官と候補者双方の負担を減らせます。結果として、選考期間の短縮と内定率向上が期待できます。
条件提示と魅力訴求の最適化
候補者が重視する給与、リモート可否、技術スタックを事前に把握し、提示内容を最適化します。条件交渉時には、柔軟な調整と将来の成長機会を提示することがポイントです。
オファー面談で企業の魅力や開発環境を丁寧に伝えることで、内定承諾率を高めることができます。
さらに、社員インタビューや技術ブログなどを活用し、プロジェクトの面白さやカルチャーを発信します。候補者の納得感が高まり、辞退リスクを抑えられます。
チャネル戦略と体制の整備
複数の求人媒体やスカウト、エージェントなどをどの割合で活用するかを設計し、全体戦略を明確にすることが重要です。単発的な運用ではなく、予算配分や優先度を決めたうえで動くことで、母集団形成の効率が上がります。
全体戦略と運用体制をセットで整えることで、チャネルごとの効果を最大化できるようになります。
さらに、チャネル運用を担当する人員や役割を明確化し、週次・月次でデータを振り返る仕組みを作ると効果的です。これにより、成果が出ているチャネルに投資を集中させ、採用全体のパフォーマンスを最適化できます。
オンボーディングと定着支援
入社直後の1〜3か月は立ち上がり支援の施策を用意し、スムーズに業務へ適応できる環境を整えます。メンター制度や定期的な1on1が有効です。
入社後のギャップを減らすことで、早期離職を防ぎ長期的な活躍につなげることができます。
さらに、キャリアパスや成長機会を明確に提示することで、モチベーションの維持につながります。結果として、定着率が向上し採用コストの再発生を抑えられます。
エンジニア採用ノウハウの獲得と共有
エンジニア採用では、求人票の書き方やスカウト文面、技術面接の設計など専門的なノウハウが求められます。社内でゼロから仕組みを作るのは難易度が高いため、知識を持つ人材を育成すると同時に外部の知見を活用しましょう。
採用代行(RPO)を活用すれば、ノウハウを持つプロが戦略設計から運用までを支援してくれるため、短期間で成果を出しやすくなります。
特に採用経験が浅い企業やスピード感が求められる状況では、外部パートナーと協働する方が効率的です。社内に知見を移管しながら改善を進めれば、次回以降の採用活動もスムーズに展開できます。
母集団形成を最大化する5つのチャネル戦略
エンジニア採用を成功させるためには、母集団形成が不可欠です。
ここでは、そのために有効な5つのチャネル戦略を紹介します。
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用制度
- SNS・コミュニティ活用
- イベント・ハッカソン出展
- フリーランス/副業人材プール
これらのチャネルについて、順に解説します。
ダイレクトリクルーティング
求人媒体やスカウトサービスを通じて、企業が候補者へ直接アプローチする手法です。転職潜在層にもアプローチできるため、母集団形成の幅が広がり、応募数を能動的に増やせるのが大きな強みです。
特にエンジニア採用では、転職市場に出ていない優秀層に接触できる点が大きなメリットとなります。
成果を出すためには、スカウト文面を候補者ごとにパーソナライズし、開発環境や技術スタックなど興味を引く情報を盛り込むことが重要です。送信対象を精査し、適切なタイミングでアプローチすることで返信率が向上し、母集団形成の停滞という課題を解消できます。
ダイレクトリクルーティングの市場規模を徹底解説!最新データと成長の背景
リファラル採用制度
社員からの紹介を通じて採用する仕組みです。企業文化や仕事内容を理解した社員からの推薦は、マッチ度の高い人材を確保できる可能性が高く、早期離職のリスクを減らせます。
さらに、通常の採用チャネルよりもコストを抑えられるため、採用単価の改善にもつながります。
効果を最大化するには、紹介インセンティブや表彰制度を整え、社員が積極的に動きやすい環境をつくることが重要です。紹介フローや必要情報を分かりやすく整理し、紹介がスムーズに行える仕組みを用意しましょう。
SNS・コミュニティ活用
Twitter(X)、LinkedIn、Qiita、Zennなど、エンジニアが集うオンライン空間を活用することで、候補者との接点を増やせます。積極的な情報発信により、採用広報と候補者接点の創出を同時に実現できます。
特に技術記事や開発ブログは、企業の技術スタックやカルチャーを伝える効果的な手段です。
継続的な運用が重要であり、社内エンジニアの協力を得てリアルな情報を発信すると信頼性が高まります。結果として、採用広報不足や企業認知度の低さといった課題を解消できます。
イベント・ハッカソン出展
ITカンファレンスやハッカソンに参加し、直接候補者と交流することで認知を広げます。技術ディスカッションや成果発表を通じて、企業の技術力や魅力を直接訴求できる点が大きな強みです。
その場で面談やカジュアル面接を設定することで、スピード感のある採用につなげられます。
また、社外での露出が増えることで技術ブランドの向上にも寄与します。結果として、応募者が自然と集まる仕組みをつくり、母集団形成の停滞という課題を解消できます。
フリーランス/副業人材プール
正社員採用だけにこだわらず、フリーランスや副業人材を積極的に活用する方法です。短期的なプロジェクト参画から長期契約への移行まで、柔軟な人材活用ができる点が特徴です。
人材不足や急な開発需要にも対応しやすく、採用難易度の高いポジションをカバーできます。
クラウドソーシングや副業マッチングサービス、専門エージェントを通じて人材を確保するのが効果的です。これにより、採用コストを抑えつつ必要なスキルをタイムリーに確保できます。
採用代行で実現できる課題解決ポイント
自社で取り組む採用施策だけでは、リソース不足やノウハウ不足で限界を感じる企業も多いのではないでしょうか。
そこで有効なのが、採用業務を専門家に委託する「採用代行(RPO)」です。
専任チームによるスピード採用やデータドリブンな運用最適化など、社内だけでは実現しにくい取り組みが可能になります。
- 専任チームによるスピード採用
- データに基づくチャネル最適化
- 候補者対応の品質向上
- 専門ノウハウと市場情報の活用
- ノウハウ移管による内製化支援
それぞれについて詳しく説明します。
専任チームによるスピード採用
採用代行では複数名の専任チームがアサインされ、媒体運用やスカウト送信を並行して実施します。これにより、求人掲載から母集団形成までの時間を大幅に短縮できます。
社内リソースだけでは実現しにくいスピード感で候補者接点を広げられるのが大きな強みです。
短期間で採用したいポジションや急募案件に特に有効です。結果として、競合に先行して優秀な人材を確保できます。
データに基づくチャネル最適化
採用代行は媒体別の応募数・通過率・コストを分析し、リアルタイムで予算配分を調整します。効果の低い媒体を止め、成果の出るチャネルへ投資を集中させます。
無駄なコストを削減し、採用単価を最適化できるのは外部パートナーならではです。
さらに、過去の運用実績や業界相場と比較して改善提案を行うため、意思決定が迅速かつ合理的になります。
候補者対応の品質向上
スカウト返信や面談調整など、対応スピードが採用結果に直結する業務をプロが代行します。候補者にとってストレスの少ないスムーズなコミュニケーションが可能です。
結果として候補者体験(CX)が向上し、面談設定率や内定承諾率が改善します。
社内の繁忙期でも候補者対応が滞らず、歩留まりの悪化を防ぐことができます。
専門ノウハウと市場情報の活用
採用代行は最新の採用トレンドや市場データを常に把握しており、戦略設計に反映できます。特に報酬相場や媒体効果の情報は社内だけでは得にくいものです。
外部の視点を取り入れることで、より現実的で成果の出やすい戦略を策定できます。
また、他社事例に基づいた施策提案も受けられるため、自社だけでは気づけない改善点を早期に発見できます。
ノウハウ移管による内製化支援
採用代行のプロセスやデータをマニュアル化し、社内メンバーに共有することで再現性を高めます。次回以降の採用では、自社だけでスムーズに運用できるようになります。
「外部に任せっぱなし」ではなく、社内の採用力を底上げする投資として活用できるのがポイントです。
結果的に、長期的には外部依存を減らし、コスト効率の良い採用体制を構築できます。
エンジニア採用課題を解決した事例
前章で紹介したように、採用代行(RPO)は母集団形成や選考スピード改善など、社内では難しい課題を解決する強力な手段です。
ここでは、実際にRPOを導入してエンジニア採用課題を解消した企業の事例を紹介します。
実際の成果や取り組み内容を知ることで、自社に導入した際の具体的なイメージが湧きやすくなります。
事例①:応募対応の遅れを解消し内定承諾率が改善
あるIT企業では、応募者への返信や面接日程の調整が後手に回り、優秀な候補者を他社に取られるケースが多発していました。採用代行を導入し、初期対応や日程調整を外部の専任担当者に委託することで、選考スピードが大幅に向上し、内定承諾率は20%アップしました。
対応の迅速化により候補者体験(CX)が改善し、企業への好印象も強化。採用担当者はコア業務に集中できるようになり、全体の採用効率が高まりました。
事例②:チャネル最適化で採用単価を大幅削減
人材紹介会社への依存が強く、採用コストが高止まりしていた大手IT企業。採用代行が媒体別の効果を分析し、スカウト文面の改善や送信対象の見直しを実施しました。
その結果、効果の薄い媒体を削減し、応募数を確保しながら採用単価を下げることに成功しました。
採用人数は計画を上回り、コストパフォーマンスが大幅に改善。ダイレクトリクルーティングの仕組みも社内に定着し、次回以降の採用も効率的に行えるようになりました。
事例③:ターゲット明確化で6か月間に7名採用
ある中小企業では、どんなスキルや経験を持つ人材を採るべきかが不明確で、求人を出しても適切な人材が集まりませんでした。採用代行がペルソナ設計からチャネル運用までを支援し、半年間でエンジニア7名の採用に成功し、急増した案件にも対応できる体制を構築しました。
さらにタレントプールも整備され、次回以降の採用スピードが向上。事業拡大計画がスムーズに進むようになり、経営陣の満足度も高まりました。
エンジニア採用の課題についてよくある質問(FAQ)
エンジニア採用の課題についてよくある質問をまとめました。
自社の採用課題はどう見極めればいい?
現状の応募数・内定率・辞退率などの指標を分析し、どこでボトルネックが発生しているかを特定します。
面接官や現場担当者へのヒアリングも有効です。
面接でスキルやポテンシャルを正確に評価するには?
現場エンジニアを同席させ、実務に即した質問やコーディングテストを実施します。
新しい技術への適応力や学習意欲も重要な評価ポイントです。
なぜエンジニア採用はこれほど難しいの?
国内エンジニア人口の不足と企業間の競争激化が主な理由です。
需要が供給を上回り、優秀な人材は複数社から同時にアプローチを受ける状況が常態化しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、エンジニア採用が難航する背景や、企業が直面しやすい課題、その具体的な解決策について紹介しました。
国内エンジニア人口の不足、技術革新の加速、採用競争の激化など、採用環境は年々厳しさを増しています。
さらに、ターゲット人材像の不明確さやスキル評価の難しさ、条件ミスマッチ、採用体制不足といった社内課題も採用成功を阻む要因です。
これらを克服するには、採用ペルソナの明確化、評価プロセスの精緻化、条件設定の見直し、採用ブランディング強化などの戦略が欠かせません。加えて、候補者体験を重視し、入社後の定着支援まで一貫した取り組みが必要です。
ぜひ本記事を参考に、エンジニア採用に取り組んでいただければ幸いです。
エンジニア採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
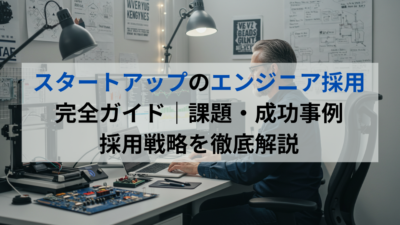
スタートアップのエンジニア採用完全ガイド|課題・成功事例・採用戦略を徹底解説
- エンジニア採用
- 採用代行
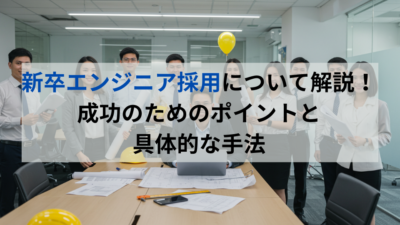
新卒エンジニア採用について解説!|成功のためのポイントと具体的な手法
- エンジニア採用

エンジニア採用のコツは?5つのステップや成功事例を解説!
- エンジニア採用
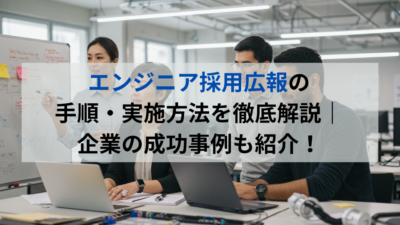
エンジニア採用広報の手順・実施方法を徹底解説|企業の成功事例も紹介!
- エンジニア採用
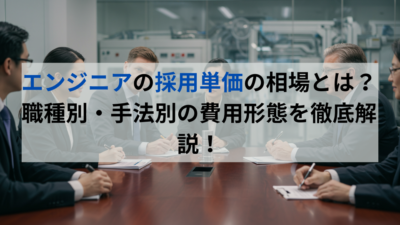
エンジニアの採用単価の相場とは?職種別・手法別の費用形態を徹底解説!
- エンジニア採用
コーポレート用アイキャッチのコピ-5-400x225.jpg)
エンジニア採用の基準を明確にする方法 注意点と運用のコツ
- エンジニア採用






