
コーポレート用アイキャッチのコピ-5.jpg)
エンジニア採用で「どんな人材を基準に採用すべきか」と悩む企業は多いです。スキルや経験はもちろん重要ですが、それだけでは入社後の活躍や定着を保証できません。背景には、採用基準が曖昧だとミスマッチや早期離職につながるリスクがあるという課題があります。
本記事では、エンジニア採用における採用基準の定義から、策定の具体的ステップ、経験者・未経験者ごとの見極めポイント、さらに基準運用の注意点まで解説します。
エンジニア採用における「採用基準」とは?なぜ明確化が必要なのか
IT技術の進化とともに、エンジニアの採用は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。しかし、「なんとなく優秀そうだから」「人柄が良さそうだから」といった曖昧な理由で採用活動を進めてしまうと、入社後のミスマッチや早期離職につながるリスクが高まります。
ここでは、まず採用基準の定義と、なぜエンジニア採用においてその明確化が不可欠なのかを解説します。なお、採用担当者の業務負担を軽減する手段として、エンジニア採用代行といったサービスも存在します。
エンジニア採用代行サービス5選!導入のメリットや選定時の注意点を解説
採用基準の定義と、明確化すべき理由
採用基準とは、「自社が必要とする人材の具体的な要件を定めたもの」です。スキルや経験といった技術的な側面だけでなく、仕事への取り組み方や、自社の文化に合うかといった人物像まで含めて定義します。
採用基準を明確化することで、以下のようなメリットが得られます。
- ミスマッチの防止:求める人物像が明確になり、選考の精度が向上します。
- 公平な選考:面接官によって評価がぶれることなく、客観的かつ公平な採用活動が可能になります。
- 採用コストの削減:採用基準に合わない応募者への対応工数を減らし、採用活動全体を効率化できます。
採用基準が曖昧な場合に発生する3つの問題点
採用基準が曖昧なまま採用活動を進めると、さまざまな問題が発生します。
入社後のミスマッチが発生しやすい
具体的な基準がないと、面接官の主観や感覚に頼った選考になりがちです。その結果、入社後に「思っていた業務と違う」「社風が合わない」といったミスマッチが起こり、早期離職につながるリスクが高まります。
実際に、厚生労働省の調査によると、自己都合退職者の約3割が、労働条件や仕事内容のミスマッチを理由に離職しています。採用基準を明確にすることは、このミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。
出典:)「令和4年雇用動向調査結果の概況」厚生労働省
採用に関わる社員間で認識のズレが生まれる
人事、現場のエンジニア、経営者など、採用に関わるメンバー間で「求める人物像」にズレが生じます。これにより、選考の途中で評価が分かれたり、適切な候補者を見逃したりする可能性があります。
応募者に自社の魅力が伝わらない
採用基準が明確でないと、求人票や面接で「どのようなスキルを持った人に来てほしいか」を具体的に伝えられません。結果として、応募者は「この会社で何ができるのか」「自分に合っているのか」を判断できず、優秀な人材からの応募を逃してしまうことになります。
、優秀な人材からの応募を逃してしまうことになります。
【5ステップ】エンジニアの採用基準を策定する具体的な手順
エンジニア採用で「応募が来ない」「入社後のミスマッチが多い」といった課題を抱えている企業は少なくありません。これらの課題を解決するためには、場当たり的な採用活動ではなく、明確な採用基準を策定することが不可欠です。
人材不足時代のエンジニア採用課題とは?背景から具体的な改善策まで解説!
ここでは、現場の意見を取り入れながら、体系的に進めるための具体的な5つのステップを解説します。
- 採用の目的・背景とペルソナを具体的に設定する
- 現場を巻き込み、必要なスキル・要件を定義する
- 必須条件と歓迎条件に分類し、優先順位を決める
- 採用市場・競合の状況を把握し、自社の立ち位置を理解する
- 決定した基準を求人票に落とし込み、応募者視点で作成する
以下で、これらについて詳しく解説いたします。
ステップ1:採用の目的・背景とペルソナを具体的に設定する
まず、なぜエンジニアを採用するのか、その背景にある事業課題を明確にしましょう。例えば、「新サービスの開発スピードを上げたい」「既存システムの負債を解消したい」といった具体的な目的です。
次に、その課題を解決できる「理想のエンジニア像(ペルソナ)」を詳細に設定します。スキルセットだけでなく、年齢、経歴、転職理由、仕事で重視することなど、多角的に人物像を定義しましょう。
ステップ2:現場を巻き込み、必要なスキル・要件を定義する
採用基準を策定する上で最も重要なのが、現場のエンジニアを巻き込むことです。彼らの意見を聞きながら、業務に必要な技術スタック、経験年数、開発手法などのハードスキルを洗い出しましょう。
また、チームでの協調性や、自律的に課題解決できる力といったソフトスキルも、現場の視点から具体的に定義することが重要です。
ステップ3:必須条件と歓迎条件に分類し、優先順位を決める
ステップ2で定義した要件を、「必須条件」と「歓迎条件」に分類します。必須条件は、業務を遂行する上で絶対に欠かせないスキルや経験です。一方、歓迎条件は、持っていると業務の幅が広がる、プラスαの要素として考えます。
この分類によって、選考のジャッジ基準が明確になり、採用活動の効率が格段に向上します。
ステップ4:採用市場・競合の状況を把握し、自社の立ち位置を理解する
設定した採用基準が、市場のトレンドや競合他社の採用状況と乖離していないかを確認しましょう。採用したいスキルを持つエンジニアの市場価値や、競合がどのような条件で募集しているかを分析することで、自社の求人票の魅力度を客観的に評価できます。
これにより、自社が採用市場においてどのようなポジションにいるかを理解し、現実的な採用戦略を立てることが可能になります。
ステップ5:決定した基準を求人票に落とし込み、応募者視点で作成する
最後に、決定した採用基準を求人票に落とし込みます。その際、単に条件を羅列するだけでなく、「なぜこのスキルが必要なのか」「入社後にどのようなキャリアパスが描けるのか」といった情報を付け加え、応募者が「自分ごと」として捉えられるように工夫しましょう。
応募者視点に立つことで、求人の魅力度が向上し、求める人材からの応募増加に繋がります。
経験者と未経験者で異なる採用基準のポイント
エンジニア採用では、経験者と未経験者で見るべきポイントが異なります。それぞれの特性を理解し、適切な採用基準を設定することが重要です。
経験者エンジニアの採用基準で重視すべきポイント
経験者エンジニアを採用する際は、技術的親和性の高さとエンジニアとして目指している将来像を重視します。
まず、自社の技術スタック(言語、フレームワークなど)と候補者の経験がどれだけ近いかを見極めることで、入社後の立ち上がりの速さが測れます。次に、候補者がどのようなキャリアを目指しているかをヒアリングし、自社で描けるキャリアパスと合致しているかを確認します。これにより、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
未経験者エンジニアの採用基準で重視すべきポイント
未経験エンジニアを採用する際は、現時点でのスキルよりも「ポテンシャル」を見極めることが重要です。
どのような方法で学習してきたか、そしてどれだけ自律的に学習を進められるかを見ます。また、作成したポートフォリオから、技術力だけでなく、課題設定力やアウトプットへのこだわりを測りましょう。さらに、コーディングテストや面接での受け答えから、物事を論理的に考え、課題解決に導く力があるかを見極めることも重要ですし。
技術スキル以外の「仕事への取り組み方」や「人物像」
経験者・未経験者問わず、技術スキルだけでなく、以下のようなソフトスキルも採用基準に含めることが重要です。
チームで円滑に業務を進めるために不可欠なコミュニケーション能力、技術のトレンドは常に変化するため、自律的に学び続ける姿勢があるかを見る学習意欲、そして自社の価値観や働き方に共感し、チームに馴染めるかを確認する自社へのカルチャーフィットです。
採用基準策定で避けるべき4つの落とし穴と対策
せっかくエンジニアの採用基準を策定しても、そのプロセスに落とし穴が潜んでいると、期待した効果は得られません。ここでは、多くの企業が陥りがちな4つの失敗例とその対策を解説します。
- 落とし穴1:人事・経営者だけで決定してしまう
- 落とし穴2:採用基準のハードルが高すぎる
- 落とし穴3:技術スキルのみに偏った基準設定
- 落とし穴4:市場相場を無視した採用基準
以下で、これらについて詳しく解説します。
人事・経営者だけで決定してしまう
現場の意見を入れずに採用基準を決めてしまうと、現場が求める人物像とズレが生じ、入社後のミスマッチに繋がりやすくなります。 対策として、必ず現場のエンジニアやマネージャーを巻き込み、実務に必要なスキルや人物像を定義しましょう。
採用基準のハードルが高すぎる
「スキルも経験もあって、リーダーシップもあって、人柄も良い」といった理想を詰め込みすぎると、応募者が極端に減り、採用活動が停滞してしまいます。対策として、採用基準を「必須条件」と「歓迎条件」に明確に分け、本当に譲れない要件を絞り込みましょう。
技術スキルのみに偏った基準設定
技術スキルが高いエンジニアでも、チームでの協調性がなかったり、自律的に動けなかったりすると、組織に馴染めない可能性があります。対策として、技術スキルだけでなく、コミュニケーション能力や自律性といったソフトスキルも、選考基準に含めることが重要です。
市場相場を無視した採用基準
市場の相場を把握せずに採用基準や待遇を決めてしまうと、優秀な候補者からの応募が得られなかったり、内定辞退が増加したりします。対策として、採用市場の動向を定期的にリサーチし、自社の求める人材の相場を把握した上で、適切な条件を設定しましょう。
採用基準を効果的に運用するための3つのポイント
せっかく策定した採用基準も、適切に運用しなければ意味がありません。ここでは、採用基準を最大限に活かすための3つのポイントを解説します。
エンジニア採用のコツは?5つのステップや成功事例を解説!
- ポイント1:各選考フェーズでの判断基準を明確にする
- ポイント2:採用に関わる社員全体で基準を共有し、浸透させる
- ポイント3:定期的にPDCAサイクルを回し、改善を繰り返す
以下で、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
各選考フェーズでの判断基準を明確にする
「書類選考」「技術試験」「面接」など、各選考フェーズで何を判断するかの基準を明確にしましょう。これにより、選考がブレることなく、一貫性のある採用活動が可能になります。
たとえば、書類選考では必須要件を満たしているか、経歴から技術的な親和性があるかなどを判断します。技術試験では実務に必要なスキルレベルに達しているか、コーディング力などを測り、面接ではチームフィットや仕事への取り組み方、コミュニケーション能力などを評価します。
採用に関わる社員全体で基準を共有し、浸透させる
採用基準は、人事担当者だけでなく、面接官を務める現場のエンジニア全員に共有する必要があります。基準の定義や見極め方について、研修やミーティングを通じて認識をすり合わせることで、面接官による評価のばらつきを防ぎ、公平な選考を実現できます。
定期的にPDCAサイクルを回し、改善を繰り返す
採用基準は一度作ったら終わりではありません。採用した人材の定着率や活躍度を定期的に検証し、基準が適切であったかを評価しましょう。その結果を基に、採用基準や選考方法を見直すPDCAサイクルを回すことで、より精度の高い採用活動へと改善を続けることができます。
「エンジニア 採用 基準」についてよくある質問(FAQ)
「エンジニア 採用 基準」についてよくある質問をまとめました。
エンジニア採用で重視すべき基準は何?
スキルや経験だけでなく、仕事への取り組み方や自社文化との相性といった人物像も含めて考えるのが重要です。
採用基準を明確化するメリットは?
ミスマッチの防止、公平な選考、採用コスト削減などにつながり、効率的で質の高い採用が実現できます。
経験者と未経験者で採用基準は違うの?
はい。経験者はスキル親和性やキャリア志向を、未経験者はポテンシャルや学習意欲を重視して基準を設けます。
採用基準は一度決めたら変えなくていい?
いいえ。定期的に検証し、定着率や活躍度を踏まえてPDCAを回し、改善していくことが大切です。
まとめ|エンジニア採用の基準を明確化し、最適な人材を迎え入れよう
いかがでしたでしょうか?本記事では、エンジニア採用における採用基準の定義や、基準を明確にする理由、策定の手順、注意すべき落とし穴や運用のポイントについて解説しました。
採用基準を明確にすることは、入社後のミスマッチを防ぎ、効率的かつ公平な採用を実現するために不可欠です。また、経験者・未経験者で重視するポイントを切り分け、現場の意見を取り入れながら柔軟に基準を設定することが成功の鍵となります。
本記事を参考に、自社に最適な採用基準を策定・運用し、長期的に活躍できるエンジニアを迎え入れてください。
エンジニア採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
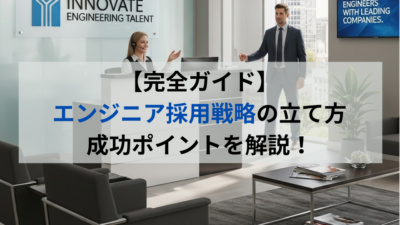
【完全ガイド】エンジニア採用戦略の立て方|成功ポイントを解説!
- エンジニア採用
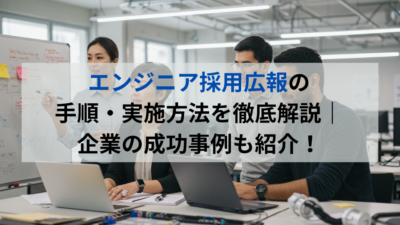
エンジニア採用広報の手順・実施方法を徹底解説|企業の成功事例も紹介!
- エンジニア採用
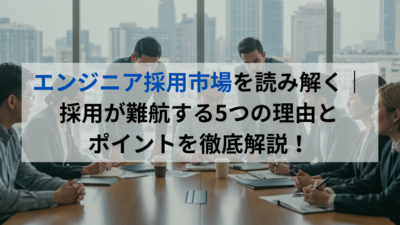
エンジニア採用市場を読み解く|採用が難航する5つの理由とポイントを徹底解説!
- エンジニア採用
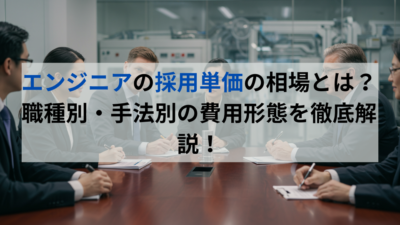
エンジニアの採用単価の相場とは?職種別・手法別の費用形態を徹底解説!
- エンジニア採用

エンジニア採用のコツは?5つのステップや成功事例を解説!
- エンジニア採用
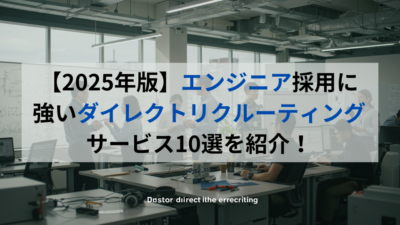
【2025年版】エンジニア採用に強いダイレクトリクルーティングサービス10選を紹介!
- エンジニア採用







