
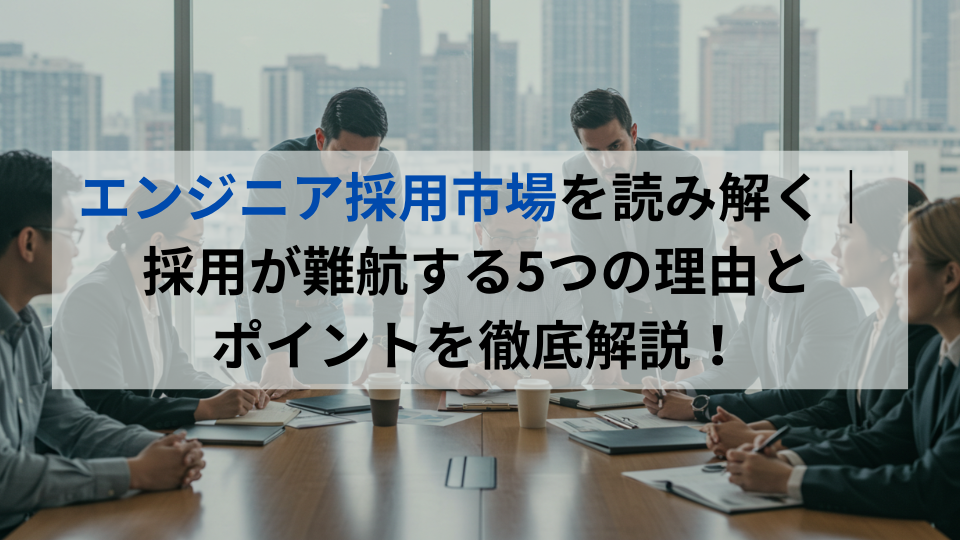
企業のDX推進が加速する現代において、エンジニアの採用は多くの企業にとって喫緊の課題となっています。しかし、「なかなか採用が進まない」「応募が来ない」といった悩みを抱えている採用担当者の方も少なくありません。
本記事では、最新の市場データやトレンド、採用成功のポイントを徹底解説。これからのエンジニア採用を成功に導くためのヒントがきっと見つかるはずです。
最新データで見るエンジニア採用市場
近年、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速し、エンジニアの採用は多くの企業にとっての課題となっています。
しかし、その一方で「なかなか採用が進まない」「応募が来ない」といった悩みを抱えている採用担当者の方も少なくありません。
ここでは以下の視点からエンジニア採用の将来を予測します。
- 有効求人倍率の推移から見る採用市場の現状
- 2030年にIT人材が約79万人不足する予測
- コロナ禍を経て加速するエンジニアの働き方の多様化
- 職種別・スキル別の需要動向
それぞれについて解説していきます。
有効求人倍率の推移から見る採用市場の現状
エンジニア採用の厳しさを物語る最もわかりやすい指標の一つが「有効求人倍率」です。
有効求人倍率とは、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標で、この数字が大きいほど企業にとって採用が難しい状況にあることを意味します。
IT・Webエンジニアの有効求人倍率は、全職種の平均を大きく上回る水準で推移しており、依然として高い値を示しています。特に、Web系やSaaS開発に関わるエンジニア、データサイエンティスト、AIエンジニアなどの専門性の高い職種では、さらに倍率が高くなる傾向にあります。
このデータは、単に求人が多いというだけでなく、企業間で優秀なエンジニアを巡る競争が激化していることを示しています。求職者側は豊富な選択肢の中から企業を選ぶことができるため、企業は「ただ求人を出すだけ」では、もはや優秀な人材を獲得することが難しくなっているのです。
【参考文献】「有効求人倍率の受理地別値(公表値)と就業地別値(試算値)」愛媛労働局
2030年にIT人材が約79万人不足する予測
経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」によると、このまま何も対策を講じなければ、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足すると試算されています。
この試算の背景には、テクノロジーの進化とDXの加速に伴うIT需要の拡大が、人材供給のペースを上回っていることがあります。特に、AIやIoTといった最新技術に対応できる人材は、現在でも圧倒的に不足している状況です。
多くの企業がDXを経営戦略の中心に据える中、エンジニア人材の獲得は企業の成長を左右する重要な経営課題となりつつあります。この需給ギャップを理解することは、自社の採用戦略を練る上で不可欠です。
出典:)「<https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf>IT人材需給に関する調査(概要) 」経済産業省
コロナ禍を経て加速するエンジニアの働き方の多様化
コロナ禍を経て、エンジニアの働き方は大きく変化しました。
リモートワークやフルフレックス制の導入が進み、働く場所や時間に縛られない働き方が一般的になりました。その結果、エンジニアは地理的な制約を受けることなく、全国、さらには海外の企業にも目を向けることができるようになりました。
また、副業やフリーランスとして複数のプロジェクトに携わるエンジニアも増加傾向にあります。
企業は、こうした多様な働き方に対応できる柔軟な採用体制を構築することが求められています。求職者が何を重視しているのかを理解し、それに合わせた魅力的な労働環境や条件を提示することが、今後の採用成功の鍵となるでしょう。
職種別・スキル別の需要動向
エンジニア採用市場では、職種やスキルによって需給バランスに大きな差が見られます。
特に、AIエンジニアやデータサイエンティスト、クラウド・セキュリティ系のエンジニアは求人需要が急速に高まっており、転職市場における売り手優位の状況が顕著です。
職種別年収データによると、プロジェクトマネジャーは平均年収約693万円、データサイエンティストは約556万円と、全体平均を上回る水準となっています。
一方で、システム開発・運用エンジニアやWebフロントエンドエンジニアは平均年収がやや低めで、スキルセットや経験年数によって年収格差が100万円以上になるケースも珍しくありません。このことは、エンジニア採用において「どの職種・スキルを狙うか」が採用難易度とコストに直結することを意味します。
【参考文献】「エンジニア職種別平均年収」Qiita Jobs
エンジニア求人倍率の推移と採用活動への影響
ここでは、エンジニア採用の難易度を測る上で重要な指標である「有効求人倍率」に焦点を当て、その推移が採用活動にどのような影響を与えているかを具体的に解説します。
有効求人倍率の高止まりは、単に採用が難しいというだけでなく、企業の採用活動そのものを根本から見直す必要性を突きつけています。
- エンジニアの求人倍率推移と高止まりの現状
- 求人倍率の高止まりがもたらす課題
それぞれについて詳しく説明します。
エンジニアの求人倍率推移と高止まりの現状
日本の有効求人倍率は、全職種平均が1倍台で推移しているのに対し、IT・Webエンジニアの分野では常にその数値を大きく上回っています。
特に、Web系エンジニアやSaaS開発者といった専門性の高い職種では、有効求人倍率が10倍を超えることも珍しくありません。
この傾向は、コロナ禍で一時的に採用活動が鈍化した時期もありましたが、その後は企業のDX投資が加速したことで再び上昇傾向にあります。求職者1人に対して10件以上の求人が存在する状況は、エンジニアが売り手市場であることを明確に示しています。
求人倍率の高止まりがもたらす課題
有効求人倍率の高止まりは、採用担当者にとって以下のような具体的な課題をもたらします。
- 応募者数の減少:候補者は引く手数多のため、特定の企業に応募するモチベーションが低くなりがちです。
- 選考辞退の増加:複数の企業から内定をもらうことが多いため、選考中に他社に決まってしまうケースが増加します。
- 採用コストの増大:一人あたりの採用にかかる費用(求人媒体費、エージェント手数料など)が高騰する傾向にあります。
- 入社後のミスマッチ:急いで採用を進めた結果、入社後のスキルや文化のミスマッチが発生し、早期離職につながるリスクが高まります。
これらの課題は、採用活動の効率を低下させるだけでなく、企業経営そのものに悪影響を及ぼす可能性があります。
採用市場から見るエンジニア採用が難航する5つの理由
エンジニア採用市場が活況を呈する一方で、多くの企業が採用活動の難しさを痛感しています。市場データが示す通り、求人倍率は依然として高水準で、候補者は複数の選択肢から企業を選べる状況です。
なぜこれほど採用が難航しているのかを理解することが、採用戦略の第一歩となります。
ここでは、採用担当者が直面する代表的な5つの課題を取り上げ、それぞれの背景と対応策を解説します。
- 企業の求めるスキルと求職者のスキルミスマッチ
- 労働市場の縮小と少子高齢化
- フリーランス・副業の拡大
- 採用手法の多様化と複雑化
- オファー競争の激化
ここでは、採用担当者が直面する代表的な課題を5つの観点から深掘りしていきます。
企業の求めるスキルと求職者のスキルミスマッチ
エンジニア採用で最も大きな課題の一つが、企業の求めるスキルと候補者側のスキルのズレです。新技術や開発環境の更新スピードが早く、企業が求めるスキル要件が常に高まり続けています。必須スキルと歓迎スキルを明確に切り分けないと、母集団が狭まり採用難がさらに深刻化します。
採用要件を厳しく設定しすぎると、潜在的に優秀な候補者を見逃すリスクもあります。企業は即戦力だけでなく、入社後の育成やスキルアップを前提とした採用基準を整えることが重要です。長期的な視点で人材育成と採用を連動させることが、採用成功率を高めます。
労働市場の縮小と少子高齢化
日本全体の労働人口は減少しており、理工系人材の新規供給も横ばい〜微減傾向です。中堅層エンジニアの絶対数が少なく、即戦力採用を狙う企業同士の競争が過熱しています。また、求人倍率は依然高水準で、採用リードタイムは長期化する傾向があります。
この人口動態の変化は今後も続くと予測されており、短期的な施策だけでは解決できません。企業はインターンやリスキリング支援を通じて若手を育成するなど、中長期的な人材投資が必要となっており、母集団形成と育成を一体化した人材戦略が求められています。
フリーランス・副業の拡大
高スキル人材の間では、案件単価や働き方を自由に選べるフリーランス・副業への流出が加速しています。その結果、正社員採用を前提とした母集団は縮小し、ターゲットが限定的になりつつあります。フルタイム正社員だけを想定した採用では、魅力を感じる候補者が減っています。
企業はプロジェクトベースの業務委託や副業人材の活用も視野に入れる必要があり、柔軟な雇用形態を導入することで、候補者層を広げることが可能になります。採用戦略と業務設計を連動させることで、優秀人材の確保と定着を両立できます。
採用手法の多様化と複雑化
求人媒体、スカウト、紹介、コミュニティ、SNSなど採用チャネルは多様化しています。チャネルごとのKPI管理やメッセージ設計が複雑化し、採用担当者の負荷が増大しており、一貫性のないメッセージやタイミングの遅れは歩留まり低下を招きます。
企業はATSやCRMツールを活用し、採用データを一元管理することで、候補者体験を最適化することで、チャネルごとの成果を最大化できます。採用チャネル戦略の設計と運用体制の強化が採用において重要となっています。
オファー競争の激化
候補者は複数社からオファーを受けることが一般的になり、条件や働き方を慎重に比較検討する傾向が強まっています。そのため、企業は報酬水準だけでなく、働き方の柔軟性や意思決定のスピードで競合と差別化する必要があります。選考が長引いたり提示条件が見劣りすると、他社に人材を奪われるリスクが高まります。
こうした状況を踏まえ、迅速なフィードバックやクロージングを意識した選考設計が求められます。加えて、リモート勤務や副業許可といった柔軟な制度を取り入れることで、オファーの魅力度を高めることができます。最終的には、スピードと条件面の最適化が優秀人材の獲得率を左右する重要な要素となります。
採用市場から見るエンジニア採用のポイント
エンジニア採用の厳しい現状を乗り越え、優秀な人材を獲得するためには、従来の「待ち」の採用から脱却し、戦略的なアプローチが不可欠です。
多くの採用成功事例に共通する重要なポイントは以下の4つです。
- ペルソナ設計と採用ターゲットの明確化
- 選考プロセスにおけるスピードと候補者体験の向上
- 採用広報の強化と自社の魅力の言語化
- 自社エンジニアを巻き込んだ採用体制の構築
これらのポイントを押さえることで、自社の採用活動を根本から改善できます。
ペルソナ設計と採用ターゲットの明確化
採用活動を始める前に、まず「どのようなエンジニアを採用したいのか」を徹底的に言語化することが重要です。
ペルソナ設計において以下のような要素を具体的に設定します。
- スキル・経験: 開発言語、フレームワーク、プロジェクト経験、マネジメント経験など
- 人物像: どのような性格か、どのような働き方を好むか、どのような価値観を持っているか
- 転職理由: なぜ転職を考えているのか、転職で何を叶えたいのか
- 情報収集源: どのような媒体やコミュニティで情報を探しているのか
ペルソナを明確にすることで、求人票のメッセージがより具体的になり、ターゲットに響きやすくなります。また、どのような採用手法が効果的かという戦略も立てやすくなります。
選考プロセスにおけるスピードと候補者体験の向上
引く手あまたのエンジニアは、複数の企業から同時に選考を受けていることがほとんどです。
そのため、選考に時間がかかると、優秀な人材は他社に流れてしまう可能性が高まります。
選考プロセスのスピードは、採用成功率に直結します。
書類選考や面接のレスポンスを素早く行い、候補者を待たせないようにすることが重要です。
また、「候補者体験(CX)」も重要です。面接官の対応、質問内容、連絡の丁寧さなど、候補者が企業に対して抱く印象は、内定承諾率に大きく影響します。
特にエンジニアはロジカルな思考を好む傾向があるため、面接では具体的な質問を投げかけ、質問の意図を明確に伝えることが重要です。
採用広報の強化と自社の魅力の言語化
エンジニアは、入社後の働き方や技術的な環境を重視する傾向が強いです。そのため、「どのような開発環境か」「どのような技術スタックを使っているか」「どのような文化があるか」といった情報を積極的に発信することが、採用成功の鍵となります。
採用広報には、以下のような手法があります。
- テックブログ: 技術的な知見や開発の裏側を記事にして発信する
- SNS: TwitterなどのSNSで日々の業務や社内の雰囲気を発信する
- 登壇・イベント: 技術カンファレンスや勉強会に登壇し、企業の技術力をアピールする
- 採用サイト: 企業の技術や文化、働くメンバーのインタビューを掲載する
これらの活動を通じて、自社の魅力を言語化し、潜在的な候補者にアプローチすることが重要です。
自社エンジニアを巻き込んだ採用体制の構築
採用活動は、採用担当者だけが行うものではありません。特にエンジニア採用では、現場のエンジニアの協力が不可欠です。
現場のエンジニアは、候補者のスキルや技術的な適性を最も正確に見極めることができます。また、候補者も、将来の同僚となるエンジニアと直接話すことで、入社後のミスマッチを避けることができます。
面接官として参加してもらうだけでなく、採用広報の記事作成やイベント登壇に協力してもらうなど、積極的に採用活動に巻き込むことで、より質の高い採用を実現できます。
エンジニア採用の最新トレンド
エンジニア採用市場は常に変化しており、最新のトレンドを把握しておくことが、効果的な採用戦略を立てる上で不可欠です。
- ミドル・シニア層の採用
- 未経験者のポテンシャル採用
- 外国人エンジニア採用
- 採用代行(RPO)の活用
ここでは、特に注目すべきITエンジニア採用の最新トレンドを紹介します。
ミドル・シニア層の採用
若手人材が不足する中、経験豊富なミドル・シニア層の採用に注目が集まっています。彼らは即戦力としてだけでなく、チームの育成やマネジメント面でも大きな価値を発揮します。
一方で、シニア層は転職動機やライフステージが多様化しており、条件交渉が複雑になる傾向があります。企業はキャリアパスや報酬設計を明確化し、候補者が長期的に働ける環境を提示する必要があります。こうした工夫が、採用後の早期離職を防ぐポイントとなります。
未経験者のポテンシャル採用
IT人材不足が深刻化する中で、ポテンシャル採用に踏み切る企業が増加しています。未経験者でも基礎的なプログラミングスキルや学習意欲があれば、育成前提で採用するケースが多くなっています。研修プログラムやOJTの仕組みを整えることで、早期戦力化が実現可能です。
一方で、採用後のフォローが不十分だと定着率が下がるリスクもあります。企業はメンター制度や学習支援をセットで用意し、スキル定着を後押しする必要があります。この際、ポテンシャル採用は短期的な即戦力よりも、中長期的な人材育成投資として考えると効果的です。
外国人エンジニア採用
グローバル採用もエンジニア不足を補う重要な選択肢となっています。特に海外拠点のリモート人材や、高度人材ビザを活用した採用が増えてきました。海外採用では言語だけでなく、文化・業務プロセスへの適応支援が成功の鍵となります。
企業はオンボーディングプログラムを整備し、コミュニケーションルールや評価制度を明確にすることが重要です。また、国際的な給与水準や福利厚生も意識し、競争力のあるオファーを提示する必要があります。こうした取り組みが、グローバル人材の定着と活躍を支えます。
採用代行(RPO)の活用
採用活動の工数やノウハウ不足を解消する手段として、RPO(採用代行)の活用が広がっています。求人票作成から母集団形成、スカウト送信、日程調整までを外部に任せることで、採用担当者は戦略立案に集中できます。特に採用リソースが限られるスタートアップや中小企業で、RPOは効果的な選択肢です。
また、RPOはデータ分析や施策改善の知見も提供してくれるため、採用のPDCAを回しやすくなります。外部パートナーと連携することで、短期的な採用成果だけでなく、中長期的な採用力の底上げも可能です。結果として、採用効率と候補者体験の両方を向上させることができます。
採用代行サービス完全ガイド|RPOの選び方・料金相場とおすすめ10社【2025年最新】
効果的なエンジニア採用手法
エンジニア採用の競争が激化する中、従来の求人媒体だけに頼った手法では十分な母集団を確保するのが難しくなっています。そこで、多くの企業がダイレクトリクルーティングや人材紹介、リファラル採用など、複数のチャネルを組み合わせて採用力を強化しています。
ここでは、それぞれの手法の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
主な採用手法は以下の4つです。
- ダイレクトリクルーティング:企業から能動的にアプローチする手法
- 人材紹介(エージェント):専門家にスキル見極めを委ねる手法
- リファラル採用:社員紹介で優秀な人材を獲得する手法
それぞれについて詳しく説明します。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が自らデータベースやSNSを活用して候補者を探し、直接スカウトメッセージを送る採用手法です。エンジニア採用では転職潜在層へのアプローチが可能で、他社に先駆けて優秀人材と接点を持てるのが大きな強みです。また、成功報酬型の人材紹介と比較して、一人あたりの採用コストを抑えやすい点も魅力です。
一方で、候補者検索やスカウト文作成、返信対応などに多くの工数が発生します。返信率を高めるためには、魅力的な文面や適切なタイミングの送信など、ノウハウの蓄積が不可欠です。効率化のためにATSや配信ツールを導入し、データ分析を活用して改善サイクルを回す企業が増えています。
人材紹介(エージェント)
人材紹介会社は、企業の求人条件をヒアリングした上で、登録者の中からマッチする候補者を紹介してくれるサービスです。特に経験豊富なエンジニアやミドル層の採用に強く、短期間で母集団形成と選考を進められる点が大きなメリットです。面接前にスキルや志向をエージェントが確認するため、ミスマッチも防ぎやすくなります。
一方で、採用が決定した際の成功報酬は年収の30〜35%と高額になる傾向があります。また、エージェントに依存しすぎると、自社内に採用ノウハウが蓄積されにくいというデメリットもあります。中長期的には、紹介チャネルと並行して自社採用力を強化する取り組みが必要です。
リファラル採用
リファラル採用は、自社社員が友人や知人を紹介することで候補者と出会う採用手法です。現場をよく知る社員が推薦するため、入社後のカルチャーフィットや定着率が高い点が大きな魅力です。さらに、外部広告費やエージェント手数料が不要なため、コスト面でも有利です。
ただし、社員のネットワークに依存するため、採用人数の上限が限られやすいという課題があります。活性化のためには、紹介インセンティブ制度や周知施策を整え、社員が紹介しやすい仕組みを作ることが重要です。ダイレクトリクルーティングや媒体活用と組み合わせることで、より強力な採用チャネルになります。
エンジニア採用市場についてよくある質問(FAQ)
エンジニアの採用市場についてよくある質問をまとめました。
エンジニアに人気の業界や職場環境って?
AI、SaaS、IoTなど技術革新の中心にある業界が特に人気です。リモートワークやフルフレックス制、モダンな開発環境を整えている企業も支持を集めています。
ベンチャー企業でもエンジニア採用は可能?
企業の成長性や技術スタックの魅力を伝えることで、ベンチャーでも優秀な人材を採用できます。特に裁量の大きさやスピード感に魅力を感じるエンジニアには刺さりやすいです。
採用活動がうまくいっている企業の共通点は?
ペルソナの明確化や選考スピード、魅力的な採用広報を行っている企業は成果を出しやすい傾向にあります。加えて、現場エンジニアの巻き込みや採用手法の柔軟性も重要です。
採用市場の動向はどこでチェックできる?
経済産業省や民間人材サービス会社が発表するレポートが参考になります。特に求人倍率や職種別動向のデータが有益です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、エンジニア採用市場の現状と課題から、具体的な採用成功のポイント、さらには最新トレンドまでを網羅的に解説しました。
エンジニア採用は、「ただ求人を出すだけ」では難しい時代になっています。市場の動向を正確に理解し、自社の魅力や強みを明確に打ち出し、多様な採用手法を戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。
本記事で紹介した内容を参考に、貴社のエンジニア採用が成功に繋がることを願っています。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
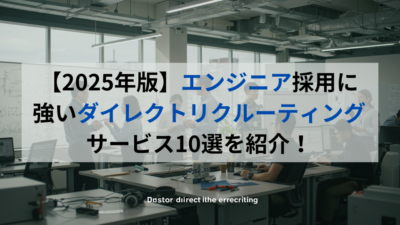
【2025年版】エンジニア採用に強いダイレクトリクルーティングサービス10選を紹介!
- エンジニア採用
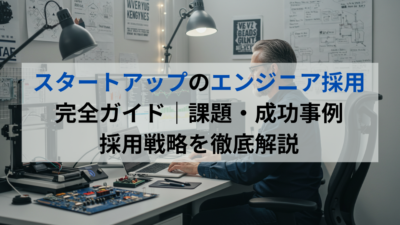
スタートアップのエンジニア採用完全ガイド|課題・成功事例・採用戦略を徹底解説
- エンジニア採用
- 採用代行
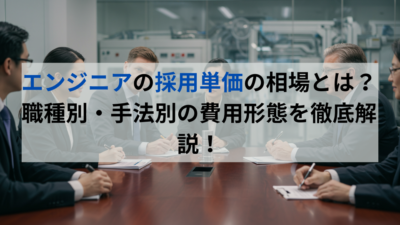
エンジニアの採用単価の相場とは?職種別・手法別の費用形態を徹底解説!
- エンジニア採用
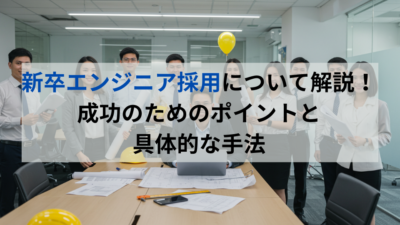
新卒エンジニア採用について解説!|成功のためのポイントと具体的な手法
- エンジニア採用
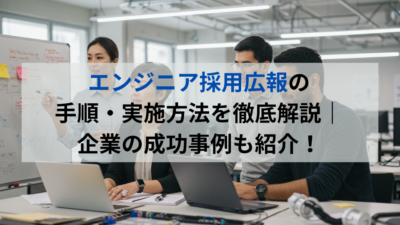
エンジニア採用広報の手順・実施方法を徹底解説|企業の成功事例も紹介!
- エンジニア採用
コーポレート用アイキャッチのコピ-5-400x225.jpg)
エンジニア採用の基準を明確にする方法 注意点と運用のコツ
- エンジニア採用







