
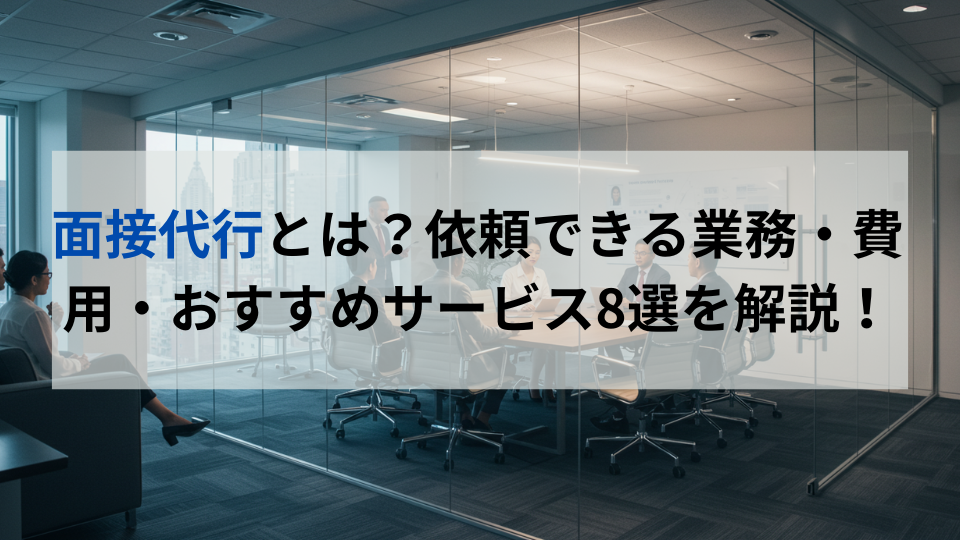
採用活動において「面接対応の工数が重い」「面接官のスキルにばらつきがある」といった課題を感じている企業は少なくありません。こうした背景から、近年注目されているのが「面接代行サービス」です。
人事リソースの不足や、面接の質を安定させたいというニーズに応える手段として、導入を検討する企業が増加しています。
本記事では、面接代行の仕組みや依頼できる業務内容、料金体系、メリット・デメリットまでを網羅的に解説し、貴社にとって最適な活用方法を見つけるヒントをお届けします。
関連動画:【採用担当必見】エージェント接点改善で応募数3倍|母集団形成術
面接代行とは何か?
企業の採用活動において、応募者との面接は最も重要なプロセスのひとつです。
しかし、近年では採用担当者のリソース不足や面接の属人化、面接件数の急増といった課題を抱える企業が増えています。こうした背景の中、「面接代行サービス」の活用が注目を集めています。
以下では、まず面接代行の基本的な仕組みと、なぜ今このサービスが選ばれているのかについて解説します。
- 面接代行サービスの基本的な仕組み
- 面接代行が注目される社会的背景
それぞれについて詳しく説明します。
面接代行サービスの基本的な仕組み
面接代行とは、企業の代わりに人材サービス会社やRPO事業者などの第三者機関が、面接業務を担うサービスです。企業は採用活動の一部、または全部を外部に委託することで、自社内の負担を軽減しながら、一定水準の面接品質を維持することができます。
具体的には、一次・二次面接の実施、評価シートの作成やフィードバック、さらには自社の面接官向けトレーニングの提供などが主な業務内容です。代行会社は事前に企業から採用ターゲットや評価基準についてヒアリングを行い、それに基づいて面接を進行します。
この仕組みによって、企業は面接にかかる時間やリソースを大幅に削減できます。加えて、評価観点の標準化が進むことで属人性の排除や採用精度の向上にもつながり、より効率的かつ戦略的な選考活動が可能になります。
面接代行が注目される社会的背景
面接代行サービスが注目される背景には、企業を取り巻く採用環境の変化が大きく関係しています。近年、多くの企業が人事部門のリソース不足に直面しており、限られた人員で採用活動のすべてを賄うことが難しくなっています。
特にIT業界やベンチャー企業では、候補者へのレスポンスの遅れが致命的な機会損失につながる場面も少なくありません。加えて、コロナ禍以降に進んだリモートワークの影響で、面接のオンライン化が進行し、それに対応できる面接官のスキルやノウハウの不足も深刻な問題として顕在化しています。
こうした状況の中で、プロの面接官による安定した対応や、候補者体験(CX)の質向上を図るために、面接代行サービスの導入が広がっています。今や面接代行は、単なる業務の外注ではなく、採用競争力を高めるための戦略的パートナーとしての位置付けを確立しつつあるのです。
面接代行で依頼できる業務内容
面接代行サービスは、単なる面接の代行にとどまらず、採用活動全体の効率化と質の向上に貢献する、戦略的なアウトソーシング手段です。企業のリソースやノウハウの不足を補いながら、選考プロセスをプロフェッショナルに運用できる点が大きな魅力です。
ここからは、面接代行サービスで具体的にどのような業務を依頼できるのか、5つの主要な項目に分けて詳しくご紹介していきます。
- 採用ターゲットやペルソナの設定支援
- 質問内容・評価基準の策定
- カジュアル面談から最終面接までの対応範囲
それぞれについて詳しく説明します。
採用ターゲットやペルソナの設定支援
面接代行を効果的に活用するためには、導入前の段階で「どのような人材を採用したいのか」を明確にしておくことが不可欠です。企業が求める人物像が不明瞭なままだと、面接の方向性がぶれ、評価の基準も曖昧になってしまい、結果として採用の質が低下するリスクがあります。
初期段階で企業と十分なすり合わせを行い、必要とされるスキルや経験の棚卸しに加え、性格や志向性といった人物面の特徴を明確にし、言語化していきます。
ターゲット像を明確化し、評価基準と紐づけておくことで、面接時の判断基準が統一され、選考のブレを防ぐことができます。結果として、ミスマッチの少ない採用が可能になり、面接代行サービスの効果を最大限に引き出すことができるのです。
質問内容・評価基準の策定
ターゲット設定が完了したら、それに基づいた「質問設計」と「評価基準」の策定を行います。ここでも代行会社が持つナレッジが活かされます。
たとえば、エンジニア採用であれば技術的質問だけでなく、チームワークや開発スタンスを引き出すための質問も組み込む必要があります。また、評価のばらつきを防ぐために、質問ごとのスコアリング方法を統一するケースも多く見られます。
こうした体系的な設計により、属人的で曖昧な面接からの脱却が可能となります。
カジュアル面談から最終面接までの対応範囲
面接代行では、初期接点のカジュアル面談から、最終フェーズの選考面接まで幅広く対応できます。対応範囲の一例としては、以下のとおりです。
- カジュアル面談:企業の魅力や働き方を伝え、興味を深める
- 一次~二次面接:ヒューマンスキルやスキルマッチを確認
- 最終面接:役員クラスが登場する前の足切り役としての機能
最近ではオンライン面接や動画面談に対応する代行会社も多く、場所・時間にとらわれない柔軟な面接運用が可能です。
面接結果のフィードバックと評価分析
面接が実施された後、面接代行会社はその内容をもとにフィードバックレポートを作成し、クライアント企業に提出します。
レポートでは、候補者の強みや懸念点、面接中の態度や回答傾向などが詳細に記載され、企業側は応募者ごとの特徴を客観的に把握できます。さらに、複数の候補者を並列で比較できるように構成されているケースも多く、最終選考時の意思決定をスムーズに進める助けとなります。
フィードバックを蓄積していくことで、採用全体の傾向や課題が見える化されていきます。その結果、面接手法や評価基準の見直しにもつながり、データに基づいた採用戦略の立案が可能になります。
面接官トレーニングや育成支援
面接代行を提供する企業の中には、単なる業務のアウトソーシングにとどまらず、クライアント企業の面接官育成を積極的に支援しているところもあります。
具体的には、模擬面接(ロールプレイ)を通じた実践的な指導や、面接後のフィードバックによるスキル向上のサポートが行われます。また、評価基準や質問設計の考え方を共有し、面接の構造化を促すことで、面接官が主観的な判断に頼らずに評価できる力を養っていきます。
こうした育成支援を通じて、企業は面接スキルを社内に蓄積し、将来的には外部に依存せずに自走できる面接体制を整えることが可能になります。結果として、持続的な採用力の強化と、より戦略的な人材獲得の実現に近づくのです。
面接代行サービスの3つの料金体系
面接代行サービスには、利用頻度や採用方針に応じて選べる複数の料金体系が用意されています。どのモデルを選ぶかによって、コストパフォーマンスや柔軟性が大きく変わるため、事前の理解と比較が欠かせません。
代表的な体系には、件数に応じて費用が発生する「従量課金型」、月ごとに一定料金で契約する「月額固定型」、採用が決定した時点で報酬が発生する「成果報酬型」の3つがあります。いずれも導入のしやすさや費用対効果に違いがあるため、自社の採用ニーズや体制と照らし合わせて選定することが重要です。
- 従量課金型
- 月額固定型
- 成果報酬型
以下では、それぞれの料金モデルの特徴や向いている企業像について、詳しく解説していきます。
従量課金型
従量課金型は、「面接1件あたり◯円」という形式で課金される最もシンプルな料金体系であり、月に数件〜十数件の面接実施を見込む企業に適しています。
面接1件あたり5,000円〜15,000円程度が相場となっており、面接件数が増えれば増えるほど総コストが上がります。逆に言えば「使った分だけ支払う」形になるため、予算管理しやすいのがメリットです。
突発的な採用増加や繁忙期対応など、スポット利用に向いている料金モデルと言えるでしょう。
月額固定型
月額固定型は、面接件数に関わらず、一定範囲の業務を毎月定額で依頼できる方式です。
費用の目安は月額20万円〜50万円程度が一般的で、以下のような企業に向いています。
- ・毎月一定数の採用を継続している
- ・面接の内製化に限界を感じている
- ・長期的なパートナーとして代行会社を活用したい
面接以外にも、事前ヒアリングや評価レポートの提出、面接官トレーニングなどをパッケージで依頼できるケースも多く、業務効率と費用対効果の両立を狙う企業にとって魅力的です。
成果報酬型
成果報酬型は、実際に候補者を採用できたタイミングで初めて費用が発生する形式です。費用は年収の15〜30%が目安とされており、採用単価が高くなりがちな中途採用などで利用されることが多いです。
このモデルの大きな魅力は、「採用できなければ費用がかからない」という点です。初期費用を抑えつつ、確実な成果を求めたい企業にとってメリットは大きいです。
一方で、成果に応じて費用が高騰するリスクもあるため、あらかじめ見積り条件や成果定義を明確にしておく必要があります。
面接代行サービスのメリット5選
面接代行サービスは、単なる業務のアウトソーシングにとどまらず、企業の採用力そのものを底上げする重要な施策です。面接のスピードや質が向上することで、採用成功率の改善や候補者体験(CX)の向上にもつながります。
特に、人的リソースの最適化や評価基準の統一といった課題を抱える企業にとって、面接代行は大きな効果を発揮します。採用活動の精度と効率を同時に高める手段として、多くの企業が導入を検討しています。
- 採用活動のスピードアップ
- 面接担当者の負担軽減
- 評価基準の可視化
- 面接ノウハウの獲得
- 選考辞退率・内定辞退率の改善
ここでは、面接代行サービスを導入することで企業が得られるメリットを5つに分けて、具体的に解説していきます。
採用活動のスピードアップ
面接代行サービスを導入することで、採用プロセスのスピードを大幅に向上させることができます。これは、社内のリソースや調整に依存する従来の面接運用に比べて、はるかに迅速かつ効率的な対応が可能になるためです。
たとえば、日程調整に時間がかかっていたり、面接の実施までに社内稟議や複数部署との連携が必要なケースでは、面接が後ろ倒しになりがちです。面接代行を活用すれば、ボトルネックを解消し、短期間で面接を実施できる体制を整えることが可能になります。
選考のスピードが上がることで、応募者の離脱を防ぎ、他社への流出リスクを軽減する効果も期待できます。結果として、採用成功率の向上や、必要なタイミングでの人材確保といった、企業にとって重要な成果に直結するのです。
面接担当者の負担軽減
面接は単に「話を聞くだけ」の業務ではなく、事前の準備や質問設計、面接後のフィードバック作成など、見えづらい部分で多くの工数を必要とする業務です。
面接代行を活用することで、こうした煩雑な面接関連業務を外部に任せることが可能となり、社内の担当者はより戦略的な業務に集中することができます。たとえば、採用全体の戦略設計や、入社後の定着率を高めるためのオンボーディング施策の企画、あるいは組織全体の人事制度の見直しなど、企業の成長に直結する取り組みに専念できる環境が整います。
業務の一部を切り出して外部に委ねることで、社内の人的リソースを有効活用しながら、業務効率と成果の両立を実現できる点は、面接代行サービスの大きな魅力のひとつです。
評価基準の可視化
採用の失敗要因としてよくあるのが、「評価者によって基準がバラバラ」なことです。
面接代行では、評価観点を定義しスコアリング方式で評価を行うため、どの候補者も公平な基準で比較できます。
たとえば「コミュニケーション力」や「論理的思考力」など抽象的な項目も、質問の構造化と評価項目の明文化によって、採点のばらつきを最小限に抑えることが可能です。
面接ノウハウの獲得
面接代行サービスを活用することで、単に業務を任せるだけでなく、社内の面接官が面接スキルを実践的に学ぶ機会を得ることができます。
たとえば、評価観点に沿って効果的な質問を投げかける方法や、候補者の本音を引き出すためのコミュニケーション術、判断に迷う候補者に対してどのように評価すべきかといったグレーゾーン対応の技術など、机上の研修だけでは身に付けにくい要素が多く含まれています。
結果として、面接を担う社員一人ひとりのレベルが上がり、組織全体の選考力や採用精度が向上します。つまり、面接代行の導入は外注による業務効率化にとどまらず、自社の採用力を内側から強化する取り組みとしても非常に有効なのです。
選考辞退率・内定辞退率の改善
面接の質が向上すると、候補者の満足度(採用CX)も高まり、選考離脱を防ぎやすくなります。
特に、カジュアル面談や初期面接での印象がよい場合、候補者の志望度は大きく左右されます。
また、代行会社による適切な動機形成や企業魅力の伝達も効果的です。
その結果、選考辞退率や内定辞退率の低下にも貢献します。
面接代行サービスのデメリットとリスク5選
面接代行は多くのメリットをもたらす一方で、導入の仕方を誤ると逆効果になる可能性もあります。特に採用は企業の根幹に関わる領域であり、外部委託によるリスクは見過ごせません。
そこで本章では、面接代行サービスを利用する前に把握しておくべき代表的な5つのデメリットと注意点を解説します。導入前にこれらを十分に理解し、対策を講じたうえで運用を設計することが、成功の鍵となります。
- 応募者との関係構築の難しさ
- 採用ミスマッチのリスク
- ハラスメント・違法リスクへの配慮
- 企業理解・魅力付けが弱くなる可能性
- コスト増の懸念
それぞれについて詳しく説明します。
応募者との関係構築の難しさ
面接は企業と応募者が直接コミュニケーションを取り、互いに理解し合う場でもあります。
しかし代行業者が介入することで、「会社の雰囲気が伝わらない」「誰と働くかがわからない」といった応募者側の不安につながることがあります。
特にカルチャーフィットが重視される職種や、社員との相性が採用基準となるポジションでは、代行によって関係性構築の機会が損なわれる可能性があります。
採用ミスマッチのリスク
面接代行を利用することで評価基準は標準化されますが、評価者と現場のイメージにズレが生じると、ミスマッチが起こるリスクもあります。
たとえば、現場が重視しているスキルやマインドセットが事前に代行会社へ正確に伝わっていなければ、本来合っていた人材を不合格にしてしまったり、逆に不適切な人材を通過させてしまうことも。
このようなケースを防ぐためには、評価基準やターゲット像のすり合わせ精度が極めて重要です。
ハラスメント・違法リスクへの配慮
面接代行サービスでは、候補者と直接接する場面が多いため、代行会社の対応ひとつで企業の印象が大きく左右されます。
たとえば、無意識のうちに年齢や性別に関する質問をしてしまったり、特定の価値観に偏った評価を行ってしまった場合、それが労働法令違反や差別的言動として指摘される可能性があります。
そのため、面接代行会社を選定する際には、実績や対応力に加えて、ハラスメント防止やコンプライアンスに関する教育体制が整っているかをしっかり確認することが非常に重要です。
企業理解・魅力付けが弱くなる可能性
本来、面接では応募者に対して企業の魅力やビジョン、社風などを直接伝えるチャンスでもあります。
しかし、代行会社がその役割を担う場合、情報が表面的になったり、企業の本質が伝わりづらくなることもあります。
特に成長フェーズの企業やカルチャー重視の採用を行う企業では、“想い”を直接届けることが採用成功の鍵となるため、代行依存には注意が必要です。
コスト増の懸念
当然ながら、面接代行サービスは外注費が発生します。
件数が多いと従量課金型では費用が膨らみ、月額契約でも面接数が少なければ割高になるケースもあります。
また、サービスによっては初期費用・設定費用が別途かかる場合もあるため、見積もり条件の確認と費用対効果の判断が求められます。
面接代行を利用するべき企業の特徴
面接代行サービスは、すべての企業にとって必須の仕組みではありません。しかし、人事リソースや面接体制に課題を抱える企業にとっては、採用活動の停滞を打破し、安定した選考運営を実現する有効な手段になり得ます。
特に「面接が回らない」「候補者対応が間に合わない」「選考がうまくいかない」といった課題を抱えている場合、面接代行によってスピード・質・体験の面で大きな改善が期待できます。
- 人事リソースが不足しており採用に手が回らない
- 面接スキルや評価基準が属人化している
- 選考辞退・内定辞退が多発している
- 面接プロセスが煩雑で時間がかかっている
- 大量採用や短期集中の採用プロジェクトがある
ここでは、面接代行の導入によって大きな効果が見込める企業の特徴を5つに整理し、それぞれの背景と対応策について詳しく解説します。
人事リソースが不足しており採用に手が回らない
急成長中のスタートアップや、少人数体制で運営される中小企業では、採用業務を専門で担当する人材がそもそもいなかったり、人事が他の業務と兼務しているケースが珍しくありません。
こうした状況では、面接日程の調整が後回しになったり、応募者への対応が遅れたりといった問題が顕在化しやすくなります。その結果、応募者の離脱や選考プロセスの停滞を招き、せっかくの採用機会を逃してしまうリスクも高まります。
このような場合、面接代行サービスを活用することで、業務のボトルネックとなっている面接対応を外部に切り出すことが可能です。結果として、応募者との接点を迅速に確保できるようになり、選考全体のスピードアップとともに、人材獲得の機会損失を最小限に抑えることができるのです。
面接スキルや評価基準が属人化している
面接が属人化している企業では、面接官のスキルによって評価が大きくばらつき、採用基準の統一が困難になります。
特に複数部門で面接を行う場合、評価観点が曖昧だと、結果としてミスマッチが頻発するリスクも。
面接代行では、評価基準の設計やスコアリングが標準化されているため、公正で一貫性のある選考を実現できます。
選考辞退・内定辞退が多発している
応募者が選考を辞退したり、内定を辞退する理由として多いのが、「レスポンスの遅さ」や「面接官の対応に不満を感じた」など、面接そのものに関するネガティブな体験です。
面接代行サービスでは、日程調整のスピードが上がるだけでなく、面接官による対応も均一化され、応募者への魅力付けメッセージも一貫性をもって伝えることができます。さらに、過去の面接データや候補者の声を活かした面接設計によって、応募者の満足度を高める工夫も加えられます。
このように、応募者体験(CX)を重視した面接運用が実現することで、選考途中での離脱を防ぎ、内定辞退のリスクも抑えやすくなります。結果として、選考通過率や内定承諾率の向上につながり、採用の質と効率を同時に高めることが可能になります。
面接プロセスが煩雑で時間がかかっている
複数の面接官や部門が関与する採用では、スケジュール調整や評価の集約が複雑になり、面接1件あたりのコストが増大します。
特に、複数回にわたる選考が必要な職種ではこの傾向が強くなります。
面接代行では、日程調整から面接の実施・レポーティングまでをワンストップで対応できるため、煩雑さの軽減と業務の見える化が図れます。
大量採用や短期集中の採用プロジェクトがある
繁忙期に向けた短期採用など、一定期間内に大量の人材を確保する必要がある場面では、社内のリソースだけでは面接対応が追いつかないケースが多く発生します。
面接代行サービスを一時的に導入することで、面接そのもののボトルネックを解消し、採用活動をスムーズに進行させることが可能になります。プロの面接官による対応は、候補者への印象も良く、短期間での選考精度を保ちながら、スピーディーな対応が期待できます。
結果として、社内業務への負荷を最小限に抑えつつ、採用目標の達成率を高めることができるのが大きな魅力です。柔軟性と即応性のある面接代行の活用は、時間に制約のある採用プロジェクトにおいて非常に有効な手段となります。
面接代行サービスの選び方5つのポイント
面接代行サービスは、導入すれば必ず成功するわけではありません。むしろ、選び方ひとつで採用成果に大きな差が生まれるといっても過言ではないでしょう。各サービスには対応範囲や強み、運用体制の違いがあるため、自社に合ったパートナーを見極める目が必要です。
そこでこの章では、面接代行を効果的に活用するために押さえておくべき5つの選定ポイントをご紹介します。失敗しない導入に向けたチェック項目としてぜひ参考にしてください。
- 代行内容と自社課題との適合度
- 柔軟性やカスタマイズ対応力
- 情報共有の方法と頻度
- 同業界・職種での実績
- サポート体制と信頼性
それぞれについて詳しく説明します。
代行内容と自社課題との適合度
面接代行サービスを選定する際、まず確認すべきなのが「その会社が提供する代行内容が、自社の抱える採用課題に適しているかどうか」という点です。ひとことで面接代行と言っても、その支援領域や専門性は会社ごとに大きく異なり、単なる面接の実施だけでなく、採用設計や評価項目の策定まで幅広くカバーしているケースもあります。
対応範囲が多様であるからこそ、まずは自社の課題を具体的に整理した上で、その課題にマッチした代行内容を提供している企業を選ぶことが求められます。
スピード重視なのか、面接の質に課題があるのか、あるいは人事リソースの補完が目的なのか。目的が明確であればあるほど、最適なパートナーを見極めやすくなります。したがって、導入前に「自社のニーズ」と「代行会社の提供内容」の適合度を見極めることが、成果につながる面接代行活用の第一歩となるのです。
柔軟性やカスタマイズ対応力
企業によって採用の進め方や評価の視点は大きく異なるため、面接代行サービスにも一定の柔軟性が求められます。テンプレート化された面接フローにそのまま当てはめるだけでは、自社の文化や要件とミスマッチを起こす可能性が高く、十分な成果は得られません。
たとえば、業種や職種によって求める人物像や質問内容は変わってきますし、急な面接数の増加にも対応できる体制が整っていなければ、選考が滞るリスクがあります。また、自社独自の評価基準を事前に共有し、それを面接プロセスに組み込めるかどうかも重要なポイントです。
こうした対応力の高い代行パートナーを選ぶことで、単なる業務のアウトソーシングにとどまらず、自社に最適化された面接体験の提供が実現できます。
情報共有の方法と頻度
面接代行サービスを円滑に機能させるには、代行会社との情報共有がスムーズかつ継続的に行われていることが不可欠です。
具体的には、連絡手段としてチャットツールや定例ミーティングをどう活用するか、面接評価の共有はどのフォーマット・頻度で行われるのかといった運用面の確認が重要です。また、候補者情報を扱う上で、セキュリティ体制が万全かどうかも必ずチェックすべきポイントです。
特にスピード感が求められる採用現場では、やり取りのタイムラグが命取りになることもあります。したがって、リアルタイムで柔軟に情報共有できる体制が整っているかは、代行会社を選ぶうえでの重要な判断基準になります。
同業界・職種での実績
面接における評価ポイントは、業界や職種によって大きく異なります。そのため、代行会社を選定する際には、自社と類似した業界・職種での支援実績があるかどうかを必ず確認する必要があります。
たとえば、ITエンジニアの採用では技術的な知見が求められますし、販売・接客業のような大量採用ではスピードと効率が重視されます。また、管理職以上のハイレイヤー人材を対象とした場合には、マネジメント経験や判断力を見極める高度なヒアリング力が必要になります。
実績が豊富な代行会社であれば、業界特有の面接傾向や評価基準に精通しており、より的確な人材の見極めと質の高い面接対応が期待できます。
サポート体制と信頼性
面接代行サービスは、一度導入すれば単発的な利用では終わらず、中長期的にパートナーシップを築くケースも多く見られます。そのため、安心して任せられる体制が整っているかどうかは、代行会社選びにおいて極めて重要な判断軸となります。
具体的には、契約時点で専任の担当者が付き、日常的なコミュニケーションや定例報告を通じて進捗を共有してくれるか。また、面接の質や運用方法についての改善提案があるかどうかなど、運用中のサポート体制が充実しているかを確認することが欠かせません。
特に、RPO(採用業務代行)を専門に行っているような企業は、これらの運用体制が整っている傾向が強く、安定的かつ高品質なサポートの提供が期待できます。
おすすめ面接代行サービス会社8選
面接代行サービスを検討する際には、対応範囲や実績、料金体系が大きく異なるため、自社の課題に合ったサービスを選ぶことが重要です。
ここでは、信頼性や導入実績が豊富で、多様なニーズに応えられるおすすめの面接代行会社8社を厳選して紹介します。
- 株式会社uloqo
- 株式会社ネオキャリア
- パーソルキャリア株式会社
- 株式会社HRアソシエ
- 株式会社トライアンフ
- 株式会社アールナイン
- 株式会社リンクアンドモチベーション
- 株式会社ONE
それぞれの特徴と費用感を比較し、自社に最適なパートナー選びの参考にしてください。
株式会社uloqo
出典:)株式会社uloqo(旧:プロジェクトHRソリューションズ)
- 候補者対応や面接官調整を含む「面接業務の丸ごと代行」が可能
- 一次〜最終面接まで幅広く対応し、企業ニーズに合わせてカスタマイズ
- 面接官トレーニングやフィードバック設計など採用力強化にも寄与
- 採用代行全般で培ったノウハウを活かし、候補者体験の最適化を重視
- 月額30万円(税抜)〜
- 依頼範囲(面接設定のみ/実施・フィードバックまで)に応じて変動
- 詳細な見積りは個別相談にて提示
株式会社ネオキャリア
出典:)株式会社ネオキャリア
- 年間10,000社以上の導入実績を持つ採用代行サービス(RPO)
- 中途、新卒、アルバイトなど幅広い採用形態に対応
- コールセンター完備で、土日祝日・夜間の求職者対応も可能
- 担当企業の課題をヒアリングし、採用戦略まで含めたカスタマイズ提案を実施
- 成功報酬ではなく、ランニング費用と初期費用のみの料金体系(成果報酬は不要)
- 月額35万円〜(中途・アルバイト採用代行・ベーシックプラン):contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 月額45万円〜(最終選考動員まで含むプラン):contentReference[oaicite:7]{index=7}
- オーダーメイドプラン:企業の採用目標や対応範囲に応じて要見積もり:contentReference[oaicite:8]{index=8}
パーソルキャリア株式会社
出典:)パーソルキャリア株式会社
- 中途採用を中心とした「総合型RPO」で、戦略立案から実行支援まで一貫対応
- 転職サービス「doda」で蓄積された豊富な市場知見・ノウハウを活用した支援
- 採用戦略設計、母集団形成、応募受付、書類選考、面接フォローなど幅広く支援
- 中途採用に加え、新卒・パート・アルバイト採用にも対応可能
- プライバシーマーク取得により、安心・安全な情報管理体制を確保
- オーダーメイド型:企業ニーズ・業務範囲に応じた個別見積もり(詳細はお問い合わせ)
株式会社HRアソシエ
出典:)株式会社HRアソシエ
- リピート率90%以上の実績を誇り、採用活動の継続的な成功と信頼を実現
- 戦略立案から説明会・面接、面接官研修、内定者・新入社員向けトレーニングまで一貫対応
- 定量・定性のデータ分析に基づき、課題を先回りして提案するスタンス
- 導入予算の目安は50万円~(サービス内容・期間により変動)
- 具体的な費用は、依頼事項に応じて個別見積もり
株式会社トライアンフ
出典:)株式会社HRアソシエ
- 採用課題に合わせて、戦略立案から実行まで一貫して伴走するRPOサービス
- 「リモート型」と「常駐型」の2種類から運用スタイルを選択可能
- 業務プロセス設計、母集団形成、書類選考、面接代行、内定者フォローなど採用工程全体に対応
- 800社以上の幅広い業界での導入実績に基づく高品質な支援体制
- 採用業務の属人化解消や可視化による業務効率・安定性の向上を実現
- 料金は「お問い合わせ」ベースで、企業毎の要件に応じた個別見積もり
株式会社アールナイン
出典:)株式会社アールナイン
- 15年以上・延べ700社以上の導入実績、30,000件以上の採用実務経験を誇る信頼体制
- 採用のプロが面接代行を実施し、候補者の志望度向上や辞退率低減に貢献
- 専属担当者が案件ごとに一貫対応し、密なコミュニケーションを確保
- スポット依頼〜継続的支援まで、ニーズに応じた柔軟なプラン設計が可能
- 「人事ライト」プラン:月額40万円〜
- 「人事アドバンス(新卒・中途)」プラン:月額75万円〜
- その他内容に応じて柔軟に対応(個別見積もり)
株式会社リンクアンドモチベーション
- 採用実務を「オペレーション」ではなく「コミュニケーション」と捉え、採用チームと⼀体となって伴走するコンサルティング型RPO
- 採用構想から実行までワンストップで支援し、リアルタイムPDCAによる進捗の見える化と軌道修正
- 「モチベーションエンジニアリング」を活用し、応募者と企業の関係構築を重視
- 母集団形成や動機醸成、アセスメント、応募者対応、フォローアップなど幅広く対応
- 採用活動後のレビュー支援(定量・定性分析、総括資料の提供)も実施
- 料金は公開されておらず、企業のニーズに応じて個別見積もり(お問い合わせベース)
株式会社ヒューマントラスト
出典:)株式会社ヒューマントラスト
- 企業に常駐し、採用業務(書類選考、面接代行、合否連絡等)を包括的に支援
- 採用後の内定者フォローまで対応するトータルサポート体制
- 人材派遣・紹介・アウトソーシングなど豊富な総合人材サービス基盤を保有
- 料金は公開されておらず、企業毎のニーズに応じて個別見積もり(要問い合わせ)
面接代行についてよくある質問(FAQ)
面接代行についてよくある質問をまとめました。
一次面接だけでも依頼できる?
一次面接のみの依頼も可能です。初期接点のカジュアル面談やスクリーニング対応にも柔軟に対応しています。
面接の結果はどうやって共有されるの?
代行会社からフィードバックレポートが提供され、候補者の強みや懸念点が明確に整理されます。比較・分析しやすい形式で、最終判断の参考にもなります。
候補者に代行業者とバレない?
多くの代行会社は、企業名で面接対応するため候補者に代行とは気づかれにくいです。違和感なく自然な面接が行える体制が整っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、面接代行サービスの概要や仕組み、依頼できる業務内容から、料金体系、導入メリット・デメリット、向いている企業の特徴、選び方までを詳しく解説しました。
面接代行を活用することで、採用活動のスピードや質を高めつつ、社内リソースの最適化や評価基準の標準化といった課題にも対応することが可能になります。一方で、候補者との関係構築や企業理解の伝達といった面での注意点もあるため、導入前に慎重な検討が必要です。
面接代行サービスが自社の採用活動にどのような価値をもたらすか、この記事を通じて理解が深まっていれば幸いです。本記事を参考に、自社に最適な面接代行の活用方法を見つけてみてください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
[cta02 page_id=”1087″]
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
コーポレート用アイキャッチ-1-400x225.jpg)
【保存版】面接官が知っておくべき心得5選|準備から注意点まで徹底解説!
- 面接代行
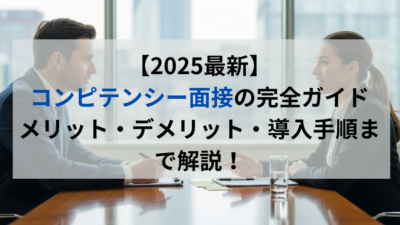
【2025最新】コンピテンシー面接の完全ガイド|メリット・デメリット・導入手順まで解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-2-400x225.jpg)
面接官の質問リスト集|質問設計方法、NG例から学ぶ注意点まで徹底解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-4-400x225.png)
カジュアル面談の正しい進め方とは?質問内容まで徹底解説!
- 面接代行
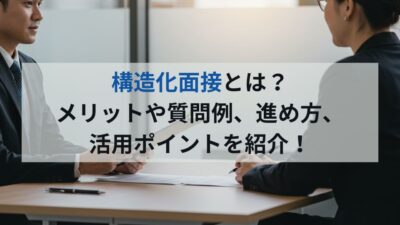
構造化面接とは?メリットや質問例、進め方、活用ポイントを紹介!
- 構造化面接
- 面接代行

面接代行の料金相場は?体系別の費用とコスト削減ポイントを解説!
- 面接代行







