
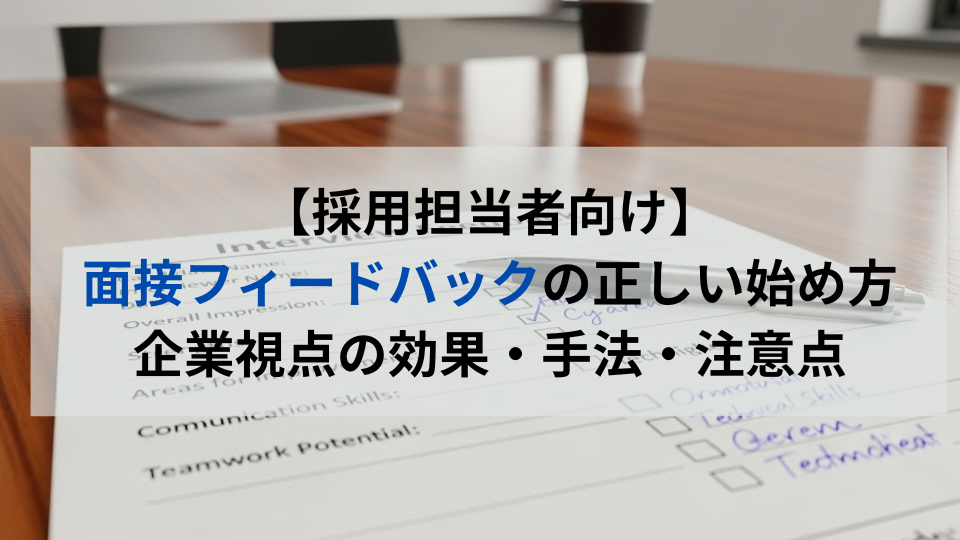
「面接で落ちた理由を知りたい」「改善点を聞きたい」といった応募者の声は年々増加しており、企業にとって面接フィードバックの重要性はかつてないほど高まっています。
特に若年層を中心に、選考プロセスそのものが企業選びの判断基準となる今、フィードバックは単なる合否通知ではなく、候補者との信頼関係を築くための重要なコミュニケーション手段と位置づけられつつあります。
一方で、実務の現場では「どこまで伝えるべきか」「誤解を生まない表現とは何か」「採用基準の漏洩につながらないか」といった不安の声も多く、フィードバックを導入・運用するには慎重な判断と設計が求められます。
そこで本記事では、面接フィードバックの意義や企業・候補者双方にもたらすメリットに加え、運用上のリスクとその対策、さらに効果的な伝え方や具体的な文例まで、採用力を高めるための実践的なノウハウを詳しく解説します。
面接フィードバックの基本知識
面接フィードバックとは、企業が採用選考の過程で応募者に対し、面接の評価や改善点を伝えるコミュニケーション施策です。
採用の現場では、志望度の高い候補者に選考辞退される、内定承諾率が上がらないという課題に対し、面接フィードバックは単なる評価の通知にとどまらず、候補者との信頼関係を築き、企業理解や志望度を高める重要な手段として注目されています。
本章では、なぜ今フィードバックが必要とされているのか、その背景やメリットを整理したうえで、実施前に押さえておくべき前提条件について解説していきます。
- フィードバックが注目される背景
- 企業・候補者双方のニーズ
- 実施前に押さえておく前提条件
フィードバックが注目される背景
近年、求職者は「企業からどう扱われたか」を重視し、採用活動のプロセス全体を企業選びの判断基準にしています。
SNSや口コミサイトの普及により、面接時の対応が企業イメージに直結する時代になったことも、フィードバックが重要視される要因のひとつです。
また、若年層の候補者を中心に、「なぜ落ちたのか知りたい」「改善点を知って次に活かしたい」という声が増加しており、丁寧なフィードバックのニーズが高まっています。
企業・候補者双方のニーズ
面接フィードバックの導入は、企業と候補者の双方にとって多くの利点があります。
企業側の立場から見ると、応募者との信頼関係を構築し、歩留まりを改善しながら志望度の向上につなげたいというニーズがあります。
候補者にとっては、自分の改善点を明確に把握し、今後の選考や就職活動に活かしたいという希望があります。また、「なぜ不合格だったのか」といった疑問を解消し、選考への納得感を得ることができるのも、フィードバックを受け取る大きな意義です。
面接フィードバックは単なる「評価の伝達」ではなく、採用プロセスにおける重要なコミュニケーション施策として機能しているのです。
実施前に押さえておく前提条件
面接フィードバックを導入するにあたっては、まず社内での評価基準を明文化し、面接官間で評価の軸を統一する必要があります。加えて、誰に対してどのような内容のフィードバックを行うのか、対象や範囲をあらかじめルール化しておくことが重要です。
また、実際にフィードバックを行う面接官には、適切な表現や伝え方に関するトレーニングも求められます。どれだけ制度を整えても、現場対応に差が出てしまっては逆効果になるため、一定のスキル標準を設けておくことが効果的です。
フィードバック内容の「伝え方」と「伝える範囲」について、詳細に伝えすぎれば選考基準の漏洩リスクがあり、逆に抽象的すぎると候補者に不信感を与える可能性があるため、社内での合意形成と運用ガイドラインの策定が必要となります。
「面接代行とは?依頼できる業務・費用・おすすめサービス4選を解説!」
面接フィードバックが企業にもたらす好影響
面接フィードバックは、単なるマナーや丁寧な対応にとどまらず、採用成果そのものを左右する戦略的な施策として注目を集めています。
採用の各フェーズにおいて、候補者とのコミュニケーションの質が企業の競争力を左右している今、フィードバックは選考プロセスにおける差がつく一手といえるでしょう。
候補者体験の改善は、企業の第一印象や志望度に大きく影響を与えます。
ここでは、面接フィードバックが企業にもたらす3つのメリットについて詳しく解説します。
- 候補者エンゲージメント向上
- ミスマッチの防止
- 企業ブランド強化・他社差別化
候補者エンゲージメント向上
選考過程で丁寧なフィードバックを受け取った候補者は、企業に対して「大切に扱ってくれた」という印象を持ちやすくなります。
これは、単なる合否連絡とは異なり、企業との信頼関係構築に直結する要素です。
とくに若年層の応募者は、「自分をしっかり見てくれているか」を重視する傾向が強く、フィードバックを通じて志望度が高まるケースも少なくありません。
ミスマッチの防止
フィードバックの中で、自社が評価しているポイントや求めているスキルを明確に伝えることは、候補者自身の理解を深めることにつながります。
その結果、「思っていた仕事と違った」というギャップを防ぐことができ、入社後の定着率にも良い影響を与えます。
また、選考段階での誤解やすれ違いが減るため、内定辞退や選考辞退の防止にも有効です。
他社との差別化
面接フィードバックは、まだ導入している企業が多くはないため、それだけで差別化要因になります。
丁寧な対応を受けた候補者が、SNSやクチコミサイトでポジティブな投稿を行うケースもあり、採用広報の一環としても有効です。
また、フィードバックは「人を育てようとする姿勢」として映るため、企業の文化や価値観を自然に伝える手段としても活用できます。これは単なる人事対応ではなく、戦略的な採用ブランディング施策と言えるでしょう。
面接フィードバックが企業にもたらすリスク
面接フィードバックは、うまく活用すれば採用成功に大きく貢献する一方で、導入と運用には慎重な設計と体制づくりが求められます。
一見、単に「丁寧な対応」と捉えられがちですが、実際の運用では工数の増大や情報管理、候補者対応の難しさなど、複数のリスクが複雑に絡み合うのが実情です。
本章では、企業が面接フィードバックを行う際に直面しやすい3つのリスクと、それぞれに対する基本的な対策の考え方について解説します。
- 面接官負荷と時間コストの増加
- 採用基準漏洩リスク
- トラブル発生の可能性
面接官負荷と時間コストの増加
面接後に個別のフィードバックを作成・送付するには、当然ながら追加の時間と手間がかかります。
特に中途採用や新卒大量採用など、候補者数が多い場合には面接官や人事担当者の負担が大きくなりがちです。
そのため、評価シートのフォーマット化や一部自動化ツールの導入など、業務効率化の工夫をあらかじめ講じておくことが重要です。
採用基準漏洩リスク
フィードバックの内容によっては、自社の評価基準や選考の観点が外部に伝わってしまう可能性があります。
これにより、次回以降の候補者が面接対策を行いやすくなり、公平性が損なわれるリスクもあるため、開示範囲のバランスには十分な注意が必要です。
たとえば、「〇〇点が評価されなかった」と明言するのではなく、「より具体的な経験や実績があると良い」など、間接的な表現で伝える工夫も効果的です。
トラブル発生の可能性
不採用通知とあわせて改善点などのネガティブなフィードバックを伝える際には、候補者から感情的な反発や問い合わせが発生する可能性があります。こうしたリスクを軽減するには、伝え方に細心の注意を払うことが重要です。
フィードバックはあくまで「面接官個人の印象」として伝えるようにし、組織の総意として一方的に評価を下す印象を与えないことが大切です。さらに、指摘を否定的に伝えるのではなく、候補者の今後に期待するという姿勢を示しながら、前向きなアドバイスの形にすることで、受け手の納得感は大きく変わります。
伝え方の質を高めることで、候補者にとっても建設的なフィードバックとなり、企業としての誠実な姿勢を伝えることができます。
効果的な面接フィードバック5つの原則
面接フィードバックは、ただ評価内容を伝えるだけでは不十分です。伝え方ひとつで、候補者の志望度や企業への印象、さらには採用広報への波及効果まで大きく左右されます。
逆に、内容が適切であっても表現方法を誤れば、誤解や不満を生み、企業イメージを損なうリスクにもなりかねません。
つまり、フィードバックの「質」は採用の成果に直結します。丁寧かつ的確に伝えることで候補者との信頼関係を築き、辞退率の低下や内定承諾率の向上にもつながります。
本章では、面接フィードバックを効果的に機能させるために押さえておくべき5つの原則を解説します。
- ポジティブ・ネガティブのバランスを取る
- 行動事実に基づいて具体的に伝える
- 面接官の一人称で伝える
- 自社価値観と結びつける「ブリッジング」を行う
- 志望度を高める言葉選びを心がける
ポジティブ・ネガティブの最適バランス
最初から改善点ばかりを伝えてしまうと、候補者のモチベーションを大きく下げてしまいます。
そのため、フィードバックは「ポジティブ→ネガティブ→ポジティブ」の順で伝える、いわゆる「サンドイッチ方式」を基本とするのが効果的です。
ポジティブな点に触れたうえで、改善すべきポイントを丁寧に伝え、最後に再度前向きなコメントで締めくくることで、候補者は全体を通して好意的に受け止めやすくなります。
このように、フィードバックの順序や構成を工夫することによって、ネガティブな内容であっても前向きに捉えてもらいやすくなるのです。
行動事実に基づいて具体的に伝える
曖昧な表現では候補者に納得してもらえません。
「印象が薄かった」ではなく、「自己PRでのエピソードが抽象的で、成果が伝わりにくかった」と伝えるなど、具体的な行動や発言を根拠とすることで、フィードバックの価値が高まります。
候補者にとって「次に何を改善すべきか」が明確になるよう意識しましょう。
面接官の一人称で伝える
「弊社では~」という表現ではなく、「私はこう感じました」と主語を面接官自身にすることで、候補者に対して対話的で自然な印象を与えることができます。あくまで個人の視点から伝えることで、押しつけがましさを避けつつ、率直な評価として受け止められやすくなります。
また、このような伝え方はクレームのリスクを低減する効果もあります。「企業から評価された」という距離感よりも、「一人の担当者が丁寧に向き合ってくれた」という印象を与えることで、誠実な姿勢が伝わりやすくなり、フィードバック全体の納得感が高まります。
自社価値観と結びつける「ブリッジング」を行う
たとえば、「あなたのプレゼン能力は非常に高いと感じました。ただ、当社の業務では顧客との長期的な信頼関係の構築が求められるため、継続的なフォロー力も重視しています」といったように、自社が評価するポイントと、候補者の特性を結びつけて伝えることで、フィードバックは企業理解の促進にもつながります。
このような「ブリッジング」の手法は、志望度を高める効果があるだけでなく、入社後の業務との相性を候補者自身が判断する助けにもなり、ミスマッチの防止にも有効です。
志望度を高める言葉選びを心がける
フィードバックは評価を伝える手段であると同時に、候補者との関係性を築くための大切なコミュニケーションの一環でもあります。
そのため、「ぜひまたチャレンジしていただきたいと思っています」や「ポテンシャルを高く感じています」といった前向きな言葉で締めくくることで、候補者に好印象を残すことができます。
改善点を伝える際も、「プレゼンの構成をもう少し整理すると、伝わりやすさがさらに向上すると思います」といったように、努力の方向性を具体的に示すアドバイス型の表現を意識しましょう。こうした言葉選びによって、候補者の志望度や企業への信頼感が自然と高まっていきます。
種類別の活用シーン:ポジティブ/ネガティブ/ブリッジング
面接フィードバックは、どのように伝えるかによって候補者の受け取り方が大きく変わります。特に、候補者との信頼関係を築き、志望度を高め、選考後の印象を左右するうえで、内容の「種類」を使い分けることは非常に重要です。
効果的なフィードバックには、大きく分けて3つのパターンがあります。それが、候補者の強みや魅力を肯定的に伝える「ポジティブフィードバック」、改善点や課題を丁寧に指摘する「ネガティブフィードバック」、そして評価を自社の価値観や業務特性に結びつける「ブリッジング」です。
ここでは、それぞれの特徴と活用シーンについて詳しく見ていきましょう。
- ポジティブフィードバック
- ネガティブフィードバック
- ブリッジング(自社価値観と結びつけた伝え方)
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、候補者の良い点や評価できた点を積極的に伝える方法です。これは単に評価を伝えるという意味合いだけでなく、選考結果にかかわらず候補者への敬意や感謝を示す重要なコミュニケーションでもあります。
面接の序盤で好印象を持った点をその場で伝えることや、不採用となった場合でも「この点は高く評価していた」と伝えることで、候補者にとっての納得感や満足度が高まります。また、採用が決まった際には、候補者の強みをどう活かしてほしいかまで具体的に言及することで、入社後の期待感を高めることができます。
このような前向きなフィードバックは、候補者の志望度を高め、選考辞退や内定辞退の防止にもつながるため、採用成功における大きな要素のひとつです。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックとは、候補者に対して改善点や不足していた点を伝えるコミュニケーションのことです。伝え方を誤れば反感を招くリスクもありますが、適切に伝えることで候補者の自己理解を深め、今後の成長につなげてもらう貴重な機会にもなります。
効果的に伝えるには、まず行動ベースで具体的に指摘することが重要です。たとえば、「成果に関する質問への回答に具体性が欠けていた」といったように、事実に基づいたフィードバックを心がけましょう。
そして、「次回はこうするとさらに良くなる」といった前向きな提案や期待を添えることで、候補者にとっても建設的な経験となります。ネガティブな内容であっても、「次に活かせるフィードバックだった」と感じてもらえるかどうかが、企業に対する印象を大きく左右します。
ブリッジングの活用
ブリッジングとは、候補者の特徴や面接中の発言を、自社の評価基準や業務特性と関連づけてフィードバックする方法です。フィードバックに対する候補者の納得感が高まるだけでなく、企業の価値観や求める人物像への理解を深めてもらうことにもつながります。
たとえば、論理性に課題が見られた候補者に対しては「当社はプレゼンテーションの機会が多く、論理的な構成力を重視しています」と伝えることで、ただの評価ではなく、自社の業務に根差したフィードバックであることが伝わります。
一方で、柔軟な対応力が印象的だった候補者には、「当社の顧客対応業務でもその強みが十分に活かせると感じました」といった形で、期待感を示すことも可能です。
このように、フィードバックを企業の文脈と結びつけて伝えることで、候補者自身が「この会社に自分は合っているかどうか」をより正確に判断できるようになります。
効果的なタイミングと手段
面接フィードバックの効果を最大限に引き出すには、「何を伝えるか」と同じくらい、「いつ、どのチャネルで伝えるか」が重要です。タイミングがずれたり、伝え方を誤ったりすれば、丁寧に準備したフィードバックも逆効果になりかねません。
特に近年では、採用プロセスそのものが企業評価につながるケースも増えており、フィードバックの伝達は単なる手続きではなく、採用広報やブランディングの一環としての機能も担います。
ここでは、選考ステージ別、手法別など多様な場面を通して、詳しく解説をしていきます。
- 選考ステージ別の最適タイミング
- 手法別の特徴
- エージェント経由で伝える場合
- ATS連携で自動化する場合
選考ステージ別の最適タイミング
面接フィードバックは、選考のどの段階で提供するかによって、その効果や候補者の受け止め方が大きく異なります。
たとえば、一次面接や二次面接の後であれば、簡易的なコメントでも十分に効果があります。この段階では、次回選考に向けたモチベーションを高めることが主な目的であり、「良かった点」に軽く触れる程度のフィードバックが適しています。
一方で、最終面接後に不採用となった場合には、より丁寧かつ納得感のあるフィードバックが求められます。候補者が選考全体を振り返る機会となるため、評価の根拠や改善点について具体的に伝えることが大切です。
このように、フィードバックの目的は選考ステージごとに異なるため、それぞれのタイミングに応じた内容と伝え方を選ぶことが、効果的な運用のポイントとなります。
手法別の特徴
フィードバックの伝達手段としては、主に以下の3つが使われます。
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| メール | 記録に残る/テンプレ化しやすい | ニュアンスが伝わりにくい/冷たい印象になることも |
| 電話 | 声のトーンで印象を柔らかくできる | 言い方を間違えると誤解されるリスク |
| 対面(次回面接の前後) | 表情や反応を見ながら伝えられる | 工数がかかる/時間調整が必要 |
いずれの手段でも、事前に言葉を整理してから伝えることが重要です。特にネガティブな内容は、冷静かつ誠実に伝えるよう心がけましょう。
エージェント経由で伝える場合
新卒・中途を問わず、紹介会社やエージェント経由で採用を行っている場合は、フィードバックもその経由で行うのが一般的です。
エージェントは候補者との関係性が構築されているため、伝達のクッションとしても機能します。
注意点としては、情報が意図せず誇張されたり、省略されたりする可能性があることです。
そのため、企業側はなるべく具体的かつ簡潔なコメントをエージェントに共有し、伝達の精度を担保する必要があります。
ATS連携で自動化する場合
候補者数が多く、個別対応が難しい場合は、ATS(採用管理システム)を活用して評価内容とフィードバックを自動化する方法も有効です。
たとえば、一次面接通過者にはテンプレート付きのフィードバックメールを自動送信するなど、業務負担を減らしつつ候補者満足度を高められます。
ただし、自動送信だけで済ませると「機械的な対応」と受け取られるリスクもあるため、ステージや候補者の状況に応じた柔軟な運用が必要です。
フィードバック内容の作り方:具体例&NG例【テンプレ付き】
面接フィードバックは単なる情報提供ではなく、候補者の行動や印象に直接影響を与える戦略的コミュニケーションのひとつです。
言葉の選び方や構成、そして表現の丁寧さが、採用活動全体の信頼性や候補者体験の質に直結するといっても過言ではありません。
本章では、実務でそのまま活用できるフィードバックの書き方・伝え方のポイントに加え、避けるべき表現例や候補者に刺さる文面を、詳しく解説します。
- 評価ポイントの効果的な伝え方
- 改善点と次回選考へのアドバイス
- NGワード・避けるべき表現
評価ポイントの効果的な伝え方
候補者の良い点を伝える際は、漠然とした印象ではなく、具体的な行動や発言を根拠にすることが重要です。
OK例:
「自己紹介でのご経歴の整理が非常にわかりやすく、要点を的確に伝える力があると感じました。」
NG例:
「感じが良かったです。」→ 抽象的すぎて伝わらない
このように、評価理由に「何が良かったのか」「どう印象づけたのか」を含めることで、候補者の納得感が高まります。
改善点と次回選考へのアドバイス
改善点を伝える際は、決して「ダメ出し」にならないよう注意が必要です。
ポイントは、「事実→改善の方向性→ポジティブな期待」の順で伝えることです。
OK例:
「自己PRの中で実績に関する具体的な数字があまり出ておらず、やや説得力に欠ける印象でした。次回は数値や成果を交えて話すことで、より強みが伝わると思います。」
このように、提案型の表現にすることで、「建設的なアドバイス」として受け取ってもらいやすくなります。
NGワード・避けるべき表現
以下のような表現は、候補者との信頼関係を損ねる可能性があるため、避けましょう。
| NG表現 | 理由 | 改善例 |
|---|---|---|
| 「なんとなく合わない印象」 | 抽象的で納得できない | 「〇〇の点が当社の業務環境においては合いにくい可能性がある」 |
| 「能力が足りない」 | 人格否定に聞こえる | 「今回のポジションでは、〇〇の経験を重視している」 |
| 「他の方が優れていた」 | 比較により不快感 | 「当社の今回のニーズにより合致した方がいた」 |
伝え方一つで、候補者の受け取り方は大きく変わるため、文面をチェックする仕組みを社内に設けておくのもおすすめです。
面接のフィードバックについてよくある質問(FAQ)
面接のフィードバックについてよくある質問をまとめました。
面接フィードバックを実施する企業は全体の何割くらい?
現在、日本国内で面接フィードバックを積極的に実施している企業は全体の2〜3割程度とされています。導入率は年々増加傾向にありますが、まだ一般的とは言えません。
フィードバックを導入することで離職率に影響はある?
フィードバックを丁寧に行うことで、候補者の企業理解が深まり、入社後のミスマッチや早期離職の防止につながるケースがあります。特に若年層では、入社前からの信頼構築が定着率を高める要因となります。
フィードバックを提供しすぎると応募が減ることはある?
詳細すぎるフィードバックは選考基準が外部に漏れる懸念があり、結果として応募をためらう候補者が出る可能性はあります。伝える範囲と内容には慎重なバランスが必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、面接フィードバックの基本から企業側のメリット、リスク、具体的な実践方法までを詳しく解説しました。
面接フィードバックは、単なる評価通知ではなく、候補者との信頼関係を築き、志望度や企業理解を高めるための戦略的なコミュニケーション施策です。うまく活用すれば、選考辞退や内定辞退の防止、採用ブランディング強化にもつながります。
一方で、伝え方を誤るとトラブルや誤解を生むリスクもあるため、内容の設計や運用体制には慎重な準備が求められます。フィードバックの質が採用の成否を左右するといっても過言ではありません。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
[cta02 page_id=”1087″]
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
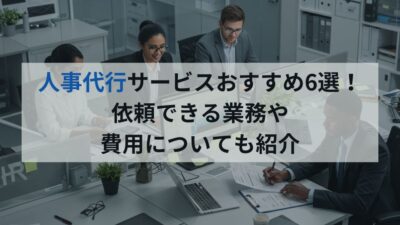
人事代行サービスおすすめ6選!依頼できる業務や費用についても紹介
- 採用代行

【徹底比較】採用代行と人材紹介の違いとは?それぞれの特徴や費用も紹介!
- 採用代行
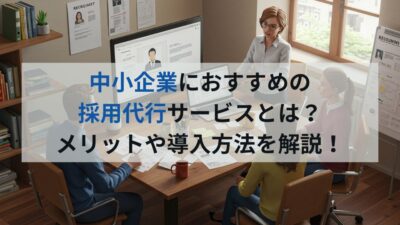
中小企業におすすめの採用代行サービスとは?メリットや導入方法を解説!
- 採用代行

【事例有】スタートアップが採用を成功させるには?戦略やコツ、手法など解説
- 採用代行
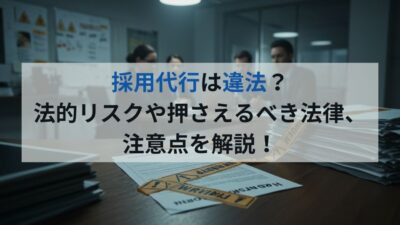
採用代行は違法?法的リスクや押さえるべき法律、注意点を解説!
- 採用代行
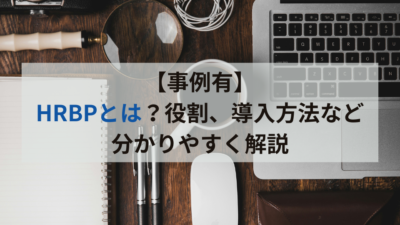
【事例有】HRBPとは?役割、導入方法など分かりやすく解説
- 採用代行







