

採用活動において、面接の日程調整は思いのほか時間と労力を消費する業務です。候補者との往復メールや、面接官のスケジュール確認、会議室やオンライン会議リンクの準備など、調整プロセスが繁雑になると採用スピードが落ち、候補者の離脱リスクが高まります。
そこで注目されているのが「面接日程調整ツール」です。これらのツールを導入することで、やり取りの自動化、スケジュールの一元管理、およびリマインドの自動送信が可能になり、採用担当者の工数削減と候補者体験の向上を同時に実現できます。
- 日程調整にかかる時間・手間を大幅に削減できる
- 候補者の離脱防止や選考スピード向上に寄与する
- リモート環境でも安定した運用が可能になる
本記事では、面接日程調整ツールの基本的な仕組みから、導入メリット・デメリット、ツールの種類別の使い分け、選定時のチェックポイント、および導入事例までをわかりやすく解説します。これから導入を検討する方、また既存運用を改善したい方に向けた実践的な内容を提供します。
面接日程調整ツールとは何か?
採用活動において、「面接日程の調整」は意外にも大きな工数とストレスのかかる業務です。
応募者とのやり取りはもちろん、社内の面接官や会議室の空き状況も調整しなければならず、特に中途採用や大量採用では属人化もしやすいポイントです。
こうした課題を解決するのが「面接日程調整ツール」です。
Web上で候補日を共有し、候補者が都合の良い時間を選択するだけで日程が確定するため、従来のやり取りと比較して圧倒的に効率的かつミスが起きにくいのが特徴です。
面接日程調整ツールの基本的な仕組みと、従来手法との違いを以下にまとめます。
- ツールを使った日程調整の基本的な仕組み
- メールや電話による調整との違い
ツールを使った日程調整の基本的な仕組み
面接日程調整ツールの代表的な仕組みは以下の通りです。
- 面接官の空き日程を登録・同期
- 候補者へ日程選択用URLを送付
- 候補者が都合の良い日時を選択
- 日程確定後、自動でカレンダー登録&通知
これにより、従来のように「この日空いていますか?」「その日は無理です」といったやり取りを繰り返す必要がなく、最短で数分で面接日程を確定することも可能になります。
Googleカレンダー、Outlook、Slackなどとの連携機能も豊富で、面接官や候補者の環境を問わず利用しやすい点も評価されています。
メールや電話による調整との違い
従来の面接日程調整では、主にメールや電話が使用されてきましたが、それには以下のような課題がつきものでした。
- 候補日を都度手入力しなければならない
- 返信が遅い・曖昧で調整に時間がかかる
- 面接官の予定が変わるたびに調整が必要
一方、日程調整ツールでは「リアルタイムな空き状況」から日程を選べるため、ミスや手戻りが発生しにくくなります。
さらに、ツールを介して自動的にリマインドを送る設定も可能で、面接の直前キャンセル防止にもつながるのが大きな強みです。
面接日程調整ツールを導入する5つのメリット
面接日程調整ツールの導入により、採用業務の工数を大幅に削減できるだけでなく、候補者との関係構築や辞退防止など、採用成果全体の底上げにも貢献します。
以下では、特に採用担当者にとって重要なメリットを5つに分けて解説します。
- 面接調整にかかる時間・工数の削減
- ダブルブッキングや予定漏れの防止
- 採用歩留まりの改善・辞退率の低下
- 複数候補者・複数面接官にも対応可能
- 遠隔・在宅勤務でも調整可能な柔軟性
面接調整にかかる時間・工数の削減
面接調整にかかるやり取りは、1人あたり平均で数往復に及ぶことも珍しくありません。
これが複数人分となると、採用担当者にとっては大きな負担です。
ツールを活用すれば、候補日をシステム上で提示し、候補者が自分で選ぶだけで完結するため、メールのやり取り回数が激減。
最大90%の業務工数削減を実現する企業もあります。
ダブルブッキングや予定漏れの防止
ツールはカレンダーとリアルタイムで同期しているため、空き時間しか選択肢に表示されません。
その結果、ダブルブッキングや入力ミスによる予定漏れといったヒューマンエラーがほぼゼロになります。
特に複数の候補者や複数面接官が関わる面接では、スケジュールの複雑さからミスが起きがちなので、効果は大きいです。
採用歩留まりの改善・辞退率の低下
面接日程の確定が遅れると、候補者の心理的なモチベーションが下がり、途中辞退や音信不通のリスクが高まります。
ツールによって即時に日程が確定できれば、候補者の不安も軽減され、辞退率を下げる効果が期待できます。
採用スピードが問われる中途採用では特に有効です。
複数候補者・複数面接官にも対応可能
従来であれば1人ひとりと個別にやり取りが必要だった複数面接・複数候補者の調整も、ツールなら条件に合致する日程を自動で提示してくれます。
面接官の空き時間や、部屋・会議ツールの利用可能時間も含めた自動調整が可能なツールもあり、属人化せずに運用できるのが特徴です。
遠隔・在宅勤務でも調整可能な柔軟性
リモートワークが一般化する中で、面接官や採用担当者がオフィスにいないことも珍しくありません。
日程調整ツールは、クラウドベースで管理が完結するため、拠点を問わずにアクセス可能。
またSlackやGoogle Meetなどの外部ツールとの連携も可能なため、通知・面接リンクの自動発行も実現できます。
面接日程調整ツールを導入する際のデメリット
面接日程調整ツールは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたって留意しておくべき課題や落とし穴も存在します。
「導入すればすぐに楽になる」と思い込んでしまうと、社内運用や候補者対応でつまずく恐れもあるため、以下に代表的なデメリットを整理しておきます。
- 社内への浸透・運用定着の難しさ
- 臨機応変な対応力の不足
- 一方向的なコミュニケーションの課題
社内への浸透・運用定着の難しさ
ツールを導入しても、全ての関係者が正しく使いこなせるとは限りません。
特に以下のようなケースでは、社内での定着に時間がかかることがあります。
- 面接官が複数部署にまたがっており、情報共有が難しい
- 操作に不慣れなメンバーが多い
- 既存の調整フローが根強く残っている
このような環境では、導入直後に「結局手動でやった方が早い」となりがちです。
ツールの活用効果を最大化するには、説明会やマニュアルの整備など社内教育にも一定のリソースが必要です。
臨機応変な対応力の不足
日程調整ツールは便利な反面、その場の状況に応じた柔軟なやりとりが苦手です。
例えば、面接官の急な予定変更や、候補者が「今日中に調整を完了させたい」と希望するケースでは、電話やチャットなどの直接対応の方が早く確実に調整できます。
ツールが提示できる選択肢は、事前に設定された条件の範囲に限られるため、「イレギュラー対応」にはやや不向きです。
一方向的なコミュニケーションの課題
日程調整ツールの多くは「URLを送って候補者が選択する」という片方向的なやりとりが基本です。
そのため、特に以下のような候補者に対しては注意が必要です。
- ITリテラシーが低く、URL操作に不安がある
- 転職活動に不慣れで、人の温かみを求めている
- 特別対応(時短勤務・リモート希望など)が必要な場合
こうした場面では、一言メールを添えたり、事前にフォローの電話を入れるなどの人間的な配慮が求められることもあります。
便利さに頼りすぎると、候補者の満足度を下げるリスクもある点に留意が必要です。
【3タイプに分類】日程調整ツールの種類
面接日程調整ツールには複数の種類があり、それぞれ調整の方法や使い勝手が大きく異なります。
自社の面接フローや関係者の人数、候補者の属性によって、向いているタイプ・不向きなタイプがあるため、事前の理解が欠かせません。
ここでは、代表的な4つの型を紹介し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを解説します。
- 予約受付型
- 日程提案型
- 投票型
- ハイブリッド型
予約受付型
「予約受付型」は、面接官側があらかじめ空いている日時をカレンダー形式で公開し、
候補者がその中から都合の良い日時を選ぶ仕組みです。
美容室やクリニックの予約と似た形式で、最も一般的に使われている調整方法です。
- 確定までのスピードが非常に速い
- 候補者側の判断だけで完結する
- 面接官のスケジュールに即時反映される
ただし、候補者が希望する日程が空いていないと離脱のリスクがあるため、十分な時間帯を用意しておく必要があります。
日程提案型
「日程提案型」は、採用担当者が候補日を複数提示し、候補者にどれが良いか選んでもらう形式です。
予約受付型よりも、ある程度人の介在があるタイプといえます。
- 候補者に合わせて柔軟に候補日をカスタマイズできる
- 面接官の都合に合わせた提案がしやすい
「この3日の中でご都合のよい日時はありますか?」といった調整をメールではなくツール上で行う形で、
個別対応を維持しつつ効率化したい企業に向いています。
投票型
「投票型」は、複数人の間で、どの日程が最も多くの人にとって都合が良いかを確認する方式です。
一つの日程を全員で共有する場合や、複数部署をまたいだ面接官が関わるときに役立ちます。
- グループ調整に適している
- 複数人の空き時間を集約・可視化できる
ただし、最終確定までに全員の入力が必要なため、調整スピードはやや遅くなりがちです。
スピードより「調整の公平性」を重視する場面に向いています。
ハイブリッド型
「ハイブリッド型」は、上記の複数の仕組みを柔軟に組み合わせて利用できるタイプです。
例えば、「基本は予約受付型として運用しつつ、特別対応が必要な候補者には日程提案型でフォローする」といった運用が可能です。
- 多様な面接パターンに対応できる柔軟性がある
- 運用負荷が下がり、属人化もしにくい
中途採用・新卒採用・役員面接などのフローが混在する企業や、
「調整の仕方を相手に応じて切り替えたい」企業に最も適した型です。
【選定前に必読】面接日程調整ツール選びのポイント
面接日程調整ツールを導入するにあたっては、「知名度」や「価格」だけで判断せず、利用目的・業務フロー・社内環境に適したものを選ぶことが重要です。
自社の選考体制や候補者層に合わないツールを選ぶと、かえって業務の非効率や候補者の離脱を招いてしまうこともあります。
ここでは、採用業務での活用を前提に、ツール選定時に必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。
- ツールの型(予約受付・提案・投票)の選択
- 操作性・UI/UXの良さ
- Googleカレンダー・Teams等との連携可否
- モバイル・マルチデバイス対応
- セキュリティ・情報管理面の信頼性
ツールの型(予約受付・提案・投票)の選択
最初に確認すべきは、ツールの「型」です。
予約受付型・日程提案型・投票型など、調整スタイルは複数あり、それぞれ適するシーンが異なります。
- 中途採用や面接スピード重視なら:予約受付型
- 特別対応や個別対応が多いなら:日程提案型
- 複数部署・複数面接官が関わるなら:投票型やハイブリッド型
現在の採用フローを振り返り、「どのような日程調整が最も頻繁に発生しているか」を基準に検討すると選びやすくなります。
操作性・UI/UXの良さ
社内で定着させるうえで、使いやすさは非常に重要です。
特に面接官や候補者がITに強くない場合は、操作が直感的であることが導入成功のカギとなります。
- 管理画面や予約ページの視認性
- 操作ステップのシンプルさ
- 説明なしでも直感的に使えるデザイン
使い方が複雑なツールは、社内教育の手間がかかるだけでなく、候補者側の離脱にもつながるため注意が必要です。
Googleカレンダー・Teams等との連携可否
ツール選定において最も見落とされがちなのが「連携機能」です。
自社で使用しているカレンダーやチャットツールと連携できないと、かえって業務負荷が増える結果になりかねません。
- GoogleカレンダーやOutlookとの双方向連携が可能か
- TeamsやSlackなどに通知が送れるか
- 面接リンク(ZoomやMeetなど)の自動発行に対応しているか
連携範囲が広いツールほど、業務自動化・ミス防止に役立ちます。
特にITツールを複数併用している企業では、事前に連携可否を確認しましょう。
モバイル・マルチデバイス対応
面接調整は、採用担当者も候補者も「PC以外のデバイス」で操作することがあります。
スマホ・タブレットでも快適に使えるかは、ツールの利便性を左右する大きなポイントです。
- スマホ表示でレイアウトが崩れないか
- iOS・Androidの両方に対応しているか
- アプリ提供の有無(あれば使用感も確認)
とくに候補者はスマホから日程を確認・選択することが多いため、候補者視点での使いやすさも大切な判断軸です。
セキュリティ・情報管理面の信頼性
日程調整ツールでは、応募者の氏名・連絡先・面接情報などの個人情報を取り扱うため、セキュリティ対策は必須です。
- 通信の暗号化(SSL/TLS対応)
- データの保存先サーバーの所在(日本国内が望ましい)
- プライバシーポリシーやセキュリティガイドラインの明示
導入前には、情報システム部門や法務と連携して、コンプライアンス上の懸念がないかを確認しておくと安心です。
【厳選5選】面接に最適な日程調整ツール
日程調整ツールは数多く存在しますが、すべてが採用業務に適しているとは限りません。
ここでは、面接目的での活用に特化して、機能性・操作性・連携性に優れたツールを5つ厳選してご紹介します。
それぞれのツールについて、導入実績や得意な活用シーンも合わせて解説しますので、自社に最適なものを選ぶ参考にしてください。
- TimeRex|採用特化型で導入実績豊富
- eeasy|URL送付のみで調整完結
- Jicoo|チーム活用に適したカレンダー連携型
- Microsoft Bookings|Office365との親和性が高い
- 調整さん|シンプルで誰でも使える
TimeRex|採用特化型で導入実績豊富
TimeRexは、GoogleカレンダーやOutlookとリアルタイムに連携し、自動で面接可能な時間を抽出・提示できるツールです。
SlackやZoom、Microsoft Teamsとも連携可能で、面接URLの自動生成や通知設定にも対応しています。
- 面接設定から確定まで全自動で完了
- 複数面接官のスケジュールも一括管理
- 国内大手・ベンチャー企業での導入実績多数
採用に特化したUI・機能設計がされており、「採用管理システムと連携しない簡易調整機能」としても非常に使いやすいツールです。
eeasy|URL送付のみで調整完結
eeasyは、特許技術を活用した自動調整ツールで、「URLを送るだけ」で候補者が日程を選び、面接が確定する仕組みが強みです。
企業側・候補者側どちらにも負担が少なく、柔軟なカスタム設定も可能です。
- 面接官・候補者の空き時間を自動抽出
- カレンダーに自動反映+リマインド通知
- 複数人調整やURL使い回しにも対応
商談・営業にも使われる多用途ツールですが、特に採用面での導入効果(工数削減・辞退率低下)に定評があります。
Jicoo|チーム活用に適したカレンダー連携型
Jicooは、Google・Outlookカレンダーとの双方向連携と、複数メンバーでのスケジュール調整に強みを持つツールです。
Slack・Zoomなどとの連携もスムーズで、チームで面接を進める企業に最適です。
- 多人数の空き時間から最適日程を自動提示
- パーソナライズされた面接設定が可能
- 日本語対応で操作も直感的
リモート面接が多い企業や、複数部署のメンバーと連携して面接を行うケースにおすすめです。
Microsoft Bookings|Office365との親和性が高い
Microsoft Bookingsは、Office365を利用している企業にとっては導入・運用のハードルが非常に低いツールです。
Outlookとの完全連携により、面接官の空き時間がリアルタイムに反映され、候補者が自分で日程を選択できます。
- Microsoft TeamsやOutlookとの完全連携
- インストール不要でブラウザ操作のみで完結
- 社内のITポリシーとも整合性を取りやすい
Office製品を中心に業務を進めている企業にとっては、最も手軽かつ安全な選択肢のひとつです。
調整さん|シンプルで誰でも使える
調整さんは、登録不要・操作が非常にシンプルな日程調整ツールです。
もともとは飲み会・イベント用として広まりましたが、社内面接やカジュアル面談など、ラフな場面での面接調整にも活用されています。
- 誰でもすぐ使える直感的UI
- スマホでもスムーズに操作可能
- アカウント作成不要で手間ゼロ
セキュリティや連携機能は限定的なため、本格的な採用管理用途よりも、簡易調整や一次面談などの用途に適しています。
面接での日程調整ツール活用手順
面接日程調整ツールは、ただ導入するだけでは効果を最大化できません。
社内の面接体制や採用フローに沿って、正しく・スムーズに運用するための手順を押さえておくことが重要です。
ここでは、採用担当者が実際に日程調整ツールを使って面接を実施するまでの具体的な流れを解説します。
- 応募者へのメール送付
- 日程調整の実施
- 応募者との面接
応募者へのメール送付
まずは、応募者に対して「面接日程調整の案内メール」を送信します。
このメールには、ツールで発行した日程選択用のURLや簡単な使い方を記載します。
メール文面の例:
本文:
この度はご応募いただきありがとうございます。
以下のリンクより、ご都合の良い日時をご選択ください。
選択後、自動で面接日程が確定されます。
▼日程調整リンク:〇〇〇〇〇〇
事前に企業側で候補日程をツール上に設定しておくことで、応募者は自分の都合に合わせてスムーズに選択できるようになります。
日程調整の実施
応募者がURLから希望日時を選ぶと、その内容が自動で反映されます。
GoogleカレンダーやOutlookなどと連携していれば、面接官の予定表にもリアルタイムで登録されます。
- 候補日を自動抽出・反映
- リマインド通知や面接URLの自動送付も可能
- 複数面接官・複数候補者にも対応可能
この段階で人手によるやり取りはほぼ不要です。
また、キャンセルや変更が発生した場合も、ツール上からワンクリックで再調整が行える仕組みが整っています。
応募者との面接
面接当日は、事前に設定されたツールのリマインダー通知により、面接官・応募者ともにスムーズに面接に臨めます。
ZoomやGoogle MeetなどのURLも自動発行・通知されていれば、リンクをクリックするだけで面接開始が可能です。
- 時間通りに面接が開始されやすくなる
- 面接官が直前に内容を把握しやすい
- 社内の面接記録ともスムーズに連携
日程調整のストレスがなくなれば、面接に集中できる環境が整い、採用の質を高めることにもつながります。
導入企業の成功事例から学ぶ活用ポイント
面接日程調整ツールは、導入するだけでなく運用方法や社内浸透の工夫によって成果が大きく変わります。
ここでは、実際にツールを導入して成功した企業事例をもとに、採用業務の改善につながるポイントを紹介します。
- 工数削減・辞退率改善に成功した企業例
- 現場の声:日程調整の負担が減った理由
- 他社との比較で選ばれたポイント
工数削減・辞退率改善に成功した企業例
あるIT企業では、週あたり平均15時間かかっていた日程調整業務を3時間以下に短縮。
さらに、日程確定までのリードタイムが短くなったことで、一次面接の辞退率が25%から10%へ低下しました。
この成功の背景には、候補者のスケジュール選択を即時反映する仕組みと、リマインド通知による「忘れ防止」があります。
現場の声:日程調整の負担が減った理由
採用担当者からは、次のような声が寄せられています。
- メールの往復がなくなり、面接準備に時間を使えるようになった
- 複数面接官の予定調整が自動化され、社内調整ストレスが減った
- 候補者からの返信率が向上した
これらは単なる効率化ではなく、面接官や候補者が面接の質に集中できる環境を作ることに直結しています。
他社との比較で選ばれたポイント
選定の決め手として多く挙げられるのは以下の3点です。
- 既存のカレンダーや社内システムとの連携
- 社内外問わず簡単に使えるUI/UX
- セキュリティと情報管理の安心感
このように、単なる機能比較ではなく「運用のしやすさ」と「安心感」が、最終的な導入判断を左右しています。
まとめ
面接日程調整ツールは、採用担当者の負担軽減だけでなく、候補者体験の向上にもつながる強力なサポートツールです。
本記事で紹介した内容を改めて整理すると、次のようになります。
- ツールはメールや電話の調整より圧倒的に効率的
- 導入により工数削減・辞退率低下・柔軟な日程調整が可能
- 社内浸透や臨機応変対応の課題もあるが、運用工夫で解決できる
- 自社の採用フローに合った種類・機能のツールを選定することが重要
導入を検討している企業は、まず自社の採用課題とフローを明確化し、それにマッチするツールを選びましょう。
正しく運用できれば、採用スピードと質の両方を向上させることが可能です。
面接日程調整ツールに関するFAQ
ここでは、面接日程調整ツールについて採用担当者からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
導入前の不安や疑問を解消し、スムーズな検討につなげましょう。
- 導入コストやランニングコストはどれくらいかかるのか?
- 無料プランと有料プランの違いは何か?
- セキュリティ面は安全なのか?
- 自社の採用管理システム(ATS)と連携できるのか?
- 候補者がツールを使いこなせない場合はどうするのか?
導入コストやランニングコストはどれくらいかかるのか?
ツールによって異なりますが、月額1,000〜5,000円程度が一般的です。 複数アカウント利用や追加機能を含めると、1ユーザーあたりの費用が増えるケースもあります。 まずは無料トライアルで実際の機能とコスト感を確認すると安心です。
無料プランと有料プランの違いは何か?
無料プランは基本的な日程調整機能が使えますが、予約枠数の制限やカレンダー連携の制約がある場合があります。 有料プランでは、複数人調整や自動リマインド、外部ツール連携など、採用現場で役立つ機能が充実します。
セキュリティ面は安全なのか?
多くのサービスはSSL暗号化通信やアクセス制限を実装しており、一定のセキュリティ基準を満たしています。 ただし、機密性の高い採用情報を扱うため、プライバシーマーク取得やISO27001認証の有無をチェックしましょう。
自社の採用管理システム(ATS)と連携できるのか?
近年のツールは、Googleカレンダー・Outlook・採用管理システムとの連携に対応しています。 ただし、すべてのATSに対応しているわけではないため、導入前に連携可否を確認することが重要です。
候補者がツールを使いこなせない場合はどうするのか?
スマホやPCに慣れていない候補者向けには、電話やメールでの代替調整フローを併用している企業もあります。 ツールはあくまで効率化の手段であり、候補者体験を損なわない柔軟な対応が求められます。
まとめ
面接日程調整は、採用活動において大きな負担となる業務ですが、面接日程調整ツールを導入することで効率化と候補者体験の向上が同時に実現できます。ツールは空き時間の自動抽出やリマインド送信を可能にし、従来のメール・電話調整よりも工数削減や辞退防止に効果的です。特に中途採用や複数面接官が関わるケースでは、ダブルブッキング防止やスピード改善が大きなメリットとなります。
一方で、社内定着の難しさやイレギュラー対応への弱さ、候補者との一方向的なやり取りといった課題も存在します。そのため、自社の採用フローに合ったツール型(予約受付型・提案型・投票型・ハイブリッド型)を選び、操作性やカレンダー連携、セキュリティ面を考慮することが重要です。実際に導入企業では、工数90%削減や辞退率低下といった成果が見られています。
総じて、面接日程調整ツールは「採用スピード」と「質」の両立を可能にする有効な仕組みです。自社の課題や候補者層に合わせて適切に運用すれば、採用成功の大きな支えとなります。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
[cta02 page_id=”1138″]
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

採用の歩留まりとは?項目例や5つの改善策を解説
- 採用代行

おすすめ採用コンサルティング会社のご紹介|サービスや導入メリットも解説!
- 採用コンサルティング
- 採用代行
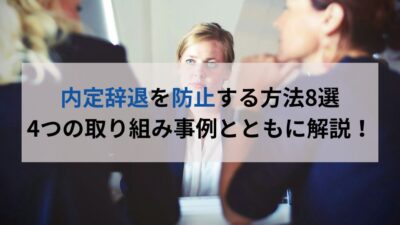
内定辞退を防止する方法8選│4つの取り組み事例とともに解説!
- 採用代行

【2025年最新】採用代行(RPO)サービス|依頼できる業務内容と選び方を徹底解説!
- 採用代行

【2025年最新版】求人媒体のおすすめランキング10選|種類解説と主要サービスを徹底比較!
- 採用代行
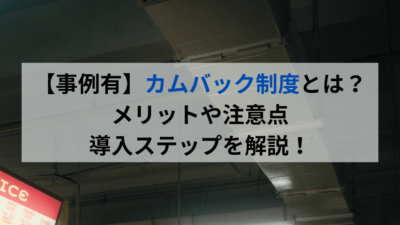
【事例有】カムバック制度とは?メリットや注意点、導入ステップを解説!
- 採用代行






