

近年、エンジニア採用は深刻な売り手市場に突入しており、「求人を出しても応募が来ない」「ようやく内定を出しても辞退される」といった声が、企業規模や知名度を問わず広がっています。
特にIT領域では、AIやSaaS、クラウドの台頭によって人材ニーズが急増し、採用競争は年々激化。これに加え、働き方の多様化や副業・フリーランス志向の高まり、キャリア観の変化など、従来の採用モデルが通用しない時代に突入しています。
本記事では、こうした構造的な採用難の要因を体系的に整理し、企業が直面している課題とその解決策を、現場目線での具体的な施策や最新のトレンドを交えながら詳しく解説します。
[cta01 page_id=”1076″]
関連動画:【採用担当必見】エージェント接点改善で応募数3倍|母集団形成術
エンジニア採用が難しい背景と市場環境
近年、エンジニア採用は「慢性的な売り手市場」と化しており、企業規模や知名度に関係なく、人材獲得に苦戦する企業が急増しています。応募が集まらない、選考途中での辞退が多発するなど、多くの企業で採用活動が計画通りに進まない事例が常態化しています。
この採用難の背景には、単なる一時的な人手不足ではなく、IT市場そのものの急速な成長や労働環境の変化、そして人材のキャリア観の多様化といった、複数の外部環境の変動が複雑に絡み合っています。
ここでは、現代のエンジニア採用を取り巻く外的要因を体系的に整理し、なぜ今これほどまでに採用が困難なのか、その構造的な理由について解説していきます。
- エンジニア求人倍率の推移と現在地
- IT市場拡大による人材需要の急激な高まり
- 働き方多様化・フリーランスシフトのインパクト
- コロナ後リモート普及が招いた採用競争の激化
- 2025年以降の需給予測と企業への示唆
エンジニア求人倍率の推移
まず、エンジニア採用が難しいとされる最大の理由は圧倒的な求人倍率の高さにあります。
レバテックの調査によれば、2025年上半期のエンジニア求人倍率は11.6倍を記録しており、1人の求職者に対して10社以上が競合している状態です。
これは他業種と比べて極めて高い水準であり、エンジニア採用は「待つだけでは成立しない」フェーズに突入していると言えるでしょう。
【参考文献】「エンジニアの求人倍率は?職種別の推移や最新動向を解説」レバテック
IT市場拡大による人材需要の急激な高まり
近年のIT市場は、AIやSaaS、IoTなどの技術革新により急拡大しており、企業にとってテクノロジー活用は経営戦略の中核となっています。それに伴い、「デジタル人材の確保」があらゆる業界で最優先課題として位置付けられるようになりました。
中堅〜上級エンジニアやAI・クラウドに強い人材への需要が集中する一方、教育機関や育成インフラの供給は追いついておらず、人材市場には慢性的なギャップが生じています。企業は単に求人を出すのではなく、他社よりも早く接点を持ち、選考体験や入社後の環境を含めた総合的な魅力訴求を行うことが重要です。
働き方の多様化
2020年以降のコロナ禍や副業解禁の流れを受け、エンジニアの働き方は大きく変化しました。正社員として1社に勤めるスタイルから、フリーランスや副業など複数企業に関わる柔軟な働き方へとシフトしています。
この変化により、企業側も正社員前提の採用戦略だけでは優秀な人材にリーチできなくなってきました。勤務地や勤務時間、契約形態に柔軟性を持たせることが、採用成功の鍵となっています。今後は「働き方の選択肢を用意できるか」が、競争力の分かれ目になるでしょう。
リモート普及が招いた採用競争の激化
リモートワークの普及により、地方企業でも首都圏の人材にアクセスできるようになりました。これは一見チャンスに思えますが、裏を返せば全国の企業が同じ人材を奪い合う時代に突入したことを意味します。
こうした状況では、都市部か地方かに関係なく、優秀な人材をめぐる競争が激化し続けています。従来の求人媒体や人材紹介だけに頼る採用手法では埋もれてしまい、自社の魅力が届かなくなる恐れもあり、戦略的な訴求と候補者目線での採用設計が求められます。
2025年以降の需給予測と企業への示唆
経済産業省の報告では、2030年にはIT人材が最大で79万人不足すると見込まれています。これは今後も採用難が長期的に続くことを示しており、企業は「一時的な人材不足」ではなく「恒常的な構造課題」として認識すべきフェーズに入っています。
つまり、従来の採用依存型組織ではなく、内製力・育成・フリーランス活用など、多様な手法を組み合わせた人材戦略が求められているのです。
【参考文献】「IT人材需給に関する調査」経済産業省
企業が抱える採用課題の真因
エンジニア採用を困難にしているのは、求人倍率や市場の変化といった外部要因だけではありません。多くの企業が見落としがちなのが、社内に潜む構造的な問題です。「なぜ採れないのか」「なぜ辞退されるのか」には、企業側の内部課題が深く関係しています。
ここでは、現場でよく見られる5つの採用課題を整理し、それぞれがどのように採用失敗につながっているのかを具体的に掘り下げていきます。
- 採用基準と市場感のギャップ
- ターゲット設計・ペルソナ設定の欠落
- スキル見極めプロセスの不備
- 候補者動機づけ・フォロー体制の弱さ
- 内定辞退を招くコミュニケーションロス
採用基準と市場感のギャップ
「実務経験5年以上」「開発リーダー経験あり」など、企業が掲げる要件が理想に偏りすぎていないでしょうか。書類選考の通過率が著しく低い、そもそも応募がほとんど集まらないといった場合、採用基準が市場実態とかけ離れている可能性が高いといえます。
母集団を確保し選考を進めるためには、「現場で活躍できるミニマム条件は何か」「あとから育成可能なスキルは何か」といった視点で、要件の取捨選択を行う必要があります。要件定義を柔軟に見直すことこそが、採用活動のスタートラインと言えるでしょう。
ターゲット設計・ペルソナ設定の欠落
採用活動において「誰を採るのか」が曖昧なまま進めてしまっている企業は、実は少なくありません。求人票の内容がぼんやりしていては、応募者が自分ごととして捉えることができず、結果として応募数も質も伸び悩むことになります。
ペルソナ設計が不十分な状態で採用を始めると、「誰にも刺さらない内容」で工数だけが膨らみ、最終的に採用目標未達に終わるリスクが高まります。自社がどのような人材を、なぜ必要としているのかを言語化することは、費用対効果の高い母集団形成にも直結します。
スキル見極めプロセスの不備
技術職であるエンジニアの採用において、スキルの見極めは極めて重要です。しかし現場では、評価を担当する面接官がエンジニアではなく、候補者の本来の実力を正しく把握できず、優秀な人材を見逃してしまうリスクが高まります。
また、選考基準そのものが属人化しており、評価ポイントが面接官によって大きくばらついている企業も多く見られます。
ポートフォリオやGitHubといった実績を確認しないまま面接だけで判断してしまうと、客観的なスキル評価が難しくなります。
候補者動機づけ・フォロー体制の弱さ
選考が進んでも「この会社に入りたい」と思ってもらえなければ意味がありません。候補者が内定を選ぶ要因の多くは、「企業からの誠実な姿勢」と「自分のキャリアに合う環境」だと言われています。
しかし、多くの企業が「スカウト送付で満足」「面接後のフォローがない」といった受け身の体制になっており、意向醸成=アトラクト施策が不足しています。
内定辞退を招くコミュニケーションロス
内定までたどり着いても、入社前に辞退されてしまうケースは少なくありません。その背景には、多くの場合、企業側のコミュニケーション不足が存在しています。
選考が終了してから実際の入社までに長い期間が空くにもかかわらず、企業側からの連絡が途絶えたままという状況は候補者に不信感を与えます。
加えて、入社後の業務内容やチーム体制、働き方といった情報が十分に共有されず、候補者の中で入社後のイメージが曖昧なままになってしまうと、候補者は他社に気持ちが傾いたり、採用自体を見送ったりする選択を取ることになるのです。
エンジニア採用を成功させる具体施策
エンジニア採用がうまく進まない理由は、社内の準備不足や運用体制の未整備といった内的な要因です。スカウトを送っても反応が薄い、内定を出しても辞退が続くなどの現象の裏には、求職者視点に立った設計や、選考プロセスの柔軟性が欠けているという構造的な課題があります。
そこで本章では、構造的な課題に対し具体的にどのようなステップを踏めばよいのかについて段階的に解説していきます。
- 雇用条件をターゲットに合わせて最適化
- 書類選考より「会って判断」を優先
- 候補者都合を最優先に日程調整
- 個別動機づけシナリオを設計する
- 内定後〜入社までのオンボーディング
雇用条件をターゲットに合わせて最適化
まず重要なのが、募集ポジションの年収、勤務条件、勤務地、使用技術などを、ターゲット人材の市場水準と照らし合わせて設定することです。
たとえば、フルリモート勤務を希望する人材に「週3出社必須」と提示してもミスマッチが起きるだけです。条件の緩和や柔軟性をもたせることが、母集団の質と量に直結します。
さらに「スキルが満たない人材には教育プランを用意する」など、長期的視点を持った採用設計が採用力の差につながります。
書類選考より「会って判断」を優先
エンジニアの技術的な素養や実務力は、文面だけでは伝わりづらいことが多く、書類選考の段階で優秀な人材を見逃してしまうリスクがあります。だからこそ、最初から形式的な書類に頼らず、まずはカジュアル面談などで直接会ってみる姿勢が重要です。
実際の現場では、技術ブログやポートフォリオの提出を促すことで、候補者のアウトプットからスキルや思考の癖を読み取ったり、1次選考に進む前のタイミングで面談を設けて人物像を柔らかく把握したりといったアプローチが有効です。
候補者都合を最優先に日程調整
競合が激しいエンジニア採用市場において、選考スピードは内定獲得の成否を左右する重要な要素です。企業側が日程調整の主導権を握り、「この日程でなければ対応できない」といった姿勢を見せると、候補者は他社と比較する中で自分に関心が薄いと受け取ってしまい、辞退や離脱の原因になります。
特にハイクラス人材や複数社から同時にアプローチを受けている層にとっては、リードタイムの短さや柔軟性がそのまま誠意と受け取られます。そのため、候補者が希望する時間帯や使用したいツール(Zoom、Google Meetなど)を優先的に受け入れ、可能であれば1日以内に日程を確定できる体制を整えておくべきです。
個別動機づけシナリオを設計する
求職者が入社を決める際、企業が提示する条件だけで判断しているわけではなく、内面的な納得感が、意思決定に強く影響します。そのため、全員に同じメッセージを送るのではなく、候補者一人ひとりに合わせた動機づけの設計が欠かせません。
実際に現場で働くエンジニアとの交流の場を設けることで、価値観の一致やカルチャーへの共感が生まれやすくなり、一貫したコミュニケーションが、選考を評価の場から信頼関係の構築プロセスへと変えていくのです。
オンボーディングとリテンション強化
無事に内定承諾を得られたとしても、それで採用活動が完了するわけではありません。むしろ本質的に重要なのは、入社前後のフェーズでエンジニアが感じる不安や懸念をいかに解消し、長期的に活躍できる土台をつくるかという点です。
たとえば、入社前に技術課題やチームメンバーとの事前面談を行うことで心理的ハードルを下げたり、SlackやNotionを活用して情報を事前共有することで安心感を高めたりするアプローチが効果的です。
また、入社後90日間をフォローアップ期間として位置づけたサポートプログラムを設計することで、早期離職の予防やモチベーションの維持にもつながります。
おすすめ採用手法と活用ポイント
エンジニア採用において、「どのチャネルを使うか」という判断は、採用の成否を左右する極めて重要な要素です。求人数の多さと応募者の少なさが続く今の市場では、「採用ターゲットに対して、最も効果的にリーチできる手段は何か」という視点でチャネルを選定する必要があります。
各チャネルにはそれぞれ強みと限界があり、目的とチャネル特性を明確に照らし合わせることで、無駄のない採用活動が実現できるのです。
ここでは、4つの採用チャネルを取り上げ、それぞれの効果を最大限引き出すための活用ポイントを整理します。
- 人材紹介サービス:即戦力採用を加速
- ダイレクトリクルーティング:母集団の質を高める
- リファラル採用:社内ネットワークの活用術
- フリーランス・副業人材:柔軟なリソース確保
人材紹介サービス
人材紹介サービスは、エージェントが自社の採用要件に合った候補者をピンポイントで紹介してくれる仕組みです。社内に採用専任のリソースが不足している企業でも、スピーディーに選考を進められる点が大きな強みです。
一方で、紹介会社をむやみに増やしすぎると、候補者へのアプローチが重複したり、進捗管理が煩雑になったりするリスクもあります。また、エージェントの質によって紹介される人材の精度が大きく異なるため、エンジニア領域に特化した専門エージェントを選ぶことが成功の鍵です。
初期費用がかからない成果報酬型であることも特徴ですが、受け身で待っているだけでは成果に結びつきません。面接設定やフィードバックのスピード、候補者への対応の丁寧さが結果を左右するため、企業側も迅速かつ誠実な対応体制を整えておく必要があります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、ビズリーチやLinkedInを活用し、企業側から候補者へ直接アプローチを行う採用手法です。応募を待つのではなく、自ら動いて人材と接点を持つことで、転職潜在層にもリーチできるのが大きな特長です。
スカウト文面は、テンプレート的な内容ではなく、相手の経歴やスキルに合わせて個別にカスタマイズされたメッセージが重要です。そのうえで、返信率や開封率を継続的に分析し、PDCAを回す運用体制を整えることが求められます。
さらに、現場のエンジニアとの連携を通じて面談設定率を高めることも不可欠です。開発チームの協力を得ることで技術的な共通言語が生まれ、候補者の信頼を得やすくなります。
リファラル採用
リファラル採用とは、社内のエンジニアや他部門の従業員が、自身の知人や元同僚を紹介することで候補者とつながる採用手法です。紹介者の存在があることで、候補者は企業への信頼感を持ちやすく、入社後のミスマッチや早期離職のリスクが低減するという利点があります。
しかしながら、紹介者にとって「誰をどう推薦すればよいのか」が明確でなければ、制度が形骸化してしまいます。そのためには、職種ごとの推薦ポイントや求める人物像を社内に明示し、紹介のハードルを下げる工夫が求められます。また、適切なインセンティブ設計によって、従業員の関与意欲を高めることも効果的です。
紹介者が評価され、成果としてフィードバックされる環境があることで、採用は人事部門だけの仕事ではなく、会社全体で支える文化へと転換していきます。こうした文化づくりこそが、リファラル採用を持続可能な仕組みにする鍵なのです。
フリーランス・副業人材
フリーランスや副業のエンジニアを活用することは、正社員採用が難航しているポジションや、立ち上げ直後のプロジェクトなど即戦力が求められる場面において非常に有効です。こうした働き方の多様化は、企業にとっても新たな人材獲得チャネルとなっています。
一方で、活用にあたっては事前の取り決めが欠かせません。契約書には知的財産や成果物の権利帰属について明記しておくことで、後々のトラブルを回避できます。また、Slackや定例ミーティングなどを通じて社内メンバーとの連携体制を整えておくことも重要です。
フリーランス人材は「即戦力だが、短期的」という特性を持っていることを理解し、自社のプロジェクトスコープや事業フェーズに応じて柔軟に活用することが求められます。
採用を加速させる社内仕組みとKPI
エンジニア採用を継続的に成功させるためには、単発の施策やツール導入だけでは不十分です。肝心なのは、採用活動を再現性ある組織の仕組みとして定着させ、社内全体で一気通貫のオペレーションを構築することです。
どれだけ優れたチャネルを活用しても、社内の巻き込みやプロセス管理が甘ければ、成果が継続しないどころか、採用活動そのものが属人的になりやすくなります。
ここでは、エンジニア採用を「組織で動かす」ために欠かせない体制整備のポイントを解説します。
- 採用KPI設計とダッシュボード運用
- エンジニア巻き込み型面接体制
- データドリブン施策改善サイクル
- グローバル採用・リモート体制への拡張
採用KPI設計とダッシュボード運用
採用活動を戦略的に進めるうえで欠かせないのが、プロセスを見える化する仕組みの構築です。KPIを事前に定め、リアルタイムで進捗を確認できるダッシュボードを整備することで、定量的な採用マネジメントが可能になります。
チャネル別の応募数や採用単価(CPA)、内定承諾までにかかる平均リードタイムなども重要な指標です。これらのデータを集計・可視化することで、ボトルネックの特定と改善がスムーズになります。結果として、感覚や経験則に頼らず、データドリブンな採用改善サイクルを実現できるようになるのです。
エンジニア巻き込み型面接体制
人事部門だけではなく、実際に働く現場エンジニアを選考プロセスに巻き込むことで、候補者との接点がよりリアルで具体的なものとなり、企業理解の深まりやカルチャーマッチへの納得感が高まります。
効果的な取り組みとしては、人事・現場エンジニア・マネージャーの三者で行うトリプル面接や、書類選考の後の早い段階から現場メンバーがカジュアル面談に参加する仕組みが挙げられます。
さらに、採用ピッチ資料や技術スタック紹介資料などを現場主導で作成することで、より実態に即した訴求が可能になります。
データドリブン施策改善サイクル
KPIを設定するだけでは、採用活動は前に進みません。重要なのは、その数値を起点にした改善サイクルです。たとえば、書類通過率が著しく低い場合、求人票の内容がターゲットに響いていないといった仮説を立て、文面の構成や表現を見直し、翌月の効果を数値で検証する。こうした小さな改善の積み重ねが、成果につながります。
改善アクションをスピーディーに実行し、その結果をダッシュボードでタイムリーに振り返ることで、感覚や属人性に依存しない意思決定が可能になります。この数字で話す文化こそが、採用の精度と再現性を高め、組織としての採用力を継続的に強化する土台になります。
グローバル採用・リモート体制への拡張
エンジニア採用の競争が年々激化する中で、優秀な人材を確保するために「国内人材のみに限定しない」方針を取る企業が増えています。特に先端分野では、日本国内だけでは人材の供給が追いつかず、海外在住のエンジニアやフルリモートワーカーへのアプローチが現実的な選択肢となっています。
その実現には、英語による選考体制の構築や、海外向けのジョブディスクリプション整備が不可欠です。また、複数のタイムゾーンで稼働するメンバーを前提としたプロジェクト設計や、リモート勤務を前提としたパフォーマンス評価基準の標準化も求められます。
エンジニア採用で失敗しないための4つの留意点
エンジニア採用は、他職種に比べて専門性が高く、わずかな対応ミスや認識のズレが致命的な結果につながりかねません。どれほど優れた戦略やチャネルを駆使しても、基本的な配慮が欠けていれば、内定辞退や企業ブランドの毀損という形で跳ね返ってきます。
特に中途採用の現場では、「良かれと思ってやったこと」が逆効果になることも多く、注意すべきポイントを体系的に把握しておく必要があります。
ここでは、エンジニア採用の実務でよく見られる見落とされがちな落とし穴について、背景と対策を交えて解説します。
- 法務リスクを見落とさない
- ポテンシャル人材を逃さない
- オファーレター条件の後出し変更は厳禁
- 選考リードタイム長期化へのバックアップ策がない
法務リスクを見落とさない
フリーランスや副業人材を活用する際に企業が陥りやすいのが、法務的なリスクを十分に考慮せずに契約を進めてしまうことです。とくに多いのは、成果物の著作権や使用権の帰属先が曖昧なまま開発が進み、後になってトラブルに発展するケースです。
さらに、副業人材の受け入れに際して、自社の就業規則や勤怠管理体制が追いついていない場合も多く見受けられます。法務部門と連携しながら、フリーランスや副業者向けの契約雛形を整備し、それに基づいた運用フローを社内に浸透させることが欠かせません。
ポテンシャル人材を逃さない
採用現場では、早期に選考を進めるために「今持っているスキル」だけで候補者を評価してしまうケースが少なくありません。しかしそのアプローチでは、将来的に大きく成長する可能性を持ったポテンシャル人材を見逃してしまうリスクがあります。
特に若手や技術領域を転換してキャリアを築こうとする人材に対しては、現時点の完成度だけでなく、学習スピードや習慣、自走力といった成長の伸びしろを丁寧に見極める視点が重要です。
即戦力ばかりを追い求める採用方針から一歩引き、「育てて活かす」視点を持つことが、結果的に組織の持続的な成長を支える人材戦略の鍵となります。
オファーレター条件の後出し変更は厳禁
エンジニア採用の最終段階で起こりやすい大きな失敗のひとつが、オファーレターを提示した後になって条件を変更してしまうことです。たとえば、提示した年収が予算を上回ったために減額を打診したり、当初リモート勤務としていたにもかかわらず急に出社日数を増やしたりするケースがあります。
このような「後出し」の対応は、たとえ企業側に意図がなくても、候補者の信頼を一瞬で損なう行為です。一度失った信用は簡単には取り戻せず、内定辞退や企業イメージの毀損につながる恐れもあります。
したがって、オファー条件は社内で事前に100%確定させたうえで提示し、どの段階でも一貫性のある誠実なコミュニケーションを徹底することが、採用成功の大前提となります。
選考リードタイム長期化へのバックアップ策がない
エンジニア採用では、選考プロセスが長期化するケースが珍しくありません。技術面の見極めや現場との面接調整、コーディングテストなどが複数挟まれることにより、スケジュールが伸びがちになります。この期間中に候補者との接点が薄れると、「放置されている」と感じさせてしまい、最終的な辞退や他社への流出リスクが高まります。
そうした事態を防ぐには、選考の合間にカジュアルな面談や近況のヒアリングを挟み、候補者の温度感をこまめに確認しておくことが有効です。さらに、現場メンバーとの座談会など、業務外のコミュニケーション機会を設けることで関係構築を継続できれば、選考期間中のモチベーション維持にもつながります。
エンジニア採用が難しいについてよくある質問(FAQ)
エンジニア採用が難しいことについてよくある質問をまとめました。
未経験エンジニアの採用は現実的?
育成体制が整っていれば、未経験者でも十分に戦力化できます。エンジニア採用では、長期的な視点で人材育成を計画することが鍵です。
他社と差別化するには何が効果的?
選考体験や社員の雰囲気、技術環境などの「カルチャー訴求」が大きな差別化要因になります。求職者目線での情報発信をすることで、働く際のイメージはしやすくなります。
エンジニアの選考ではどんな質問が効果的?
過去の開発経験や課題解決のプロセスを深掘る質問が有効です。技術力だけでなく、思考力や協調性も見極めやすくなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、エンジニア採用が難しい背景と構造的課題、さらにその解決に向けた具体施策までを体系的に紹介しました。
エンジニア採用は、単なる人手不足ではなく、IT市場の急成長・働き方の変化・人材ニーズの高度化といった複合的な要因が絡む難易度の高い領域です。だからこそ、社内の採用体制やチャネル選定、候補者との向き合い方を一つひとつ見直すことが欠かせません。
本記事を参考に、自社に合った施策を見つけ、再現性のある採用体制構築に向けた第一歩を踏み出してみてください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
[cta02 page_id=”1087″]
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
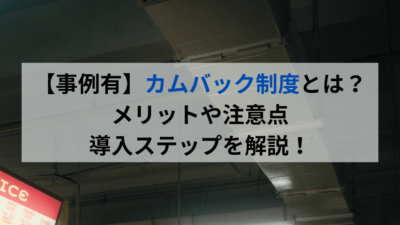
【事例有】カムバック制度とは?メリットや注意点、導入ステップを解説!
- 採用代行

【2025年最新】採用代行(RPO)サービス|依頼できる業務内容と選び方を徹底解説!
- 採用代行
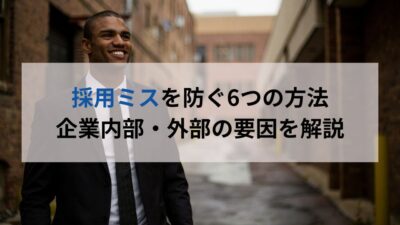
採用ミスを防ぐ6つの方法|企業内部・外部の要因を解説
- 採用代行

デザイナー採用が難しい理由は?7つの採用手法や見極め方法を解説!
- 採用代行
コーポレート用アイキャッチのコピ-8-400x225.jpg)
【2025年版】採用コンサルティングとは?おすすめサービス4選を解説
- 採用代行
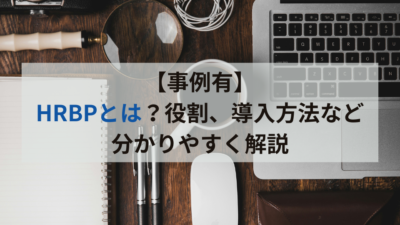
【事例有】HRBPとは?役割、導入方法など分かりやすく解説
- 採用代行






