
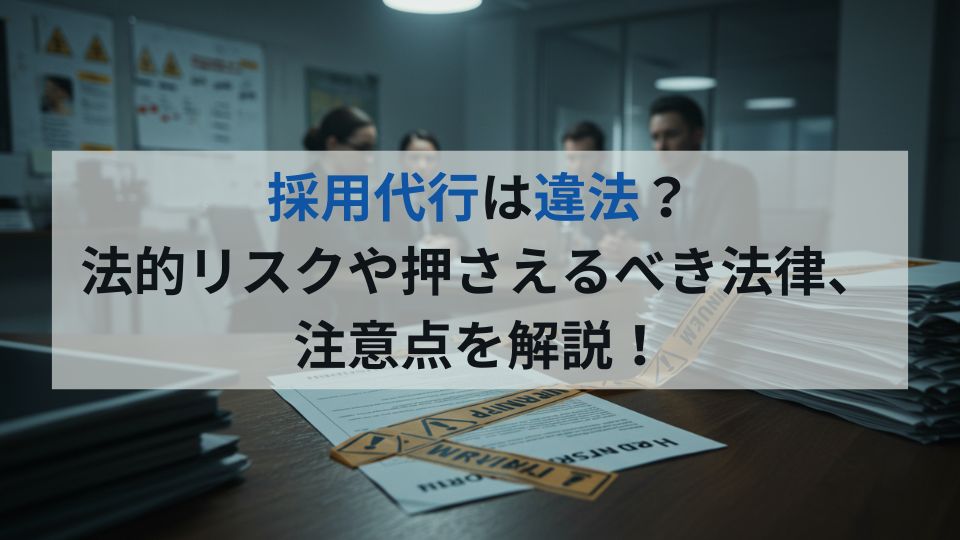
採用活動を効率化する手段として注目を集める「採用代行(RPO)」ですが、利用方法を誤ると違法行為に該当するリスクがあることをご存じでしょうか。
職業安定法や労働基準法、個人情報保護法など、採用代行には複数の法律が関わっており、無許可の委託募集や虚偽の求人広告、応募者情報の不適切な管理はすべて企業自身の責任問題につながります。
本記事では、採用代行の違法性に関わる代表的なケースと、違法リスクを回避するために押さえておくべき契約・業者選び・社内体制のポイントをわかりやすく解説します。
改めて知りたい、採用代行とは
採用活動の高度化・多様化が進む中、近年多くの企業で導入が進んでいるのが「採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)」です。
採用代行とは、企業の採用活動における一部または全部の業務を外部の専門業者に委託するサービスです。
業務範囲は、求人票の作成や応募者対応、日程調整といったバックオフィス的な業務から、書類選考・面接代行、採用戦略の立案・運用支援にまで及びます。
企業の採用ニーズやリソース状況に応じて、カスタマイズした支援を受けられるのが特徴です。
背景には、採用市場の競争激化や、人事部門の業務過多、そして人材の専門性が求められるようになったことがあります。
特に中小企業やスタートアップでは、専任の採用担当者が不在であったり、複数の業務を兼任していたりすることも多く、こうした負荷軽減と精度向上を目的に採用代行を導入するケースが増えています。
ただし、業務範囲や契約内容によっては、法的な規制が関わる部分もあり、注意が必要です。
企業側が押さえるべき関連法
採用代行サービスを利用する際には、その業務の内容や範囲によって複数の法律が関係してくるため、企業として法的観点を押さえておくことが不可欠です。
知らずに違法行為に該当してしまうリスクを避けるためにも、以下の主要な関連法のポイントを理解していきましょう。
- 職業安定法
- 労働基準法
- 個人情報保護法
- 労働者派遣法
- 行政手続法
職業安定法
職業安定法は、求人・求職活動や職業紹介に関する基本的なルールを定めた法律で、採用代行業務において最も中心的な法令のひとつです。
とくに注視すべきは「委託募集」と呼ばれる形式です。
企業が外部に求人募集業務を委託する際には、受託側に対して職業紹介事業や労働者供給事業の許可が必要となる場合があります。
許可を得ずに行うと法令違反に該当するリスクがあるため、委託内容が職業安定法の対象業務に当たるかどうかを事前に確認することが重要です。
労働基準法
労働基準法は、雇用契約や労働条件の明示など、労働者の権利保護に関するルールを定める法律です。
採用段階での労働条件通知書の交付や、労働時間・賃金に関する記載内容の正確性も求められます。
代行業者がこれらの情報を提示したり、面接で説明を行う場合、誤った内容を伝えると委託元企業が責任を問われる可能性があります。
個人情報保護法
採用活動では、応募者の履歴書や職務経歴書など、多くの個人情報を取り扱います。
採用代行を活用する場合、その情報が第三者である業者に渡るため、個人情報保護法に基づく取り扱いの適正性が問われます。
応募者本人への事前同意取得や、委託先に対する契約書での守秘義務規定の明記が必要です。
また、個人情報の保存期間や削除ルールについても、明確な基準を設けておくべきでしょう。
労働者派遣法
労働者派遣法は、労働者を他社に派遣して働かせる事業を規制する法律です。
採用代行のうち、業務内容が一時的に企業の業務指示下で働くような性質を帯びる場合、派遣契約として扱われることがあります。
派遣法の適用対象になると、業者側に派遣事業許可が必要になるほか、就業場所や就業条件の管理責任も発生します。
行政手続法
採用代行に関連する許可申請や届出を行う際には、行政手続法が適用されます。
例えば、委託募集に該当する業務を行うには、厚生労働省や都道府県労働局への届出・申請が必要であり、これを怠ると行政処分の対象になることがあります。
手続きの透明性・公平性を保つためにも、行政手続法で定められた期限・書式・提出先を守ることが求められます。
【5選】違法となる主なパターン
採用代行サービスは便利である一方で、業務の内容や範囲によっては法に抵触するリスクが潜んでいます。
企業が注意すべき代表的な違法パターンについて、以下に分けて解説していきます。
- 委託募集の無許可での実施
- 業務範囲を超えた採用支援行為
- 違法な求人情報の掲載
- 応募者情報の不適切な管理・使用
- 報酬体系の職安法への抵触
委託募集の無許可での実施
もっとも代表的な違法行為が、無許可での委託募集です。
職業安定法において、企業が採用活動を第三者に委託し、候補者との接点を持たせる行為(例:スカウト、求人情報の掲載、面接代行など)は「職業紹介」とみなされる場合があります。
このような業務を委託先が行うには、厚生労働大臣の認可を受けた有料職業紹介事業者である必要があります。
認可を得ていない事業者に委託すれば、企業側も共同責任を問われる可能性があるため、委託先の許可状況を事前に確認することが不可欠です。
業務範囲を超えた採用支援行為
採用代行の契約内容を超えて、業務範囲外の行為が行われるケースも要注意です。
例えば、委託先が労働条件の提示や内定通知の発行を勝手に実施した場合、それは法令に基づく企業責任の逸脱と見なされる可能性があります。
受託者にその権限が明確に付与されていない状態で、採用決定に関与する行為を代行させることは、法律的にグレーまたは違法とされるリスクがあります。
違法な求人情報の掲載
虚偽や誤解を招く求人広告の掲載は、労働基準法や景品表示法の観点からも重大な違反行為に該当します。
採用代行会社が求人票を作成・掲載する際に、企業から十分な確認を取らずに情報を記載した場合、事実と異なる記載になってしまうリスクがあります。
この場合、最終的には委託元である企業が責任を問われる可能性が高く、慎重な内容確認とガイドラインの共有が欠かせません。
応募者情報の不適切な管理・使用
個人情報保護法に違反する恐れのある行為として、応募者情報の目的外利用や、安全管理措置の不備が挙げられます。
採用代行業者が履歴書や評価記録を適切に管理せず、第三者に漏洩した場合、企業側も監督責任を問われることになります。
たとえ故意でなくても、不正アクセスやデータの持ち出しなどが起きた場合には、法令違反として厳しく追及されます。
報酬体系の職安法への抵触
成果報酬型の契約内容が、職業安定法に違反するケースもあります。
「採用1名につき●万円」など、採用実績に基づいて報酬が発生する契約は、事実上の職業紹介とみなされる可能性があり、許可のない事業者には認められていません。
このような報酬体系で委託する場合には、業務の内容が完全に紹介行為に該当しないかを慎重に判断する必要があります。
【3選】コンプライアンスを守る採用代行の選び方
採用代行サービスを導入するにあたって、最大のリスクは「違法な委託によって企業自身が法的責任を問われる」ことです。
ここでは、法令遵守の観点から信頼できる採用代行業者を見極めるためのポイントを3つに絞って解説します。
- 許可・認可の有無の確認
- 実績と専門性の見極め
- セキュリティチェック
許可・認可の有無の確認
最初に確認すべきは、業者の許可・認可の有無です。
採用代行の業務内容が「職業紹介」や「労働者派遣」に該当する場合、業者は厚生労働省からの認可を受けている必要があります。
有料職業紹介事業許可や労働者派遣事業許可を取得していない業者に委託すると、たとえ無自覚であっても企業側が違法行為に関与したとみなされる恐れがあります。
業者のウェブサイトや契約書で、許可番号や取得日などが明記されているかを必ず確認しましょう。
実績と専門性の見極め
次に重視すべきは、業者の実績と専門性です。
採用代行は単なる業務の「外注」ではなく、企業の人材戦略に関わる重要業務です。
過去にどのような業界・職種で支援実績があるか、RPOに関するノウハウや選考設計の知見がどれほどあるかなどを丁寧にヒアリングし、これを判断基準としましょう。
特に「法令を順守した運用」に関する知見の有無は、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。
セキュリティチェック
応募者情報や選考結果など、機密性の高い個人情報を扱う以上、セキュリティ体制の確認は不可欠です。
具体的に、情報の暗号化通信の有無、アクセス権限の管理方法、ログの記録と監視体制、サーバー保管場所の明記など、情報管理基準が高い業者ほど信頼性が高いといえます。
また、ISMSなどの情報セキュリティ認証を取得している業者であれば、一定水準の対策が講じられていると判断できます。
法的リスクを最小化する社内体制
信頼できる採用代行業者を選んだとしても、企業側が適切な社内体制を整えていなければ、法令違反のリスクを完全に排除することはできません。
法的リスクを最小限に抑えるために必要な自社内体制の構築ポイントを紹介します。
内製・委託業務の線引き
まずは、内製業務と委託業務の明確な切り分けが必要です。
たとえば、労働条件の提示、採用の最終決定、契約締結など、法的責任を伴う部分は原則として企業側が担うべきです。
一方で、面接日程の調整や書類の一次選考といった業務は代行可能です。
あらかじめ委託可能な業務範囲を明文化し、契約書で定義しておくことで、責任の所在を明確にすることができます。
社員教育とガバナンスの徹底
次に重要なのが、社員への法令順守教育と、部門間のガバナンス体制の整備です。
採用に関わる部門(人事、現場マネージャーなど)が、外部委託のリスクを正しく理解し、委託先との連携において適切な判断を下せるよう研修を実施することが有効です。
また、委託先との契約更新や業務報告の確認を行う監査的な役割を担う部署を明確にしておくことも、統制強化につながります。
顧問弁護士・社労士の活用
外部の法律専門家の知見を活用することも、リスク管理の上で極めて有効です。
採用代行契約を締結する際のリーガルチェックや、法令改正時の対応方針のアドバイスなど、顧問弁護士や社会保険労務士の意見を参考にすることで、
契約内容や運用方法におけるリスクを事前に把握・回避することが可能になります。
社内に法務部がない中小企業こそ、こうした外部リソースの活用を検討すべきです。
定期モニタリングと改善プロセス
いかに優れた体制を整えても、継続的な改善とチェックがなければ、運用上のリスクは蓄積していきます。
採用代行業務の進行状況や成果、トラブルの有無などについて、定期的なモニタリングを実施し、必要に応じて業務フローや契約内容を見直すプロセスを構築していきましょう。
定例会議やレポートの提出をルール化し、透明性の高い情報共有を実現することで、潜在的なリスクの早期発見と是正につながります。
採用代行を活用する際の注意点
最後に、改めて実際に採用代行を利用する際に押さえておくべき注意点を整理していきましょう。
業務委託契約書の明確化
採用代行を利用する際には、契約書で業務内容を明文化しておくことが大前提です。
業務範囲、成果物の定義、報告義務、秘密保持、法令遵守、損害賠償責任などを明記し、曖昧な表現を避ける必要があります。
特に、労働条件の提示や内定通知の有無といった法的リスクの高い業務については、委託範囲外と明記するなど、リスクを回避する文言を盛り込むことが有効です。
成果物の検収ルールの設定
成果物の品質管理も非常に重要です。
求人票や選考報告書などの検収基準を契約時に定めておくことで、代行業者のパフォーマンスに対する評価基準が明確になります。
また、検収に不備があった場合の修正依頼方法や、納品後のトラブルに備えた責任分担についても、事前に合意しておくことが望ましいです。
業者まかせの状態では、思わぬ品質低下や責任の押し付け合いに発展しかねません。
対応業務範囲の合意と文書化
契約前後での認識の齟齬を防ぐためにも、対応業務範囲は文書化しましょう。
採用計画の策定から、求人媒体選定、応募対応、面接調整、結果通知に至るまで、どこまでを委託し、どこからを自社で対応するのかを、具体的な業務リストとして整理することで、役割分担を明確にし、双方が責任を持てる体制を築くべきです。
利用ツール・データ連携の確認
採用代行業務では、ATS(採用管理システム)やチャットツールを通じた情報共有が日常的に発生します。
利用するシステムのセキュリティレベルや、データの取扱ルール、アカウント管理、ログの取得有無など、情報連携のあり方についても事前にすり合わせが必要です。
万が一のデータ紛失や不正アクセスを防ぐためにも、アクセス権限の設計と社内承認フローの整備は欠かせません。
業務見直し・改善のPDCA設計
採用代行は「導入して終わり」ではありません。
定期的な業務見直しと改善サイクルの設計が求められます。
KPI(応募数、通過率、内定率など)を定め、達成状況に応じて改善策を講じる体制を作ることで、採用活動全体の最適化につながります。
また、委託先との定期レビュー会議を設けることで、柔軟な対応や関係性の強化も期待できます。
採用代行についてよくある質問(FAQ)
採用代行についてよくある質問をまとめました。
採用代行を使うと違法になるの?
違法になる可能性はあります。特に職業紹介や委託募集に該当する業務を許可なしで行うと、企業も法的責任を問われることがあります。
違法な業者を見分けるには?
厚生労働省の認可を持っているかをまず確認しましょう。加えて、契約書の明確さや実績、セキュリティ体制をチェックすることが重要です。
契約書にはどんな内容を盛り込むべき?
業務範囲や成果物、秘密保持、責任分担などを具体的に記載する必要があります。特にリスクの高い業務は委託対象外と明記しておくと安心です。
違法性に対して社内で気をつけるべき点は?
委託範囲を明確化し、社員教育や定期的なモニタリングを行うことが大切です。さらに、弁護士や社労士といった専門家の活用もリスク回避に有効です。
採用代行を安全に使うにはどうすればいい?
まずは信頼できる業者を選び、法令を意識した契約や運用を徹底しましょう。あわせて、社内のガバナンスやセキュリティ体制を整備することが欠かせません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、採用代行が違法になってしまう場合があるリスクと、法令遵守のために押さえておくべきポイントを詳しく解説しました。
採用代行には多くのメリットがある一方で、業務範囲や契約内容によっては違法行為に該当するリスクも潜んでいます。
職業安定法・労働基準法・個人情報保護法など、複数の関連法令に注意を払いながら、業者選定・契約書の内容・社内体制を適切に整備することが重要です。
ぜひ本記事を参考に、採用代行を活用した採用への準備・見直しを進めてみてください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

エンジニア採用で失敗しないための質問16選|優秀な人材を見抜く質問も解説!
- 採用代行

【2025年最新版】ITエンジニア不足の現状と企業が取るべき対策を徹底解説!
- 採用代行
コーポレート用アイキャッチのコピ-8-400x225.jpg)
【2025年版】採用コンサルティングとは?おすすめサービス4選を解説
- 採用代行

自社に最適な採用チャネルとは?種類と特徴、サービス選定のポイントを徹底解説!
- 採用代行

採用ができない理由は?13個の原因と解決策を徹底解説
- 採用代行
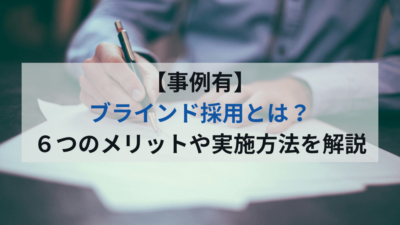
【事例有】ブラインド採用とは?6つのメリットや実施方法を解説!
- 採用代行







