
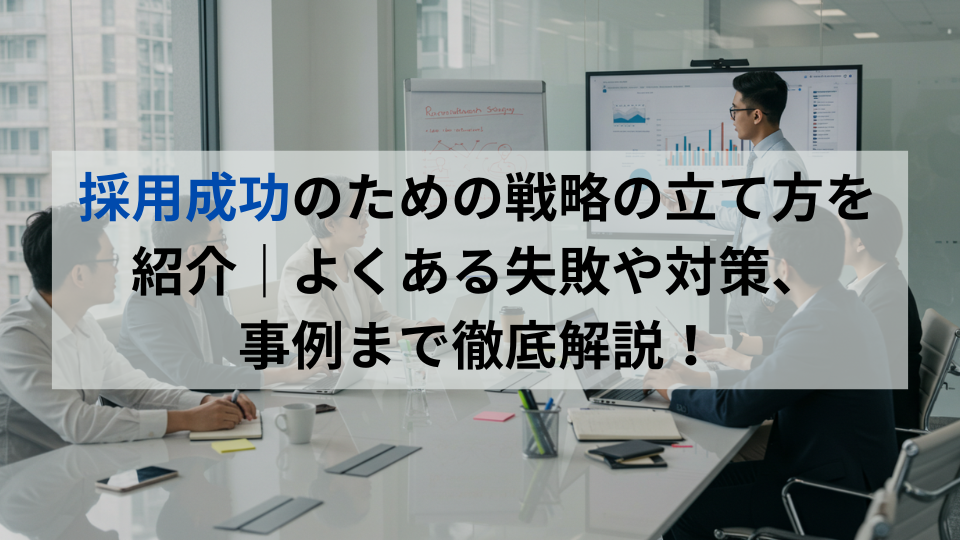
近年、有効求人倍率の上昇や人材獲得競争の激化により、採用活動はますます複雑化しています。
「応募が集まらない」「欲しい人材が採用できない」と悩む企業も多く、感覚的な採用活動では成果が出にくい時代になりました。こうした状況を打開するためには、場当たり的な施策ではなく、経営戦略と連動した採用戦略を立てることが不可欠です。
本記事では、採用戦略の立て方、得られるメリット、失敗しやすいポイントとその対策、さらに成功事例までを網羅的に解説します。
採用戦略が重要視されている背景
企業の成長において「採用」は事業推進の要となる領域です。しかし採用市場の変化は激しく、従来の方法だけでは優秀な人材を確保することが難しくなっています。
そのため、採用を計画的かつ戦略的に設計する重要性が高まっています。
- 人材獲得競争の激化
- 事業計画と採用計画の連動
- 採用コストの高騰
- 採用チャネルの多様化
- データ活用の必要性
以下では、これらの背景について詳しく解説します。
人材獲得競争の激化
採用市場では優秀な人材をめぐる競争が年々激しくなっています。求職者は複数企業から同時にスカウトやオファーを受けるため、企業は目に留まる採用活動を設計する必要があります。
戦略的にメッセージや選考プロセスを設計することで、競合に差をつけることができます。
計画なく採用活動を進めると、タイミングのずれや魅力訴求不足で候補者を逃してしまいます。採用戦略を立てることは、母集団形成から内定承諾まで一貫性のある体験を作るために不可欠です。企業は採用を経営課題として捉える視点が求められています。
事業計画と採用計画の連動
企業成長のスピードは、必要な人材を確保できるかどうかに直結します。事業計画と採用計画がずれていると、現場のリソース不足が発生し、成長が停滞するリスクがあります。
採用戦略は経営戦略と同期させることで、適切な人員確保と事業推進を同時に実現できます。
具体的には、採用人数や職種の優先順位を明確にし、必要なタイミングで適切な採用手法を選定します。これにより、事業のロードマップに沿った安定的な人材供給が可能になります。
採用コストの高騰
求人広告や人材紹介の費用は年々上昇しており、効率的な運用を行わないとコストが膨らみます。採用コストは単なる費用ではなく、投資として最大限のリターンを得るべきものです。
戦略的に採用チャネルを組み合わせることで、採用単価を抑えつつ質の高い人材を獲得できます。
コスト分析を行い、無駄な応募母集団形成や面接回数の削減などを検討することが重要です。限られた予算の中で最大限の効果を出すためには、採用計画の見直しと改善を継続する必要があります。
採用チャネルの多様化
近年は求人広告、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS採用など、選択肢が急速に増えています。これらのチャネルを闇雲に使うと、工数やコストがかさむだけで成果が出にくい状況になります。
自社に適したチャネルを見極める戦略がなければ、採用活動は非効率になりがちです。
KPIを設定し、各チャネルの応募数・面接通過率・採用決定率を定期的に分析することが重要です。データに基づいて優先順位をつけることで、最適なチャネルミックスを見つけることができます。
データ活用の必要性
勘や経験だけに頼った採用活動は、成果の再現性が低くなります。データに基づいて意思決定を行うことで、採用活動を可視化し、継続的な改善が可能になります。
応募数・通過率・辞退率などのデータ分析は、ボトルネックの特定と改善施策の立案に不可欠です。
ATSやBIツールを活用すれば、採用の各フェーズを数値化し、改善の優先度を明確にできます。データ活用は採用戦略を科学的に進め、結果を最大化するための強力な武器となります。
採用戦略の立て方
ここでは、採用を成功させるために特に重要な採用戦略の立て方やコツについて詳しく解説します。単なる採用活動の流れではなく、経営戦略と連動した計画を立てることで、より効果的な人材獲得が可能になります。
採用戦略を立案するための人員確保
採用活動は人事部だけに任せるのではなく、経営陣や現場の責任者を巻き込んだ強固な体制を構築する必要があります。人事だけの視点では現場の課題やリアルなニーズを十分に反映できず、戦略が形骸化するリスクがあります。
経営・現場・人事が一体となった専用の採用チームを立ち上げ、全社的な方針と一致した戦略を策定することが不可欠です。
こうした体制を整えることで、意思決定のスピードが上がり、現場が求める人材をタイムリーに採用できるようになります。
採用に関する現状分析と数値の可視化
採用戦略は、正確な現状把握なしには成り立ちません。採用課題や目標、必要スキルセットを明確にしなければ、施策が場当たり的になり効果が見えにくくなります。
応募〜内定までの各フェーズを数値で管理し、どこで候補者が離脱しているかを可視化することで改善ポイントが明確になります。
定量データに基づいた改善は再現性が高く、採用効率を継続的に高めるサイクルを作り出します。
具体的には、以下の点を分析します。
・面談から入社までのプロセス
・各フローにおける進捗率や見送り率
・現在利用している採用チャネルの効果
採用ターゲット・ペルソナの再確認
現状分析の結果をもとに、必要な人材のスキル・経験・人物像を具体的に定義し直します。抽象的なターゲット設定のままでは、ミスマッチによる採用のやり直しや早期離職のリスクが高まります。
ターゲットペルソナを詳細に設定することで、スカウト文面や求人票が刺さる内容になり、応募の質と採用成功率が大幅に向上します。
さらに、ペルソナをチーム全体で共有することで、採用基準のブレを防ぎ、選考プロセスに一貫性が生まれます。
コミュニケーション手法の見直し
求職者とのやり取りは、採用成功率を大きく左右する決定的な要素です。返信が遅れたり、情報が不足していると、候補者はすぐに他社へ流れてしまいます。スピード感と情報量の両立が求められます。
コミュニケーションフロー全体を再設計し、候補者体験を高めることで、辞退率を下げて採用成功率を最大化できます。
面接やオファーまでのリードタイム短縮、選考途中のフォローアップなど、細部まで丁寧に整備することで企業の信頼度が向上します。
確認すべきポイントは以下の通りです。
・書類選考のスピード
・求職者のニーズに応じた情報提供
・面接時における自社の魅力の伝え方
求人媒体の選定と作成
計画的に人材を確保するには、ターゲット人材が集まりやすい媒体を見極める必要があります。ダイレクトリクルーティングや求人広告、リファラル、SNS採用など複数チャネルを比較し、費用対効果の高いものを選定します。
求める人材が最も多いチャネルに集中投資し、求人票やスカウト文面を戦略的に作り込むことで、応募の質と数を同時に高められます。
媒体選定は一度で終わらせず、定期的に効果測定を行いながら見直すことで、常に最適なチャネルミックスを維持できます。
採用計画と目標の設定
採用活動を成功させるには、具体的な採用人数、選考フロー、KPIを明確に定義する必要があります。目標が曖昧なままでは、現場との認識がずれ、採用が長期化するリスクが高まります。
達成基準と期日を明確に設定し、定期的に進捗を検証することで、計画の精度と成果が飛躍的に向上します。
さらに、現場と結果を共有し改善点を協議することで、次の採用サイクルではより効果的な戦略を立案できます。
採用戦略を立てることで得られるメリット
採用戦略を立てることで、単なる採用活動が「計画的な投資」へと変わり、成果が最大化されます。戦略があるかどうかで、採用にかかるコストやスピード、社内体制の成熟度は大きく異なります。 優秀人材を確実に採用するためには、採用活動を場当たり的に進めるのではなく、データと計画に基づいた取り組みが欠かせません。
- 優秀人材の採用成功率向上
- 採用コストの最適化
- 採用スピードの向上
- 社内の採用体制強化
- 候補者体験(CX)の向上
これらのメリットを順番に解説し、採用戦略を立てる意義を具体的に見ていきましょう。
優秀人材の採用成功率向上
戦略的にターゲットやチャネルを設計することで、欲しい人材からの応募が増えます。現場のニーズに合った採用メッセージを発信することで、候補者の関心を引きやすくなります。
結果として内定承諾率が高まり、優秀人材を確実に採用できる確率が上がります。 計画的な採用は、競合他社よりも早く優秀な人材にアプローチできる点でも有利に働きます。
採用コストの最適化
戦略のない採用活動は、必要以上の母集団形成や広告費の浪費を生みやすくなります。どのチャネルに投資するかを決めずに進めると、成果の出ない施策にコストが偏るリスクがあります。チャネルごとの効果を定量的に検証し、費用配分を最適化することで、採用単価を抑えながら優秀人材を確保できます。
このプロセスを継続的に行うことで、限られた予算の中でも高いパフォーマンスを発揮できる採用体制が整います。結果として、採用ROI(投資対効果)の最大化が可能になり、経営資源の無駄を減らせます。
採用スピードの向上
採用戦略を立てると選考フローが整理され、内定までのリードタイムを短縮できます。スピード感のある対応は、候補者に安心感を与え、選考離脱を防ぎます。優秀人材を確実に採用するには、面接設定や合否通知を迅速に行う仕組みづくりが欠かせません。
面接日程の自動調整や書類選考の即日対応など、運用改善も並行して行うとさらに効果的です。迅速な選考は競合他社より先に意思決定できる強みとなり、採用成功率が向上します。
社内の採用体制強化
戦略的な採用は、人事部だけでなく経営層や現場を巻き込んだ体制づくりを促進します。部門間の情報共有が活発になることで、採用基準が明確化され、選考のばらつきも減少します。
全社的な採用文化を醸成することで、継続的に強い採用チームを育成できます。ノウハウが社内に蓄積されることで、次回以降の採用サイクルはより効率的になり、長期的な採用力強化につながります。
候補者体験(CX)の向上
候補者へのレスポンスの早さや情報提供の質が高まると、企業への信頼度と好感度が向上します。面接や選考過程でポジティブな体験ができれば、候補者は自社への志望度を高めやすくなります。
候補者体験を重視した採用戦略は、内定承諾率や入社後の定着率を引き上げると同時に、企業ブランディングにも直結します。競争の激しい市場では、この差が採用成功の決定打となり、長期的な人材確保の優位性を生み出します。
採用戦略を立てる際によくある失敗とその対策
採用戦略は立てること自体が目的ではなく、事業成長に直結する人材確保を実現するための手段です。しかし、戦略があっても運用が不十分だと成果につながらないケースも少なくありません。
ここでは、採用担当者が陥りやすい失敗と、それを防ぐための具体的な対策を整理します。
- 経営戦略と採用戦略が連動していない
- ターゲットが不明確なまま採用を開始
- チャネル選定と投資配分の誤り
- 選考スピードが遅く候補者を逃す
以下では、それぞれの失敗がなぜ起きるのか、どのように対策すべきかを具体的に解説します。
経営戦略と採用戦略が連動していない
事業計画と採用計画がずれていると、必要なタイミングで人材が不足し、プロジェクトの遅延や現場の負荷増大につながります。採用人数やスキル要件を場当たり的に決めてしまうことが原因です。経営陣と現場を巻き込んで採用計画を策定し、事業ロードマップと連動させることが必須です。
四半期ごとの進捗レビューを設けることで、変化に応じた計画の見直しが可能になり、採用の遅れを防げます。
ターゲットが不明確なまま採用を開始する
求める人材像が曖昧なまま採用を進めると、ミスマッチによる早期離職や選考工数の増加が発生します。求人票やスカウト文面が抽象的になることも多いです。ペルソナ設定を詳細に行い、求めるスキル・経験・人物像を明確化することが重要です。
社内で採用基準を共有することで、選考の一貫性が生まれ、ミスマッチを防ぎやすくなります。
チャネル選定と投資配分の誤り
効果の低い媒体に予算をかけすぎたり、複数チャネルに分散投資しすぎて成果が見えにくくなる失敗も多く見られます。データを取らずに感覚で判断すると非効率です。 各チャネルの応募数・通過率・採用決定率を分析し、投資配分を最適化することでROIを高められます。
定期的な見直しを行い、効果の高いチャネルに集中投資することで、採用単価を抑えつつ成果を最大化できます。
選考スピードが遅く候補者を逃す
面接日程調整や合否通知が遅れると、候補者が他社で内定を受けてしまうケースが発生します。スピード感のない採用は候補者体験の満足度を下げる原因にもなります。 面接設定や合否通知を自動化し、選考リードタイムを短縮する仕組みを整えることが重要です。
選考プロセスを定期的に見直してボトルネックを解消することで、優秀人材を確保する確率が高まります。
採用の成功事例9選
まずは採用の成功事例を企業別に8個紹介します。採用に成功している企業は自社の強みを上手く訴求しています。自社のリソースなども踏まえて、できそうなものを参考にしてください。
キャディ株式会社
資本金:100百万円
従業員数:563名
キャディ株式会社は、以下の三つの取り組みで、2021年2月には約80名だった従業員数を、わずか9ヶ月で160名増加させることに成功しています。
①Webサイトの最適化
採用候補者からのフィードバックをもとに、情報をリサーチし、Webサイトの改善に取り組んでいます。また、「兆単位プラットフォームへの10の課題」と題した具体的な課題や業務内容を公開し、求職者に企業のビジョンをより明確に伝えています。
②プレスリリースの活用
資金調達成功時のプレスリリースに採用リンクを掲載することで、自社サイトへのアクセスが2.5~3倍に増加しました。この手法により、より多くの求職者に企業の魅力を伝えることができています。
③イベント開催
資金調達後には、投資家や社内メンバーが登壇するイベントを開催し、ビジョンや戦略を共有しています。これにより、企業文化や将来の展望に共感する人材を集め、定着率を高めることができています。
株式会社スタディスト
資本金 :資本金:103百万円
従業員数:200名
株式会社スタディストは、採用からオンボーディングまでのプロセスを見直し、個人の意欲(Will)と企業の必要性(Must)を継続的にすり合わせる仕組みを構築しました。これにより、従業員が定着する組織作りを実現しています。主な取り組みは以下の2つです。
①会社が提供できる価値の再確認
企業が従業員に提供できる価値(EVP)を整理し、発信しています。採用サイトや開発ブログでEVPを積極的に発信することで、求職者とのミスマッチを防ぐ努力をしています。
②マッチングインタビューの導入
選考フローを見直し、一次選考後に5〜10分の「マッチングインタビュー」を追加しています。このインタビューでは、候補者の転職軸トップ3を確認し、その希望に会社がどの程度応えられるかを誠実に説明しています。
入社後の「ポートフォリオ研修」では、新メンバーが自身の意欲やスキル、責任を言語化し、自己開示を促進する仕組みを整えています。また、継続的に1on1ミーティングを行い、「やりたいこと・できること・やるべきこと」の重なりを見つけています。
株式会社九州パール紙工

引用元:https://www.kyusyu-pearl.co.jp/
従業員数:145名
資本金 :3,000万円
株式会社九州パール紙工は、販路拡大のためECサイトを開始しましたが、担当従業員の離職により運営が困難になり、特にコロナ禍での需要増に対応できず、高い離職率も課題でした。
解決するために、副業人材マッチングサービスを利用し、ECサイト運営やSNSの活用について専門知識を持つ副業人材を採用しました。これにより、若手従業員にノウハウを伝授し、販路拡大に成功しました。
具体的には、SNSの発信により毎年3~4名の高校生を順調に採用でき、離職率も低下し、社内の活性化につながりました。
クラスメソッド株式会社
資本金 :1億円
従業員数:760名
クラスメソッド株式会社では、エンジニアが主体となってエンジニアを採用する仕組みが確立されています。求職者とのコミュニケーションを重視し、現場のチームメンバー全員が参加する実技試験や面接を通じて、求職者との接触機会を増やしています。
面接においては全員の同意がなければ採用を行わず、それぞれが採用の決定権を持っています。
さらに、リファラル採用を積極的に行い、同社の強みであるAWS関連技術を活かしたテックブログ「DevelopersIO」を通じて、採用チャネルを増やすだけでなく、技術力やエンジニアの成長過程、将来性を効果的にアピールしています。
このように、現場エンジニアとの時間を共有することにより、採用プロセスには時間がかかるものの、内定承諾率の向上やその後の離職率の低下に繋がっています。
株式会社doors
従業員数:64名
資本金 :800万円
株式会社doorsは、多様な事業展開により、多岐にわたるスキルを持つ人材の確保が課題として挙げられていました。
解決策するために、地域貢献活動やイベントを通じて企業の認知度を向上させ、地元の多様な人材を採用しました。特に若手に積極的に仕事を任せることで、意欲的な人材を引きつけることに成功しています。
結果として、インフラメンテナンス事業では1.5倍の増員に成功し、飲食事業でも必要な採用数を確保することができました。
株式会社エイチーム
売上高 :27,552百万円
従業員数:872名
株式会社エイチームは、2017年卒から2019年卒にかけて内定承諾率を50%から80%に向上させることに成功しました。その具体的な取り組みとして、全ての説明会をオンライン化し、3ヶ月以内に内定を出すプロセスを導入しました。
説明会をオンライン化することで、求職者に伝える情報量が増加し、選考への移行率が向上しました。また、内定を早期に出すことで内定承諾率を30%も向上させることができました。
株式会社ユーザーベース
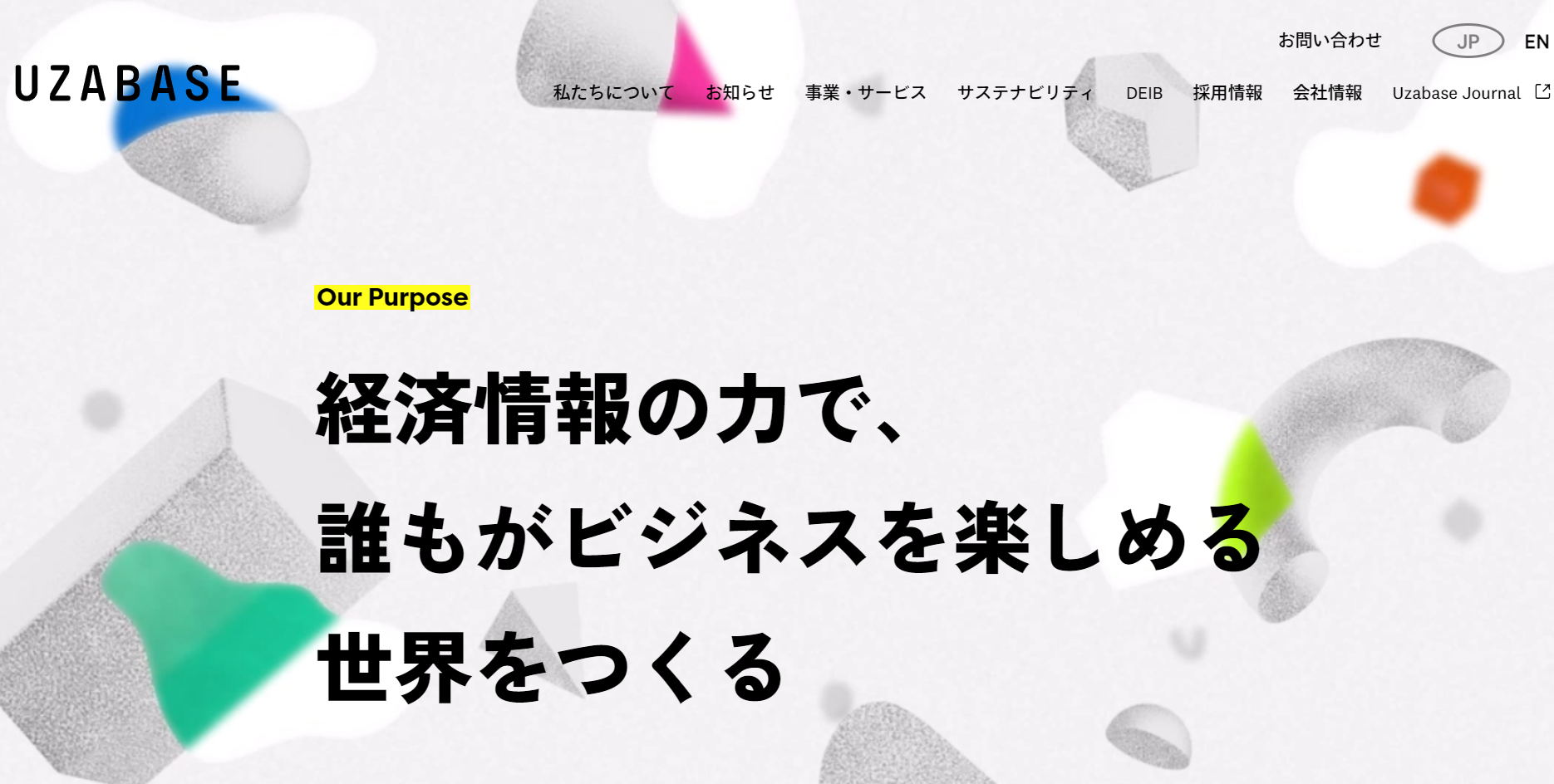
引用元:https://www.uzabase.com/jp/
売上高 :16,060百万円
従業員数:1055名
株式会社ユーザーベースは、SPEEDAやNewsPicksなどのサービスを提供する企業で、求職者に入社後のイメージを効果的に伝えることが課題となっていました。同社は、この課題を解決するためにスカウトメールの返信率をKPIとして設定し、その改善に取り組みました。
具体的には、スカウトメールにポジションに関する記事コンテンツのURLを添付することで、返信率を大幅に向上させることに成功しました。
株式会社ツクルバ
売上高:1,624百万円
従業員数:256名
株式会社ツクルバは「『場の発明』を通じて欲しい未来をつくる」というミッションを掲げ、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォームを提供しています。同社では、ダイレクトリクルーティングの採用チャネルにおいて、面談参加者数をKPIとして設定しています。
スカウト送信数をKPIとするのではなく、実際の面談参加者数を重視することで、単にスカウトを送信することが目的化しないようにしています。一人一人に熱意のこもったメッセージを送信したことが、成功の要因となっています。
アソビュー株式会社

引用元:https://www.asoview.co.jp/
資本金 :10 億円
従業員数:約 220名
アソビュー株式会社は、「1次面談数」をKPIとして設定しており、面談数を増やすために多くの担当者を確保する必要があるため、採用活動の情報を社内で積極的に共有し、コミュニケーションを密に取っていました。
また、各KPIに基づくデータ分析を行い、採用プロセスのどの段階に問題があるのかを検証し、その改善に取り組んでいました。KPIを活用してPDCAを効果的に回したことが、採用成功の要因となっています。
採用戦略の立て方についてよくある質問(FAQ)
採用戦略の立て方についてよくある質問をまとめました。
ペルソナ設定はどのくらいの粒度で行うべきですか?
具体的なスキルセット・経験年数・価値観・志向性まで落とし込むのが理想です。曖昧にするとミスマッチが起きやすいため、社内メンバーとすり合わせながら詳細に定義しましょう。
採用KPIはどの指標から設定すると効果的ですか?
まずは応募数・面接通過率・内定承諾率など、採用ファネルの各ステップを可視化できる指標がおすすめです。数値化しやすいKPIから始めることで、改善ポイントが見つけやすくなります。
チャネル選定で失敗しないために見るべきデータは何ですか?
応募数だけでなく、面接通過率や最終的な採用決定率まで追うことが重要です。費用対効果(応募単価・採用単価)も併せて確認し、成果につながるチャネルを優先しましょう。
採用戦略の効果検証はどのサイクルで行うと良いですか?
四半期ごとにKPIを集計し、改善策を反映するサイクルが推奨されます。採用市場の変化が早いため、定期的な見直しで戦略の鮮度を保ちましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、採用戦略の立て方からメリット、よくある失敗とその対策、さらに実際の成功事例まで幅広くご紹介しました。
採用活動を成功させるためには、まずペルソナを明確に設定し、自社の強みを的確に発信することが欠かせません。戦略を持つことで、コストやスピード、候補者体験の質が大きく改善されます。
現在の採用活動を見直すタイミングで、ぜひ今回のポイントや成功事例を参考にしてください。今日からできる小さな改善を積み重ねることで、優秀人材の確保と事業成長につながる採用戦略が実現します。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

採用広告とは?各媒体のメリットや選定方法、効果的な活用方法まで徹底解説!
- 採用代行

採用ピッチ資料とは|10つの事例や作成フロー、メリットも紹介
- 採用代行
コーポレート用アイキャッチのコピ-12-400x225.jpg)
人材採用コンサルタントとは?サービス内容から選び方まで徹底解説!
- 採用代行
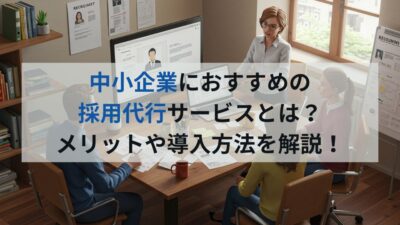
中小企業におすすめの採用代行サービスとは?メリットや導入方法を解説!
- 採用代行
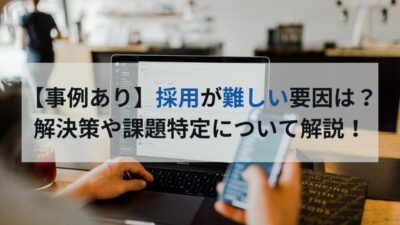
【事例あり】採用が難しい要因は?解決策や課題特定について解説!
- 採用代行
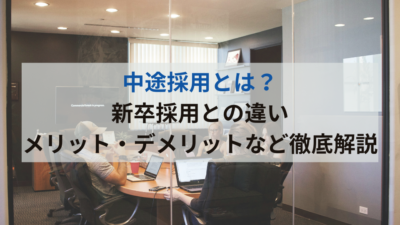
中途採用とは?新卒採用との違い、メリット・デメリットなど徹底解説
- 採用代行












