
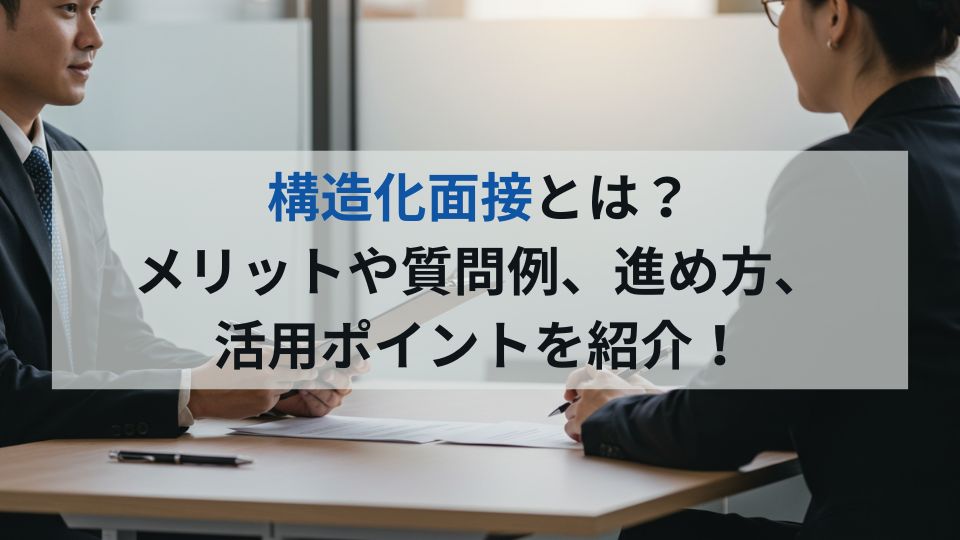
「評価のばらつきが気になる…」「面接官ごとに基準が違う気がする」
そんな悩みを抱える採用担当者も多いのではないでしょうか?
公平性の高い選考を行いたい一方で、面接の運用には多くの工数と工夫が求められます。
そこで本記事では、近年注目されている「構造化面接」の基本から、導入ステップ、メリット・デメリット、質問例や活用ポイントまで詳しくご紹介します。

構造化面接とは?
現代の採用現場では、面接の形式や手法が多様化しています。
その中でも「構造化面接」は、評価のブレを最小限に抑える面接手法として、多くの企業に注目されています。
以下では、その基本的な定義と、他の面接手法との違いについて解説します。
構造化面接の定義
構造化面接とは、あらかじめ設定した評価基準・質問内容に沿ってすべての候補者に同一の質問を行い、統一的な尺度で評価する面接方式です。
「公平性」と「再現性」が高いのがこの手法の最大の特徴です。
面接官の感覚に依存せず、求める人材要件に基づいて質問と評価を設計できるため、採用判断におけるばらつきを防ぎやすくなります。
このようにして、企業が求める人物像と一致するかを、より客観的に見極めることができるのです。
非構造化面接・半構造化面接との違い
面接形式は大きく以下の3つに分類されます。
- 非構造化面接:質問内容が固定されておらず、面接官が自由に質問を行う。柔軟性は高いが、評価が主観に偏りやすい。
- 半構造化面接:一部の質問を事前に設定しつつ、状況に応じてアドリブで質問を追加。構造化と非構造化の中間的な位置づけ。
- 構造化面接:すべての質問と評価項目を事前に決定し、それに基づいて面接を進行。評価の一貫性と公平性を担保できる。
このように、構造化面接は他の形式に比べて、評価軸が明確で信頼性が高いという点で優れています。
一方で、柔軟なやり取りがしにくいというデメリットもありますが、それでも採用ミスを減らしたい企業には非常に効果的な選択肢となっています。
面接代行とは?依頼できる業務・費用・おすすめサービス8選を解説!
構造化面接が注目されている背景
2020年代に入り、企業の採用活動は大きく様変わりしています。
オンライン選考の一般化、採用ブランド強化の必要性、そして候補者の満足度を重視する動きが加速する中で、構造化面接の導入が注目されてきました。
以下では、構造化面接を取り巻く時代的背景を3つの観点で整理して解説します。
- リモート・オンライン採用の加速
- 採用ブランディングの強化
- 候補者体験(CX)の重視
リモート・オンライン採用の加速
新型コロナウイルスの流行以降、オンライン面接が急速に普及しました。
しかし、リモート環境では表情や空気感といった「非言語的な情報」が読み取りづらく、評価の公平性が揺らぎやすくなります。
この課題を解決するのが構造化面接です。
事前に定めた質問と評価項目を用いて、すべての候補者を同じ基準で評価することができるため、リモート環境でも評価の一貫性を保てるという利点があります。
採用ブランディングの強化
人材獲得競争が激化する中、企業は「選ばれる立場」としての姿勢を明確にする必要があります。
採用ブランディングの一環として、厚生労働省の述べているように公平で透明性のある選考プロセスを構築することは極めて重要です。
構造化面接は、質問の意図や評価の根拠が明文化されており、候補者に対して「しっかりと考えられた採用」を印象づけることができます。
その結果、企業の信頼性やブランドイメージの向上にもつながります。
出典:)厚生労働省|公正な採用選考の基本 厚生労働省
候補者体験(CX)の重視
候補者体験(Candidate Experience)とは、応募から面接、内定までのプロセスを通じて、候補者が感じる全体的な印象のことを指します。
これは、入社意欲に直結する重要な要素です。
構造化面接では、選考の進め方がスムーズかつ論理的であるため、候補者に対し「整備された企業体制」と「フェアな選考」を印象付けやすくなります。
結果として、候補者体験の向上と志望度の強化につながります。
【5選】構造化面接のメリット
構造化面接は、従来の自由な形式の面接と比べて、明確な評価基準と質問設計に基づく一貫性のある手法です。
ここでは、構造化面接を導入することで得られる主なメリットを5つに分けて解説します。
- 評価基準の明確化
- 採用ミスマッチの削減
- 面接時間・工数の削減
- オンライン面接との相性の良さ
- 採用担当の属人性の排除
評価基準の明確化
構造化面接の最大の利点は、評価基準を事前に明確化できることです。
候補者全員に同じ質問を投げかけ、統一された評価項目で採点するため、評価のばらつきを抑えることができます。
また、採用要件に沿って評価指標を設計することで、「何を基準に採用するのか」が社内でも共有されやすくなり、複数の面接官による選考でも整合性の取れた意思決定が可能になります。
加えて面接内容に統制が取れることから、人権への配慮など、面接の大前提の全体認識を一致させることも可能となります。
出典:)広島労働局|公正採用選考の考え方と質問例
採用ミスマッチの削減
構造化面接では、企業が求めるスキルや行動特性を明確にした上で質問を設計するため、実際の業務に適した人材を見極めやすくなります。
入社後の活躍可能性にフォーカスした質問を通じて、表面的な印象や経歴に左右されず、実践的な判断が可能です。
結果として、早期離職や期待外れによるミスマッチを未然に防ぐ効果があります。
面接時間・工数の削減
事前に質問と評価基準を設計しておくことで、面接官は当日の準備や進行にかかる負担を大幅に軽減できます。
質問の流れが定まっているため、面接が効率的かつ時間通りに進みやすくなるのも大きな利点です。
さらに、評価の記録やフィードバックもテンプレート化できるため、選考全体のスピードアップにもつながります。
オンライン面接との相性の良さ
リモートワークや在宅勤務が広がる中で、オンラインでの選考が一般化しています。
その際、表情や雰囲気といった非言語的な情報が読み取りにくいという課題があります。
しかし構造化面接では、評価項目が可視化されているため、画面越しでも一貫した判断がしやすくなるというメリットがあります。
オフラインとオンラインのギャップを埋める手法として、非常に効果的です。
採用担当の属人性の排除
自由な面接形式では、どうしても面接官の個人的な経験や価値観が評価に反映されてしまうことがあります。
それに対し構造化面接は、質問と評価基準が事前に設計されているため、属人的な判断を排除しやすい仕組みになっています。
この結果、評価のばらつきを防ぎ、どの面接官が担当しても同等の判断ができる体制を構築することが可能です。
【4選】構造化面接のデメリット
構造化面接には多くのメリットがある一方で、導入・運用にあたっては注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、企業が導入前に把握しておきたい4つの代表的な課題を整理して解説します。
- 柔軟な質問や印象評価が難しい
- 応募者の新たな一面を見逃しやすい
- 面接内容が外部に漏洩するリスク
- 対策されやすくなる可能性
柔軟な質問や印象評価が難しい
構造化面接では、あらかじめ定めた質問と評価項目に沿って面接を進める必要があります。
そのため、面接官の自由な掘り下げや印象をもとにした柔軟な評価が難しくなります。
面接そのものが機械的な印象を与えることもあり、候補者との距離感や信頼形成に課題が生じる可能性があります。
対話型の面接を好む職種や文化においては、導入に注意が必要です。
応募者の新たな一面を見逃しやすい
構造化された設問に限定されることで、候補者が持つ多面的な魅力や、想定外のエピソードを評価する余地が少なくなります。
そのため、書類に現れにくい個性やポテンシャルを見落とすリスクが高まります。
特に、クリエイティブ職や柔軟性が求められるポジションでは、この点が採用ミスマッチにつながる可能性もあります。
面接内容が外部に漏洩するリスク
構造化面接では質問や評価基準が明文化されているため、それらの情報が社外に流出した場合、候補者にとって事前準備がしやすくなります。
「想定問答」を準備された状態で臨まれることで、本質的な見極めが難しくなるという課題があります。
特に人気企業や学生向け採用では、SNS等を通じて情報が拡散しやすいため、設計段階から対策が必要です。
対策されやすくなる可能性
構造化面接は評価の透明性が高い反面、その構造が候補者に読まれやすいという側面もあります。
事前に質問意図を分析され、模範解答を準備されると、本来見極めたい行動特性や判断力が見えづらくなる恐れがあります。
このようなケースでは、評価者側の目線での深掘り力や、追加質問の設計がカギとなります。
構造化面接における質問例
構造化面接では、事前に設計された質問を通じて、候補者のスキルや適性、行動特性を客観的に評価します。
特に有効とされているのが「行動面接」と「状況面接」の2つの形式です。
ここでは、それぞれの特徴と活用方法について解説していきます。
行動面接|過去の経験に基づく質問
行動面接(Behavioral Interview)は、候補者が過去に実際に取った行動をもとに能力や価値観を評価する手法です。
特に、「過去の行動は将来の行動を予測する最良の指標である」という考え方に基づいています。
代表的なフレームワークとして「STARモデル(Situation, Task, Action, Result)」が用いられ、候補者に過去の経験を論理的に語ってもらうことを通じて、課題解決力や対人スキル、リーダーシップなどの要素を評価します。
この形式の質問は、営業やマネジメント職など、過去の成果や対人対応が評価される職種に向いています。
状況面接|未来に起こりうる状況を想定した質問
状況面接(Situational Interview)は、候補者に仮想の状況を提示し、「この場合、どう行動しますか?」と問いかけることで、問題解決力や判断力、価値観の一貫性を探る手法です。
この手法は特に、職務経験が浅い新卒採用やポテンシャル採用で有効とされており、現場で起こりうる具体的な場面を設定することがポイントです。
この形式により、候補者の意思決定プロセスや対人関係スキル、リーダーシップ適性を測ることが可能です。
【導入ステップ】構造化面接導入の進め方
構造化面接を効果的に機能させるには、準備から実施、評価まで一貫した設計と運用が欠かせません。
以下では、導入に必要な5つのステップを順を追って解説します。
- ステップ1:採用基準・評価項目の明確化
- ステップ2:質問項目の設計
- ステップ3:評価基準と採点方法の整備
- ステップ4:面接官のトレーニング
- ステップ5:フィードバック体制の構築
ステップ1:採用基準・評価項目の明確化
最初のステップは、構造化面接の「軸」を作ることです。
求める人物像を具体化し、どのようなスキルや行動特性が必要かを明文化します。
この段階で評価の方向性がブレると、後続の設計がすべて曖昧になります。
職種や役割に応じた評価項目を洗い出し、必要に応じて現場部門と連携しながら要件定義を行いましょう。
ステップ2:質問項目の設計
次に、評価項目に対応した質問を構築します。
行動面接や状況面接の手法を取り入れつつ、評価したい能力ごとに2〜3個の設問を準備するのが一般的です。
質問は抽象的ではなく、具体的なエピソードを引き出せる内容が望ましいです。
また、候補者にとっても答えやすく、公平性が保たれるよう配慮することが重要です。
ステップ3:評価基準と採点方法の整備
質問に対する回答をどう評価するかを定めます。5段階評価や行動評価マトリクスなど、客観的にスコア化できる仕組みを設けることで、面接官間の判断のズレを防ぎます。
さらに、「この回答なら何点」という基準例を用意しておくと、面接官の認識を揃えやすくなります。
ステップ4:面接官のトレーニング
構造化面接は「誰がやっても同じ質」が理想です。
そのため、面接官には事前に評価軸や質問の意図、フィードバックの伝え方などをレクチャーする必要があります。
評価者研修を通じて、判断の一貫性と正確性を担保することが、構造化面接の成功に直結します。
面接官のやり方と心得|役割や質問例を紹介
ステップ5:フィードバック体制の構築
面接が終わった後の記録・共有・フィードバックも重要な工程です。
面接記録のフォーマットや保存場所、合否判断の流れをあらかじめ整備し、複数の関係者間でスムーズに連携できるようにしておきましょう。
選考プロセス全体が「見える化」されている状態を作ることで、より精度の高い採用が実現できます。
構造化面接の効果を最大化するポイント
構造化面接は設計通りに運用すれば一定の効果が得られる手法ですが、より高い成果を得るためには、導入後の運用体制や他施策との連携も欠かせません。
構造化面接を最大限に活用するための具体的なポイントを3つに整理して解説します。
- 導入前の社内調整
- 面接以外との組み合わせ(カジュアル面談・適性検査)
- 評価の透明性を担保する体制づくり
導入前の社内調整
構造化面接を効果的に導入するためには、現場や他部署との連携が不可欠です。
特に、評価基準や質問内容を現場のニーズとすり合わせることは重要なステップです。
採用チームだけで設計を進めると、実務とのズレが生じる可能性があるため、職種ごとに求められるスキルや行動特性について、現場の声をしっかり反映させる必要があります。
面接以外との組み合わせ(カジュアル面談・適性検査)
構造化面接だけで全ての適性を見抜くのは難しいため、他の手法と併用することで補完性を高めることができます。
たとえば、選考前にカジュアル面談を実施することで候補者の本音を引き出したり、適性検査を通じて非認知能力を測定したりすることで、多面的な人材評価が可能になります。
これにより、構造化面接単体では把握しきれない情報も収集でき、ミスマッチのリスクを下げることができます。
カジュアル面談の正しい進め方とは?企業側のコツや注意点を紹介!
評価の透明性を担保する体制づくり
構造化面接の信頼性を高めるためには、評価プロセス全体がオープンかつ一貫していることが求められます。
評価結果をしっかり記録し、関係者間で共有できるような体制を整えることが大切です。
また、評価がどのように下されたかを説明できる状態を作ることで、候補者へのフィードバック精度も上がり、企業の信頼度や採用ブランディングにも好影響を与えます。
構造化面接についてよくある質問(FAQ)
構造化面接についてよくある質問をまとめました。
構造化面接と一般的な面接の違いは?
構造化面接は質問と評価基準が事前に決められており、すべての候補者に同じ質問をする点が特徴です。一般的な面接と比べて、評価の一貫性と公平性を担保しやすくなります。
どんな職種に構造化面接は向いてる?
営業やカスタマーサポート、エンジニアなど、具体的なスキルや行動が求められる職種に向いています。定量的な評価がしやすい職種と相性が良いです。
構造化面接の質問内容が外部に漏れたらどうなる?
候補者が模範解答を準備しやすくなるため、評価が難しくなるリスクがあります。定期的に質問の見直しを行うのが望ましいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、構造化面接の定義から他手法との違い、導入のステップやメリット・デメリット、そして質問例や活用のコツまで詳しく解説しました。
構造化面接は、採用の質と効率を高める非常に有効な手法です。
自社の採用課題にあわせて柔軟に取り入れ、選考プロセスの改善に役立ててみてください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
コーポレート用アイキャッチ-2-400x225.jpg)
面接官の質問リスト集|質問設計方法、NG例から学ぶ注意点まで徹底解説!
- 面接代行
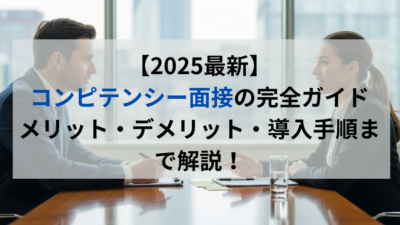
【2025最新】コンピテンシー面接の完全ガイド|メリット・デメリット・導入手順まで解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-1-400x225.jpg)
【保存版】面接官が知っておくべき心得5選|準備から注意点まで徹底解説!
- 面接代行
コーポレート用アイキャッチ-4-400x225.png)
カジュアル面談の正しい進め方とは?質問内容まで徹底解説!
- 面接代行
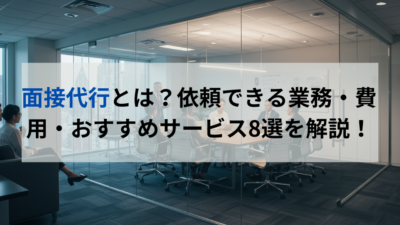
面接代行とは?依頼できる業務・費用・おすすめサービス8選を解説!
- 面接代行

面接代行の料金相場は?体系別の費用とコスト削減ポイントを解説!
- 面接代行






