
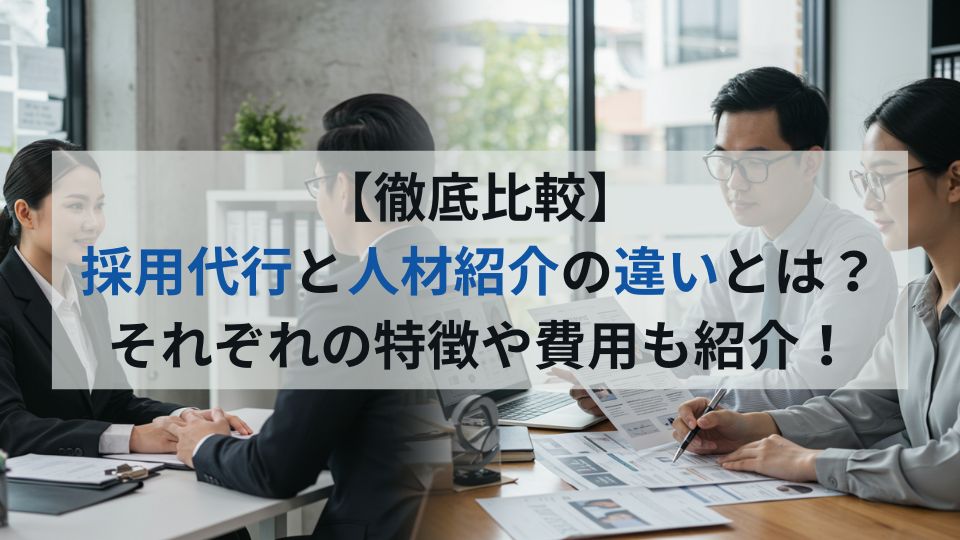
採用活動を外部に委託する手段として代表的なのが「採用代行(RPO)」と「人材紹介」です。一見似たサービスですが、関わる工程や契約形態、費用発生のタイミングなど、仕組みには大きな違いがあります。
これらを正しく理解せずに導入すると、採用計画やコスト効率に影響が出ることも少なくありません。
本記事では、採用代行と人材紹介の特徴を7つの観点から比較し、それぞれのメリット・注意点、自社に適した選び方まで詳しく解説します。
採用代行と人材紹介とは?
採用支援サービスは外部リソースを使って自社の採用力を補う仕組みです。ここでは以下の項目を順に説明します。
- 採用代行(RPO)とは?
- 人材紹介とは?
それぞれについて詳しく説明します。
採用代行(RPO)とは?
採用代行(RPO)とは、企業の採用業務の一部または全てを外部の専門会社に委託し、継続的に支援するサービスです。
その結果、社内の採用担当者の人手不足やノウハウ不足を補いながら、効率的かつ質の高い採用活動を実現できます。
具体的な支援内容には、求人媒体の選定、応募者対応、面接日程の調整、採用基準の整理、採用データの分析など多岐にわたる業務が含まれます。これらを代行することで、社内の負担を軽減しつつ、採用の質を高めることが可能です。
採用代行は、採用業務の効率化と質の向上を同時に実現したい企業にとって、非常に有効なサービスと言えます。
人材紹介とは?
人材紹介は、企業が求めるスキルや経験に合った候補者を、専門の紹介会社が外部ネットワークから探し出し紹介するサービスです。主に中途採用で利用され、採用が決まった場合に成功報酬として紹介料が発生します。
紹介会社は、求人条件のヒアリングから候補者のスクリーニング、面接調整、内定後のフォローまでを支援します。
その結果、企業は自社だけでは見つけにくい即戦力人材を効率的に採用できます。
さらに、人材紹介では非公開求人の活用が可能で、競合他社に知られずに優秀な人材を確保できるメリットもあります。一方で、成功報酬型のため採用コストが高くなるケースもあるため、予算とのバランスを考慮することが重要です。
人材紹介は即戦力となる人材をスピーディに確保したい企業にとって有効な採用サービスと言えます。
採用代行に依頼できる8つの業務|代行会社の料金、選び方を解説!
採用代行と人材紹介の7つの違い
採用支援サービスには主に採用代行(RPO)と人材紹介の2種類がありますが、それぞれの特徴は大きく異なります。自社の採用課題に合ったサービスを選ぶためには、両者の違いを正しく理解することが欠かせません。
本章では、以下の7つの視点から採用代行と人材紹介の違いを詳しく解説します。
- 違い①:サービス内容
- 違い②:費用体系
- 違い③:法律や許認可
- 違い④:導入スピード
- 違い⑤:責任範囲
- 違い⑥:向いている企業
- 違い⑦:依頼時の注意点
それぞれについて詳しく解説していきます。
違い①:サービス内容
採用代行と人材紹介はどちらも採用支援を目的としますが、その提供するサービス内容には大きな違いがあります。
採用代行(RPO)は、求人媒体の選定から応募者対応、面接調整、内定手続きまで採用プロセス全体または一部を包括的に代行します。企業の採用担当者が不足している場合や、採用体制の強化を目指す場合に適しています。
一方、人材紹介は、企業の求めるスキルや経験に合った人材を紹介することに特化しています。
採用決定後に成功報酬が発生する仕組みであり、即戦力の確保や特定のポジションの採用に効果的です。
違い②:費用体系
採用代行は一般的に月額料金や期間契約で費用が設定されるケースが多く、採用活動全体の運用を委託するため安定したコストが見込めます。
その結果、継続的な採用支援や複数名の採用に適しています。
一方、人材紹介は成功報酬型が主流で、採用が決まった場合に初年度年収の一定割合(一般的に20〜35%程度)を紹介料として支払います。採用人数が少ない場合や特定のポジションに対して効果的ですが、採用人数が増えるとコストが高くなりやすい特徴があります。
違い③:法律や許認可
採用代行は一般的に「労働者派遣法」や「職業安定法」の許認可は不要で、企業の採用活動を支援するサービスとして位置づけられています。そのため、比較的スムーズに導入しやすいという特徴があります。
一方、人材紹介サービスを提供するには、厚生労働省の認可を受ける必要があります。これは「職業紹介事業」として厳格に規制されており、そのため、適切な許認可を持つ安心性の高い企業のみがサービス提供を行えるという特徴があります。
出典:)「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です 」雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です
違い④:導入スピード
採用代行は、企業の採用プロセス全体または一部を代行するため、導入にあたって業務内容のすり合わせや体制構築が必要です。そのため、準備期間として数週間から数ヶ月を要することが一般的です。しかし、一度導入すると継続的な採用運用が可能となり、中長期的な採用活動の効率化につながります。
人材紹介は、必要なポジションに適した候補者を迅速に紹介することが目的であるため、契約締結後すぐに人材紹介が始まります。導入スピードは非常に速く、短期間で即戦力の採用を目指す企業に適しています。
違い⑤:責任範囲
採用代行は、採用プロセス全体または一部の運用を委託するため、応募者対応から選考管理まで幅広い業務を代行します。
そのため、採用活動の進捗管理や質の向上に対する責任を負いますが、最終的な採用判断や雇用契約の締結は企業側が行います。
人材紹介は、企業に適した候補者を紹介し、採用決定までのマッチングを担当します。紹介した人材の質に対して一定の責任を負いますが、採用後の労働条件や雇用関係の管理は企業側の責任となります。成功報酬型のため、紹介した人材の定着や活躍が重要な評価ポイントとなります。
違い⑥:向いている企業
採用代行は、採用業務の負担が大きく社内リソースが不足している企業や、採用プロセスの改善・効率化を目指す企業に向いています。
複数名の採用や中長期的な採用戦略を必要とする場合に効果的です。
人材紹介は、特定のポジションに対して即戦力となる人材を迅速に確保したい企業に適しています。少人数の採用や専門性の高いポジションなど、スピード重視で人材を求める場合に効果を発揮します。
違い⑦:依頼時の注意点
採用代行を依頼する際は、委託範囲や業務内容、採用基準を明確にすることが重要です。社内との情報共有や認識のずれを防ぎ、スムーズに業務を進めるための連携体制を整える必要があります。
人材紹介を依頼する際は、紹介料の費用対効果や紹介される候補者の質を見極めることが重要です。企業の採用基準や求める人材像を具体的に伝え、ミスマッチを防ぐための連携体制を整える必要があります。
採用代行の4つのメリット
採用代行を利用することで、企業はさまざまなメリットを享受できます。
ここでは、特に重要な4つのメリットを以下の視点から解説します。
- 業務効率が上がる
- 採用の質が安定する
- 工数を大幅に削減できる
- 基準やフローが整う
これらのポイントを理解することで、採用代行を効果的に活用し、採用成功につなげることが可能です。
業務効率が上がる
採用代行の導入により、求人広告の掲載から応募者対応、面接調整、合否連絡まで一連の採用業務を専門のスタッフに任せられます。
その結果、企業の採用担当者は日々のルーティン作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。
また、採用代行は豊富なノウハウと最新の採用ツールを活用して効率的に業務を進めるため、無駄な手間や時間を削減し、採用活動全体のスピードアップにもつながります。結果として、採用活動の遅延やミスを減らし、よりスムーズな運営が可能になります。
採用の質が安定する
採用代行の導入により、専門知識と経験豊富なスタッフが採用基準に基づき一貫した選考を行います。
その結果、採用代行会社は業界動向や市場の最新情報を把握しているため、適切な採用戦略を提案し、質の高い人材を効率的に確保するサポートが可能になります。
こうした専門的な支援は、採用のばらつきを抑え、長期的に組織力を強化することにつながります。
工数を大幅に削減できる
採用代行の導入により、採用にかかる工数を大幅に削減できます。
求人票の作成や応募者対応、面接のスケジューリング、結果のフィードバックといった時間と労力のかかる作業をアウトソースすることで、社内リソースの負担が軽減されます。
特に中途採用や大量採用の場合、応募者数の多さから手が回らなくなることもありますが、採用代行は効率的な管理体制でスムーズに対応できるため、採用活動全体のスピードアップに貢献します。
その結果、採用担当者は戦略的な企画や面接の質向上など、より価値の高い業務に集中できるようになります。
基準やフローが整う
採用代行の導入により、採用基準や選考フローの整備が促進されます。専門スタッフが企業のニーズに合わせて明確な採用基準を策定し、一貫した選考プロセスを構築するため、採用のブレやムラを防ぐことができます。
また、標準化されたフローにより、応募者への対応スピードや評価の公平性が向上し、企業の信頼度アップにもつながります。
その結果、採用活動全体の質と効率が高まり、長期的に安定した人材確保が可能になります。
採用代行のデメリットとその対策
採用代行は多くのメリットを提供しますが、一方で利用にあたってはいくつかの注意点も存在します。特に、ノウハウの社内蓄積の難しさや、ミスマッチのリスク、社内連携の課題は見逃せません。
ここでは、採用代行の主なデメリットと、それに対する効果的な対策について詳しく解説します。
- ノウハウが社内に残らない
- ミスマッチの恐れがある
- 社内連携が難しい
それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
ノウハウが社内に残らない
採用代行を利用すると、採用業務の多くを外部に委託するため、業務のノウハウが社内に蓄積しにくいという課題があります。
この課題への対策としては、採用代行会社との定期的な情報共有や、業務の一部を社内担当者と連携して進めることが挙げられます。また、採用代行から得られたノウハウやデータをドキュメント化し、社内で活用できる仕組みを作ることも効果的です。
ミスマッチの恐れがある
採用代行を利用すると、外部の担当者が自社の雰囲気や細かいニーズを完全に理解しきれないことがあります。そのため、採用した人材が実際の仕事や社風に合わず、ミスマッチが起きるリスクがあります。
この課題への対策としては、企業側が採用基準や求める人材像をしっかり伝え、定期的にコミュニケーションをとることが大切です。また、採用代行側にフィードバックを伝えて改善してもらう仕組みを作ることも効果的です。
社内連携が難しい
採用代行を利用すると、外部の担当者と社内の採用チームや関係部署との連携がうまくいかない場合があります。情報の共有不足や認識のズレが生じると、採用活動の効率や成果に悪影響を及ぼすことがあります。
この課題への対策としては、社内外の担当者間でこまめに情報共有を行い、共通の採用目標や進捗を確認する場を設けることが重要です。明確なコミュニケーション体制を構築することで、連携の質を高められます。
人材紹介の3つのメリット
次に人材紹介のメリットについて説明します。人材紹介サービスは、多くの企業にとって効率的かつ効果的な採用手段の一つです。
ここでは、人材紹介を利用する際に特に注目すべきメリットの3つを以下の観点からご紹介します。
- 初期費用が不要
- 客観的なPRが可能
- 非公開求人の活用が可能
これらの特徴を理解することで、人材紹介サービスの効果的な活用方法を知ることができます。
初期費用が不要
人材紹介サービスは、採用が決まった場合にのみ報酬が発生する成功報酬型が一般的です。そのため、採用活動の開始時に大きな初期費用がかからず、コストリスクを抑えられます。
この仕組みにより、企業は実際に効果があった場合にのみ費用を支払うため、無駄な投資を避けることが可能です。特に予算に制限のある企業にとって、初期費用不要は大きなメリットとなります。
客観的なPRが可能
人材紹介サービスでは、第三者の視点から企業の魅力や強みを客観的に伝えることができます。そのため、自社だけでは気づきにくいポイントを効果的にアピールし、求職者に魅力的な企業イメージを届けられます。
また、専門のコンサルタントが求職者のニーズに合わせて情報を調整し、マッチングの精度を高めるため、より適した人材の採用につながります。
非公開求人の活用が可能
人材紹介サービスでは、一般には公開されない非公開求人を活用できます。そのため、競合他社に知られたくない重要なポジションや、特定のスキルを持つ人材をターゲットにした採用が可能です。
非公開求人を利用することで、質の高い応募者を効率的に集めることができ、採用成功率の向上に寄与します。また、求職者にとっても特別感があり、応募意欲を高める効果があります。
人材紹介のデメリットとその対策
人材紹介サービスは採用を効率化する一方で、注意すべきデメリットも存在します。
特に、採用コストの高騰や候補者探しの困難、さらに採用後の辞退や早期離職のリスクは企業にとって大きな課題です。
ここでは、人材紹介利用時に陥りやすい問題点と、それに対する具体的な対策を解説します。
その結果、サービスの効果を最大限に引き出し、リスクを最小化することが可能になります。
- 採用コストが高騰する
- 候補者探しが困難である
- 辞退や離職のリスクがある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
採用コストの高騰する
人材紹介サービスは成功報酬型であるため、採用が決まった時点で報酬が発生します。その報酬率は一般的に採用者の年収の20〜35%と高額になることが多く、採用コストが増大するリスクがあります。
特に大量採用や中途採用で頻繁に利用する場合、コストが膨らみ経営に負担をかけることも考えられます。
この課題への対策としては、複数の人材紹介会社を比較検討したり、報酬率の交渉を行うほか、自社の採用計画に合った利用頻度を見極めることが重要です。
候補者探しが困難である
人材紹介サービスでは、求めるスキルや経験に合った候補者を探すことが必須ですが、条件が厳しい場合や専門性が高いポジションでは、適切な人材を見つけるのが難しくなります。
また、優秀な人材は複数の紹介会社からアプローチを受けていることも多く、競争が激しいため採用までの時間がかかる場合もあります。
この課題への対策としては、条件の優先順位を明確にし、現実的な要件を設定することが大切です。また、紹介会社と密に連携して情報共有を行い、迅速な対応を心がけることも効果的です。
辞退や離職のリスクがある
人材紹介サービスを採用した場合でも、内定辞退や早期離職のリスクはゼロではありません。紹介会社を介することで候補者との距離感が遠くなり、企業の魅力や職場環境が十分に伝わらないことが原因の一つです。
また、採用後のミスマッチにより、短期間で離職されるケースもあります。
この課題への対策としては、企業側が採用基準や業務内容を明確に伝えることに加え、紹介会社と連携して候補者への情報提供を丁寧に行うことが重要です。
さらに、入社後のフォロー体制を整備し、早期離職を防ぐ仕組みづくりも必要です。
採用代行、人材紹介の選ぶ基準
採用代行と人材紹介はそれぞれ特徴や強みが異なるため、企業の採用課題や状況によって適したサービスは変わります。どちらが自社に合っているかを見極めることが、効率的で効果的な採用活動を実現するポイントです。
ここでは、選択の判断基準となるポイントや、それぞれのサービスが適している企業の特徴を説明します。
- 判断のポイントは何か
- 採用代行が向いている企業
- 人材紹介が向いている企業
- 併用という選択肢
それぞれの判断基準を抑えたうえで、最善の選択をしましょう。
判断のポイントは何か
採用代行と人材紹介のどちらを選ぶかは、以下のポイントを基準に判断すると良いでしょう。
| 採用代行 | 人材紹介 | |
|---|---|---|
| 採用の規模 | 大規模 | 少数 |
| スピード | 長期的 | 短期的 |
| 求める人材の専門性 | 専門性の低い | 専門性の高い |
まず、採用の規模やスピード、求める人材の専門性が重要です。大量採用や長期的な採用体制の強化を目指す場合は、採用代行が適しています。
一方、即戦力の人材を迅速に確保したい場合や、専門性の高いポジションの採用には人材紹介が向いています。
また、コスト面やリスク許容度も判断材料になります。採用代行は月額制で安定した運用が可能ですが、初期投資が必要です。人材紹介は成果報酬型のため初期費用は抑えられますが、採用単価が高くなることがあります。
これらの要素を総合的に考慮し、自社の採用戦略と状況に合ったサービスを選ぶことが成功の鍵となります。
採用代行が向いている企業
採用代行は、採用プロセス全体を効率化し体制を強化したい企業に有効です。
たとえば、大量採用や中長期的な採用計画を抱えている企業では、安定した母集団形成と効率的なフロー運営が求められます。また、社内の採用リソースが不足している場合でも、外部の専門家を活用することで業務負担を軽減できます。
さらに、採用の質を安定させたい企業や、選考基準やフローの整備が必要な企業にとっても、第三者の視点とノウハウが効果を発揮します。
つまり、採用代行は「効率化と体制強化を同時に実現したい企業」に最も適したサービスだといえます。
人材紹介が向いている企業
人材紹介は、即戦力となる人材をスピーディに確保したい企業に有効です。
たとえば、専門性の高いポジションの採用を行う企業では、豊富な候補者データベースを活用して適任者を早期に見つけることができます。また、初期費用を抑えたい企業にとっても、成果報酬型である人材紹介は無駄なコストをかけずに採用活動を進められる点が魅力です。
さらに、少人数の採用を効率的に行いたい場合や、自社の魅力を客観的にPRしたい場合にも、人材紹介会社のノウハウや第三者の視点が役立ちます。
人材紹介は、「即戦力人材を効率的かつ低リスクで確保したい企業」に最も適したサービスだといえます。
併用という選択肢
採用代行と人材紹介は、それぞれ異なる強みを持つサービスです。そのため、両者を併用することで、採用の幅を広げ、より効果的な採用活動が可能になります。
たとえば、採用代行で基盤となる採用体制を整えながら、人材紹介で専門的なポジションや即戦力人材をスピーディに補う形が考えられます。
併用することで、採用人数の増加や質の向上、社内リソースの最適化など、多様なニーズに柔軟に対応できるのがメリットです。
【5ステップ】採用代行・人材紹介サービス導入の進め方
採用代行や人材紹介サービスの導入は、導入のスピードなど異なるところはありますが、基本的には同じです。
ここでは、基本的な5つのステップをわかりやすく解説します。
- ステップ① 課題を明確にする
- ステップ② 採用KPIを設定する
- ステップ③ 依頼内容を決める
- ステップ④ 採用基準・選考フローの整理する
- ステップ⑤ パートナーを選定する
それぞれのステップをしっかり把握しましょう。
ステップ① 課題を明確にする
採用支援サービスを導入する際は、まず自社の採用における課題をはっきりさせることが重要です。
例えば、応募者数の不足や選考に時間がかかること、ミスマッチの多発など、具体的な問題点を把握しましょう。
この課題を明確にすることで、どのようなサービスが必要か、どの部分を重点的に改善すべきかを判断しやすくなります。社内の関係者から意見を集めたり、過去の採用データを分析することも効果的です。
ステップ② 採用KPIを設定する
課題を整理したら、次に採用活動の成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。具体的な数値目標を立てることで、進捗管理や効果測定がしやすくなります。
例えば、応募者数、面接通過率、内定承諾率、採用完了までの期間などをKPIとして設定することが一般的です。明確な目標を持つことで、採用支援サービスとの連携もスムーズに進みます。
ステップ③ 依頼内容を決める
採用KPIを設定したら、次に採用支援サービスに依頼する具体的な業務内容を決めます。求人媒体の選定や応募者対応、面接調整など、どの範囲を委託するかを明確にすることが大切です。
依頼範囲をはっきりさせることで、期待する成果や役割分担が明確になり、サービス提供者との認識のズレを防げます。 自社のリソースや課題に合わせて最適な範囲を選びましょう。
ステップ④ 採用基準・選考フローの整理
依頼内容を決めたら、次に、採用基準や選考フローを整理しておくことが重要です。
その結果、採用支援サービスが自社の求める人材像や選考プロセスを正確に理解し、一貫した対応が可能になります。
採用基準や選考フローが曖昧だと、ミスマッチや選考の遅れにつながる恐れがあります。事前に明確にしておくことで、スムーズな採用活動が期待できます。
ステップ⑤ パートナーを選定
最後に、自社のニーズや課題に合った採用支援サービスのパートナーを選定します。複数の候補からサービス内容や実績、費用、対応力を比較検討し、信頼できる企業を選ぶことが成功のカギです。
また、選定後も定期的にコミュニケーションを取り、課題の共有や改善点のフィードバックを行うことで、より効果的な採用支援が期待できます。
採用代行と人材紹介の違いについてよくある質問(FAQ)
採用代行と人材紹介の違いについてよくある質問をまとめました。
採用代行を依頼する会社はどうやって選べばいいの?
実績・対応範囲・業界理解度を比較し、自社の課題に合ったサービスを選ぶのがポイントです。複数社に相談して相見積もりを取るのがおすすめです。
人材紹介会社ごとに紹介される人材って違うの?
保有している人材データベースや得意分野が異なるため、紹介される人材も会社ごとに違います。複数社を併用することでより幅広い人材に出会える可能性が高まります。
両方使うときの予算配分ってどう考えればいい?
採用人数やポジションの重要度に応じて、採用代行は月額固定、紹介は成果報酬としてバランスを取るのが基本です。年間採用計画に合わせて柔軟に配分しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では「採用代行」と「人材紹介」の特徴や違い、メリット・デメリット、選び方や導入の流れまで詳しく解説しました。
採用代行は採用プロセス全体を包括的にサポートし、効率化や体制強化に向く一方、人材紹介は即戦力人材を短期間で確保するのに効果的です。それぞれに適した企業像や注意点を理解することで、自社に最適なサービスを選びやすくなります。
本記事の内容を参考に、自社の採用課題や目標に合ったサービスを見極め、効果的な採用活動につなげてください。
【9事例】採用を成功させるには?採用戦略や広報のコツを解説
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事
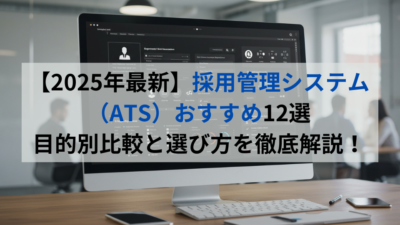
【2025年最新】採用管理システム(ATS)おすすめ12選|目的別比較と選び方を徹底解説!
- 採用代行
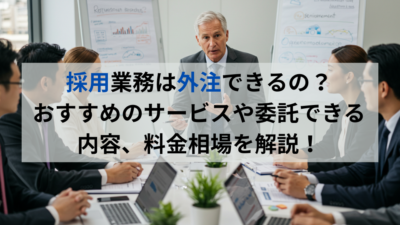
採用業務は外注できるの?おすすめのサービスや委託できる内容、料金相場を解説!
- 採用代行
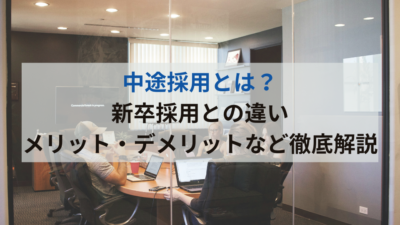
中途採用とは?新卒採用との違い、メリット・デメリットなど徹底解説
- 採用代行
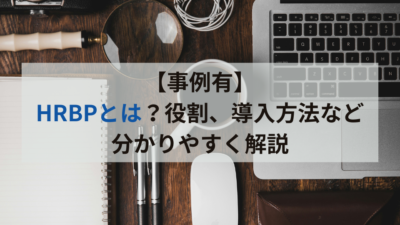
【事例有】HRBPとは?役割、導入方法など分かりやすく解説
- 採用代行
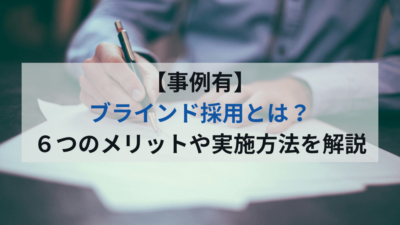
【事例有】ブラインド採用とは?6つのメリットや実施方法を解説!
- 採用代行

アルバイト採用に強い採用代行サービス5選!|費用相場やメリット・デメリットまで徹底解説!
- 採用代行







