
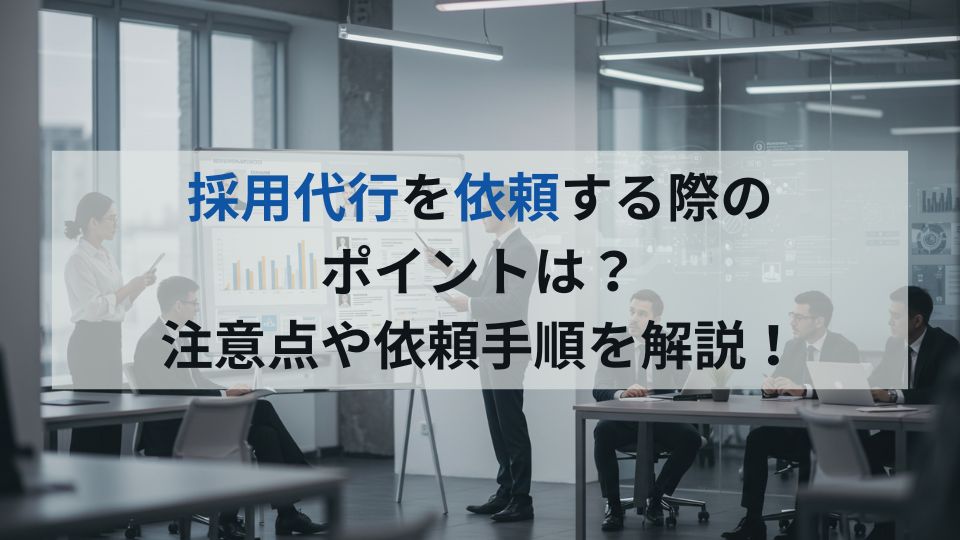
採用活動において、「求人を出しても応募が集まらない」「採用担当者のリソースが足りない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。採用市場の競争が激化し、必要な人材を必要なタイミングで確保することがますます難しくなっている今、外部の専門パートナーに業務を委託する 採用代行(RPO) が注目を集めています。
しかし、採用代行はただ業務を丸投げすればよいわけではなく、成果を最大化するには 依頼する際のポイントを押さえること が欠かせません。
本記事では、採用代行に依頼できる業務内容や料金体系、メリット・デメリットを整理しつつ、依頼の手順や選定のポイントをわかりやすく解説します。
改めて知りたい採用代行(RPO)とは?
企業の人材確保が難しくなっている今、多くの企業が注目しているのが「採用代行(RPO)」というサービスです。
RPOとは「Recruitment Process Outsourcing」の略で、企業の採用業務の一部または全体を外部の専門業者に委託する手法を指します。
採用代行は、単に応募者管理や面接日程の調整などの「作業」を代行するだけではありません。
近年では、採用戦略の設計やペルソナ策定といった上流工程から支援するケースも増えています。
採用活動は、新卒・中途・アルバイトなど多様な採用区分があるだけでなく、業界や職種によっても最適な手法が異なります。そのため、専門性の高い採用代行会社は、それぞれのニーズに応じてカスタマイズした支援を提供しています。
このように、採用代行とは単なるアウトソーシングではなく、採用成功の鍵となる存在です。
採用代行に依頼できる5つの業務範囲
採用代行(RPO)サービスの導入を検討する際、企業が具体的にどの業務を委託できるのかを明確にしておくことは非常に重要です。
そこで、特に依頼されることの多い5つの代表的な業務領域について順に解説していきます。
採用計画・戦略立案
採用活動のスタート地点となる「採用計画・戦略立案」は、全体の成果を左右する非常に重要な工程です。
企業の事業計画や中長期的な人材ニーズを踏まえ、採用人数・採用時期・ターゲット像・募集チャネルの選定などを明確にします。
特に人材市場が激しく変化する昨今、自社だけでこれらの要素を的確に判断・設計するのは簡単ではありません。
採用代行会社は、各業界の採用動向や成功事例を熟知しており、最新データをもとに効果的な計画を立案します。
また、ターゲットとなる人材の明確化や、KPIの設定、競合企業との差別化ポイントなども第三者の視点から整理されるため、実行性が高くなります。
このように、計画段階の外部支援は、成功する採用の出発点として大きな効果を発揮します。
母集団形成
計画が整った後、実際に求職者を集める段階が「母集団形成」です。
ここでは、求人広告の作成・出稿、媒体の選定、スカウト配信、SNS活用、イベントの開催など、多様な手法が用いられます。
採用代行はこれらの手段に精通しており、業種や職種、ターゲット人材の属性に応じたチャネル戦略を設計してくれます。
また、過去の配信実績や応募率のデータを基にした改善提案も期待できるため、採用の打ち手が場当たり的になるリスクも避けられます。
効果的な母集団形成によって、採用成功への土台が整うのです。
候補者管理
応募者が集まった後は、「候補者管理」の業務が始まります。
このフェーズでは、エントリー情報の整理、進捗管理、面接日程の調整、連絡業務、ATS(採用管理システム)の運用などが含まれます。
特に同時に複数ポジションの採用を進める場合や、大量応募が見込まれる求人では、人的リソースの確保が難しくなることも多いでしょう。
採用代行を活用することで、情報の一元管理が実現し、対応漏れや属人化を防ぐことができます。
選考・面接
採用代行では、書類選考や一次面接の代行まで対応することが可能です。
たとえば、事前に評価項目やスクリーニング基準を共有しておけば、外部パートナーが企業の判断基準に沿って評価を行い、一定の質を保った選考を代行できます。
また、面接の日程調整、面接官との連携、合否連絡などのオペレーション業務もまとめて依頼できるため、担当者の工数削減に大きく貢献します。
選考工程における精度とスピードを両立させたい企業にとって有効な手段です。
内定後フォロー・定着支援
採用活動のゴールは「入社」ではなく、「定着と活躍」です。
内定後の辞退防止や、入社手続き・オンボーディング支援を行うことで、早期離職リスクを抑えることができます。
採用代行会社は、内定者との定期的な接点の確保、質問対応、入社準備の進捗管理なども支援してくれます。
また、入社直後のフォロー面談やアンケートの実施、上司とのコミュニケーションサポートまで提供するサービスもあり、早期定着率の向上に直結します。
こうした施策により、採用ROIを最大化することが可能です。
採用代行を依頼する際の料金体系
採用代行サービスの導入を検討するうえで、料金体系の理解は欠かせません。
費用感が不透明なままでは予算計画が立てづらいことも多くあります。
そのため、代表的な3つの料金体系について詳しく解説します。
定額制(月額)
定額制(月額制)は、採用代行において最も広く利用されている料金モデルのひとつです。
企業は毎月決まった料金を支払うことで、契約範囲内の業務を継続的に委託することができます。
料金は対応業務や採用規模により異なりますが、一般的に月10万〜30万円前後のプランが多く、業務ボリュームが大きい場合には月100万円を超えるケースもあります。
このモデルの最大の利点は、予算の立てやすさにあります。
月々の支出が一定で変動しないため、採用コストを平準化しやすく、経理部門との調整も容易です。
さらに、長期的に同じパートナーと連携することで、企業理解が深まり、採用業務の精度が向上しやすくなります。
ただし、採用件数が少ない月も同額の費用が発生するため、稼働量と費用のバランスを見極める必要があります。利用頻度が低い企業には割高に感じられる可能性もあるため、依頼内容を明確にした上で契約条件を調整することが大切です。
成果報酬型
成果報酬型は、実際に採用が決定した時点で料金が発生する方式です。
中途採用において人材紹介会社が用いる形態と似ており、「採用成功1件につき◯万円」または「年収の◯%」といった設定が一般的です。
このモデルの魅力は、成果が出た分だけ支払うため、無駄なコストが発生しにくい点です。
採用が成立しなければ費用はかからないため、初期コストを抑えたい企業にとっては導入しやすい料金体系と言えるでしょう。
一方で、成果を出すことに焦点が置かれすぎると、候補者の質よりも「採用の数」に偏りがちになるリスクもあります。
さらに、高額な報酬率が設定されているケースでは、結果的に定額制よりもコストが高くなる可能性もあるため、料金と成果のバランスを見極めた判断が求められます。
従量課金型
従量課金型は、対応件数や作業量に応じて料金が発生するモデルです。
たとえば「スカウトメール100通あたり◯円」「面接調整1件◯円」といった形で、業務単位での価格設定がされます。
この方式のメリットは、必要な分だけ依頼できる柔軟性にあります。
特定業務のみを一時的に外注したい場合や、採用ニーズが波のある企業には非常に適したモデルです。
必要最小限のコストで効率よく採用活動を補完することができます。
ただし、業務ごとに金額が変動するため、最終的な費用総額が予測しづらくなる場合もあります。また、細かい業務単位で契約を結ぶ必要があるため、仕様設計や管理コストが増える懸念もあるでしょう。
採用代行サービスを依頼する際の重要ポイント
数多くの採用代行サービスが存在する中で、自社に適したサービスを選ぶことは決して簡単ではありません。
ここでは、採用代行サービスの選び方において特に重要視すべき3つの観点を紹介します。
- 自社の課題と対応範囲の適合度
- 費用
- 導入実績
自社の課題と対応範囲の適合度
採用代行サービスの選定において、最初に確認すべきポイントは、自社が抱える採用課題とサービスの対応範囲が合致しているかどうかです。
「母集団形成に課題があるのか」「候補者管理にリソースが割けないのか」「面接以降の選考業務が煩雑なのか」といった点を具体的に把握しましょう。
その上で、各代行会社がどのフェーズに強みを持ち、どの業務領域に対応しているのかを調べ、課題と支援内容の重なりが大きい業者を選ぶことが成功の鍵です。
戦略設計に長けた企業もあれば、現場のオペレーション代行を得意とする企業もあります。
さらに、特定職種(エンジニア、営業、新卒など)や雇用形態(正社員、アルバイト)に強みを持つ業者も存在するため、自社のニーズと照らし合わせて判断することが求められます。
費用
採用代行サービスの選定において、費用面の確認は欠かせません。
料金体系は主に「定額制(月額)」「成果報酬型」「従量課金型」の3パターンがあり、採用規模や期間、採用目標に応じて最適な形式を選ぶ必要があります。
費用対効果を見極める視点も重要で、単に安いから選ぶのではなく、自社の課題を解決できるかを基準に判断しましょう。
また、追加費用の有無(例えば求人媒体の掲載料や面接代行の回数超過分など)もあらかじめ確認しておくことで、導入後のトラブルを回避できます。
導入実績
採用代行サービスの信頼性や実績は、選定時の重要な判断材料です。
導入実績が豊富な企業は、業種・業界・企業規模ごとの特性を把握しているため、より現実的で効果的な支援が可能です。
とくに、自社と同業種や同規模の支援実績があるかは注目すべきポイントです。
たとえばスタートアップや中小企業であれば、リソースが限られた中でも成果を上げてきた事例のある代行会社が望ましく、大企業であれば複雑な選考フローや大量採用の対応経験が求められます。
実績紹介や導入事例が公式サイトに掲載されているかを確認し、できれば事前にヒアリングを通じて詳細を聞くこともおすすめです。
【5ステップ】採用代行を依頼する手順
採用代行サービスの導入を成功させるには、闇雲に依頼するのではなく、段階を踏んで準備を進めることが肝要です。
ここでは、依頼から運用・評価に至るまでの5つのステップを解説します。
採用課題の明確化
採用代行を依頼する前には、まず自社の採用課題を明確にすることが重要です。
採用がうまく進まない要因がどのフェーズにあるのかを具体的に洗い出しましょう。
課題が明確であるほど、代行会社に依頼する業務範囲や期待値を明確に設定でき、ミスマッチを防ぐことができます。
代行会社の選定
課題が整理できたら、その解決に適した代行会社を選定します。
選定の際は、自社の業界知識を持っているか、過去に同様の課題を解決した実績があるかなどを確認しましょう。また、支援範囲や対応体制が自社に合っているかも重要です。
複数社を比較検討し、面談や提案を通して相性も見極めることが成功の鍵となります。
業務範囲・契約条件のすり合わせ
依頼前には、どこまでの業務をどのように対応してもらうのかを明確にし、契約書に落とし込む必要があります。
人票作成・応募者対応・選考管理など、対応内容ごとに双方の役割分担を明示しておくとトラブルを防げます。
また、業務量やKPI(重要業績評価指標)、対応時間帯などの条件もすり合わせておくことで、運用開始後の齟齬を回避できます。
運用開始
契約締結後は、実際の運用が始まります。
初期段階では、キックオフミーティングを実施し、改めて目的や業務範囲、報告体制などを確認します。運用初期はトライアル的に小規模でスタートし、定期的なコミュニケーションやレビューを通じて改善を図っていくと良いでしょう。
スタート段階での丁寧な設計が、長期的な成果につながります。
採用代行の効果検証
運用後は、必ず効果検証を行いましょう。
採用スピードの改善、採用コストの削減、応募者対応の質向上など、設定したKPIをもとに実績を分析します。
もし想定通りに進んでいない場合は、代行会社との連携が重要です。
定期的な評価と見直しを続けることで、採用活動をより効果的に最適化できます。
採用代行を依頼する際の注意点
採用代行サービスは非常に便利な一方で、導入後にトラブルやミスマッチが発生するケースも少なくありません。
ここでは、依頼時に気をつけるべき重要なポイントを3つに絞ってご紹介します。事前の注意を払うことで、スムーズな連携と最大限の成果を得ることができます。
ナレッジ蓄積のルール制定
採用代行を活用することで業務は効率化されますが、その一方で自社内に採用に関する知見が蓄積されにくくなるという課題があります。
特に初めて外部に採用を委託する企業の場合、業務を任せきりにしてしまうと、担当者が異動や退職した際に再現性のある運用ができなくなってしまうことがあります。
この問題を避けるためには、情報共有とナレッジの蓄積ルールを事前に整備しておくことが重要です。外注に頼り切るのではなく、あくまでパートナーとして情報交換を密に行う姿勢が、ナレッジの積み上げとともに質の高い採用を実現する鍵になります。
自社担当領域と依頼範囲の線引きの明確化
採用代行サービスを効果的に活用するには、自社が担うべき業務と外部に委託する業務の範囲を明確に線引きしておくことが不可欠です。線引きが曖昧なまま運用を開始すると、担当者間での認識のずれが発生し、対応の重複や漏れといった運用トラブルを引き起こしかねません。
たとえば、面接の日程調整を代行に任せる場合、候補者とのメール文面の確認は誰が行うのか、面接官のスケジュール調整は誰が責任を持つのかなど、細かな業務ごとに責任の所在を明示する必要があります。こうした分担が明確になることで、双方が安心して業務に集中でき、無駄なやり取りや手戻りも防げます。
また、依頼する範囲が広がるほど、自社の意思決定が関与すべき場面も増えます。そのため、業務の粒度を細かく定義し、意思決定プロセスを含めた運用ルールを設けておくことが理想です。これにより、採用活動全体の透明性と一貫性が保たれ、期待した成果にもつながりやすくなります。
採用代行依頼についてよくある質問(FAQ)
採用代行依頼についてよくある質問をまとめました。
採用代行と人材紹介の違いは?
採用代行は企業の採用業務全体を外部に委託する仕組みで、求人広告の出稿や面接調整まで幅広く対応します。
一方、人材紹介は特定の候補者を紹介するサービスに特化しており、業務支援の範囲は限定的です。
採用代行はどの規模の企業に向いている?
中小企業から大手企業まで幅広く利用されています。
特に採用担当者のリソースが限られていたり、急な採用が発生する企業では、導入によって大きな業務効率化が見込めます。
途中で契約を見直すことはできる?
多くの採用代行会社は契約期間中でも内容の調整が可能です。初期のすり合わせや定期的なレビュー機会を設けることで、柔軟に対応できる体制を整えましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、採用代行(RPO)の基本から、依頼できる業務内容、料金体系、選定のコツ、依頼手順、注意点までを詳しく紹介しました。
採用代行は、単なる業務の外注にとどまらず、戦略設計から定着支援までを網羅する重要なパートナーです。特に人事リソースが限られる企業や、急な採用ニーズに直面した企業にとって、大きな力となるでしょう。
自社の課題を明確にし、適切なサービス範囲や契約内容を見極めた上で、信頼できる代行会社と連携することが、成功への近道です。
ぜひ本記事を参考に、採用代行依頼をご検討ください。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

採用コスト(採用単価)の相場は?削減方法やおすすめ採用手法、注意点を解説
- 採用代行
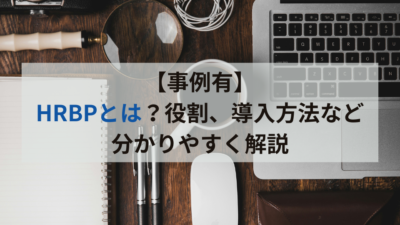
【事例有】HRBPとは?役割、導入方法など分かりやすく解説
- 採用代行
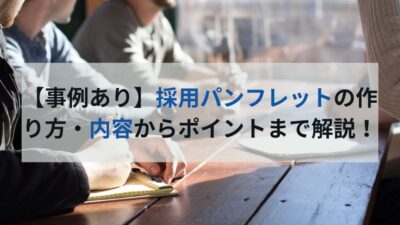
【事例あり】採用パンフレットの作り方・内容からポイントまで解説!
- 採用代行

採用ができない理由は?13個の原因と解決策を徹底解説
- 採用代行
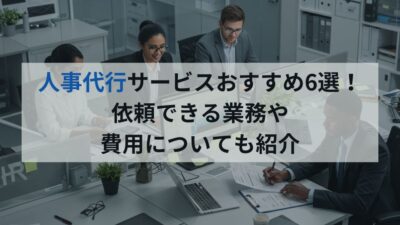
人事代行サービスおすすめ6選!依頼できる業務や費用についても紹介
- 採用代行

自社に最適な採用チャネルとは?種類と特徴、サービス選定のポイントを徹底解説!
- 採用代行







