
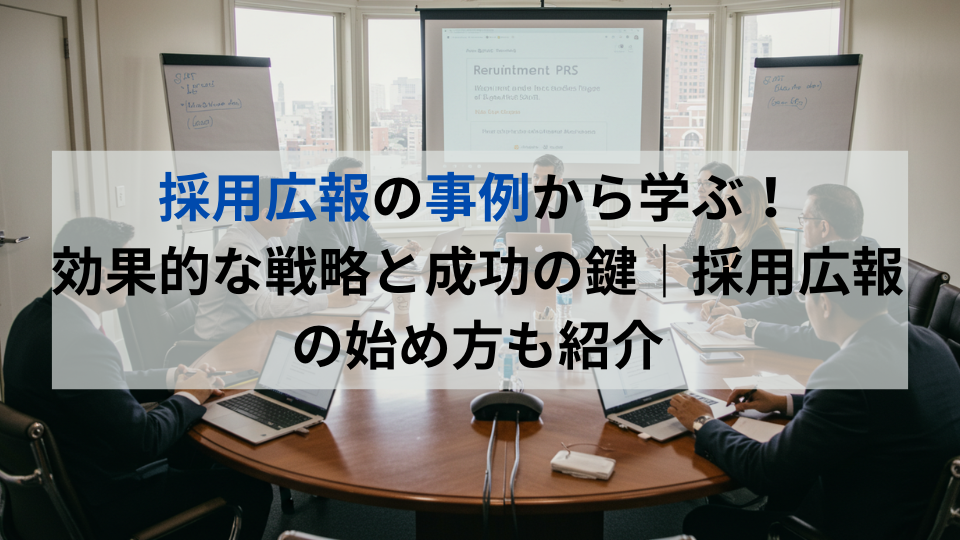
「いい人材が集まらない」「応募が来てもミスマッチが多い」と悩んでいませんか?労働人口の減少や求職者の価値観の多様化が進む今、従来の求人広告だけでは、求める人材にアプローチするのが難しくなっています。
そこで注目されているのが「採用広報」です。
本記事では、なぜ今採用広報が重要なのか、その具体的な進め方、そして成功企業の事例から学べる実践的なノウハウを詳しくご紹介します。この記事を読んで、自社に最適な人材を獲得するための第一歩を踏み出しましょう。

採用広報とは?その重要性と注目される背景
近年、企業の採用活動において「採用広報」の重要性が増しています。
- 採用広報の定義と基本的な役割
- 採用広報が注目される3つの背景
- 採用広報を怠るデメリットと取り組むメリット
この章では、まず採用広報の基本的な定義と、なぜ今これほど注目されているのか、その背景について解説します。
採用広報の定義と基本的な役割
採用広報とは、企業が自社の事業内容、カルチャー、働く人々の魅力などを多角的に発信し、求める人材からの認知度・志望度を向上させるための広報活動です。単に「人が欲しい」と伝える採用活動とは異なり、求職者が「この会社で働きたい」と感じるような、会社のブランドイメージを構築する役割を担います。これにより、応募者数を増やすだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、社員の定着率向上にも繋がる重要な取り組みです。
採用広報が注目される3つの背景
採用広報が注目される背景には、主に以下の3つの変化が挙げられます。
- 労働人口の減少による採用難易度の上昇
- 求職者の情報収集の変化(企業側の透明性が求められるように)
- 求職者の価値観の多様化(「何をやるか」だけでなく「誰とやるか」「どう働くか」を重視)
特に現代の求職者は、給与や待遇だけでなく、企業の文化や働く人々の雰囲気を重視しています。そのため、一方的な情報発信ではなく、企業のリアルな姿を伝える採用広報が不可欠になっています。
採用広報に取り組むメリット
採用広報を怠ると、多くのデメリットが生じます。最も深刻なのは、企業の認知度が上がらず、そもそも応募者が集まらない「母集団形成の失敗」です。また、情報が少ないことで求職者が企業への理解を深められず、入社後のミスマッチによる早期離職にも繋がりかねません。逆に、採用広報に積極的に取り組むことで、潜在層を含む幅広い人材にアプローチが可能となり、応募者数の増加、質の高い人材の確保、そして採用コストの削減といった多くのメリットを享受できます。
採用広報の戦略を立てる【5つのステップ】
採用広報は、場当たり的にSNS投稿や記事を作成するだけでは効果を発揮しません。成功させるためには、明確な戦略に基づいた計画的な実行が不可欠です。
- STEP1. 採用広報の「目的」と「ターゲット」を明確にする
- STEP2. 自社の「魅力」と「独自性」を言語化する
- STEP3. ターゲットに合わせた発信内容と手法を決定する
- STEP4. 適切なKPIを設定し、効果を可視化する
- STEP5. 施策を実行し、効果測定と改善を繰り返す
ここでは、採用広報の戦略を立てる際に欠かせない5つのステップを解説します。
STEP1. 採用広報の「目的」と「ターゲット」を明確にする
採用広報を始める前に、まず「なぜ採用広報を行うのか?」という目的を明確にしましょう。例えば、「応募者数を増やす」「特定の職種の人材を獲得する」「入社後のミスマッチを減らす」など、目的によって戦略は大きく変わります。次に、その目的に応じて「どのような人物にアプローチしたいのか」というターゲット像(ペルソナ)を具体的に設定します。これにより、発信する情報や媒体を絞り込み、効率的な広報活動が可能になります。
STEP2. 自社の「魅力」と「独自性」を言語化する
目的とターゲットが定まったら、次に自社の魅力を棚卸し、言語化します。他社にはない強みや独自のカルチャー、働く社員の生の声など、求職者が「この会社で働きたい」と感じるような独自性を掘り起こしましょう。例えば、ユニークな福利厚生や働き方、社員同士のコミュニケーションの様子など、求人票だけでは伝わらないリアルな情報を整理することが重要です。これを基に、採用広報のコアメッセージを構築していきます。
STEP3. ターゲットに合わせた発信内容と手法を決定する
設定したターゲットに、言語化した自社の魅力を届けるための発信内容と手法を決定します。例えば、若年層のエンジニアがターゲットであれば、技術ブログやテック系のイベント情報の発信が効果的です。また、手法としては「オウンドメディア」「SNS(X、Instagramなど)」「採用ピッチ資料」「採用動画」などが考えられます。どの手法が最適かは、ターゲット層の情報収集方法を分析し、最適な組み合わせを選ぶことが重要です。
STEP4. 適切なKPIを設定し、効果を可視化する
採用広報の効果を測り、改善していくためにはKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。例えば、「採用サイトのPV数」「SNSのフォロワー数」「イベントへの参加者数」「コンテンツからの応募数」など、目的と連動した具体的な指標を設けましょう。これにより、施策が計画通りに進んでいるか、どの部分に課題があるのかを定量的に把握できます。曖昧なまま進めるのではなく、数値で成果を追うことで、次の一手を論理的に判断できます。
STEP5. 施策を実行し、効果測定と改善を繰り返す
戦略に基づいて施策を実行したら、定期的にKPIをチェックし、効果測定を行います。当初の計画通りに進んでいない場合は、なぜ期待した成果が出ないのかを分析し、改善策を検討します。例えば、PV数が伸び悩んでいるならコンテンツ内容を見直したり、SNSの投稿時間や頻度を変えたりします。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを回すことで、採用広報の精度は継続的に向上していきます。
【5分で分かる】採用代行とは?費用、メリデメ、委託可能な業務を解説
【採用担当者必見】採用広報の主要な手法と最新トレンド
採用広報の戦略を立てた後、実際にどのような手法を用いて情報を発信していくかが重要になります。手法は多岐にわたるため、自社のターゲット層やリソースに合わせて最適なものを選ぶ必要があります。
- 採用広報の代表的な手法(オウンドメディア、SNS、採用ピッチ資料など)
- 今知っておくべき採用広報の最新トレンド
- 各手法のメリット・デメリットと選び方のポイント
ここでは、代表的な手法と、近年特に注目されている最新トレンドについて解説します。
採用広報の代表的な手法(オウンドメディア、SNS、採用ピッチ資料など)
採用広報の手法には、主に以下のようなものがあります。
- オウンドメディア:自社ブログや採用サイト。企業のリアルな文化や社員の働き方を深く伝えられる。
- SNS(X、Facebook、Instagramなど):気軽に情報を発信でき、求職者とのコミュニケーションも図りやすい。
- 採用ピッチ資料:会社の概要や事業内容、募集職種をまとめたスライド資料。社内の透明性を伝えられる。
- 採用動画:オフィスツアーや社員インタビューなど、映像で会社の雰囲気を直感的に伝えられる。
これらの手法は単独で使うだけでなく、複数を組み合わせて多角的に情報を発信することで、より効果を高めることができます。
今知っておくべき採用広報の最新トレンド
近年、特に注目されている採用広報のトレンドは以下の通りです。
- 動画コンテンツの活用:TikTokやYouTubeなどのショート動画で、企業の魅力をスピーディーに伝える。
- 音声コンテンツの活用:Podcastなどを使って、移動時間にも聞けるコンテンツで潜在層にアプローチ。
- 「技術広報」の専門化:エンジニアなど専門職向けに、技術的な内容に特化した情報発信を行う。
これらのトレンドは、求職者が情報を得る手段の多様化を反映しています。特に動画は、文字情報だけでは伝えきれない臨場感や雰囲気を伝える上で非常に強力なツールとなります。
各手法のメリット・デメリットと選び方のポイント
各手法にはメリットとデメリットがあります。例えば、オウンドメディアは深い情報を発信できる反面、運用に時間がかかります。一方、SNSは手軽に始められるものの、炎上リスクなどの注意点もあります。手法を選ぶ際は、自社のターゲット層がどの媒体をよく利用するか、そして自社の人材や予算といったリソースを考慮することが重要です。まずは無理なく始められる手法から着手し、徐々に発信媒体を増やしていくのが賢明でしょう。
【事例10選】採用広報を成功させた企業から学ぶ戦略とノウハウ
採用広報を成功させるには、実際に成果を出している企業の事例から学ぶのが最も効果的です。ここでは、採用広報に力を入れ、成果を出している企業の成功事例を10社ピックアップし、その戦略とノウハウを解説します。
メルカリ:多角的な情報発信でカルチャーを伝える
メルカリは、採用サイトやオウンドメディア「mercan(メルカン)」を通じて、多様な働き方やカルチャーを積極的に発信しています。社員インタビュー、プロジェクトストーリー、社内イベントの様子など、多岐にわたるコンテンツで、求職者が働くイメージを具体的に持てるように工夫しています。特に、入社後のオンボーディングや評価制度など、採用後の情報も隠さずに開示する透明性の高さが特徴です。これにより、応募者のミスマッチを防ぎ、入社後の高い定着率に繋がっています。
サイボウズ:独自の働き方と多様性を前面に押し出す
サイボウズは「100人いれば100通りの働き方」というメッセージを掲げ、多様な働き方を許容する独自の文化を強く発信しています。採用広報の中心は、代表や社員が執筆するオウンドメディア「サイボウズ式」です。このメディアでは、仕事への価値観や会社の課題についても正直に語っており、単なる美談ではない、等身大の企業の姿を伝えています。これにより、サイボウズの価値観に共感する求職者が集まり、カルチャーマッチした人材の採用に成功しています。
LINE:企業としてのブランドイメージと親近感の両立
LINEは、一般消費者向けのSNSとしての高い知名度を活かしつつ、採用広報にも力を入れています。採用サイトや公式SNSでは、エンジニア向けの技術情報から、社員のインタビュー、オフィス紹介まで、幅広いコンテンツを発信しています。特に、動画コンテンツを豊富に活用し、オフィスや社員の雰囲気を臨場感たっぷりに伝えることで、企業としての先進的なイメージと、親しみやすいカルチャーの両方を求職者に伝えています。これにより、優秀なIT人材からの応募を増やしています。
freee:具体的な社員インタビューで働く魅力を深掘り
freeeは、オウンドメディア「freee Developers Hub」や「freeeの採用広報」を通じて、社員の仕事内容やキャリアパスを詳細に紹介しています。特に、具体的な業務内容やチームの雰囲気、日々の働き方を深掘りした社員インタビュー記事は、求職者にとって非常に有益な情報源となっています。また、カジュアル面談やイベントの情報を積極的に発信し、求職者との接点を増やすことで、入社前の段階から企業理解を深めてもらうための機会を創出しています。
その他、業界別・手法別の成功事例(SNS、動画など)
上記の事例以外にも、多くの企業が独自の採用広報で成果を上げています。
- 株式会社ナイル:オウンドメディアとブログ記事で、企業のビジョンと働き方を深く伝える。
- 株式会社Gunosy:「技術広報」に特化したブログで、優秀なエンジニアにアプローチ。
- 株式会社ベッセル(ホテル業):SNSで働く社員のリアルな日常を配信し、業界のイメージを変える。
- トゥモローゲート株式会社(TikTok):面白く、インパクトのあるショート動画で企業の認知度を飛躍的に向上。
- ベルフェイス株式会社:採用ピッチ資料を公開し、会社の文化や待遇を正直に伝える。
これらの事例から共通して言えるのは、自社の強みや独自性を明確にし、ターゲットに合わせた媒体で、継続的に発信しているという点です。
採用広報を成功させるための【3つのポイント】
これまでの解説や成功事例から見えてくる、採用広報を成功させるために不可欠な3つの重要なポイントをまとめました。
- ポイント1. 全社を巻き込む協力体制を構築する
- ポイント2. 求職者視点に立った、リアルで透明性の高い情報を発信する
- ポイント3. 継続的な運用とPDCAサイクルを回す
これらの点を押さえることで、自社の採用広報の質を飛躍的に向上させることができます。
ポイント1. 全社を巻き込む協力体制を構築する
採用広報は、人事や広報担当者だけが担うものではありません。社員一人ひとりが自社の魅力を発信する「アンバサダー」となることが重要です。社員ブログの執筆、SNS投稿への協力、カジュアル面談への参加など、現場の社員を巻き込むことで、よりリアルで説得力のある情報が発信できます。トップダウンで進めるのではなく、社員の自発的な参加を促すような仕組みづくりが成功の鍵を握ります。
ポイント2. 求職者視点に立った、リアルで透明性の高い情報を発信する
求職者は、企業が発信する「いい話」だけでは満足しません。仕事のやりがいだけでなく、大変なこと、チームの課題、入社後のキャリアパスなど、リアルな情報を求めています。成功事例の企業が実践しているように、良い面だけでなく、課題や改善点も正直に伝えることで、企業への信頼が高まります。透明性の高い情報発信は、ミスマッチを防ぎ、入社後のエンゲージメント向上にも繋がります。
ポイント3. 継続的な運用とPDCAサイクルを回す
採用広報は、一度きりのイベントではありません。継続的な情報発信と、効果測定に基づく改善が不可欠です。定期的なブログ更新、SNS投稿、イベント開催など、発信を途切れさせないことが重要です。また、前述のKPI設定に基づき、どのコンテンツが、どの媒体で、どれだけの効果があったのかを常に分析し、次の一手を考えていきます。この地道なPDCAサイクルが、長期的な採用成功への道を開きます。
【2025年最新】採用代行を依頼するには?業務範囲や料金、選び方、手順を解説!
採用広報のよくある課題と解決策
採用広報を始めたものの、「リソースが足りない」「コンテンツのネタが尽きてきた」「効果が見えない」といった課題に直面する企業は少なくありません。
- リソース不足の解決策:外部委託(採用代行)も視野に
- コンテンツの企画・ネタ切れの解決策
- 効果測定が難しい場合の解決策
ここでは、これらのよくある課題に対する具体的な解決策を解説します。
リソース不足の解決策:外部委託(採用代行)も視野に
採用広報は、継続的な運用が求められるため、社内のリソースが限られている企業にとっては大きな負担となりがちです。その場合、採用広報を専門とする外部サービスや、採用代行(RPO)サービスの活用を検討するのも有効な手段です。コンテンツ制作、SNS運用、採用イベントの企画・運営など、プロに任せることで、社内の負担を軽減しながら、質の高い採用広報を実現できます。
コンテンツの企画・ネタ切れの解決策
「どんな記事を書けばいいかわからない」「社員インタビュー以外にネタがない」といった悩みもよく聞かれます。解決策としては、「社員の1日」密着取材や「チームの飲み会」レポートなど、日常の切り取り方を工夫するのがおすすめです。また、業界のトレンドや技術情報、社員が個人的に学んでいることなど、業務外の視点を取り入れることで、コンテンツの幅を広げることができます。
効果測定が難しい場合の解決策
「せっかく採用広報を始めたのに、効果がわからず評価できない」という課題には、まずKPIの見直しから始めましょう。応募数や内定承諾率だけでなく、SNSのエンゲージメント率(いいね、シェア数)、サイトの滞在時間、特定のコンテンツからの流入数など、中間指標を細かく設定します。これにより、施策のどこにボトルネックがあるのかを特定しやすくなり、次の改善策が明確になります。
採用広報についてよくある質問(FAQ)
採用広報に関するよくある質問をまとめました。
採用広報はどんな会社に向いている?
従業員数や業種を問わず、自社の魅力を発信したいすべての企業に向いています。特に、知名度を上げたいスタートアップや、採用難易度の高い専門職の人材を求めている企業にとって非常に有効な手法です。
採用広報はいつから始めればいい?
採用活動が本格化する前、つまり「人が欲しくなる前」から始めるのが理想的です。継続的な情報発信が重要なので、長期的な視点を持って計画的に取り組むことが成功の鍵となります。
採用広報の担当者は誰がやるべき?
人事担当者だけでなく、広報担当者や各部門の現場社員を巻き込むのが効果的です。特に、現場の社員がアンバサダーとして魅力を発信することで、よりリアルで説得力のある情報が伝えられます。
コンテンツのネタが尽きてきたらどうすればいい?
社内の日常を切り取ったり、社員の個人的な学びやキャリアパスに焦点を当てたりすることで、コンテンツの幅を広げられます。また、業界のトレンドや技術情報など、業務外の視点を取り入れるのも有効です。
まとめ
本記事では、採用広報の基本から、成功企業の事例、そして具体的なノウハウまでを幅広く解説しました。少子化による労働人口減少や、求職者の価値観の多様化が進む現代において、採用広報は単なる情報発信ではなく、企業の未来を創るための重要な経営戦略と言えます。
本記事で解説した「5つのステップ」で戦略を立て、「3つのポイント」を押さえながら、継続的に採用広報に取り組むことで、自社にマッチした優秀な人材の獲得に繋がります。ぜひ、この機会に貴社の採用広報を見直してみてください。
関連記事
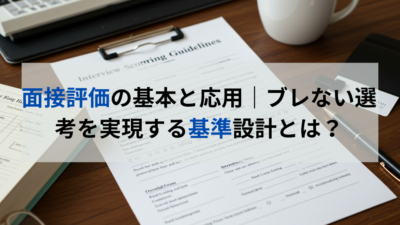
面接評価の基本と応用|ブレない選考を実現する基準設計とは?
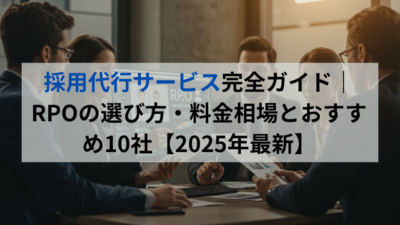
採用代行サービス完全ガイド|RPOの選び方・料金相場とおすすめ10社【2025年最新】
- 採用代行

採用広告とは?各媒体のメリットや選定方法、効果的な活用方法まで徹底解説!
- 採用代行
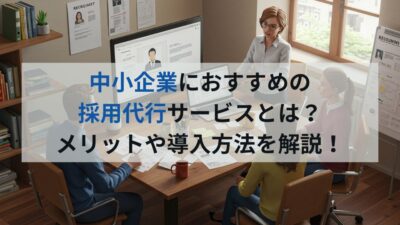
中小企業におすすめの採用代行サービスとは?メリットや導入方法を解説!
- 採用代行

【事例付き】採用ブランディングとは?進め方・ポイント、発信手段を解説
- 採用代行

エンジニア採用に効く!採用ピッチ資料の作り方と活用法を徹底解説
- 採用代行






