

日本の多くの企業が直面しているIT人材不足は、企業のデジタル化やDX推進を大きく阻害する深刻な問題です。経済産業省の調査では、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されており、この課題は「2025年の崖」やスキルギャップの顕在化など、さまざまな要因が絡み合って複雑化しています。本記事では、IT人材不足の現状と将来予測、その背景にある構造的要因、企業経営への影響、そして特に不足しやすいスキル領域について解説します。さらに、社内での人材確保・育成、外部リソースの活用といった多角的な対策アプローチを提示し、持続的な企業成長のための戦略を深掘りしていきます。
【参考文献】「参考資料 (IT人材育成の状況等について)」経済産業省
関連動画:採用媒体4社を徹底比較!Green・Wantedly・Findy・LAPRAS SCOUTの特徴とは?
IT人材不足の現状・将来予測
現在、国内外問わず深刻化しているのがIT人材不足の問題です。特に日本においては、この課題が企業のデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を大きく阻害している状況にあります。この章では、現状の数字や将来予測をもとに、企業が直面する人材難の実態を明らかにします。
- 2030年に最大約79万人不足との試算
- 「2025年の崖」による老朽化したシステム刷新の需要が向上
- 人数不足に加え、スキルギャップという新たな課題も顕在化
- IT市場の成長スピードに供給側が追いついていない
IT市場拡大に対する供給の遅れ
経済産業省の調査によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足するとの予測が示されています(出典:「IT人材需給に関する調査」経済産業省)。この不足は、AIやIoT、ビッグデータ、クラウドなど高度IT技術の導入が急速に進む一方で、それに対応できるスキルを持った人材の供給が追いつかないために起こります。
特に中小企業にとっては、採用競争が大企業よりも不利になりがちで、人材不足の影響がより深刻に現れることが懸念されています。
「2025年の崖」による老朽化したシステム刷新の需要が向上
「2025年の崖」とは、老朽化した基幹システムの限界が訪れる時期として経産省が警鐘を鳴らしている概念です。多くの企業では、20年以上前に構築されたレガシーシステムが今も稼働していますが、それらを支えてきた技術者の高齢化や退職により、保守も困難な状況になっています。
これに伴い、システムの刷新・再構築ニーズが爆発的に高まる見込みであり、この対応を担うIT人材が圧倒的に不足するとされています。結果として、経営リスクの増大や業務停止のリスクさえ想定されます。
人数不足に加え、スキルギャップという新たな課題も顕在化
単に人数が足りないという問題にとどまらず、IT人材の「質」に関する課題も顕在化しています。特にAI、クラウド、セキュリティといった先端分野では、実務経験のある人材が極めて少なく、採用してもすぐに戦力化できないケースが多発しています。
また、旧来型のインフラやシステム運用に特化した技術者と、今後求められるデジタル人材との間にはスキルのミスマッチが大きく広がっており、社内の教育制度やリスキリング支援も急務となっています。
IT市場拡大に対する供給の遅れ
クラウドサービスの普及や、企業のDXニーズの高まりを背景に、日本のIT市場は年々拡大しています。しかし、それに見合った人材の供給が行われていないのが現状です。特に地方ではIT教育の機会が限られており、都市圏との人材偏在も深刻な問題となっています。
企業が求める技術者のレベルや専門性に対応できる教育機関・学習環境が十分に整っていないため、「育てられない」「採れない」二重苦に直面している企業も少なくありません。
IT人材が不足する4大要因
IT人材不足の背景には、単に求人倍率が高いといった表層的な問題だけでなく、より深層に根差した4つの構造的要因があります。ここでは、企業が人材確保に苦戦する本質的な理由を明らかにし、今後の対策を検討する土台とします。
- 技術進化と教育制度のタイムラグ
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 人材流動性の高まりと早期離職の常態化
- 需要と育成体制のミスマッチ
技術進化スピードと教育のタイムラグ
AI、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術は、年々スピード感を持って進化しています。対して、大学や専門学校のカリキュラム改訂や、社内研修の見直しは即時的には進まず、教育と現場ニーズとの間に大きなギャップが生まれています。
例えば、クラウドネイティブなアーキテクチャやセキュリティ対応など、企業が今まさに必要としている知識を新卒が持っていないというケースが多発。これにより「採用しても育成に時間がかかる」「現場が求めるレベルに達しない」といった課題を引き起こしています。
少子高齢化による労働人口の減少
日本全体で進行している少子高齢化の影響は、IT業界にも深刻な影響を及ぼしています。特に若手人材の絶対数が減少しており、今後は中堅・ベテランの人材層が抜ける一方で、補充が追いつかない構造が顕著です。
これにより、企業内の技術継承が困難になったり、管理職候補の育成が滞ったりすることも少なくありません。人口動態という不可逆的な要因であるため、単なる採用努力だけでは解決が困難です。
人材流動性の高まりと早期離職の常態化
転職が一般化し、IT人材の流動性は年々高まっています。特に若年層では「より柔軟な働き方」「やりたい技術に携われる環境」などを求めて、入社1〜3年以内に離職するケースも増加傾向にあります。
企業側にとっては、せっかく採用した人材が定着せず、教育投資が回収できないという大きな痛手になっています。また、プロジェクトの途中で離職された場合、納期遅延やチーム再編が必要となるなど、業務効率にも大きな影響を及ぼします。
需要と育成体制のミスマッチ
日本のIT教育や新人研修は、今なお旧来のプログラミング言語やシステム構築技術に偏っている傾向があります。その一方で、実際の企業現場ではクラウド環境、セキュリティ設計、DevOpsといったスキルが急速に求められています。
つまり、育成された人材が現場で即戦力とならない「ミスマッチ」が発生しているのです。現実に沿った育成カリキュラムの整備や、企業側のOJT強化が急務となっています。
人材不足が企業経営へ及ぼす影響
IT人材の不足は、単なる採用の課題にとどまらず、企業の経営戦略や競争力にも大きな影響を及ぼします。ここでは、IT人材不足がもたらす4つの主な経営リスクについて解説します。
- エンジニアへの過重な業務負担と離職リスクの向上
- 開発遅延やDX停滞による機会損失
- 情報セキュリティリスクの増大
- 競争力の低下と収益構造の悪化
エンジニアへの過重な業務負担と離職リスクの向上
人材が足りない状況では、既存のエンジニア一人ひとりへの業務負荷が増加します。特にプロジェクトが同時並行で進むような環境では、長時間労働や休日出勤が常態化しやすく、モチベーションの低下や離職のリスクが非常に高まります。
また、チーム全体の士気にも悪影響を与えることから、採用活動を強化するだけでなく、現職エンジニアのケアや業務負担の分散が不可欠となります。
開発遅延やDX停滞による機会損失
IT人材不足により、開発スピードが著しく低下するケースは少なくありません。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進中の企業では、基幹システムの刷新や新サービス開発が停滞し、競合に後れを取るリスクが現実のものとなります。
例えば、デジタル顧客接点を持つWebサービスの公開が遅れれば、潜在顧客の取りこぼしに繋がり、収益機会の損失に直結します。
情報セキュリティリスクの増大
IT人材が不足すると、セキュリティ対策に必要なリソースも不足しがちになります。パッチの適用遅れや脆弱性対応の放置、運用体制の未整備などが発生しやすくなり、サイバー攻撃への耐性が著しく低下します。
実際、IPA(情報処理推進機構)の調査では、セキュリティ人材不足が原因で「インシデント対応に支障が出た」という企業が増加しています(【参考文献】「情報セキュリティ10大脅威 2024」IPA)。
競争力の低下と収益構造の悪化
最終的に、IT人材不足は企業の競争力そのものに影響します。業務効率の低下、製品開発の遅延、サービス品質の低下などが重なれば、顧客の信頼を失い、売上減少や市場シェアの喪失にも繋がりかねません。
さらに、エンジニアの採用コストが上昇することで人件費の増加も招き、収益構造の悪化という財務上の問題にも波及します。
特に不足しやすいスキル領域4選
IT人材全体が不足する中でも、特に企業ニーズが高く、かつ供給が追いついていない「スキル領域」が存在します。これらの領域に精通した人材は市場価値が非常に高く、採用競争が激化しているのが現状です。ここでは、代表的な4つの不足領域を取り上げ、それぞれの重要性や不足の背景について解説します。
- DX推進を担う先端人材
- AI・データサイエンス人材
- 情報セキュリティ専門人材
- クラウド/アプリモダナイゼーション技術者
DX推進を担う先端人材
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためには、単なるITスキルだけでなく、ビジネス理解や変革マネジメント能力を持つ「プロジェクト型人材」が必要です。たとえば、業務プロセスを見直し、テクノロジーと融合させて組織変革を進める役割を担う人材は、高度なITスキルと経営感覚を併せ持つ希少存在です。
しかし、現場レベルでそのような人材を育成する機会が少ないため、多くの企業で「リーダーが不在」「推進スピードが遅い」といった課題が生じています。
AI・データサイエンス人材
データドリブン経営が浸透しつつある中で、AIエンジニアやデータサイエンティストの重要性は年々高まっています。特に、機械学習モデルの構築やビッグデータ分析が行える人材は極めて希少で、育成コストも時間も非常に高いことが採用難の一因です。
加えて、AI分野は海外との競争も激しく、優秀な人材はグローバル企業へ流出しているのが実情です。そのため、日本国内でこの分野の人材を確保するには、待遇や裁量、成長機会など、魅力的な環境を用意する必要があります。
情報セキュリティ専門人材
サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる中、セキュリティエンジニアの需要も急増しています。特に、クラウド環境やゼロトラストアーキテクチャに対応した知識・経験を持つ人材は限られており、即戦力人材の確保が困難な領域です。
さらに、セキュリティ分野は継続的な学習・アップデートが不可欠であり、定着率を上げるためには長期的なキャリアパスを設計し、技術研鑽を支援する体制が求められます。
クラウド/アプリモダナイゼーション技術者
老朽化したシステムをクラウド環境へ移行し、最新技術に対応する「アプリモダナイゼーション」は、今や多くの企業が取り組むテーマです。これに対応できるインフラエンジニアやクラウドアーキテクトは、需要に対して供給が著しく不足しています。
特にAWS、Azure、GCPといった主要クラウドプラットフォームに精通し、かつレガシー環境にも知見のある人材は貴重な存在であり、採用市場でも高騰しています。
社内でIT人材を確保・定着させる方法
人材不足が続く中、社外からの採用だけに頼るのは非現実的です。自社でIT人材を「確保し、かつ定着させる」ための具体策を講じることが、企業競争力の鍵を握ります。この章では、働きやすさやキャリア形成支援、多様な人材の受け入れといった社内施策を中心に、実効性のある方法を解説します。
- 労働環境と待遇改善による魅力づけ
- フレックスタイム・リモート勤務の導入
- 新卒・第二新卒層の早期囲い込み
- 多様性を受け入れる組織風土の形成
労働環境と待遇改善による魅力づけ
IT人材の採用・定着には、報酬だけでなく「働きやすさ」の要素が極めて重要です。近年のエンジニアは、給与だけで職場を選ぶのではなく、職場の雰囲気や裁量の有無、キャリア支援の充実度など、総合的な環境評価で企業を判断しています。
たとえば、残業の削減、評価制度の透明化、上司との定期的な1on1ミーティング導入など、日々の働きやすさを地道に向上させる取り組みが、離職率低下に寄与します。
フレックスタイム・リモート勤務の導入
フレックスタイム制度やリモートワーク制度の整備は、働く場所や時間に柔軟性を求めるIT人材にとって極めて魅力的です。特に若手層や育児・介護と両立したい層にとって、柔軟な働き方は定着の重要要素です。
リモート環境での業務管理体制や成果評価のルールを整備しつつ、SlackやZoomなどのツールを活用することで、物理的な距離を超えたチームワークも実現可能です。
新卒・第二新卒層の早期囲い込み
中途市場での競争が激化する中、新卒・第二新卒層をターゲットとした「早期接触」「インターンシップ活用」は効果的な手段です。特にIT系の専門学校・大学との連携や、SNS・口コミを活用した情報発信により、就職活動以前の段階から自社に興味を持ってもらう仕組みづくりが求められます。
また、入社後の教育制度やOJT体制の明示により、若手人材に「ここで成長できる」というイメージを持ってもらうことが重要です。
多様性を受け入れる組織風土の形成
国内のIT人材だけでなく、外国籍人材の活用も現実的な選択肢です。特にASEANや南アジア出身のエンジニアは高度なスキルを有しているケースが多く、ビザ制度の整備と社内受け入れ体制があれば十分に活躍が期待できます。
言語や文化の違いを尊重し、配慮のあるマネジメントを行うことで、チーム全体の多様性も向上し、イノベーションの土壌が育ちやすくなります。
社内でIT人材を育てる方法
採用難が続く中で、社内人材をIT人材として育てる「戦力化戦略」はますます重要性を増しています。社内に眠るポテンシャルを引き出し、成長支援によってスキルギャップを埋めることは、長期的な人材安定化にも寄与します。ここでは、社内育成を効果的に進めるための2つの重要施策を紹介します。
- リスキリングのプログラムを組む
- 教育体制を充実させる
リスキリングのプログラムを組む
「リスキリング」とは、既存社員に対して新たなスキルを獲得させる再教育施策です。特にIT分野では、業務系社員がプログラミングやデータ分析を学ぶケースが増えており、社内異動を通じてIT部門へ転換する取り組みも注目されています。
ポイントは、座学ではなく実践中心のカリキュラムを構築することです。たとえば社内のシステム改善案件を教材とし、メンターを付けながら段階的に習得を支援する方法が効果的です。
また、経済産業省の「マナビDX」や民間のeラーニングサービス(Udemy、TechAcademyなど)との連携も有効です。
教育体制を充実させる
社内でIT人材を育成するには、単発の研修で終わらせず、継続的な学習を支援する制度の整備が必要です。たとえば、以下のような施策が挙げられます。
- 階層別の教育プログラム(初級〜上級)
- 社外セミナー・資格取得支援制度
- 月次での学習進捗レビューとフィードバック
教育効果を高めるためには、単にスキルを教えるだけでなく、実務と直結した内容にすることがカギとなります。理論ばかりでなく、「なぜそれが必要なのか」「現場でどう活かせるのか」をセットで教えることで、学びの定着が進みます。
また、教育の成果を正当に評価する仕組みも、社員のモチベーションを高める上で欠かせません。
外部リソースの活用方法
社内育成だけでは即戦力の確保が難しい場合、外部リソースの柔軟な活用がカギとなります。特に中小企業やIT専門人材が限られる企業では、外部協力先を戦略的に選定・活用することで、開発スピードや技術品質を大幅に底上げできます。ここでは、代表的な外部活用手段4つを紹介します。
- アウトソーシング・SIerとの協業
- フリーランス・副業人材の活用
- オフショア・ニアショア開発の導入
- ITツール導入による生産性向上
アウトソーシング・SIerとの協業
業務システムの開発・運用をアウトソーシングすることで、社内リソースの制約を超えた対応が可能になります。特にSIer(システムインテグレーター)との協業は、企画・設計・開発・保守まで一貫支援を受けられる点が大きな強みです。
ただし、発注側にも一定の技術的リテラシーが求められます。丸投げにならないよう、RFP(提案依頼書)の明確化や、成果物レビューの体制整備が重要です。
フリーランス・副業人材の活用
即戦力のIT人材をピンポイントで確保したい場合、フリーランスや副業人材の活用が効果的です。契約の自由度が高く、短期間・特定技術領域に特化した支援を受けやすい点が魅力です。
たとえば「3カ月だけAIモデルのチューニングができる人がほしい」といった場合、フリーランスなら迅速にアサイン可能です。ただし、情報管理・セキュリティポリシーの共有を徹底する必要があります。
オフショア・ニアショア開発の導入
コストを抑えつつ一定規模の開発体制を構築したい場合には、海外(オフショア)や地方(ニアショア)の開発拠点を活用する方法があります。特に東南アジアや中国、ベトナムなどは、IT人材が豊富で、日本企業との取引実績も増加傾向にあります。
要件定義や設計を日本側が担い、開発実装を海外に委託する分業体制が一般的です。ただし、言語・文化・時差の壁を乗り越えるためには、窓口担当者のコミュニケーション力が重要です。
ITツール導入による生産性向上
人材そのものの確保が困難な場合は、ツールやシステムによる業務自動化・効率化も有力な選択肢です。たとえば以下のような分野でのツール導入が効果的です。
- RPA(定型業務自動化)
- ローコード/ノーコード開発
- クラウド型プロジェクト管理ツール
ツール導入のポイントは、導入後の活用教育と運用支援体制の整備です。ツールは「入れたら終わり」ではなく、現場で活かせて初めて価値が生まれます。
エンジニア不足 対策についてよくある質問(FAQ)
エンジニア不足の課題に直面する中で、企業の採用担当者からよく寄せられる疑問に対して、簡潔かつ実践的に回答します。施策に踏み出す前の不安解消や、社内での説明材料としてもご活用ください。
なぜエンジニアが不足しているの?
技術の進化スピードが非常に速く、教育体制が追いついていないことが主因です。加えて、少子高齢化による労働人口の減少、人材の流動性増加、育成の遅れといった構造的な要因も重なり、慢性的な人材不足が発生しています。
エンジニア不足による企業への影響は?
開発の遅延、DX停滞、セキュリティ体制の不備などが顕在化し、結果として競争力や収益力の低下につながります。さらに、既存社員の離職リスクも高まり、人材確保の負のスパイラルに陥る可能性があります。
社内でエンジニアを確保するには?
労働環境の整備、フレックス制度やリモート勤務導入、キャリア支援などが必要です。また、多様な人材(若手・女性・外国籍人材など)の採用を柔軟に進める姿勢も、重要な要素となります。
未経験者を育成して戦力化できる?
可能です。リスキリングプログラムやOJTを整えれば、未経験者でも半年~1年で一定のIT業務に対応できるレベルに成長できます。育成制度とフォロー体制が鍵です。
外国人エンジニアを雇う際の注意点は?
言語・文化面での理解とコミュニケーション支援が重要です。また、在留資格(ビザ)管理や労働条件の整備など、法務・労務面の体制構築も欠かせません。
外注先を選ぶときのポイントは?
技術スタックの適合度、過去実績、責任範囲の明確さ、運用サポート体制などを総合的に評価する必要があります。価格だけで判断するのはリスクが高いため注意が必要です。
フリーランス活用のメリットと注意点は?
専門性の高い人材を短期間で確保でき、コスト調整も容易です。ただし、継続性や情報管理の面では一定のリスクも伴います。契約前の要件整理とポリシー共有が欠かせません。
ITツール導入で人材不足は解決できる?
完全な解決にはなりませんが、RPAやローコード開発ツールの導入により、定型業務を効率化してリソースを浮かせることは可能です。ツールの選定と定着支援が成功の鍵となります。
まとめ
IT人材不足は、今後10年を見据えたときに最も重要な経営課題のひとつです。採用・育成・定着のいずれにも課題があり、加えて外部リソースの活用や業務効率化といった包括的なアプローチが求められます。本記事がこれらの課題解決の参考になれば幸いです。
採用課題にお困りの方へ!uloqoにお任せください
[cta02 page_id=”1087″]
▼サービスに関するお問い合わせはこちらから
関連記事

【最新版】エンジニア採用が難しい理由とは?市場背景・社内課題・解決策を徹底解説
- 採用代行
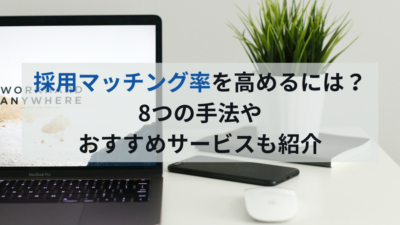
採用マッチング率を高めるには?8つの手法やおすすめサービスも紹介!
- 採用代行

フリーランス採用代行おすすめ9選|メリット・デメリットや選定ポイントも徹底解説!
- 採用代行

採用代行の費用相場は?料金体系、低額で利用可能なサービスを紹介
- 採用代行

【徹底比較】採用代行と人材紹介の違いとは?それぞれの特徴や費用も紹介!
- 採用代行
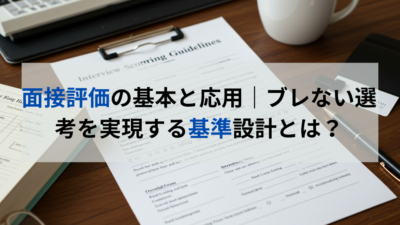
面接評価の基本と応用|ブレない選考を実現する基準設計とは?







